
【668】算数の教え方 ー公約数とベン図ー
昨日は公約数はベン図で理解しようと書きました。続けます。
公約数を教えるときのベン図の使い方です。
そもそもベン図とは、こういうやつです。

重なっているのが、共通するところです。
厳密にはツッコミどころもありますが
分かりやすいです。ZENさん天才です。
ベン図は、現行の教育課程では
高校の数Aで習いますが、先生次第では
小学生であっても、場合の数や確率などで、
ベン図を習うことがあります。
中学受験する小学生は「集合算」という
数Aの「集合」みたいなものがあるので、
ベン図を使うことがあります。
今日は本格的な「集合」でベン図を習う前に
公約数で使うの教え方を書いてみます。
公約数の「公」という字は、
「みんなの」や「共通の」という意味です。
なので、公約数とは、
2つ以上の整数に共通する約数のことです。
言い換えると、2つの数の約数をあげたとき
「両方ともにある約数」が公約数です。
18と24の公約数は、1,2,3,6です。
なので最終形はもちろん、こうなります。

大人ならこのベン図だけで分かるでしょうが
ボクの教え方の信条は「分解」です。
算数が苦手な子には、順番に、丁寧に、
教えてあげることが重要だと思っています。
順番に、丁寧に。
①まず1つの円だけで
18の約数を見てもらいます。
18の約数「以外」の数字も書きます。
18の約数は全部で6個なので
それもメモしておきます。
このメモは書き忘れ予防です。

②同様に、24の約数とそれ以外、も。
色分けしておくと良いです。

③そして、円を重ねます。
上のオムライスのベン図を使いながら
重なっているところが共通するところだと
説明します。
④そのうえで、数字を入れていって
公約数とは何かを見てもらいます。
最初はお子さんには見てもらうだけです。
数字を入れるのは大人です。
⑤公約数とは、「両方にある約数」という
説明とともに、改めて完成形のベン図を
見てもらいます。
このとき最大公約数にも触れてあげます。

次は、ベン図を一緒に作ります。

一般的に学校で習う公約数の探し方の
これ↑を都度確認しながら、ベン図に数字を
いれていきます。
⑥まず、ベン図の円だけを用意します。

⑦18の約数は?と聞いて、
約数をお子さんに言ってもらいながら
数字は大人が書きいれます。
このとき、公約数の数字は、
重なったところにいれます。

⑧次に、24の約数は?と聞いて、
書き込んでいきます。
色分けしつつ、重なったところには
公約数をいれます。

⑨最後に、重なったところが
数字が重複しているので、
消し込んでいきます。

この「消し込む」ステップは、
公約数の理解自体には不要です。
ただ、今後いろいろと使うベン図です。
【重複した数字は消す】
この超重要ポイントを見てもらうことが
今後、集合などで本格的にベン図を使うとき
理解を助けることになります。
集合とは、こういうやつです。
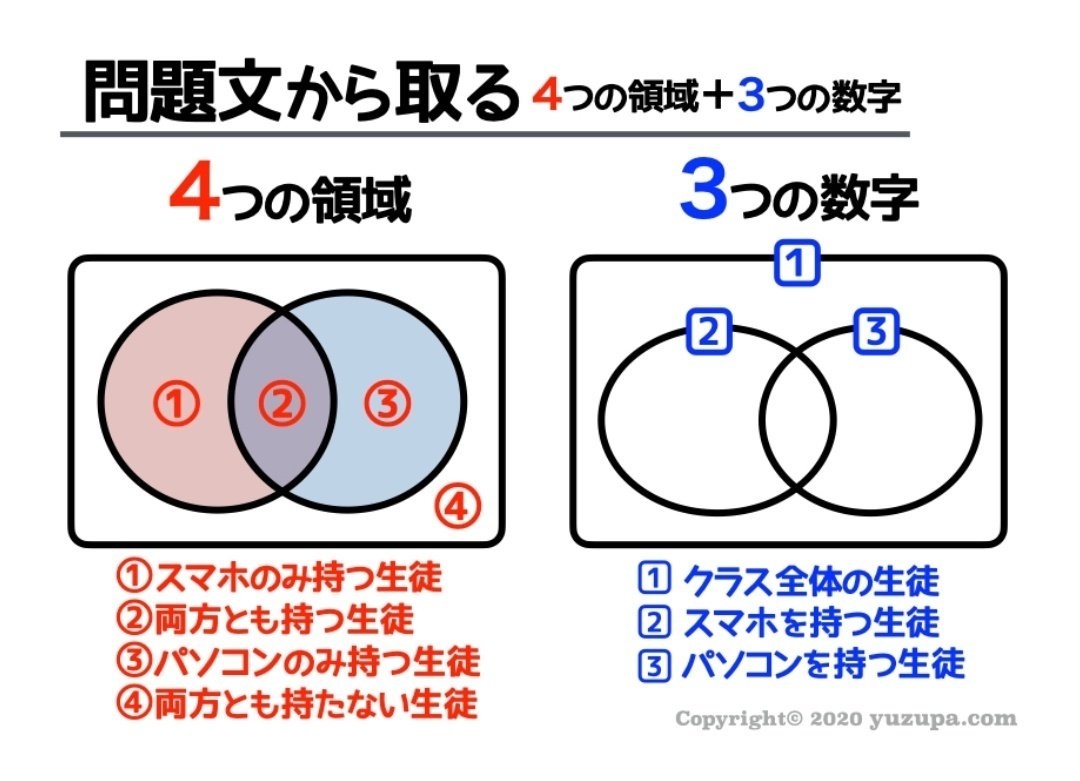
この画像の例なら、スマホかパソコンの
どちらかでも持っている人数を
計算するとき、単純な足し算ではなく
【重複した②の数字を引き算する】
という概念が、最大のつまづきポイントです

だからボクは、公約数のときも
あえて数字を2コ書いて、あとで消す
という作業を入れています。
絶対に覚えろとは言いませんが、
「知っておく」だけでも大切と思っています。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
