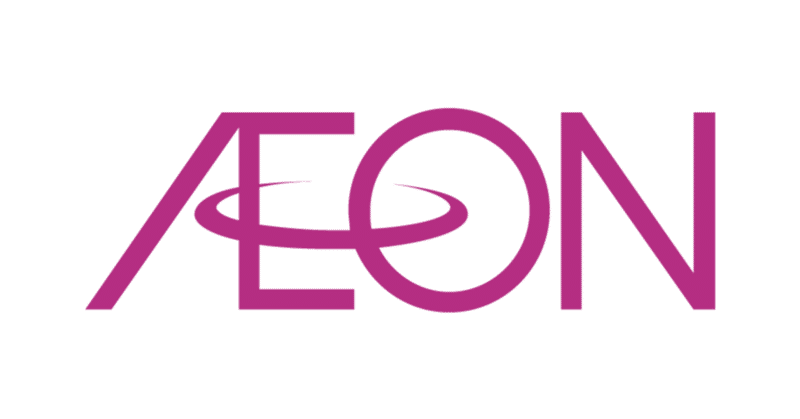
5分で分かる!人気銘柄イオングループを評価~企業財務分析
挨拶
このページをご覧になってくれている方ありがとうございます。改めましてコブータと申します。私は米国公認会計士や簿記2級の学習を通じて会計のマニアになりました。企業の財務分析を行うことで皆様の投資判断の材料にしたり、就職、転職の企業分析にお役立ちいだだければと思います。今回はイオングループについて解説していきます。日本で一番有名なスーパーといえばイオンと答える人も多いでしょう。どこの企業の分析をしてほしいとリクエストがありましたらコメント等に残してくれると嬉しいです!
企業概要
イオングループは岡田屋として1926年9月21日に設立されました。当初から小売業を経営しています。そして1970年の合併によって旧ジャスコの社名に変わりました。イオンと呼ばれるようになったのは2001年からでした。割と最近のように思えますが、もう20年以上経ったんですね。
事業内容
イオングループの事業は下記の9個の事業に分けられています。
GMS事業
SM事業
DS事業
ヘルス&ウエルネス事業
総合金融事業
ディベロッパー事業
サービス・専門店事業
国際事業
その他事業
かなり多くのビジネスを手がけていますね。
GMS事業は総合スーパーのイオンやオリジン弁当の事業が含まれています。
SM事業は小型スーパーやコンビニですね。イオンより少し小さいスーパーはこちらになるようです。まいばすけっとが有名ですね。
DS事業はディスカウントストアです。イオンビッグというディスカウントストアを経営しています。
ヘルス&ウエルネス事業はドラッグストア、調剤でウェルシアはイオングループです。
総合金融事業はクレジットやイオン銀行ですね。
ディベロッパー事業はショッピングモールの開発や賃貸を行っています。
サービス・専門店事業はその他小売店です。
国際事業はアセアンや中国での小売業です。
その他事業はモバイルマーケティング事業、デジタル事業等です。ここは社内向けの売上が多いです。
人員について
イオンの従業員数内訳は下記の通りです。
従業員数は約16万人の大企業です。小売業ということもありかなり多いですね。パートやバイトの人も合わせると25万人を超えます。その中でもGMS事業で多くの人が働いています。サービス・専門店事業やSM事業にも多くの人材が割かれており、本業に力を入れている印象があります。

働きやすさについて
現在注目されている働きやすさですがイオングループの有価証券報告書には特に記載はありませんでした。ですが、イオングループは育休を取得する従業員に対して100%の賃金を保証する等、力を入れています。通常は育休期間中のお金は会社からではなく雇用保険から支払われます。それも給与の2/3だけです。イオングループは1年間100%の賃金を保証するようなのでとてもありがたいですね。
イオングループの収益構成
イオングループは収益約9.1兆円の大企業です。そしてイオングループは収益の約30%以上の3.1兆円をGMS事業で稼いでいます。やはり総合スーパーのイオンが多くの収益を上げています。その次に稼いでいるのがSM事業で、ヘルス&ウェルネス事業と続きます。
2021年度と比較すると売上は約4%増えています。過去5年を振り返ってもコロナ禍にも関わらず売上を毎年少しずつ増やしていました。コロナから回復してきて2022年度は直近5年の間では最高の売上額です。
その大きな要因は国際事業の拡大とヘルス&ウェルネス事業の収益増加です。直近5年は売上を増加しているので今後も売上増加が期待できそうです。

営業利益と当期純利益
収益が増加しているのも重要ですが、営業利益と当期純利益についても無視することはできません。
イオングループの営業利益率は約2.2%となっています。小売業は利益率が低いと言われますが2%台は低すぎますね。小売業という性質上、土地も建物も多くの場所に必要で、その分従業員も必要なので販管費も多くなってしまっている印象です。また、光熱費が倍近く上がっているのも痛いですね。イオングループは光熱費の高騰を受けて利益率が悪化しています。一方、デジタルシフトを推進しているので、今後の利益率の改善には注目です。
2021年度はGMSグループが赤字でしたが、ネットスーパーの拡大や、トップバリューブランドの強化により2022年度は黒字になっていますね。それでも日本の小売事業はどの事業も極端に利益率が低いです。唯一利益率が高いのは総合金融事業ですが他の事業と比較すると収益額が少ないです。
当期純利益は約210億円でコロナに入る前と比較すると当期純利益の額はまだ戻ってきていないですね。関連株式会社売却で約240億円の特別利益を上げています。これはミニストップの韓国事業を売却したようです。
1株あたりの配当金は直近5年は一定です。配当性向は100%を超えてしまっていますが、今後も配当額はキープか、それ以上を出す方針のようです。一見、嬉しいですが儲けた以上に配当を出しているので長期的に見ると利益率の改善が重要になってきます。今後の目指す配当性向としては30%台ですので今後も売上が増え続ければ、今後の配当金の増加も期待できそうですね。
イオングループの倒産リスクは?
会社が潰れてしまう可能性があるか?を判断するには流動比率の分析はかかせません。流動比率とは流動資産÷流動負債で求めることができ、短期的な資金繰りに問題がないかが分かります。
流動資産は1年以内に現金になりえる資産、流動負債は1年以内に払う負債のことです。流動資産が流動負債より多ければとりあえずOKです。
ですが気をつけるのは棚卸資産の項目です。棚卸資産は1年以内に販売できるかできないか分からないからです。その前段階である原材料も考慮が必要でしょう。
イオングループの流動資産を確認すると約7.6兆円あります。その内棚卸資産は約6,000億円ですので流動資産の約10%以下です。一方で、流動負債は約7.4兆円と流動資産より約3,000億円少なくなっています。棚卸資産を除いたら資産は約7兆円と若干流動負債が流動資産を上回っています。ですが、わずかに上回っているだけですし、イオングループは銀行業も営んでおり、流動負債の内、半分以上の約4.4兆円が預金になります。預金はすぐに顧客に返済しなければいけない負債ではないので短期的な支払い能力には問題はなさそうです。
イオングループの固定資産
イオングループの固定資産は増加しています。2021年度には約4.4兆円の固定資産でしたが、2022年度は約4.6兆円と約2000億円程度増加しています。その理由は新規店舗の出店、既存店舗の改良が大きな要因です。特にGMS事業とディベロッパー事業のショッピングモールの建設、新規店舗の出店が大きかった様です。海外にもショッピングモールを建設しており、さらなる収益拡大が期待できそうです。
まとめ
2021年度と比較すると売上が4%増加。コロナ禍から売上はずっと上昇
営業利益率は低い。小売業という体質で固定資産、人件費がかかる上に光熱費の高騰が痛い
コロナ以降回復しているが、今後も増益し続けられるかは注視が必要
配当額は純利益に対してかなり多め。配当を減らす方針はないが今後の利益に注視が必要
短期的な資金繰りについてすぐには問題にはならなさそう
ショッピングモールの建設など設備投資は行っているので、今後の業績の成長性に期待
評価
成長性:4
収益性:2
安全性:4
生産性:3
配当:3
合計:16/25
ここまで読んでいただきありがとうございます。コメントにどの企業の分析をやって欲しい等書いていただければ分析します!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
