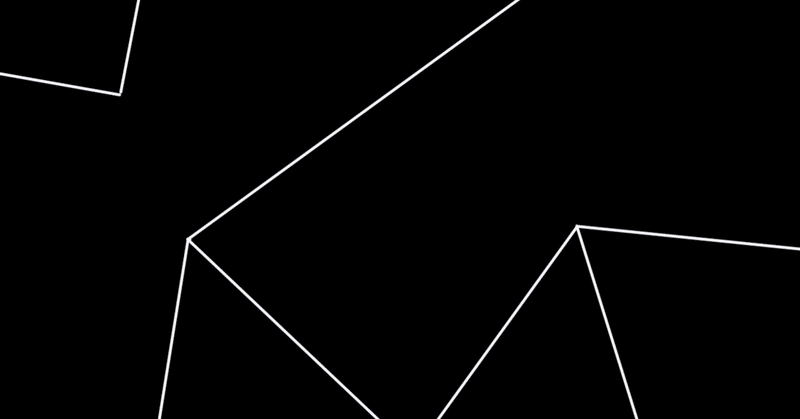
【短編】箱の男(2600字)
真っ暗だ………。
何も見えない。
本当の暗闇がそこにあった。
ただ、狭い……圧迫されるような感じだけがある。
ここは、どこだ…………?
俺は、気付くと暗くて狭い箱の中にいた。
ここはどこなんだ……?
俺は、考えを廻らせる……。
ここに来る前の記憶というものが、一切ないのだ。
なにも、わからない。
ただ、何か箱のようなものに詰められている。
そのことしか、わからない。
カタカタカタ……
不規則な振動が、微かに男を揺さぶった。
耳を澄ませれば僅かながら、でも確かに外界の音が男の耳に届いた、
かもしれない。
車の走る音。街の喧騒が。
男は、箱のようなものに詰められ、どこかに運ばれてゆく………。
一体、どこへ………。
この閉塞的な空間……。
ほんの小さな光りさえ見えない暗闇………。
ここはどこで、そしてどこへ行くのか………。
自分は、どうして、何のためにここに詰められているのか。
全てが闇に包まれていて、恐怖心を湧き起こさせた。
思い出せ………。
どうして、ここにいるのか。
俺は、脳内の記憶の断片を探り始めた。
そうしているうちに気付いた。
さらに驚愕の事実に、はっとする。
俺は、誰だ…………?
わからなかった。
自分が何者かさえ、わからないのだ。
―――
うわぁああぁぁっっ!!
とてつもない恐怖を感じ、思わず叫んだ。………はずだった。
が、声が出ない……?
と、いうより声を発する咽が存在するのか、それを聞き取る耳がそこにあるのか、その概念が消えてしまったように。
俺、という概念が………
スッパリと切り取られた自分に関する記憶と共に、失われたような感覚に陥った。
俺は、どこだ…………?
暗闇。
目を閉じているのか、開けているのかもわからない。
―――いや。
物を見る目というものが、存在するのか、もはやその感覚は失われている。
真の暗闇。
一切の光りのないこの空間では、例えその目が機能し開いていたとして、自分の一部を見ることさえ叶わない。
その時。
――ふとよぎった記憶の断片。
前にも、こんな暗闇を体験したことがあった。
そうだ。
あの時も、全てを無に帰すかのような、ブラックホールの大きな口に飲み込まれ、自分自身の存在を失いそうな感覚に取り憑かれたんだ。
思い出すのは、取材で訪れた沖縄。
ムッとする熱気が、その中では幾分ひんやりとしたものに感じられた。
それは、過去の凄惨な出来事がこの場所にもたらす独特な空気だろうか………。
同行カメラマンの袖に、大人げもなく始終縋り付いていた。
そうでもしていないと、自分という概念を失いそうだった。
ここで、太平洋戦争中の沖縄戦で、何人もの人間が命を落とした。
光りを使うことも、音を立てることも許されぬ壕の中で。
本当の暗闇の中で、空腹に泣き声を上げる赤ん坊を自らの手で二度と声を上げぬようにした母親もいた。
敵に見付かることを恐れ、血の臭いが立ち込める穴の中で、息を殺して生きていた。
あれから60年もの月日が流れても、この場所には無念のまま亡くなった魂の哀しみが宿っているような………。
真夏の沖縄に、蝉の鳴く声もなく肌を冷気が包む。
あの場所は、糸数のガマだ。
どうして。
こんな記憶だけが、ぽっかりと思い出されたのだろうか………?
ただ、この暗闇に捕われた状況が、あの日の感覚を呼び起こした。
しかし。
これと似た感覚を体験したのはこれだけではなかった。
自分という概念が失われる感覚………。
そんな感覚に陥ったのは、この一回きりではない。
もう一度、どこかで………。
そして、沖縄のガマでの体験とは対象的に、その時は、この身を焼くような熱さを感じていた。
そんな気がするが、どうしてもハッキリ思い出せない。
とにかく、ほんの一片でも、記憶を取り戻したのだ。
そこから、広げていくことにしよう。
暗い穴から出た先の光りを、俺は見たはずなんだ。
俺は、誰で、どうしてここにいる?
そして、ここはどこだ?
この先には―――?
沖縄。取材。
その単語に、いくつかの風景写真の断片が脳内を駆け巡る。
青い珊瑚礁。どこまでも続くきび畑。色黒の老夫婦の笑顔。
俺は、日本全国駆け巡り、郷土や地域の住人を取材していたんだ。
あらゆる渓谷。山々の四季。農業に従事する人々。野に咲く花。
田舎暮しに屈託のない笑顔………。
今まで、記憶としてインプットされていた景色や人間の顔が、小川のせせらぎや笑い声と共に頭を駆け巡る。
記憶を手繰り寄せろ。
現在に結び付く記憶を………。
そして、一瞬。
また、身を焼く業火の中にいるような身体の暑さを感じた。
なんだ、これは……。
現在に一番近い記憶……?
カタカタカタ。
その時。
男を乗せた車が停まった。
そして、男は何者かに運ばれて建物に入る。
そこは懐かしいような、それでいて悲しみを喚起させるような臭いに満ちていた。
これは。
線香――――。
――――
男は瞬間、その臭気を知覚することができた。
その途端、蘇る………あの感覚。
熱い!熱い!
業火に焼かれる………。
俺は、自分の概念を奪われる感覚に陥れられた。
そして、肉体を奪われた――。
―――もっと、前だ。
白い天井。
俺の身体はベッドに横たえられ、何本もの管で機械と繋がっている。
鼻にチューブ。口にはマスク。
ベッドサイドには、神妙な面持ちの医師と、その後ろに悲痛な表情の看護師。
反対側、俺の手を握り泣き崩れる女性は。
おふくろ。
それから、それに寄り添うように親父。
どうして、泣いている?
あの親父が。
「洋ちゃん、取材で行ってたんだってね」
「……そう。北アルプスの登頂があの子の夢だったからねぇ」
千賀子叔母さん、とおふくろの声だ。
男にはその声が届いていた。
「もう、納骨はできるんだけどねぇ……なんだか、まだ………信じられなくて………」
おふくろの声は最後には鳴咽で掻き消された。
泣くなよ。
おふくろ。
俺は、今、全ての記憶を取り戻したぞ。
そうか。
俺は、死んだんだったな………。
暗く狭い箱は、もう怖くはなかった。
肉体は失った。
けれど。
俺は、ここにいる。
家へ帰ってきたんだよ。
タダイマ――――。
俺の肋骨が、カタカタと鳴った。
「箱の男」
-END-
この短編は、2007年に“久坂 葵”名義で「魔法のiらんど」に投稿したものです。この頃から知覚への興味があったようですね。本質的なテーマということでしょうか。不思議な気がします。14年前の作品が、少しでも多くの方の目に留まればうれしく思います。(加筆・修正済)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
