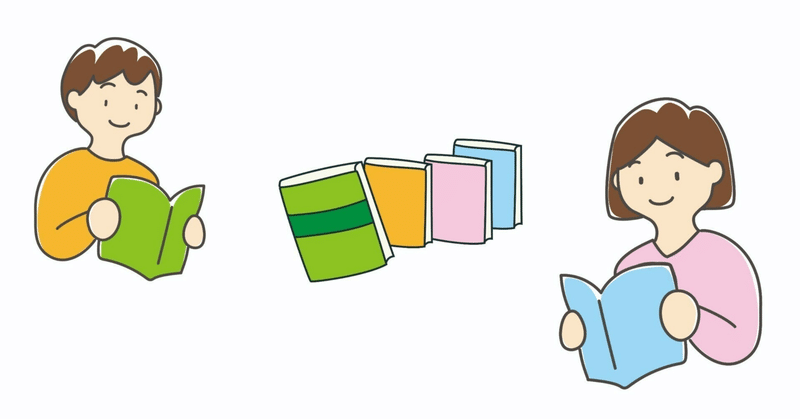
週末は子どもと一緒に図書館に(後編):子どものために本を選ぶコツ
目指す方向性
この記事は、読書と図書館に関する前編の続きである。
前編では、うちの子どもたちの日本語力の向上のために、読書が大切だと思い立ったことを書いた。そして、読書と言語能力に関する研究をいくつか紹介した。
研究をふまえて目指すべき方向性は、『読書と言語能力』の中で猪原氏が述べている以下の点に集約されると思う。
本人の言語力にアンバランスなところがなく、最低限の水準まで高まっていることを確認した上で、本人の言語力の水準に合わせた本を読ませる
「本人の言語水準に合わせた本」というのは、知らない単語が多少含まれているぐらいが理想的である。文脈からの類推で、語彙を増やしていくことができる。難しすぎるとこの類推が働かないし、易しすぎると(少なくとも言語能力の面では)得るものが少ない。
これを子どもたちに強制することなく、楽しく実現していくことを、私は目標として掲げることにした。そしてそれをどう実践していったかが、今回の内容だ。前編の記事は研究の紹介が中心だったが、今回の内容は、私の個人的な経験にもとづく(したがって主観的な)話である。
再び図書館へ
前編で書いたように、一時期は図書館から足が遠のきがちだった。子どもの読書の大切さに気づいて再び図書館に通うようになったのは、娘が小学校二年生になってからのことだ。
以前は図書館といえば絵本コーナーだったのだが、二年生ともなると児童書の低学年向けコーナーになる。驚いたことに、娘はそこで本を選ぶと、夢中になって読みだした。上の猪原氏の本からの引用でいえば「最低限の水準」がこの時期に既に満たされていたのだろう。
そういうわけで、前編の冒頭に書いたような、図書館で本を借りると子どもたちが静かに読み始めるというパターンが、この頃から始まった。
本を買うか、図書館で借りるか
図書館のことを書いたが、本は必ずしも図書館で借りなくてもよい。書店(リアルの書店やAmazonなどのインターネット上の書店)で買うという方法もある。
書店で買うのと図書館で借りるのとどちらが良いかについて、最初のうちは特に意識していなかった。しかし、経験を積むうちに、図書館を利用することのメリットが圧倒的に大きいことに気づいていった。
図書館のメリット1:お金がかからない
これは当たり前のことだが、図書館で借りればお金がかからない。当たり前のことなのだが、多読(つまり本をたくさん読ませる)路線で行く場合、とても重要なことだ。
日本の児童書はハードカバーが多く、一冊1000円以上することが多い。それでいて、特に小学校低学年向けの本はページ数が少ないので、あっという間に読めてしまう。前回の記事でうちの娘が年間300冊以上読んだと書いたが、娘が読むような低学年向けの児童書だと、それぐらい読むのは実は別に驚くべきことでもない。ただ、その300冊の本を全て買っていたら30万円以上かかることになるので、あまり現実的ではない。
図書館のメリット2:場所をとらない
これも当たり前のことなのだが、図書館で借りた本は図書館に返すので、場所をとらない。300冊の本を全て購入しても、それを置くスペースがうちにはない。もちろん、ブックオフなり古書店で売ったり、メルカリで売ったりすることもできるだろうが、それはそれで手間がかかる。
図書館のメリット3:読むのを気軽にやめられる
これが実は、図書館で借りることの最大のメリットだと思っている。子どもは読み始めた本を途中でやめてしまうことがよくある。もし購入した本だと、「せっかく買ったのにもったいないから、ちゃんと読みなさい」と子どもにいってしまいがちである。でも、上に書いたように、子どもに本を読ませることを強制したくはない。図書館で借りた本なら、子どもが読まないでいても、あまり気にならない。また別の本を借りればいいだけだ。
子どもが本を読むのを途中でやめてしまうのには、二通りの理由があると思っている。一つは、内容がその子を惹きつけるものではない(それは、その子の好みにあっていないのかもしれないし、単純にその作品が駄作なのかもしれない)か、その子にとって難しすぎるかである。特に後者のパターンが多いのではないかと思う。
本のレベルを判断するのは、実はけっこう難しい。本をパラパラっと見て、長さや、字の大きさや、漢字の多さで判断してしまいがちだが、一見簡単なように見えても、その子にとって知らない語彙が多く含まれている本というのはある。
うちの娘を見ていると、一年前にちょっと手にとって読むのをやめてしまった本を、今になって夢中で読んでいるということが、よくある。一年の間に成長し、その本を読めるレベルに達したのだろうと思う。
図書館のメリット4:本がたくさんある
近所の書店に行くと気づくのだが、絵本の品ぞろえがけっこうある一方で、小学生向けの児童書の品ぞろえは、驚くほど少ない。『かいけつゾロリ』のような人気シリーズと、「〇歳までに読みたい名作」みたいな名作を短くしたシリーズと、読書感想文のシーズンに大量入荷したであろう指定図書の売れ残りのような本ぐらいしかなかったりする。(ちなみに私は、「〇歳までに読みたい名作」などのシリーズは、わざわざ短いバージョンを〇歳までに読まなくてもよいと思っている。その年齢の子にあった児童書はたくさんあるし、名作はその完全版を読める年になってから読めばいいと思う。その方が絶対に面白い。)
もちろん、大型書店に行けば、もっとたくさんの品ぞろえがある。ただ、私たちの住んでいる街には、近所に大型書店があるわけではない。
図書館はもっと身近にあるし(といっても、徒歩圏内にないのが残念だというのは、前回の記事に書いた通り)、バリエーションに富んだ児童書をそろえている。
もちろん、なんでも図書館で借りればいいというわけではなく、買ったほうがいい場合もある。
買った方がいい場合1:新刊や人気の本
新刊は図書館に入るまでに時間がかかる。また、「かいけつゾロリ」のような人気シリーズだと、新刊が図書館に入っても予約待ちですごく時間がかかったりする。夏の読書感想文のシーズンには、課題図書に指定された本の予約待ちもすごいことになって、ようやく借りられるようになったときには既に夏休みが終わっていたりする。(ただ、うちの子の場合、今のところ新刊を読みたいと言うことはない。というかそもそも、新刊が出た自体を子どもたちが把握していない。)
買った方がいい場合2:お気に入りの本
図書館で借りてとても良かった本は、後で買ってもよいかもしれない。例えばうちの娘の場合、本当に面白かった本だと、私や妻にも読むように勧めることが、ときどきある。それぐらいお気に入りの本だと、自分の手元に置いておくことには、きっと意味がある。それに、良い児童作家さんたちをサポートすることにもなる。(ただ、このように思ったのは最近のことなので、まだ実践していない。)
誰が選ぶか、どう選ぶか
さて、図書館で本を借りるとして、誰が選ぶか。これにはもちろん、二通りある。
子どもが自分で選ぶ
親が選ぶ
うちの場合は両方ある。子どもが自分で選ぶと、子どもの関心がどのあたりにあるのかがよくわかる。一方で、子どもが選ぶと易しすぎるものを選びがちなので、それはそれで借りるとして、親がちょっとだけレベルの高めのものを選ぶことになる。
親が選ぶ場合、さらに二通りのやり方がある。
2a. 図書館で直接見ながら選ぶ
2b. 家でリサーチして予約する
これも両方やっている。図書館でパラパラみながら本を選ぶ一方で、家でインターネットなどでリサーチして予約する。私がふだんどのようにリサーチしているかは後で書くが、リサーチしてから図書館のサイトで検索すると、ふだん行く図書館の書架に並んでいる本が利用可能な図書のごく一部でしかないことに気づく。図書館の書架で見かけないのは、その図書館で所蔵されていないか、人気があって常に貸し出し中だからなのだが、市内の他館にあることが多く、たいていの本は予約すると1週間以内に行きつけの図書館に送られてきて、借りられるようになる。
読書記録アプリ
せっかく読書をよくするようになったので、読んだ本を読書アプリに記録するようにしている。これは、本人に達成感を持たせるという意味もあるが、私が子どもの本を選ぶとき、過去に読んだ本を参考にしたり、同じものを二度借りてしまわないようにするために参考にするという側面が大きい。
読書記録アプリはいろいろあるが、子ども自身でも使えるようにするにはシンプルなものがよいと思って、Bibliaというアプリを使っている。
ただ、「子ども自身でも使えるように」と書いたが、子どもが面白がって自分自身でやったのは最初の頃だけで、今はだいたい私が入力している。
ちなみに、このアプリに記録した情報はcsv形式でDropboxに保存できる。そのcsvファイルをExcelで読み込み、眺めていると、子どもの読書傾向が見えてきて面白い。その気になれば、Rで統計的に分析したりとかもできそうである。(やっていないけれど。)
本を探すコツ
本の選び方に話を戻すと、家でリサーチして本を探す場合、いろいろな方法がある。
コツ1:既存のリストを使う
公文の推薦図書は、数は多くないが、レベル順に並んでいるので、適切なレベルの本を探しやすい。古典的な児童書が多いが、比較的新しい本もところどころ混じっている。
また、青少年読書感想文全国コンクールの課題図書も参考になる。その年度の課題図書だけだと数が少ないが、毎年新たに課題図書が出ているので、過去の課題図書もリストとして使える。
ただし、うちの娘の場合、いま3年生だが中学年向けの本は難しく感じるようで、低学年向けから選ぶことが多い。子どもによって読めるレベルが違うので、その子のレベルに合ったものを選べばいいと思う。
コツ2:同じ作家の作品を探す
子どもが読んで気に入った本があったら、その本の作家の書いた別の作品を探してみる。児童作家はいろいろな年齢向けの作品を書いていることが多いので、この方法だと、子どもが内容的に気に入りやすく、レベル的にはちょっと高めという本を見つけやすい。子どもが手に取ってちょっと難しいなと感じても、「この本、〇〇を書いた人が書いた本だよ」というと、興味を持って読んでくれたりする。そして、レベルがちょっと高そうでも、読めたりする。
例えば、図書館でたまたま借りて読んで娘が気に入った本に『ななとさきちゃん ふたりはペア』という作品がある。
この本を書いた山本悦子氏の作品のうちで、より言語的なレベルが高い(そしておそらく、もっと有名な)作品として、『先生、しゅくだいわすれました』というものがある。上の『ななとさきちゃん』の本を借りたすぐ後に、この本も借りてみて、そのときは難しいのかと読もうとしなかったのだが、数か月後に改めて借りてみたら、けっこう夢中になって読んでくれた。
(ちなみにうちの娘は、こういう小学校を舞台とした作品が好きらしい。)
コツ3:同じ出版社の同じシリーズから探す
児童書の出版社は、児童書をよくシリーズのかたちで出している。子どもが気に入って読んだ本は、なんらかのシリーズの一部を成していたりする。シリーズの他の本を探してみると、レベル的にも内容的にも近いものが多いので、そこから選ぶと外れが少ない。
これもたまたま借りて読んで娘が気に入った本なのだが、『三年一組、春野先生!』というのがある。
この本は実は、『三年二組、みんなよい子です!』という本の続編として出たものなのだ。娘がそっちも読みたいというので、そっちも借りてみた。
で、実は、この本は講談社の「おしごとのおはなし」というシリーズの一つとして出ている。というわけで、このシリーズからもいくつか借りてみた。
ちなみに、上に挙げた『春野先生』の本のほうは、よく見てみると講談社の「わくわくライブラリー」というシリーズに収められていることがわかる。なので、今後はこっちのシリーズからも選んでみるといいかもしれない。
なお、こういった本を選ぶコツは、子どもたち自身も意識するようになるといいと思う。特に、本を書いた作家を意識することは大切だと思う。どうしたら意識を向けさせられるかは、これからの課題だけど。
それと、読書は理想的にはジャンルの幅を広げることも重要だと思うのだけれども、これもあまり出来ていない。娘は基本的にフィクションばかりを読んでいる。「コツ2:同じ作家の作品を探す」で、お気に入りの作家さんがフィクションとノンフィクションの両方を書いているといいのかもしれないけど・・・児童作家の皆さん、よろしくお願いします。
ライバル登場
さて、ここまで主に娘の読書のことばかりを書いてきたが、2歳下の息子のほうも気になっている。息子のほうは、日本語の本をあまり読まない(ということは、以前の記事にも書いた)。読むのは、マンガの「ドラえもん」ぐらいだ。
ちなみに、前編で取り上げたクラッシェンの『読書はパワー』によれば、マンガの読書も言語能力の向上に効果があるらしいし、マンガの読書がその後の活字の読書につながることもあるらしい。
また、図書館に通うようになって娘が読書にはまり出したのは小学校2年生のことだったので、小1の息子は、まだ早いのかもしれない。先の猪原氏の本で言っていた「最低限の水準まで高まっていることを確認した上で」ということでいえば、まだ「最低限の水準」に至っていないとみることもできる。
ただ、絵本ぐらいは読んでもよさそうなものなのに、興味を示してくれないので、心配はしていた。
そんなとき、「ヨンデミー」というオンラインの子供向けサービスを見つけた。
このサービス、いろいろな児童書をAIで分析し、そのレベルがデータベース化されているらしい。そして、それにもとづき、子どもにぴったりの本を選んでくれる。なお、英語圏の読書アプリのようにアプリ上で読めるというわけではなく、お薦めされた本は図書館で借りるなり買うなり、自分で調達しなければならない。そのようにして読んだ本について、子ども自身がサイト上で質問への答えを入力していく。難しかったか易しかったかとか、面白かったかとかだ。
これを今、息子にやらせてみている。まだ始めたばかりで無料のトライアル期間中だが、今のところお薦めされた本(今はまだ絵本のレベル)をほぼ毎日しっかり読んでいる。うまくいっているのだと思う。(宣伝のようになってしまいましたが、別にこの会社からお金をもらって紹介しているわでではないです。)
このサービスは、私がやってきたような子どものための本選びを、AIが代わりにやってくれているようなものだと思う。
私はふだんから子どもの本選びを熱心にやっているので、そんなパパは他にいないと妻から言われたりするのだが、子どもの本選びは私自身好きでやっている。なので、ヨンデミー先生の登場は、私にとっては強力なライバルの出現のようなものだと思っている。負けられないと思っている。
おわりに
前編・後編にわたってずいぶん長々と書いたが、読書や図書館だけでこれほどたくさん書きたいことがあるのは、私自身がたぶん、読書や図書館という空間が好きだからなのだと思う。だから、静かに本を読んでいる子どもたちを見るのも好きだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
