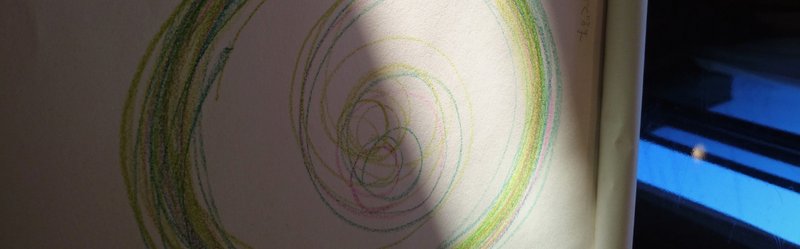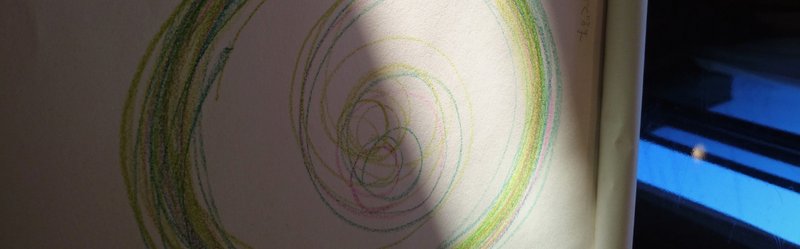○をつける、てことが無粋におもえてきた
ずっと慣れ親しんできた方法だけど楽曲が次々並んでいるテキストを順番に生徒に弾かせて「できたら」○をして次のページをめくる。
ほぼ無意識に繰り返してきたこの方法も疑問に思い始めました。
いや、うすうすかんじていながら、手放せないだけ、なんですが。
子どもたちにとっては、○をしてもらう、というのは先生に認めてもらった、とい思えるし、お母さんも褒めてくれるから、嬉しいのでしょう。わーい、なんて手を上げて喜んでくれると、私の方もいい気持ちになります。○をつけて次へ進むというのは推進