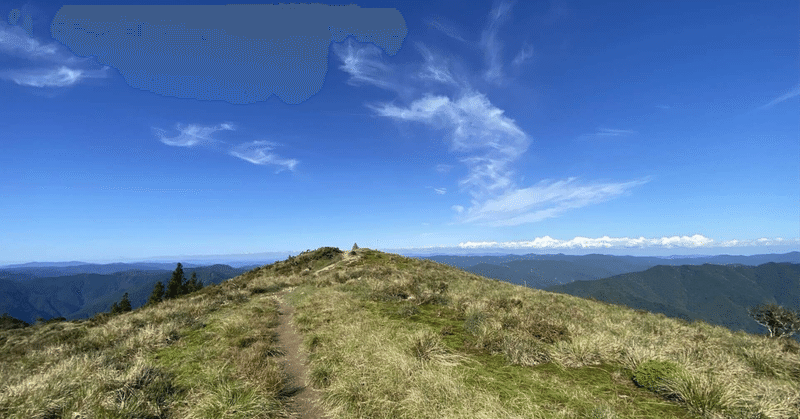
【ボイトレ】「うたうこと」について読み解いてみた Part6【「第2章 まず聞く、それから知る」p21 1行〜p22 20行】
本ブログは以下の2冊について取り扱い、私の理解をシェアするものです。
・1冊目
フレデリック・フースラー、イヴォンヌ・ロッド・マーリング著
須永義雄、大熊文子訳
『うたうこと 発声器官の肉体的特質 歌声のひみつを解くかぎ』
・2冊目
移川澄也著
『Singing/Singen/うたうこと F・フースラーは「歌声」を’どの様に’書いているか』
お手元にこれらの本があると、よりわかりやすいのではないかと思います。
今回は第2章のまず聞く、それから知る p21 1行〜 に入っていきます。
第2章 まず聞く、それから知る (p21 1行〜)
今回の三行まとめは以下のとおりです
・まず「聞き分ける」能力を鍛え、その後に知識をつけること。
・現代の人間の聴覚は衰えており、訓練する必要があること。
・声はいつも「聞いたことを真似すること」で訓練されてきたということ。
1.まず「聞き分ける」ことを覚え、その後に知識をつけること。(p21_1
〜14)
第2章のはじまりは、
’この本はもともと歌手と教師に向けたものである。’
という一文から始まります。
そして次の文
’その目的は、実際的な見地から、歌うときに声を出すことについての諸問題を、できる限り明らかにしようと試みることである。’
ここから読み取れる意図は、あくまでこの本はフースラーにとって「実践書」である。ということです。
これは解説版でも同じ様に表現され、度々触れられています。
そして続けて本文に入ります。
まず、’’具体から抽象へと進むことを強く要請したい’’
この文はわかりにくいですね。
これはその続きにある内容、すなわち’’言いかえると’’の続きを読むと解決するのですが、わかりやすく翻訳するならば
’’実際にあるものから理論的なものへと進んでいくこと’’
というのが適切だと解説版でもされていますし、そのように読んでよいと考えます。
そしてその言い換えとして、章題にある通りいきなり、
「まず聞き分けることを覚え、それから後に正確な知識へと進むこと」
と述べられています。
「異なった音質をはっきりと聞き分けられるまでに耳の感受性を高めなければならない。」
「歌声に含まれるさまざまな音響的現象を聞いて、はっきり区別できるようになってはじめて、「歌声の中の音響的現象」と「それを作り出している器官」との間の関連性をりかいしにかかってもよいようになるだろう」
14行目までこういった内容が続き、とにかく「聞き分ける」ことができるようになりなさい、といった内容が述べられています。
11〜14行の段落は、あえてものすごく砕いた表現をしますが、
「先に知識をつけてばかりで、聞き分ける能力が無ければ、歌手の役に立つどころか迷惑をかけ、意味のない知識をひけらかすだけになるよ」
といったことが書かれています。
なんとも怖いことです。
2.現代の人間の聴覚は衰えており、これを訓練する必要がある。(p21_15〜26)
1番で、まずは聞くこと、その後に知識をつけること、という「私たちがまず何をしなければいけないか」を指し示しました。
ここでは視覚と聴覚の違い、聴覚の原始性、どういうレベルで鍛えるのか、そんな話がされます。
まず
’’音声生理の科学は、その存在のために視覚のおかげもこうむっている’’
これは、音声学において用いいられる視覚化技術のことをいっていると考えられます。
例えば音声波形をフーリエ変換を用いて周波数成分に分解し、これを解析することでその音響特性を分析したりします。
簡単にいうと、音を数値化して→図を書くことで→視覚化する、ということです。
これは視覚情報に変換して私たちは「考える」ことをしているので、音声生理の科学は視覚にも頼ってるよーというのが理解できます。
そして解説版では「視覚でわかるこうした科学的事実は、実際の歌唱の場では限界があるものでしかない」とし、興味深い例を挙げています。
’’例を挙げれば「歌声の鳴り」という印象を生み出すとされる「4000ヘルツ辺りの倍音」である。「優れた歌い手達の声を蒐集し、共通な性質を調べたら、この倍音が顕著であった」という’音響データ’がその根拠だ。これが、現場においてどう役に立つだろうか。ほとんど聴覚に頼っている現場に電子機器を置けば「4000ヘルツを持つ声」が実現されるのだろうか。’それ’はあり得ない’’(解説版p88_21〜24)
4000ヘルツの倍音を持つ声を出すために「測定機器をおいて4000ヘルツの測定をできるようにしました!」と言われても人間がパッと4000ヘルツの倍音を乗せた声を出せる訳ではないですよね。
人間というのは周りの人にとって当たり前でない信じられない能力を有している方もいらっしゃるので、「かならず全ての人類が」とは言いませんが、一般的には不可能に近いほど難しいことだと言えると思います。
視覚化するだけ、統計をとって分析しただけ、では実際の歌唱の現場で役に立つのは難しいということですね。
続けて15〜21行目は何やら難解な話の展開です。
①目は耳とは根本的に異なる心理作用をする。
②言語発生以前の時代の能力の高さを比較すると、聴覚は視覚よりもはるかに原始的な感覚である。
③耳はもともとの性質として、原因と結果を区別するための理解力を持っていない。
④もっぱら想像力によってのみ最初の原因を引き出すことができる。
順番に、理解しやすく言い換えたバージョンを太字で書いていきます。
①=目と耳は根本的にことなる知能活動をする
②=聴覚は視覚よりも原始的な感覚で、より直感的なものだ。
③④=直感的なものである聴覚は、想像で情報を補う。
順番に①の「心理作用」、これは原著英語の「mentality」にあたり、
精神活動、知能、ものの見方・考え方、といった意味がある言葉です。
作用というよりは、目と耳の使い方の違い、といった表現と受け取るのが理解しやすいと考えますので、ここは「知能活動」と表現をするべきと考えられます。
(解説版も同様の表現をとっています。)
それを前提として、②に入ると、
そもそも視覚と聴覚を比較すると、聴覚って原始的で直感的だよね、といった内容につながっていきます。
まず「原始的」、これは様々な捉え方があると考えられますが、ここでは小型の哺乳類であったと例を挙げている解説版の例えを元にお話しします。
大型の哺乳類と比較して、素早く身に迫る危機を察知する必要があることを考慮すると、聴覚も鋭くなければ生き残れません。
であれば、聴覚能力が高い動物が生き残り、子孫を残していくと考えると、自然淘汰説とも辻褄が合うと考えられます。
非常に長い進化の過程で、そういった時代を考慮に入れるならば、それは原始的であったと言えます。
そして小さな哺乳類であったということは、脳も小さい=思考能力も今よりも発達していないと考えられます。
そして「直感的」、これは先ほどの「原始的」を踏まえるとわかりやすく、小さな哺乳類、現代にも生きる種で例えるとネズミなどでしょうか。それらは聴覚で危機を察知した場合、素早く逃走していくのは想像に容易でしょう。
これは論理的に思考した結果というよりは、直感的に「音」から「危機が近づいている」と想像した結果と考えられます。
少し別の例えにはなりますが、原始性という考え方をしていく時、人間が母体の中で育っていく過程を考えると、耳は比較的初期の段階で作られるようです。
さらに、生まれる前の母親の体内にいる状態の赤ちゃんはすでに耳が聞こえているという話もあります。
この「原始性」という言葉には様々な捉え方があります。
ここについてはある程度想像の余地が残されている箇所と捉えても良いと考えます。
そして次の、「最初の原因」、というのはその音の原因、と捉えるとわかりやすいです。
例えば誰かがグラスを落として割った、そういったことが起こった時にその現場を目撃できなかったとしましょう。
グラスを落とした(最初の原因)
→パリーン!と音が鳴った
→聴覚情報が耳に届いた
→音から、「グラスが割れた」と想像する。
実際に起こった時はおそらく視覚情報を手に入れようと人間は周りを見回すと考えられるのですが、このように聴覚情報しか手に入らない場合、音からグラスが割れたと想像するしかありません。
ただし視覚情報を得ていた場合、すなわちグラスが落ちる瞬間を目撃していた場合は、「グラスが落ちた→だからパリーンと音が鳴った」といった具合に、原因と結果を容易に結びつけることができます。
そこに「想像力」は必要ありません。
このように、聴覚は想像力を使って情報を補っていることが、視覚と違って直感的な能力と言える点と考えられます。
さて、例え話で大きく脱線してしまいました。
改めてここでフースラーが述べたいと考えられることを解読した内容を並べますと
・聴覚は視覚よりも原始的な感覚である。
・なぜなら、哺乳類は大昔に遡れば夜行性であった。
・聴覚は直感的な感覚で、何か起こった時、想像力で情報を補う必要がある。
・対して視覚は何か起こった時、何が起こったのかを視覚と思考で情報を整理でき、想像力は必要ない。
といったことが述べてあると私は読解しています。
そして、その原始性を失っているからこそ耳の能力は本来の能力よりも衰えており、故に「まず聞き分ける」、すなわち、まず耳を訓練しろとフースラーはここで述べています。
実際に「音」に対する人間の聴覚とその能力が、視覚に比べて具体性に乏しい情報がoutputされるのが一般的と思います。
もう一度、今度は違う例を挙げますと
視覚を使わず「聴覚情報」のみを手に入れた時、その音が具体的に「何の音」なのかがわからない場合は「重い、大きい、響いている…」このように、印象レベルの情報まででとどまる場合が多いと思われます。
対して「視覚情報」でその音源の情報を手に入れた場合、もっと具体的に「大きな筒に膜が張られている、その膜を棒でもって叩いている、そしてその膜が振動している」と、例えば太鼓の音が鳴る一連の原因と結果の情報を手に入れることができます。
(実際に初めて太鼓を見た人間がそこまで分析できるかどうか、と考慮するとまたややこしくなってしまうのですが…)
聴覚情報と一緒に視覚情報を得ることでどんな状態のものが、どうなって、どのような働きをするのか、そういった情報の整理ができます。
そしてフースラーのいう結論、どういった具合に聴覚を鍛えなければならないのか?
それは25、26行目にあり、
’’耳と、思考し理解する目との間に連結ができるようになるまで訓練されなければならない’’
なんともわかりにくいなと私は感じる文ですが…。
ややこしい部分を取っ払うと、すなわち
「耳」と「目」の間に連結ができるようになるまで訓練せよ。
ここからはこれまでの記述からの推察も含まれます。
視覚と聴覚に隔たりがあり、視覚情報からは思考し理解することができる、一方で聴覚からではそれが難しい…という話を展開して、「聴覚は原始的」で本来はもっと鋭かった、といった話を前提としています。
ここから推察できることとして、もっと聴覚で情報を手に入れなさいということが言われていることは確かです。
連結という言葉はおそらく、視覚情報で「思考し理解する」ことが人間にはできるので、そういった能力を耳とも連結させよ、ということを述べているのだと考えられます。
私の読解での結論はこうです。
『聴覚情報だけが耳に入ってきたとしても、まるで目で見えているかのように感じ取って思考し理解することができる、そういうレベルまで訓練せよ』
わかりやすく声の話に変換すると、
「声が聴覚情報で入ってくる」、そしてその音の情報から「発声器官の働き方を思考し理解する」(まるで発声器官の動きが見えているかのように)
ということです。
3.歌っている時の声の調節は「耳で聞いている」+「内部知覚している」(p21_27〜p22_12)
まずここは「最近の音声研究の業績の中にある記述」にある『歌っている時の声の調整は耳を通して行うのではなく内部知覚している』といった文章から始まります。
これまでの「聴覚を鍛えよ」といった旨の内容とは相反することが書かれています。
フースラーはこれについて’’この文章は事の半分しか言っていないので誤解を生ずる恐れがある’’とし、補足をしています。
まず「声の質」とは発声器官が働いた結果が、音となって現れたものであること。
そして歌手はその「出音」から、発声器官の働いた過程を読み取っているとしています。
要するにまず自分の声を耳で聞いて調整していると言っています。
そして続けて、「内部知覚」に触れています。
発声器官が働いた時に生じる音響現象は衝撃、刺激を与え、それによって「内部知覚」が発動すると。
要するに、歌う時の声の調整は耳で聞いて発声器官の働きを読み取って、内部知覚によって調整しているのだと言いたいのだと読み取れます。
4.大事なのは声はいつも「聞いたことを真似すること」で訓練されてきたという事実。(p22_13〜20)
ここは、邦訳をそのまま読むと「???」となってしまう箇所かと思います。
ですがここで述べていることは要約するととてもシンプルです。
聞き分けること、すなわち聴覚能力の大切さをこれまで述べてきています。
ここでもその話の続きです。
訳文らしい読みにくい言葉が多いですが、一つずつまとめると以下のようになります。
「聴覚は発声器官よりも古い器官。」
「発声器官は、聴覚のコントロールの元に発達してきた。」
「正常な発声を行うには、聴覚のコントロールが必要」
そして、それに続いてこの話の核でもある大事な部分が出てきます。
’’簡単な事実は、声はいつも聞いたことをまねることによって訓練されてきた’’
これはおそらくボイストレーニングをしたことがない方にもわかる内容ではないでしょうか?
話す声と歌う声で違いはありますが、どちらも訓練されていく過程は常に「聞いたことを真似する」ことであると言えます。
赤ちゃんの発話の習得についても、大人が使っている言葉を真似して発話することから始まります。
(ぱぱ、ばば、あぶ、などはまだ子音の形成が難しい段階の赤ちゃんですから、私たち大人の言う「真似」にはなっていないかもしれませんが、発話することが模倣であると私は考えています。)
そして小学生、音楽の授業の時間で歌を練習する時も、先生の歌声や、ピアノでとられた音程を真似して歌うことから始まります。
このように、モノマネ、真似、すなわち模倣はいつでも発声器官が訓練される過程に存在しており、ということはそもそも「聞こえている」という前提があるのです。
これがフースラーが「まず聞く」とする理由の一端を担っているのは確実かと思います。
そしてこの章はカナリヤの例え話と「ろう唖」の話が出て終わります。
・カナリヤの卵が雀によって孵された時は、歌う能力のある鳥にならない。
・聴力のない人は、発声器官を持ってはいても、声はない。(ろう唖)
後半については補足します。
ろう唖、漢字で書くと聾唖です。
聾は耳が聞こえないこと、唖は話せないことを意味します。
乳幼児期に聴力を失い、高度の難聴のため言語不明瞭、会話困難の方は聾者と呼ばれます。(現代では手話などで会話ができておりますので、聾唖という呼び方は憚られる側面もあるようです。)
フースラーはこれを「声はない」といった表現を用いていますが、現代的に言うとこの表現はやや過激です。
この本が書かれた当時はこういった身体障害者…現代では「障害」と言う言葉も用いなくなってきていますが、当時はこういった表現が少し緩かったのだと推察できます。
こう言った方々は確かに手話などで会話ができますし、発話ができる方もいらっしゃいますが、言語が不明瞭となる場合もあります。
そう言った場合を考慮すると、やはり耳が聞こえないということは発声器官の成立に対して大きなハンデを背負った状態になってしまいます、というのがここでの例え話と受け取ると良いと考えます。
さて、今回は第2章、まず聞く、それから知るについて解説してきました。
聴覚を鍛える…あるいは本来の鋭さを取り戻すとも言うべきでしょうか。
その重要性について説かれているのが第2章と言えます。
私もモノマネボイトレと銘打って、モノマネをするボイトレ(そのままですが)を以前発信したことがありますが、こういったものが背景にあります。
あまり「聞く」ことを意識していなかったという方は、一度意識してみてはいかがでしょうか。
次回は第3章に入っていきますので、よろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
