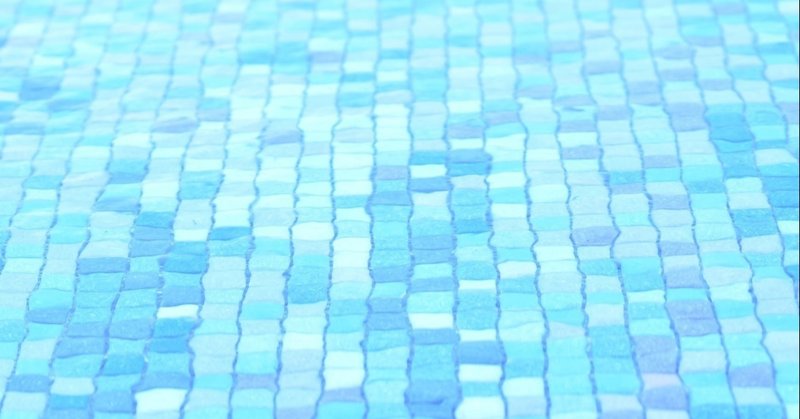
いろいろなひとの(きょうの本)
最近は、仕事にいっていない日は家にいるか、近所にあるいついってもひとがいないがらがらの映画館にいくかくらいかしていないので本を読むのもはかどります。
今回はまずこちら。
李琴峰『星月夜』。
台湾出身の日本語講師とウイグル出身の留学生が東京のW大学で出会い、というお話。
女性同士の恋愛、国籍の違い、それぞれの経済状況、学問に向き合おうとするとき立ちはだかるだろう男女差、あとほかにもいろいろと、台湾出身の先生とウイグル出身の学生というカップル(という言い方もこのならびであげるとなんだかちがうような気もするのだけれど)を軸にして立ちあらわれるいろいろなひとたちのいろいろな差が描かれています。
この作品に登場するひとたち、ことにこのふたりのカップルの置かれた状況を手荒くひっくるめてしまうやりかたになりそうで気がひけるのですが、彼女たちが外国籍をもって日本に滞在しているひと、ということとして、ひきくらべてこの文章を書いているわたしは日本国籍をもって日本に居住している者です。
このわりとおおざっぱなくくりでもって、彼女たちを少数派、わたしを多数派として、そうした立場でわたしはこの小説を読みました。
彼女たちを国籍が日本ではない、というおおざっぱなくくりでマイノリティとしてしまうとそれはそれで彼女と彼女の国の違い、背景の違い、状況の違いにもふたをしてしまうことになるのですが、そこはべつの目線から小説のなかできちんと書かれているし、読者としてのわたしもたぶんそれは読みとれている……はずです、たぶん、小説読むのあまりうなくないけどたぶん大丈夫読みとれてる。
と、くだくだしく話してはおりますが、要するに、日本国籍をもって日本に居住している、おそらくはこの国の多数派としてひとをも身をもとらえられているうちのひとりであるところのわたしは、この小説を読みながら、少数派としての彼女たちの境遇をおそらくはまったく理解しないまま多数派としてなにひとつ苦労もせずにこの国に住まうことができているのだということにいまさらながら、ほんとにいまさらながら思い知らされ、そしてとまどっています。
もうかなりむかしのことになるけれど、きっとわたしも大学生のとき、きっとキャンパスのなかに確実にいただろう「柳先生」や「ユーリートゥーズー」のまわりで、彼女らのわからない、聞き取りにくい言葉で笑ったり話したりしていたのだろうなと、この作品を読みながらおもいました。
小説を読むとき語り手に自分の姿を見るのはわりとよくあるパターンですが、この物語はどうにもちがった。
わたしはむしろ、ここに出てくる柳先生やユーリートゥーズーの背景にいる日本人学生たちにかつての自分の姿を見ていました。
もしくは道をたずねにきたユーリートゥーズーを連行した交番のおまわりさんや警察にいたひとたちのなかにもわたしはいるのかもしれません。かもしれませんなんて体裁のいいことを言ってはいますが、彼女が連行されるところをみかけてそれはおかしいと声をあげないかぎり、いえ声をあげたとしても、わたしはユーリートゥーズーにとって交番のおまわりさん側の人間なんだなとそんなことをおもいました。
マジョリティは自分とはちがう立場の人間の境遇を知らないでも生きていけるし、それゆえにマジョリティなのだとおもいます。
自分がマジョリティとしてあたりまえのように暮らしている世界に、そうではなく暮らしているひとの姿が見えた場合、とまどうよりほかのことが自分にできるのか、わたしにはわかりません。
だって(だって!)自分でその立場を選んだわけでもなく、あなたが安閑として生きているのは既得権だとマジョリティ側のひとびとからいわれてもなにがよそと違いなにがよそより恵まれているのか、自分の立場もよその立場もきちんとわかっていない(ままで生きていくことが可能な)のではっきりさせることもできない。
どうしたらいいのかわからない。
そのうえ、国籍と居住地をもって自分がマジョリティという立場にカウントされるのももちろん一義的なもので、無数のカテゴリが自分のなかにはあって、一本のものさしでマジョリティ側に選別されてもそれだけじゃないことをすくなくとも自分は知っている。
のできっと、「そんなこといわれたってわたしだってあの場合だったら少数派っぽいしこの場合だってこんなだしこまってることはたくさんあるし」と反論したくなる、ときもあるかもしれません。
といういいわけをあれこれくりひろげたところでわたしは日本国籍をもち日本語を話し代々さかのぼってもたぶん500年くらいは先祖も日本に生きていると証明できる時点で、日本においてはかなりのマジョリティです。
だからこの小説を読んでいるあいだ、マイノリティであるところのユーリートゥーズーや柳先生などのマイノリティにカテゴライズされるひとたちのふるまいや状況を知り、マイノリティのひとたちに「責められている」ような気がしました。
というとちょっと相手に責任をなすりつけていすぎていてずるいかな。
うん、めっちゃずるいな。
柳先生もユーリートゥーズーも、わたしになにも強いてはきません。
彼女らはただあるがままをわたしに見せてくれている。
そしてわたしはそのあるがままの世界に、マジョリティとしてうしろめたさを感じてしまう。
自分はマジョリティなのだと認めることはこんなにも責任が重いことなのかと、逃げだしたくなるようなきもちでした。
と、長々と国籍についてのみ語ってきましたが、はじめに申し上げましたとおり、この作品は国籍のほか恋愛(ていう言い方もたぶんなんかちょっとちがうんだけど)、経済状況など登場人物たちのあいだにある差はさまざまであり、みなたがいにあまり重なるところがありません。
マイノリティだとかマジョリティだとか、いろいろなカテゴリのなかで立場がくるくると入れ替わり、それぞれの差が浮き彫りになっては沈んでいく。
最近のニュースやSNSなどを見ていると、ひとそれぞれの差や違いについてあれこれ語られるたびに「もういいよ、そういうのどうでもいいよ」と癇癪を起したがったり「平等なんかない」と諦めるひと、というのがすくなからず見受けられるような気がします。
そういう発想もまた、それぞれのひとたちが真剣にものごとに向き合おうとした結果なのかなと最近はおもいます。
この小説では描かれるたくさんの差にたいして読者が「もういいよ」と投げやりにならずに済むように、というか、それぞれの登場人物たちのありかたが丁寧にえがかれているので投げやりになるまえにそれぞれの姿が読み手のなかに染みていくというか、うまく言えませんがなんだかそんな感じでした。
よい小説でした。
なんだかときどきちょっと急にお行儀がよくなるというか、日本文学の王道パターン、みたいなのが骨組みにあって、そのなかで国や恋愛や経済状況や、といういまどきのものが描かれているところの味わいがなんだかちょっとふしぎな感じもしました。
なんだかたくさん感想を書いた。
おもしろかったです。
李先生のほかの作品も読んでみたいです。
あとはいろいろ。
塩見鮮一郎『差別の近現代史』。
ドロシー・L・セイヤーズ『ピーター卿の事件簿』。
三田誠『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿』4.
田野大輔『ファシズムの教室』。
江戸時代の被差別部落や貧困などを基盤に書かれた「差別」の本を読んでから20世紀なかごろにイングランドで書かれた英国貴族の華麗なる推理(日本語に訳されているとはいえ身分差も階級差も人種差もわりと「おおらか」に出てくる)を読み、そしてつぎに読んだ21世紀初頭に日本で書かれた英国貴族はポリコレに配慮しているなあ、『差別の近現代史』で描かれたキリスト教の正統と異端という点でも対をなすなあとおもい、それから関西の私立大学で行われていたファシズムの体験学習のレポートを読み、それぞれの違いとか、時代の推移について思いを馳せました。
たぶんそれぞれあまりつながりのない本のなかに、ふと相似形をみつけるときがあって、そういうところもおもしろかった。
読書ってたのしいね。
うまれ、育ち、暮らし、ものごとの見方、いろいろなものがちがうひとたちが生きている、そういう社会でわたしも生きています。
わたしの書いたこの文章も、こうしてネットに発表した以上きっとだれかの目にとまり、そうしてそのひとのなかにあるものとつながって、わたしの意図とはべつのなにかにきっと変わっていくのでしょう。
それでいいのだろうなと、そんなことをおもいつつ、けれど「みんなちがってみんないい」などとさかしらに唱えるだけではなにひとつマジョリティとしての責任は回避できないしなにひとつさきに進まない、すくなくとも現代の日本ではと、そんなことをおもっています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
