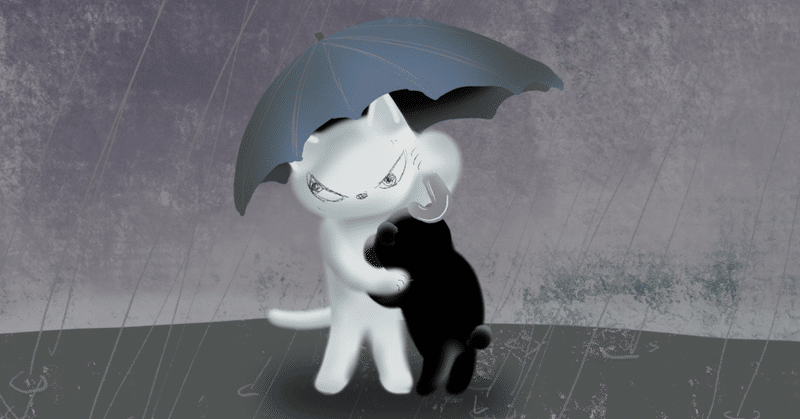
生きる意味をデザインできるのか? #316
今回の記事は私の仮説が多いため、ご了承ください。
Spirituality Designとの出会い
『システミックデザインの実践』の共著者であるクリステル・ファン・アール氏が、「システミックデザインの次にはSpirituality Designが来るだろう」と話していた。ここでのスピリチュアルは、非科学的な現象というような意味ではない。「sense in life」や他者や自然とのつながりという文脈で話していたことから、ここでのspiritualityは「生きがい」や「生きる理由・意味・意義」というニュアンスだろう。
spiritualiyがデザインの対象となるのか疑問に思うかもしれないが、デザイン思考の書籍にも『スタンフォード式 人生デザイン講座』や『スタンフォード大学dスクール 人生をデザインする目標達成の習慣』などがあるように、人生をデザインするというのは珍しいものではない。
ただし、これらは「どう生きるか」というHowに注目している一方で、Spirituality Designでは「なぜ生きるのか?」というWhyに注目しているという違いがありそうだ。まだ具体的な方法論や豊富な事例があるわけではないようだが、デザインで扱いたいテーマを言語化してくれていると感じられる経験だった。
宗教と科学の対立、誰もが実存に悩む時代へ
クリステル氏がSpirituality Designが重要になると考えている理由を推察するために、歴史的な背景から考えてみる。
近代はデカルトなどから始まる科学の時代だった。宗教が科学から矛盾や誤りを突き付けられて信頼を失い、科学的であることが重宝されるのが近代。現代もその延長線上にあると言えるだろう。「とある宗教で言われているから」よりも「科学的にこう言われているから」と言われた方が納得しやすいはずだ。
科学が宗教の代わりに信頼できる情報を与えてくれるようになったが、これらは「どう生きるべきか?」までは教えてくれない。科学では確率・統計的な因果関係を教えてくれるが、その行為をするべきかどうか、同様の因果関係が自分にも当てはまるのかまでは示してくれないからだ(主観やn=1は非科学的だから)。科学によって「神様」のような絶対的に信じられる存在を失った人々は、生きる意味や指針を失ってしまった。
そんな時代の流れと相まってか、哲学には実存主義というテーマも誕生した。哲学と言えば「真善美」のような万人が納得できる真理・本質を探究するというのが王道だが、「私にとっての真理を知りたい」「私とは何か?」「私はどう生きていけばいいのか?」という「私」に焦点を当てた実存主義というものもある。代表的な哲学者・思想家には、キルケゴール、ニーチェ、ハイデガー、サルトルなどが挙げられる。
哲学では百年以上前からこの問いに向き合い始めているが、今の時代では哲学者以外の人も実存的な問いを考えるようになっているのではないか。物語でも「私らしく生きよう」という結論になる例をよく見かける。でも、そもそも「私らしい」とは何だろうか? アニメやドラマの登場人物が見つけていく「私らしさ」も、作者という神様が決めた生き方を選んでいるように見えてしまう。一方の現実世界を生きる私たちは、終わりなき実存的な苦しみからは逃れられないままだ。
宗教にも資本主義にも頼れない
ニーチェの「神は死んだ」という言葉は、一度宗教(キリスト教)が絶対的な真理ではないと知ってしまったならば、心から信じることはできないという意味に解釈できるだろう。まさに彼が予測したように、絶対的に信じられる存在を失った世界はニヒリズムの時代に突入した。
宗教を信じられなくなった後、代わりに資本主義を信じることになるのだろうか。多くの宗教が禁欲的な教えを採用する一方で、資本主義は欲望に忠実であることを推奨するため人口に膾炙しやすい。そして、欲しいものを手に入れたいならばお金を稼がなければならないというシステムに参加するようになる。そもそも資本主義を信じる信じないにかかわらず、お金が価値あるもの(交換価値のあるもの)という社会的な合意からは逃れられない。
ただし、行動経済学などの研究によれば、一定程度までは収入の増加が幸福度に寄与するものの、それ以上は幸福度との相関はあまり見られなくなるらしい。それよりも人間関係が幸福度や健康につながるという研究結果もある。「お金を稼いで欲しいものを買えば幸せになれる(かも)」という資本主義の前提も「なぜ生きるのか?」という問いへの答えは与えてくれない。
というわけで、「なぜ生きるのか?」についての答えは各々に委ねられている。数多ある宗教から自分に合ったものを選んで参考にすることもできるだろうし、資本主義の中で経済的成功や経済的自立(FIREなど)を目指すのもアリだろう。どちらにせよ、やはり結論は「あなたが好きなように生きればいい」となり、「私らしさとは何か?」という問いとの堂々巡りになってしまう。これが実存的な問いの難しさであり、哲学で問われ続ける理由だろう。
デザインに頼るならば(卒業制作を例に)
「生きる意味はあなた次第」という現状にデザインで何ができるのか? 私の卒業制作の取り組みを例に書いてみる。まだ試行錯誤の中にあるが、その一端が垣間見えれば幸いである。
パーソンズ美術大学・Transdisciplinary Designの卒業制作ではテーマを自分で決める必要があったのだが、その過程で「自分の生き方や生きる意味を考えるような実存主義的な視点に重きを置いたデザイン」という言葉を書いていた。従来のデザインが「世界を変える」という立場なのに対し、「私を変える」というデザインを提案しようとしていた。
ただ、このテーマはデザインとして参考にできる先行研究が見当たらず行き詰まった。そのため、より現実的なテーマ設定に絞っていくようになり、「私とは何か?」という漠然とした問いを「日本人がデザインを学ぶとはどういうことか?」という問いに言い換えていった。こうして、西洋由来のデザインと東洋由来の禅を掛け合わせるという内容にたどり着いた。
最終的には注意経済を促進するようなデザインを疑いたいという主張でまとめることにし、テーマもデザイン倫理とした。もちろん私が興味のあるテーマであり自信作であることは間違いないのだが、私の興味のほんの一部分を表現できたに過ぎないとも感じる。「日本人のデザイナー」としての実存は見えてきたが、未だ「私」の実存は揺らいだままだ。
まだSpirituality Designの定義が明確になされているわけではないので、私の目指すデザインをそう呼ぶのは時期尚早だが、他のデザインよりは言い表しているのではないかと期待している。
まとめ
Spirituality Designという言葉がこれから普及するのかは予測できない。興味を持つのも「私が生きる意味って何だろう?」と考える人だけだろうから、メインストリームなデザインになるのは難しいのかもしれない。
それでも、朝起きる理由が見つからないような人はこの世界に数%はいるわけで、こうした実存的な苦しみに向き合うデザインの需要は必ずあるはず。少なくとも私自身は求めている。これが人間の根源的な苦しみならば、私以外にも求めている人がいるはずだ。
いただいたサポートは、デザイナー&ライターとして成長するための勉強代に使わせていただきます。
