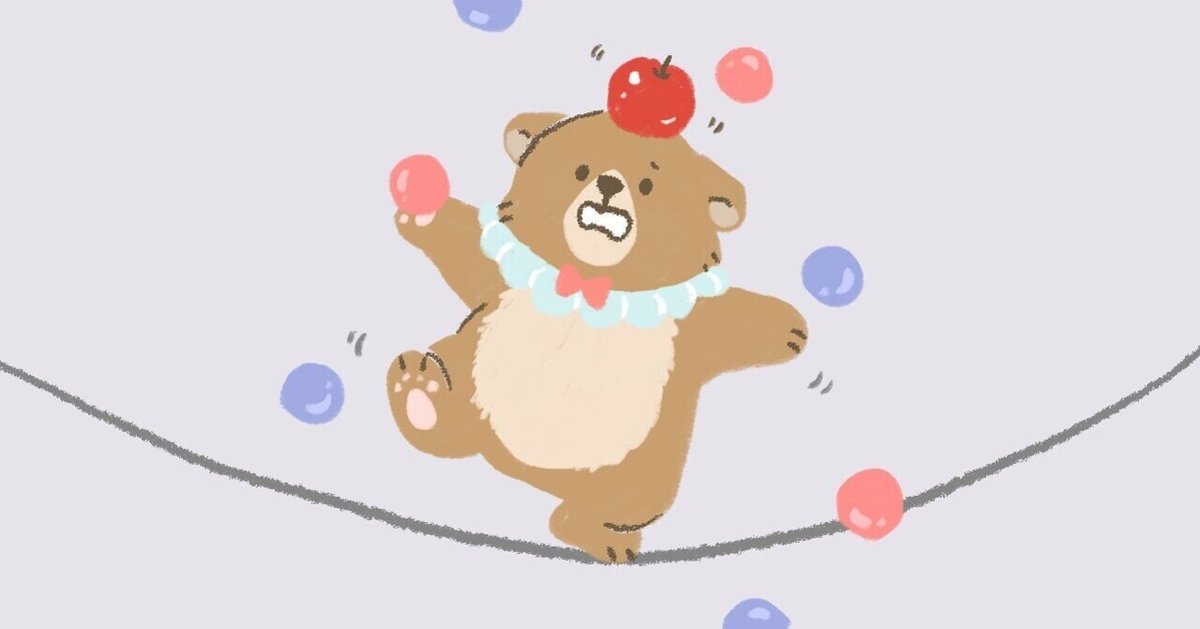
パフォーマンスデザイン "Performance Design" #122
自己紹介はこちら
前回の記事でスペキュラティブデザインの立ち位置を表した図を紹介しました。この図を見た時にアートとデザインの関係性に興味を持ちました。MoMAを訪問して現代アートを鑑賞したことも影響しているかもしれませんが。

そんなこともあってアートについても自分なりに少し調べていくなかで、パフォーマンスアートというアートの一形態があることを知りました。
この動画で紹介されているマリーナ・アブラモヴィッチさんのTED Talkも見つけたので共有します。
アーティスト自身もアートの一部として参加している「イベント」を展示して、それを鑑賞した人に何かを感じてもらうというパフォーミングアートの手法と、スペキュラティブデザインやクリティカルデザインの手法の類似性を感じています。
「行為」よりも「存在」
こちらの動画は、吉田松陰や孔子、イエスキリスト、ガンディーなどが歴史に残した功績から「影響を与えるとは何か」について話したCOTEN RADIOの雑談回です。要約すると以下のような内容でした。
・資本主義では目に見える成果を短期的に出すことを求められるけど、長期的な影響は行為ではなく存在からもたらされる。
・ある現象がいいか悪いかも、簡単には評価できない。
・自分がエネルギーが出ることをすればいい。
・存在が「極端に何かを示唆する」と他人に大きな影響を与える。ある生き様の人間の存在を知ることが人間に影響を与える因子になる。
・たとえ人生で何もしなかったとしても、それがどう影響していくのかは誰にもわからない。
この話から思ったのは、デザインそのものが社会に影響を与えるという側面はもちろんあるけれども、そのデザインをするデザイナーの考え方や生き様も社会に影響を与えるという視点もあるのではということです。
デザインはあくまでもデザイナーの思想(それが意識的であれ無意識的であれ)を人に伝えるための「インタフェース」であるという考え方です。
パフォーマンスデザイン?
パフォーマンスアートと「存在」の持つ影響力の話の2つから、デザインにもパフォーマンス的な方法があるのではないかと思いました。
パフォーマンスアートがアーティストの体や動き自体がアートになるのならば、デザイナーがデザインを使って問題解決に取り組んでいるということ自体がデザインではないかという仮説です。
すると、パフォーマンスデザインではデザイナーのライフスタイルや生き方自体もデザインになる。つまり、単発的なイベントではなく、人生という数十年にもかけて続く長期的な現象を通して社会をデザインするという考え方です。
現代のデザイン界においては、脱植民地化やジェンダーに関する問題に対処する際に、デザイナーの当事者性が問われます。デザイナーの立場とデザインが切っても切り離せないことが指摘されているのです。
自分自身の生き方を省みること、自分の生き方を通して社会を良くしようとする試み、そして、自分が「良い」と信じる生き方を貫いているという自分自身の人生そのものを「パフォーマンスデザイン」と呼べるのではないかと思ったというお話でした。
この記事が参加している募集
いただいたサポートは、デザイナー&ライターとして成長するための勉強代に使わせていただきます。
