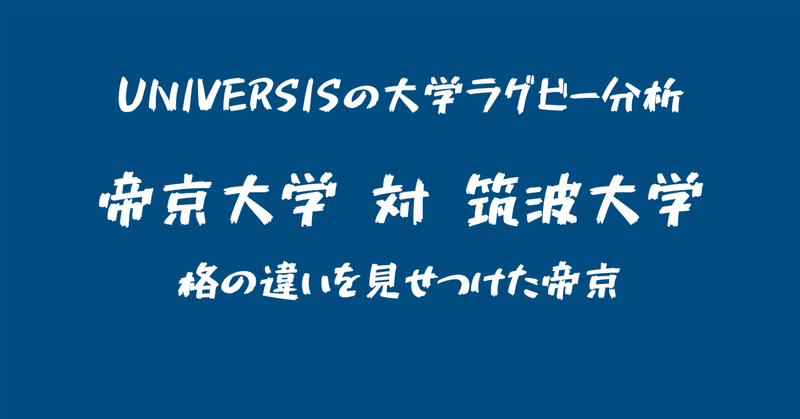
2023大学ラグビー関東対抗戦:帝京対筑波を簡単な数字で見てみた
みなさんこんにちは
悔しさのあまりふて寝していた今本です
今回は10/15に行われた関東大学対抗戦、帝京大学対筑波大学の試合についてレビューをしていこうと思います
それではメンバー表から

次にスタッツです

うーん、悔しい
順番に見ていきましょう
帝京大学のアタック・ディフェンス
帝京大学のアタックシステム
解説に入った栗原さんもおっしゃていましたが、正直今の帝京が他のチームに対して苦労するビジョンが見えないですね
筑波がうまくいかなかったことも影響しているかと思いますが、大学カテゴリーで敵がいるのかというところが本気で気になってくるくらいには強さが圧倒的です
システム的には1−3−3−1を基準として9シェイプに3人のFW、10シェイプに3人のFWをそれぞれおいてSOの井上選手などのゲームコントローラーがその間のパスをコントロールしてアタックを組み立てている形をとっています
アタックはものすごくシンプルなのですが、帝京の恐ろしさはその実行力の高さとチーム全体のラグビー理解度のアベレージの異常な高さです
目立っているのは各選手の体の強さになってくるとは思うのですが、個人的に見ていて感動するのは選手のチーム戦略の理解度の高さにあり、各々の立ち位置にエラーがほとんど起きないのが脅威的です
どのような崩れたシチュエーションやチャンスのシチュエーションでも選手のポジショニングが的確かつ早いセットとなっており、味方選手と被ったり非効果的な位置に立つような状況はほとんど見られませんでした
パーフェクトすぎて怖かったです
基本的なゲームメイクの流れとしてはFW、特にタイトファイブと呼ばれる1〜5番の選手のコンタクトを中心に接点で上回り、バックローに入った選手が要所要所でバックスラインに参加したりすることでシンプルなアタックの中に強度的なアクセントを付け加えています
BKの選手も体の強さや速さが大学トップレベルを誇っており、主に外のエリアやエッジエリアで相手を振り切る勝負に出ることができていました
また、ブレイクダウンの部分でもクオリティの高さを見せており、オーバーの選手が二人で完結してかつ完全に越え切ることができていることから相手のオフサイドラインを下げたりプレッシャーのレベルを下げることにも成功していました
相手選手の上に立ったり相手よりも後に倒れ込んだりと体のコントロールのうまさから筑波の選手にブレイクダウンで仕事をさせていませんでしたね
キック戦略としてはそこまで凝ったものはなかったような印象で、一般的なLongを用いたエリア獲得と適宜Puntを織り交ぜたゲーム展開を見せており、心理的にも戦略的にもかなり余裕を持った展開に持ち込むことができていたかと思います
帝京のキャリー
強い!
正直その一言に尽きると思います
ただ、その裏には練習やトレーニングに裏打ちされた体の強さと使い方のうまさが潜んでおり、日本人が大学レベルで到達することのできるコンタクトのトップレベルに達していました
このクオリティでラグビーのコンタクトができるのは他のチームの外国人選手くらいだったので、正直今回の試合では衝撃を受けました
誰が目立ったと言えないくらいにコンタクトレベルのクオリティのアベレージが高く、どの選手もコンタクトシチュエーションで必ず前に出ることができており、弾くコンタクトといなすコンタクトを備えている選手も多かったためにコンタクト場面で筑波の選手を圧倒していましたね
回数としてはキャリーがちょうど100回生まれておりキリが良かったですね
その中で11回のトライを生み出していることから、約9回のキャリーごとにトライが生まれている換算となります
今節で行われた早稲田の試合では早稲田がキャリー数の割にトライにつなげ切ることができていなかったため、それと比べてもクオリティの高いアタックをしていたということができるかと思います
細かく見ていきましょう
9シェイプでのキャリーが30回とちょうど30%を占めており、10シェイプでのキャリーが10回と、他のチームに比べると10シェイプを用いたアタックの多さが見て取れます
一方でシェイプ外のキャリーは30回となっており、そのうち中央エリアでのキャリーが13回、エッジエリアでのキャリーが17回と外方向のベクトルを持ったアタック傾向を示していました
帝京のパス
10番の井上選手をはじめ、BKの選手のパスの判断が良かったですね
ロングパスもショートパスも高いクオリティを示しており、相手の勢いを殺すことなく前に出る勢いそのままにパスをすることができていました
また、バックローの中でも青木選手と奥井選手は強さの中に器用さを兼ね備えているような選手なので、少し崩れた姿勢や適切なフォーム以外でのパスも放ることができてましたね
オフロードパス自体はそこまで極端に目立った数値とはなっていませんでしたが、キャリアーがしっかり前に出て相手の体から離れた位置でオフロードをするためミスが少なく、またオフロードパスの質も高いことからかなり効果的なアタックに寄与していたと思います
回数を見ていきましょう
パス回数は155回と多い中でも、キャリー・パス比が2:3とシンプルかつ平均的なアタック傾向を示していました
帝京の強さは凝ったパスや強いキャリーにあるというわけではないということがこの比率からも分かりますね
細かく見ていくとラックからのパスアウトのうち33回が9シェイプへ、25回がBKへと展開されていることから、若干FWに寄った傾向を示しながらもアタック方針としてはBKの選手がアタックに適宜絡んでいるということができるかと思います
1stレシーバーは基本的には10番の井上選手が担っていましたが、時には15番の山口選手が入ることもありましたね
BKに渡った後のチョイスとしては14回が10シェイプへのパスとなっており、一方でバックスライン上でのパスワークは27回となっていました
結構バックスライン上で回しているような印象だったのですが、ある程度コントロールされていることで回しすぎず、必要なタイミングでしっかり外に回し切るということができていたかと思います
Otherも一定数あったのですが、崩れたパスというよりかは流れの中で生まれたうまくカテゴライズすることのできないパスというだけであり、他のチームであるような「うまくいかなかったパス」というようなものはほとんどなかったような印象です
帝京のディフェンス
ディフェンスに関しては意外とタックル成功率が低い形とはなっていましたが、これはタックルの総数がそこまでなかったことあったからかと思います
実際ミスタックル自体は10回に抑え切っていたので、ほぼ完璧なゲーム運びをすることができていたかと思います
ディフェンスとしてはある程度前に出る一般的な傾向を示しており、特に目立ったところとしては相手の9シェイプに対するプレッシャーが強烈だったように思います
FWの選手のディフェンスのクオリティ、特にDFを苦手とすることの多いフロントローの選手も高い成功率を誇っていたように見えました
ダブルタックルの質も一定のものをキープしており、筑波の選手がコンタクトレベルで一歩劣っていたこともあってか相手にほとんど前に出られることはなかったですね
また筑波のダブルタックルと違うところとしては、タックルに入った選手が基本的には相手の上に回ることができているという点ですね
ダブルタックルとはいえ下に巻き込まれてしまうと、次のプレーへの移動が遅くなってしまったりペナルティにつながったりとデメリットも多くなってしまうので、その点ではかなり良いディフェンスをしていました
筑波のアタック・ディフェンス
筑波のアタックシステム
筑波といえばキャリーが少なくてもトライを取り切ることのできるアタック効率の良い傾向を示すことができるチームであることが特徴の一つであると思いますが、今回の試合ではそのトライ効率の陰に隠れた「再現性の低さ」がかなり露骨に出てしまっていたかと思います
筑波のアタックはポッドに拘らない、少し複雑さがありながらも選手のひらめきとスキルでアタックを継続する傾向にあるチームですが、今回は数少ない取り決めであると思われる9シェイプの人数や立ち位置に一貫性が感じられないシーンも散見されており、アタックの方針がチームの中でまとめ切ることができていなかったような印象です
また、数値ではなくあくまでも試合を見ている中での印象ですが、やはり帝京に比べると「個人で前に出ることのできる選手」の人数が少なく、特にFWの選手はよくいえば堅実、少し何のある言い方をしてしまうと淡白なキャリーとなる選手が多くなっていたように思います
特にFWの選手の主戦場となる9シェイプのところで前に出ることができておらず、テンポもうまく出すことができていませんでしたね
キックも帝京に押し込まれていたような印象で、意図的に蹴っているというよりかは帝京のゲーム運びによって蹴らされる方向に動かされていたような印象です
Longが重となっており、一部Grubberを狙ったシチュエーションもありましたが意図的というよりかは質の低い状況判断による部分もあったと思うので、効果的な方向に持っていくことはできていなかったように思います
ラックのところでも帝京のプレッシャーを受ける場面が多く、オーバーに入る選手が相手よりも早く倒れてしまっていたりそもそもラックに入るタイミングが遅れてしまっていたりとうまくいかないことが多かったような印象です
元々SHの白栄選手はテンポを遅らせることが多い傾向にあるかとは思いますが、今回の試合では意図的というよりかは結果としてラック内でボールをキープせざるを得ないようなシチュエーションが多く、テンポは思ったように出すことができていなかったように見えました
筑波のキャリー
先述したようにキャリーの部分ではかなり後手に回ってしまったような印象があり、テンポを出すのに必要な「前に出る」という部分で戦える選手があまり多くなかったことも影響しているように思います
谷山選手がCTBに入ったことで相手一人一人のディフェンスレンジが広い状況下で彼がボールを持つことができていましたが、帝京のディフェンスがきっちりと前方向へのプレッシャーをかけてきていたため、谷山選手がボールを持つ頃には目の前に相手選手がいたりと効果的な使い方はできていなかったようにも見えました
ただ、そんな中で相手を外すことのできるような動きをしていたのは身体能力を示す結果となったでしょう
キャリーの回数を見ていくと前後半合わせて53回という回数に抑え込まれており、その数少ないアタックもあまり前に出ることができていなかったりとチャンスメイクをすることができていませんでした
そもそも敵陣22mよりも奥のエリアでラグビーをすることができていた状況が極めて少なく、アタックそのものがうまくいかなかったことも相まって効果的なアタックがあまり見られませんでした
細かく見ていきましょう
そもそもキャリー回数が少ないこともありますが、9シェイプでのキャリーが8回、10シェイプでのキャリーが6回とFWを使ったアタックの方向性がうまく定まっていなかったような印象です
また、シェイプ外のキャリーは23回となっており、シェイプ外でのキャリーが多いということがわかりますね
シェイプ外のキャリーの中では中央エリアでのキャリーが13回、エッジエリアでのキャリーが10回となっており、傾向的には少し内向きの印象を受ける形となっています
実際、エッジからのアタックの後にすぐ折り返して狭いサイドへアタックを広げるような傾向は筑波のアタックには見られないため、シェイプを使ったアタックが中央エリアで起きていることを鑑みるとアタックがかなり中央によっていたということができるかもしれません
筑波のパス
パスワーク自体に凝ったものがないという点に関しては帝京と似たところがあるかと思いますが、このスコアの差につながったのは、やはり実行力や精度の差かと思います
帝京はほとんどパスミスをすることがなく、無理につなげず確実に繋げられるところからチャンスを作っていましたが、筑波の選手は繋ぐ意識が高いからか崩れたシチュエーションでも外に回そうとするイメージが見られており、無理に回していると取られてもおかしくないようなパス回しをしているようにも見えました
SOの楢本選手も過去の試合に比べると判断力が研ぎ澄まされてきているような印象ですが、なにしろ選択肢があっても効果の程がまちまちとなっており、結果的にチョイスが絞られてしまうという状況も見られないことはないため、もう少し何かしらの工夫が見られると良いのかもしれません
回数を見ていくとパスは98回となっており、キャリー・パス比は1:2に近いような数値になっていることからキャリー回数に比べて比率的にパス回数が多いということができるかと思います
試合を見た実際の印象でもパスをかなり繋いでいたように見えたので、意図的にパス回数を増やしてエリア的に散らすということには成功していたのかなと思います
細かく見ていくと、ラックからのパスアウトのうち15回が9シェイプへのパスとなっており、バックスラインへの展開は9回となっていました
傾向的には若干FWが多いということができるでしょうか
ただ、総数が少ないということもあり、傾向というほどの形には届いていないかなという印象です
バックスへボールを回した後は6回が10シェイプへのパス、16回がバックスライン上での展開となっていました
一応10シェイプを使うことは意識しているかと思うのですが、システム的にきっちりと配置しているというような印象はそこまで見てとることができず、少し選択肢としてはイマイチ足りなかったようにも見えました
一方で気になるのがOtherにカウントされているパスの多さですね
もちろんカテゴライズが難しいパスが含まれているということもあったかと思いますが、試合を見ていく中で気になったのは「パスとしては次の選手につながってはいるが、ワンバウンドしたりと綺麗に繋がることのなかったパス」が一定数あったかのように思います
帝京もOtherがある程度の数見られていましたが、精度の部分で筑波とは差が見られており、この辺りのクオリティについても筑波が後塵をはいしていたように見えました
筑波のディフェンス
数値的には悪くない状態をキープすることはできていましたが、詳細を詰めてみていくとタックルに至らずクリーンブレイクされていたような状況も多く、「成功率に影響を与えない悪いアウトカム」が多かった形ですね
タックルの質を見ていくと、どちらかというと相手に上にのられてしまうようなアウトカムが多く、もしくは外されたり足先に何とかしがみつくだけにとどまったりと、相手のモーメンタムを止めるまでには至っていなかった印象です
帝京は前に出るモーメンタムからシンプルなアタックでスコアに繋げるタイプのチームなので、その辺りの噛み合わせが悪かったですね
ダブルタックルには入ることができていましたが、先述したように相手の下になってしまっていたりすることによって相手に対して相対的に不利な状況に追い込まれたままディフェンスを続けていたので、ディフェンスラインが崩れるシーンが多かったように思います
筑波はディフェンスが一度崩れると立て直すのに苦労するチームなので、今回は帝京の勢いに押し切られてしまった形ですね
まとめ
一筑波OBとしては極めて悔しい結果となりました
ただ、帝京はその悔しさすらも振り切るような強さを見せてくれました
まだ試合をしていないチームもありますが、正直学生レベルで提供に勝つのは難しいのではないかというような完璧なチームづくりを進めていると思います
一方、ここまでの完成度を誇るチームがこのレベルで試合を続けることが適切なのかどうかについては疑問に思う部分もあります
もちろん帝京の選手は勤勉かと思うので課題をしっかりと見つけて改善を図るかと思うのですが、もっと上のレベルでの試合も必要なのではないかと思う次第です
今回は以上になります
それではまた!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
