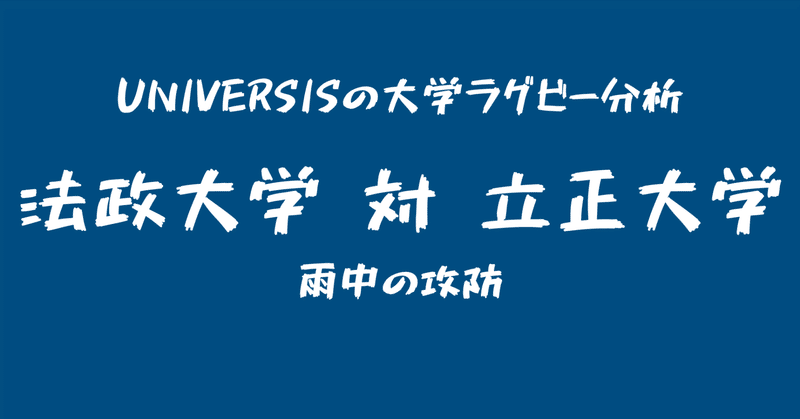
2023関東大学ラグビー春季大会Bグループ:法政対立正を簡単な数字で見てみた
みなさんこんにちは
サブタイトルを考えるのが大変になってきた今本です
今日は6/11に行われた法政大学対立正大学の試合をレビューしていきたいと思います
メンバー表をば

この時期にはメンバーも安定してきましたね
次にスタッツです

若干奇妙な数値になっていますね
その辺りも踏まえて順番に見ていきましょう
法政大学のアタック・ディフェンス
法政のアタックシステム
基本的には1−3−3−1で見ていっても良いかと思います
その基本スタンスに対して、後半にかけて表裏を使ったアタックをしたり強いランナーが前に出て攻撃を進めていくといった形でしょうか
言い方を変えればシステム的な穴をつくアタックがそこまでできていないのが法政の現時点でのアタックかなとは感じました
春シーズンはあまり相手の分析はしないと小耳に挟んだので、その要因も影響しているかもしれませんが、ビッグゲインやラインブレイクに関しては偶発的ないしは個人の能力に依るところが大きかったように見受けられます
とはいえ、NO8の高城選手や後半で言えば16番の石川選手など良いキャリアーは散在していたので、そういった選手をうまく組み合わせることができればかなり伸びてくると思います
例えば10シェイプにそういった強い選手を置いてポジション別のミスマッチを狙ったり、大外をFW2枚にして数的・質的なミスマッチを狙ったりですかね
法政のキャリー
約1/3が9シェイプかそれに類するアタックと、先述したように強いFWの選手を起点に崩すといった意図を持っているのかな、というようなキャリー数でした
キャリー回数自体は少なく、なかなか傾向は見て取りづらいですが、10シェイプは少なかったですね
ちょっと強い言葉を使うと、強いキャリアーはいるのですがあまり活かしきれてない感も少しありましたね
9シェイプが多いのは至極当然のこととは思うのですが、その対面には同じFWの選手が立つことが基本的には多いので、相手とのバトルに勝つことができなければそこを起点には組み立てられないわけです
なので、キャリーするエリアを変えたり、選手を変えたりして同じFW同士の勝負でも質的な優位をとっていくことが求められます
法政のパス
パス回数は少なめで、キャリーと同様に9シェイプへのパスが最も多いという形になりました(Otherはパスのごった煮なのでスルー)
中でも少し勿体無いなと思ったのはポッド内でのパスや表裏を活かしたパスワークなど、「相手からずれるパス」を使う回数が少なかったことです
後半でこそバックドアへのパスは増えましたが前回は1回で、ポッド内のパスについては総じて1回とほとんど使われていませんでした
とは言えパスはランとの組み合わせがあってこそだと思うので、キャリーに脅威があり、かつその脅威を最大限に使ってずらすパスが活き始めると思います
今回は中盤でのキャリーに脅威があまりなかったので、それよりかは1対1を勝つことの繰り返しをした方が良い、ということもできるかもしれません
法政のブレイクダウン
少し3人かけないと完結できなかったラックが多いのが印象に残っていますね
数としても発生したラックの約半数で3人オーバーがついていると考えるとその多さが際立つと思います
ディフェンス面では、ジャッカルをしたり越えきったりと良い点が見られており、崩れるほどには至っていませんでした
ただ、プレッシャーは少しかけきれなかった印象もあり、コメントは分かれそうですね
法政のディフェンス
タックル成功率は悪くはないですが、欲を言えばもう少し高めていきたいといった感じですね
ただ、システムが大崩れしてトライを取られた、もしくはビッグゲインを切られたという感じではなかったので、微修正もしくはスキルの向上で良くなると思います
あえてコメントしていくとすればロータックルがうまくはまっていなかったり逆にボールを狙いにいって相手に圧をかけられなかったりといった場面、またはその逆の場面が生じたりと発生した事象に一貫性が無かったのがちょっと気になるところでしょうか
システム上の大崩れがあればそこの修正で済むのですが、偶発的なエラーや一貫性のない難点は修正が難しいので、ちょっとコーチングの見せどころになるかもしれません
立正のアタック・ディフェンス
立正のアタックシステム
原則はシンプルですね
基本的には9シェイプと10シェイプにそれぞれ3人ずつ立っていることが多いので、1−3−3−1を起点に考えていきましょう
とはいえ、CTBの選手がポッドのトップに立ってくることもあるのでその辺りは柔軟というか、「強い選手を先頭に立たせたポッド」を起点に組み立てているといった方が近いでしょうか
ただ、あまり決まった形のポッドが形成されていた印象は少なく、「そこにいる選手に対してSHが判断してパスをする」といった形にも見えました
バックスのアタックラインに関しても背番号と役割があまり一致していないというか、10番の鈴木選手がキャリーが多くて12番のヴェイタタ選手が1stレシーバーからの繋ぎ役になることが多かったですね
14番のフルックス選手も1stレシーバーになることもあったりするので、少しフレキシブルかもしれないですね
というか、コンタクト姿勢が怖かったですけど鈴木選手のキャリー強かったですね
違う意味で感動しました
今回の試合は若干ながらキッキングゲームの様相を呈していたのでLongやLong Puntが多めで、キック自体はヴェイタタ選手をバックフィールドにおいて蹴り合いをしていました
ヴェイタタ選手のキックは長く高く伸びるため、その能力を買われて後ろに立っているのかもしれませんね
ただ、(キックがLongかPuntか読みづらいこともありますが)キックが伸びすぎて相手と競り合う意図が見て取れなかったので、味方のチェイスがうまく追いついていませんでした
立正のキャリー
外国出身選手の貢献度が大きく、ヴェイタタ選手やフルックス選手が特にゲインや繋ぎに貢献していました
一人一人の細かい数値はやゲイン率に関しては取っていないのですが、逆にいうとその2人の選手が抑えられると厳しい戦いになる可能性が出てきます
リモリモ選手はオフロードを繋ぐことも多いですが、繋がずにキャリーで完結することも多く、今回はそこまでゲインには寄与していなかったように感じました
蹴り合いが多いこともあってキャリー回数は少ない数にとどまり、後述しますが後半に関してはパス回数よりキャリー回数の方が多いというある種のバグが発生していました
というのも今回の試合で立正はゴール前でのラインアウトからのモールトライやピック&ゴーなど、パスを重ねずにトライまで繋げるパターン(繋がらないこともありましたが)が多く、結果としてパス回数がトータルとして少ない形になっていました
立正のパス
パス回数の方がキャリーよりも多くなるというバグが発生しました
バグじゃないんですけどね
パス回数がここまで少ないのも珍しく、春季大会でキャリー・パス比が1:1以下は正直初めてです
先述した理由からですが、それに合わせてあまりパスを外まで細かく繋いでゲインを図る方向性には至っていなかったことも要因かと思います
ミスパス・飛ばしパスは何度か見られましたが、例えばSO→CTB→CTB→WTBのような複数の選手が何人も絡むアタックはほぼ見られなかったように記憶しています
実際、バックスライン上でのパスは61回のパスの内3回に留まっています
いわゆるバックドアと呼ばれるような位置に立っている選手へのパスも数回にとどまっており、もう少しバリエーションがあれば違うアタック方針を立てることもできるのかなとは感じました
立正のディフェンス
成功率は要改善と言われるかもしれませんね
同じミスタックルでも普通ならうまく入って倒し切ることができているようなシチュエーションにおいてのミスタックルが少し多めな印象を受けました
例えば、9シェイプにダブルタックルに入って2人とも外されてしまったり、といった「そこは外すとしんどい」といったシチュエーションでのミスタックルも見られ、システムというよりもスキルエラーによって倒しきれない場面が見られましたね
ダブルタックルそのものも、1人が下で1人が上に入るというよりは2人が各々入った場所が結果的にダブルタックルになっていた形が多く、もしくは2人とも上か2人とも下かといった形が散見されました
ディフェンスラインに関しては比較的うまく構築されていたと思いますが、少しラックに目を奪われている選手が多めかな、というのが引っかかっています
もう少し首を動かして視野を広げてもいいかもしれません
まとめ
総じて見るとコメントがなかなか難しい試合でしたね
お互いに崩してトライをとったというよりも再現性の少し低めなプレーによってトライが生まれていたので
まぁ、それでトライを取り切ることができるというのもそのチームの実力ということができるので、第三者ですが勝手に楽観的に見てます
今回は以上となります
それではまた!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
