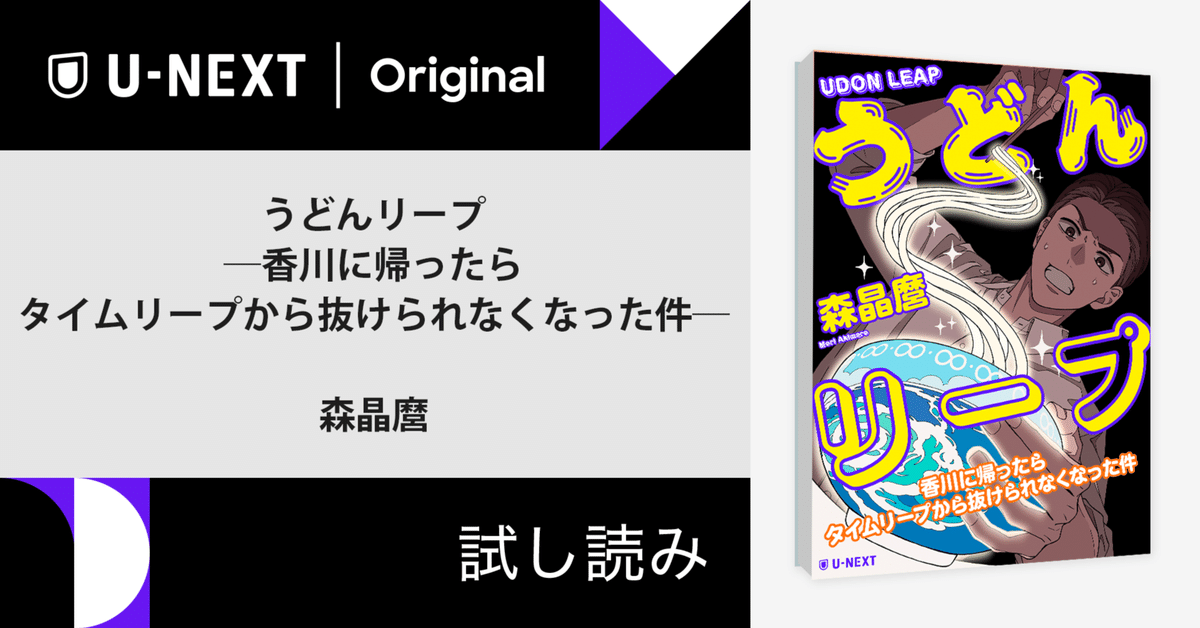
【試し読み】森晶麿さん『うどんリープ—香川に帰ったらタイムリープから抜けられなくなった件—』

■著者紹介
森 晶麿(モリ・アキマロ)
1979年生まれ。2011年『黒猫の遊歩あるいは美学講義』で第1回アガサ・クリスティー賞を受賞。著書にこの「黒猫シリーズ」や「探偵シリーズ」「偽恋愛小説家シリーズ」、その他の著書に『キキ・ホリック』『探偵と家族』『超短編! ラブストーリー大どんでん返し』『チーズ屋マージュのとろける推理』などがある。香川県在住。
■あらすじ
大学進学を機に郷里の香川を出、東京の企業に就職した達也はある日縁談を進められる。乗り気になったものの、地元には遠距離恋愛中の恋人がいた。大型連休の金曜に香川へ帰省し、別れ話をするはずが、気がつくと帰省最終日の日曜朝になっている。何とか恋人に別れを告げるものの、時間はなぜか金曜夜に戻ってしまい、やり直しの会話の中で、達也は恋人の秘密に気づく。本当に彼女とは終わりなのか。達也の本当に望む未来はどこに——?
■本文
1 四月三十日 日曜日──困惑
それが喉を通過する瞬間、体がほんの少し清められた気がした。釜揚げうどんを吸い込んだ心地よさと神聖な感じが、目覚めてなお残っていた。そして、目覚めたはずなのに、現実と意識の間にわずかなズレがある。
和紙を纏った照明は、いまは灯がついておらず、その向こうでは笑った猿に見える天井の木目が、俺を見下ろしていた。子どもの頃はあれが動き出しそうで怖かったものだ。
ええと? まだ体を起こす気になれず、寝転んだままで考える。どうも妙な感じだ。夢の皮を一枚剝がされてなお、夢の中にいるみたいな。
頭の芯がぼんやりしすぎている。もう一回布団を頭からかぶった。微かな太陽の匂い。日の光も知らぬ東京のアパートのベッドからは嗅ぎようもないそれ。子どもの頃、当たり前に嗅いでいた匂い。
ああ、これ実家の布団じゃないか。和紙の照明も天井の木目模様も、実家の俺の部屋のそれ。どうりで体によくなじむ。
待て。実家の布団だって? 頭の芯が覚醒してきた。どうして俺は実家で眠っているんだっけ?
もう二度寝はやめ。さっき見ていた夢が思い出せないのは目覚めた瞬間のつねだが、眠る前の出来事まで思い出せないのは困る。
身は起こさぬまま、手だけを枕周辺に這わせて、スマホを見つけた。画面を確認すると、四月三十日の日曜日、とある。
「にちようび……? え、マジか……」
俄には信じがたかった。いくら何でも飛びすぎている。
半身を起こして周囲を見回した。茶簞笥の上には高校時代のバンド部の集合写真。押し入れの襖には埃をかぶったギターケースが疲れた旅人みたいに寄りかかっている。本棚にはさんざん練習したギター教本。間違いない。ここは俺の部屋。もっとも、帰省のとき以外は、物置きと化していると聞くが。
「焦るな、麦野達也。順番に思い出せ。そう、まず……」
先週のことを思い出そう。深く息を吸って、ゆっくり吐き出しながら目を閉じた。
取引先の上司に娘との縁談を持ち掛けられたのは、先週の月曜のことだった。
「麦野君、しょうじき君ほどやんちゃな逸材は初めてでね」
老舗ベビーカー製造会社の専務である鹿嶋さんは、どんな小さなプロジェクトの打ち合わせでも、必ず初回は顔を出すらしい。上等な背広に見合う上等な口髭と海焼けであろう浅黒い肌が印象的だ。
鹿嶋さんとの付き合いが生まれたのは、俺が勤める玩具会社のマシンをベビーカーに搭載すべきだと、飛び込みで営業をかけたからだった。
最初は難色を示されたが、会議室に知り合いの赤ちゃんを連れていって実験を見てもらうと、鹿嶋さんの鶴の一声で即プロジェクトが動き出した。そこで、俺は前々から研究していた日本製ベビーカーの不満点のクリアを条件として突きつけた。この強気な態度が、意外にも鹿嶋さんのツボにハマったらしかった。
「わが社にほしい人材だが、それではお世話になっている御社に申し訳ない。でも、私の娘の婿にならちょうどいいんじゃないか、と」
こう鹿嶋さんが話してきた時、もしかしたら自分にはわからぬビジネス戦略かもしれない、などと穿った考えをもった。しかし、帰社して最初に相談した部長は、渡りに船だ、と言った。
「うちは今、勢いこそいいが、新参と見(み)做(な)されて信頼されない面もある。大手老舗と縁づくメリットは計り知れんぞ」
その場では「ちょっと時間をください」と返事を濁した。鹿嶋さんの娘は、以前から知っていた。何度か打ち合わせの席で顔を合わせている。秘書課らしく、洗練された身のこなしは好ましかった。
問題が一つだけあった。小中高と同じ学校だった幼馴染の未波との関係だ。大学進学のために上京したときから、未波とは長らく遠距離恋愛にあった。それでも学生時代は、辛うじて年に数回の帰省で関係が保てていた。だが、社会人になると、初年度は激務に次ぐ激務、二年目は大きな取引をものにしようと休日返上で働き、帰省の機会を逃した。最近では、数週間に一度、電話で話すのが関の山。
二年間会っていなくても恋人という言葉が機能するのなら、俺には恋人がいることになる。
——ねえ、うちの話聞いとるん?
このところ、電話でそう聞かれることが増えていた。
——なんや、最近すごく遠くにおる人みたいやわ。火星とか。
——飛行機で一時間のとこにいるよ。
——そのわりに全然帰ってけーへんやん。
——空間的な問題じゃなくて、時間的な問題。時を止められるならいくらでも……とにかく今年こそ帰るから。もうちょっと待って。
ここ数カ月は、電話を切る間際はいつもそんなやり取りがあった。内心では、俺は一体いつ帰る気なんだ? と思っていた。そもそもまだ未波を好きなのか? 思うに、自分の内面を把握するのも、いまの時代、時間に余裕のある人だけの贅沢なんじゃないだろうか。
とどのつまり、社会人になり、倍速再生動画みたいな日々を重ねる俺には、時間の工面はおろか、自分の恋愛感情さえ管理不能なのだ。だから、入社三年目に降って湧いた縁談話を、断る明確な理由が浮かばなかった。もともと長いものには巻かれる主義なのだ。
とはいえ、ことを進めるなら、未波との関係も改めてはっきりさせる必要がある。そういうわけで、香川に帰省する計画を立て、金曜の夜に珍しく早退し、その足で新幹線に乗った。
岡山まで行き、マリンライナーで海を渡った──ところまでは何となく思い出せるが、その先が曖昧だ。着いてどうしたんだっけ?
「なぜすでに実家?」と「なぜ日曜日?」という二つの疑問が渦巻いている。渦──この言葉になにかしら反応している自分がいる。ぐるぐると中心に向けて吸い込まれる感じ。最初は鳴門海峡の渦潮のことを考えていた。それが、いつの間にかうどんを茹でる時にできる渦に変わっていた。ああ、そうか、さっきうどんを食べたせいだ。あれは、夢だったのだろうか?
2 四月三十日 日曜日──覚悟
「今年は全然雨が降らんのや」
爆音で流れるハービー・ハンコックの《カメレオン》にかき消されそうな久々の父の声は、少ししゃがれ具合が増して聞こえた。そろそろ煙草をやめさせたほうがいいかもしれない。
「それ毎年やん」
「毎年降らんけど、今年はもっと降らんのや」
「天気予報、例年通り言うてたで」と母が横から茶々を入れると、父はムッとした顔になり、お茶を飲む。
「熱! やけどするか思うたわ!」
「何年お茶飲んどるん、親父。淹れたては熱いわ、そら」
咄嗟に讃岐弁で返しながら、こんな会話、ここに暮らしている頃は毎日だったな、と思った。子どもの頃からほぼ変わらない光景。母がしょうゆ豆、セトダイの刺身、味噌汁とご飯を運んでくる。
「あ、俺、朝飯パス。今日の昼は?」
「うどんに決まっとる」
だろうね、という言葉を飲み込んだ。うどんの国で、昼飯がうどん以外の選択肢であったことなんて数えるほどしかない。友人同士で遊ぶときでさえ、「昼はマクド? うどん?」という二択がごく普通に出てくる。
「達也も食べて帰るやろ? まだ電車まで時間あるんやし」
「電車? ああ、そうか……」
帰省していた記憶はないが、日曜ならばもう東京に戻らねばならない。スマホの中のスケジュール表を確認すると、東京行十三時十分発、と書いてある。
「いや、ええわ、ちょっとはやめに出るけん」
この混乱と向き合うには、家族から離れたほうがいい。しょうじき二日間の記憶がないというのは異常事態だ。場合によっては医者の診断でも仰いだほうがいいかもしれない。
「ほうか」
室内の空気が急に老け込んだ。母も父も、どちらも明るく頷いたのに、その裏に落胆の色が透けて見える。
「出かけるんやったら、気ぃつけぇや」
「え? 何に?」
「こないだ山からイノシシが下りてきて騒動になってんて」
「ああ、それ去年も言うてなかった?」
「去年もあったけど今年もあってんて。ほんまに珍しい」
珍しい、という言葉の意味をしばし考えてしまう。いや、わかる。たぶん珍しいのだろうが、ほぼ毎年聞いている話題だ。
「そんなことよりおまえ酔うとタチわるいで。気ぃつけや」と父。
やはり飲んだのか。そりゃそうだろう。飲んだのでなければ、記憶が消える理由が見つからない。試しに口に手を当てて息を吐いてみた。すぐに酒臭い息が鼻孔に跳ね返ってくる。
「まあ今はええけど、三十すぎたら二日続けて飲むんはきつくなるけん、今のうちに酒量抑える練習せなあかんよ」
「そうやな……」
頷きながら、情報を整理する。なるほど、金曜も土曜も飲み会が続いていたようだ。それで記憶が不確かになったのか。仕事疲れもピークの体で飲み会二連続は記憶が飛ぶのも理解できる。
だが、前日の記憶まで消えた経験はかつてない。
インターホンが鳴ったのはそんなタイミングだった。
「お、お迎えちゃうかぁ?」
「え? 誰の?」
「誰のて、おまえのやろが。なあ?」と父がにたにた笑って言うと、母もそれに同意するように笑い出した。
「……未波が?」
箸を置き、急いで玄関に向かった。未波は上がり框に腰を下ろし、こちらに背を向けて頰杖をついていた。デニムにTシャツという、十代の頃と変わらぬラフな出で立ち。
未波が振り返った。化粧っ気はない。派手な顔立ちではないけれど、それでいて何も足す必要のない雰囲気が、彼女にはある。
「行こうか、たっちゃん」
「……そ、そうだな」
気後れしながら、荷物をとりに二階に戻った。それからそっとため息をついた。未波の様子から察するに、まだ別れ話を切り出していない。駅に着くまでに言わなければ、帰省が無駄になる。
ため息で逃がした希望を寄せ集めるように深く息を吸いこむと、荷物をまとめた。網戸越しに入り込んだ風が、何かを訴えていたが、俺にはそれが何なのか読み取ることはできなかった。
3 四月三十日 日曜日──宣告
「なんもしゃべらんのやね」
未波が切り出したのは、車を発進させてから十五分ほど経過してのことだった。
「いや、しゃべってるじゃん」
「『じゃん』て何、きっしょ! しゃべっとらんし」
カーステレオからは、ビル・エバンス・トリオの《ワルツ・フォー・デビー》のテイク2が流れていた。もう最近はジャズなんてまったく聴かなくなった。聴いている暇がないのだ。体はつねに情報が渋滞を起こしていて、帰宅したらもう音を一切体に入れたくないのだ。
「今しゃべっとるって」と讃岐弁モードに切り替えて答えつつ、不意に胃がしゅくしゅくと縮んでいく。これから別れを切り出すのか。逃げたい。嫌いでもない相手を傷つけるなんて辛すぎる。
二人の生きる速度がズレただけ。個人の好悪の念ではどうしようもない距離と時間が生んだズレ。誰も悪くないのにな。きっと未波だって、彼女と同じ時間感覚で生きている男と付き合うほうが幸せなはずだ。
「なあ、週末に屋島の水族館行ったり、〈三ぶた〉でお茶する恋人が必要なんちゃう?」
「……何それ」
「おまえの隣をちゃんと歩ける奴。社畜でろくに話題も思いつかない奴やなしに、自然と会話が出てくるような」
「……それがたっちゃんの願いってこと?」
「ま、そやな。俺、幸せなおまえを見たいんや」
鈍器に見えない鈍器で殴っている自覚はあった。
「わかった。それがたっちゃんの決断なら」
恐れていたよりも、静かな返答だった。
「今まで、楽しかったで」
噓はなかった。楽しい時があった。ここ数年はないけれど。未波は俺の言葉に小さく、曖昧に頷き、それから気持ちを切り替えるように一息ついた。
「まだ時間あるし、駅前で立ち食いうどん、食べて行きまい」
未波のほうでも別れは想定内で、とっくに見切りを付けていたのかもしれない。ふと、そんな気がした。
「ええな、それ」
車をコインパーキングに停めて駅まで歩くあいだ、不思議と大学に入学した頃のことを思い出した。あの頃も、こんなふうに駅まで未波が車で送ってくれたのだ。何を話したのかは忘れてしまった。覚えているのは、駅で未波が急に泣き出したこと。
——このままたっちゃん遠い存在になるような気ぃするんよ。
生きていると、ただそれだけで取り返しがつかないほど過去は遠ざかってしまう。
駅前のうどん屋〈ぐるりん〉に入った。カウンター席だけの狭い店内に、中年男性の客が一人いるだけ。いつも混んでいるから運がいい。
釜揚げうどん二つ、と店主に告げた。口髭がダンディな、丸眼鏡に痩せ型の店主が、「はいよ」とシンバルでも叩くように威勢よく麺の湯切りをしながら応じた。
「ずっと昔も、こうやってここに入ったね。覚えとん? あの頃は大学終わったらたっちゃんが地元に帰ってくると思うてたんよね。いつかまた一緒にいられる日がくるって……」
気づいた時にはもう遅かった。明るい話題に切り替える隙もなく、未波の目には大粒の涙が浮かんでいた。
「へい、毎度」
店主が、勢いよく俺たちの前に釜揚げうどんを置いた。
「……食べようで。『うどんはさっと食べるほどうまい』やろ?」
高校時代の未波の台詞を真似た。未波は泣き笑いで頷いた。
葱と生姜をいりこ出汁の麺つゆが見えなくなるくらい入れる。生姜の匂いが、滅多にないくらい強烈だった。どこまで続くのかと訝(いぶか)りたくなるほど長いうどんを、途中で箸で切ってつまんでつゆにつけた。食べ終える頃には、未波の涙が笑顔に変わりますように。そう祈りながら、一気に——啜った。
※ 続きは電子書籍版でお楽しみください。
U-NEXTオリジナルの電子書籍は、月額会員であれば読み放題でお楽しみいただけます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
