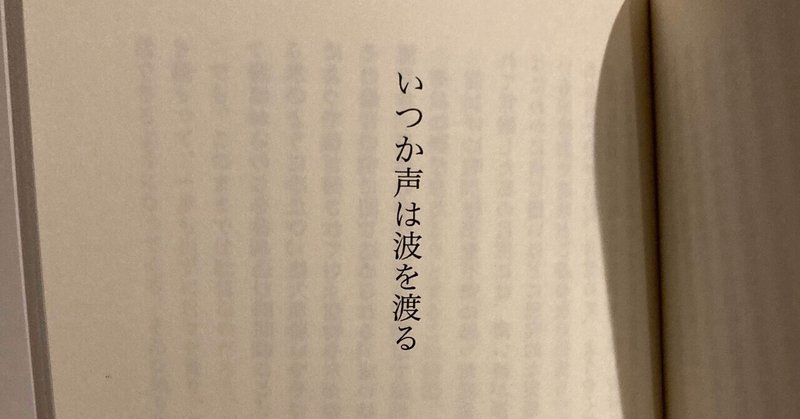
いつか声は波を渡る【試し読み】
あらすじ
2011年3月11日、春香は親友であるあーちゃんを喪った。以来強い喪失感を抱き続けたまま生きていたが、津波の夢を見た六年後のとある日、同棲している夏希に宮城に行きたいと話を持ちかけた。あーちゃんの故郷である女川へと向かう旅で、爪痕と復興を同時に見つめながら、春香はあーちゃんの生きていた断片を探すように海へと近づいていく。その先で、彼女が見つけるものとは。
いつか声は波を渡る
一
濁流がいのちを呑み込む瞬間のこと。
氷のように冷たい、絶大な勢いでやってくる。静かなる轟音と共に。水の音、そして水によって薙ぎ倒されていく建物や木々の音。呑み込まれた瞬間に、音は止む。自らもまたその轟音の中に閉じ込められる。或いは破壊される。公平に、同様に、破壊される。押し流され、身体の中は汚濁し、やがて溺れてどうにもならず窒息して瓦礫に埋もれている。
そんな夢だった。
苦しげに喘ぐ様子を不安に思った夏希が、無理矢理起こしてくれた。何度も名前を呼ばれて覚醒した私の目尻には、薄い涙が滲んでいた。止め処ない恐怖に曝された夢は、夢とはにわかに信じ難いほどに現実的な実感として襲いかかってくる。水の音も、温度も、臭いも、強大で逃げどころのない恐怖も、あまりにも詳細で本当に押し流されていたように私を引き摺り込む。目覚めて、ようやく初めてそれが夢であったと気付く。残滓となった恐怖に心臓を高鳴らせながら、深い安堵に包まれて、涙を拭う。
気分を入れ替えるように、覚束ない手つきで窓を開ける。冷たく張り詰めた朝の風が部屋に入り込み、風のふもとで、ほとんど枯れたような枝に桃色が点在している。
桃の花。
ああ、今年も。
今年も巡ってきた。私は生きたままで。
宮城への訪問を決意したのは、昨日見た悪夢がきっかけだった。
寒気の峠を過ぎようとするこの時期、私はきまって体調を悪くする。付き合いが長くなってきた夏希もそのことを理解してくれているから、殆ど同棲状態となって、身の回りのことを、先回りしてこなしてくれる。いつも申し訳なくなりながら、どうにも身体も心もうまく作動しなくて、甘えている。私は、ぼんやりと、いつかこの人と結婚することになるだろう、と考えている。夏希もそうしたことをぼんやりといつかの約束事のように考えているから、こんな弱々しい人間のことを世話してくれるように思う。
でも、このままでは駄目なのだろう、という予感がどこかでしていた。毎年、部屋に引き籠もって、一歩も出ずに日々を貪り、その日が過ぎた頃合いからようやく人間として生活できるようになってくる、そんな繰り返し。いつまでも、向き合えずにいるのは、夏希にも申し訳ないし、私自身にも毒であり続ける。毒は毎年私の中をくまなく循環し、細胞の一つ一つに至るまで蝕み、動けなくする。おかげで、私は定職につくことができない。アルバイトでなんとか生計を立てて、家賃をはじめとした必要経費だけは払っているけれど、この時期は収入が消える。だから夏希の支えは、有難い。けれど、私はいつまで経っても自立することができない。それでいいと夏希は言ってくれるけれど、この反復に、いつかは終止符を打たなければならない。
その日も朝から晩まで私の体調は悪く、夏希の作ってくれた野菜と卵をやわらかくほぐしたお粥をのろのろと噛み締めていた。夏希は他愛もない話を延々としている。私は相槌を打つ。テレビからは、夏希の気に入っているというお笑いの動画が空回り気味に流れていた。
「夏希」
ふと、言葉がするりと喉から出て行く。言おう、と決意した風ではなかった。まるで、自分ではない誰かが不意に言い出したような、他人事のような感覚だった。外は暗くて、暖色の照明の下で夏希が私に視線を向けた。
「私、宮城に行きたい」
夏希が息を詰めたのが、空気で解った。
お笑い芸人のやりとりが、妙に空疎に部屋に鳴り響き、やがて動画は終わって静寂に包まれる。
「えっと」
夏希は動揺を隠せず、目を泳がせている。
「その、いいの?」
「うん」私は頷く。相変わらず、自分ではないような感覚だった。「でも、夏希についてきてほしい」
「勿論、それはいいけど」
夏希は言い淀む。緊張している。心配してくれているのだろう。ただでさえ体調を悪くしているというのに、砦のようなこの部屋から出て、遙か東北の地に向かって、どうなるのか。気を病むばかりではないか。
私にも懸念はあった。けれど、いずれ行かなければならなかった。
そうでなければ、私たちはいつまで経っても前に進むことができない。
二
秋菜、通称あーちゃんは、私の友人である。
昔馴染み、というわけではなく、知り合ったのは大学の時だ。田舎から東京に出てきたばかりの私は、都会の華やかさに昂揚と緊張を抱いていた。田舎を出ることを第一目標にして受験したけれど、きちんと馴染んでいけるか不安だった。東京は私を受け入れてくれるのだろうか。寂しさで嫌になるのではないだろうか。コンクリートジャングルに辟易するのではないだろうか。人混みに窒息してしまうのではないだろうか。
地元を出るまでは、そうした不安よりも東京進出の喜びが勝った。けれど、引っ越し先の、何も無い小さなワンルームに足を踏み入れたとき、ここが私の城になるのだという念願を上回って、急に不安になったのだった。本当にここでやっていけるのだろうか、と。
入学式を恙無く終え、大学構内はサークルや部活の勧誘で大いに盛り上がっていた。一にも二にも友人関係を構築することが最優先だったので、興味のあるものからさほど惹かれないものまで、手当たり次第にあたってみた。毎晩居酒屋やカラオケでの新歓コンパに参加して、未成年だけれど初めてお酒を嘗めてみたりした。甘いカシスオレンジ。ジュースみたいな瑞々しさや楽しさとは裏腹に、毎日繰り広げられる賑わいに少しだけ疲弊していた。
あーちゃんと出逢ったのは、軽音サークルの新歓コンパだ。偶然隣席になったのだった。活発で、聞き慣れないイントネーションを操る人だった。なんとなく、東北っぽいな、と思っていたら、話を聞くと宮城出身だということだった。大学にきてから驚くほど広範囲の出身地をもつ人々に出逢ってきた。東北も珍しいわけではなかったのだけれど、宮城の人は初めてだった。
「宮城って、あれだよね。伊達政宗とか」
「渋いなあ。牛タンとかあるのに」
あーちゃんは少し驚いたようだったが、嬉しそうだった。
私とあーちゃんは性格が違う。私は最初こそ頑張って、華があって活気のある人たちが集まっているサークルに足を運んだが、本当はもっと地味な人間だ。ゲームや漫画が好きだけれど、それほど入れ込んでいるわけではなく、運動は得意ではない。中途半端な感じだ。一方のあーちゃんは、身体を動かすことが大好きで、とりわけ水泳が得意な女子だ。さばさばとしていて、田舎っぽさの薄い人。だけど話し込んでみると、隠していた東北弁のイントネーションが次々と溢れてきて、時折何を言っているのかよく分からなくなる。
強引だが簡単に分類すると、私はインドア派で、あーちゃんはアウトドア派、という棲み分けが出来るだろう。でも、私たちは何故だか気が合った。最初は、恐らく田舎者同士、東京ってきらきらしているけど大変だよね、とか、星が全然見えないよね、とか、都会へのちょっとした愚痴を言いながらも、実は気になっているお店があって、と希望を乗せた話が膨らみ、不思議と意気投合していろんなお店に一緒に行くようになった。新宿に渋谷、下北沢だとか上野動物園。表参道は一度行ったっきり。
結局、私は写真サークルに入り、あーちゃんは水泳部をメインにして、一緒に写真サークルにも入った。活動頻度がさほど多くなく、そもそも活動日などあってないようなもので、あーちゃんのように兼部している人はたくさんいた。夏に合宿があったり、おのおの好きに集まって写真を見せ合ったり話したり、撮影会を企画したり、秋の文化祭に向けて準備をしたり、ほどほどの熱意が苦しくなくちょうど良かった。
私は意外とのめりこんで、バイト代と仕送りをちょっぴり合わせて、先輩に勧められた一眼レフカメラを買ってみたりした。本格派じゃんとあーちゃんは笑った。馬鹿にするようなものではなく、ほくほくと笑った。あーちゃんは携帯電話、途中からはスマートフォンを使っていた。私も本腰を入れて撮影する時以外は、携帯電話で風景や猫やあーちゃんをしきりに撮った。ごはんも撮ったし、他の友達も撮った。スマートフォンに移行する際も抜かりなく写真を全て移した。今も私の手中には、あーちゃんをはじめ、大学時代に溜めた思い出が積もり、巨大な地層を成している。その中で、途中から夏希も登場するようになる。
夏希とはバイト先の本屋で出逢った。一年生の、一眼レフを買う資金を貯めていた頃のことだ。私より一歳年上で、大学は違う。告白は夏希からだった。私は今まで異性と付き合ったことがなかった。高校の時、隣のクラスの生徒会長のよく通る声が好ましくて、全校集会などの際に両耳を傾けてその声の調子をじっと聴いていた期間があって、ただ、恋慕とはずれていたように思う。ぼんやりと過ごしていたせいか目立った恋をしたことがなかった。どうしたらいいのかわからなかった。ただ、夏希と本の話をしているのは楽しかったし、夏希の声もまた、私は好きだった。チェロのようなちょうどいい重みを感じさせる低音は、あの生徒会長にも似た響きを感じることに、後からふと気付いた。お試しに、という雰囲気でひとまず付き合い始めたけれど、私はあまりにも未熟で、あーちゃんにも随分相談した。
あーちゃんには、地元に高校から付き合っている彼氏がいる。高校の水泳部で一緒になった同級生で、高校卒業後そのまま実家の漁師を継いで働いているとのことだった。私の地元は海が無いこともあり、漁師という響きが新鮮で、随分驚いたことを憶えている。あーちゃんは、海の人間だった。健康的に焼けていて、海のよく似合う人だった。繊細で儚い、波打ち際で佇んでいる像ではない。どこまでも泳いで行けそうなエネルギーに満ちた、激しさや荒々しさを内包した海の人間。思いっきり笑うと、特徴的な八重歯がよく見える、海の女性。
そんなあーちゃんだが、恋愛ごとにも積極的に相談に乗ってくれた。些細な言動に揺れる私に「彼氏のこと大好きじゃん」「嫁にきてほしいわあ、夏希くんじゃなくて私にしようよ」など冗談交じりに笑いながら話を聞いてくれた。ゆっくり、ゆっくりとした歩みで進んでいく私と夏希に対して多少やきもきしていたけれど。
夏希を含めて初めてあーちゃんと会ったときには「あと冬がいればコンプリートだね」と話して笑った。春香、夏希、秋菜。残念ながらあーちゃんの彼氏は善嗣と実に古風な名前で、冬とはまったく関係がなかった。あとで、夏希は初めてあーちゃんと出逢った時のことについて「まるで春香の親御さんに挨拶するような緊張感があった」と神妙な顔つきで話していた。あーちゃんは親友だけれどとても密接に過ごしていて、夏希との話にもよく登場していた。私がマイペースでぼんやりしがちなので、あーちゃんは時々お姉さんかお母さんのように思うときがある、と冗談っぽく話していたせいかもしれない。でも、一度会って夏希とあーちゃんはすぐに仲良くなった。夏希は温厚で好かれやすい人柄だし、あーちゃんも社交的で誰とでもうまく喋れる人だ。夏希について「あの人ならハルをとられても仕方が無いかなあ」と嬉しそうに笑っていた。
大切な思い出ばかりが過る。
大学四年間、はじめからずっと、記憶には殆どあーちゃんがいる。夏希のことは、すごく大事だ。温度が似ているというべきか、雰囲気が近いおかげで肩肘張ることがないし、ずっと一緒にいても大きな苦にならない。一緒にいたい、と思う。でも、あーちゃんは、夏希とはまた違う大切さがある。あーちゃんがいない生活は、夏希がいない生活以上に考えられなかった。高校までの私は、どうやって過ごしていたのだろうと思うくらい、私はあーちゃんと一緒にたくさんの経験をした。喧嘩もしたし、意見が全然合わないときもあったけれど、すぐに仲直りした。お互いの家には数え切れないほど行った。あーちゃんの積極性に手を引かれて、いろんな場所を旅行した。カフェ巡りをしたし、温泉に行ったし、沖縄に行ったし、ライブに行ったし、ディズニーには何度も行った。
機械に記録されたアルバムを覗くと、そんな青春の日々が鮮明なまでによみがえる。
私は、当たり前みたいに、卒業式を一緒に過ごせると思っていた。赤い生地に大ぶりの牡丹が描かれた袴のあーちゃんと、深い緑の生地に椿が描かれた袴の私、隣り合って、記念写真を撮るのだと、信じて疑わなかった。
あれは、ちょうど最後の春休みの最中だったのだ。
卒論を終え、就職を控え、モラトリアムを最後まで満喫しようとしていた頃。夏希は大学院に進学していたので、私は一足先に社会人になろうとしていた。
まだ寒さは厳しかった。東北は寒く、まだ冬の只中だったはずだ。
東京にいる私たちにも、その揺れは襲いかかった。縦に揺れる、大きな衝撃。地震は何度か経験しているけれど、人生で最も激しい揺れだった。私は自宅にいて、慌てて机の下に入った。棚に入った漫画や雑貨が音を立てて床に落ちた。雷がいつまでも鳴っているかのようだった。言い知れない恐怖にひとり震えながら、やがてその揺れは止んだ。急激に早まった心拍のまま、まずはテレビをつけた。大きな揺れだったので、関東周辺が震源かと思ったら、震源は東北の沖合だった。あーちゃんはちょうど帰省していることを私は当然のように把握しており、そのあーちゃんの故郷から震源地は近かった。あーちゃんは、漁師の子で、海の女性だった。だから慌てて連絡をとったが、電波が途切れているのか、いくら電話をかけても繋がらなかった。なんだか、嫌な予感がしていた。そのとき、私と同じように安否を確認する電話が東北に殺到しただろう。しかし、かの地は、断絶されていた。
少し時間を置いてから、テレビを見て、自分の目を疑った。
宮城を含む、東北の太平洋海岸線沿いに、赤い線が引かれている。高台へ避難してくださいと、興奮と緊張を押し殺しきれずにアナウンサーが早口で繰り返している。
それから暫くしてテレビ画面に映ったのは、猛烈な濁流が、津波が、田畑や建物を、薙ぎ倒していく様子。逃げようとする車がエンジン全開で走るけれど、波に行く手を阻まれて動けなくなり、そのまま流されていく様子。高台に避難した人が撮影した、町が猛烈に深い波に呑み込まれて浸ってしまっている動画。
私は、震えながら、何度もあーちゃんにLINEを送った。毎日、毎日、送った。
あーちゃんから、どうしても、返事が来なかった。
どうしても、来なかったのだ。
後日、大学を通じて、連絡が来た。
あーちゃんが、行方不明だということ。
それからもう少し経ってから、もう一報が届いた。
瓦礫に埋もれた彼女の遺体が見つかったこと。
私の世界は、突如として終わりを迎えた。
三
あれから、六年。
早朝から、夏希の車に乗って、東京から宮城へと向かう。あーちゃんが住んでいたのは女川という町で、津波の被害は特に酷かった。今回の目的地も女川である。
相変わらず私の体調は優れず、頻繁にサービスエリアに寄って休みながら、ゆっくりと旅をする。そういえば夏希と旅行をするのは久しぶりだった。夏希もとうに社会人になり、忙しなく生活している。どちらかというとインドアな二人なので、家でゆっくりしているだけでも不足は無かったのだった。
私と夏希の間に流れるのは、旅行特有の昂揚感ではなく、沈黙の緊張感である。長いドライブの間、ラジオをぼんやりと聴いている時間の方がずっと長かった。夏希もまた、私ほどではなくても、身近な知り合いが津波で死んだことに小さくはない衝撃を受けた。喪失という傷を舐め合って私たちは今も生きている。傷に向き合うことには、鈍い痛みを伴う。
もっと早く来るべきだったのだろう、という思いは拭えない。後ろめたさとも言い換えられる。震災直後で混乱していた時期に訪れず、二の足を踏んでいる間に足下では数年を跨いで、少し落ち着いてきたかもしれない頃合いを見計らって、現地に向かう。復興にはまだ時間がかかるが、当時の破壊し尽くされた光景は、ある程度片付けられているだろう。そうしたタイミングでの訪問は、どこかずるい印象がある。その感情に蓋をする。そうはいっても、向き合うには時間がかかるのだと、言い訳がましい理由を楯にする。
私の鞄には、一眼レフカメラが入っている。大学を卒業して以来、埃を被ってしまっていた。久しぶりに手に取ったのは、一つでも多くあーちゃんとの思い出を形にしたものを手元に置いておきたかったからだった。それが多ければ多いほど、あるいは思い出の強いものほど、彼女が勇気をくれるという錯覚を信じていた。
「春香、見て」
高速を降りてからしばらくして、ぼんやりとしていた私は薄目を開けた。
「海だ」
夏希の声は上擦っている。
湾曲する道をずっと行った遠くに、静寂の水平線がぽつんと見える。冬独特の色をした、灰色の海。私の目には、悍ましいものに映ってならない、恐ろしいもの。あーちゃんを奪った、憎むべき大海。
私は寝たふりを続けるつもりで、瞼を閉じ、僅かに首を捻る。
喉にこみあげてくる嘔気が強くなったら、夏希に頼んで車を下ろしてもらおう。
夏希は一本松を見たかったようだが、現時点で今回の旅は岩手まで走らせる予定はなかった。今回の目的はあくまであーちゃんの故郷を訪れることであり、私の意向に対して譲歩してくれたのだった。とはいえ、気にしないでと力無く笑って下がる目尻を見つめていたら、何か悪いことをしてしまったようで、私は目を逸らした。
「でも、たった一本残っていたなんて、かわいそうな気もする」
小ぶりのうつわに盛られた海鮮丼をよそに味噌汁を啜ってから、私は言う。
「かわいそう、というと」
尋ねながら、淡く輝く白身魚と酢飯を箸先に抱き込み、口内で溢れているであろう瑞々しい味を噛み締めて感極まった声を漏らす。夏希は一口ずつ入れるたびにうまいだとかおいしいだとか呻きのような感嘆を漏らし、ご満悦の様子だった。彼はどちらかというと骨が露骨に浮かんでいるような細身の体格だが、決して少食ではない。見た目に寄らずよく食べるのだけれど、食べた分がそのまま出て行っているかのような体質をしている。
「一人ぼっち、というより、一本ぼっちというのかな。みんな押し流されていく中で自分だけ耐え抜いたっていうのは、寂しいように思わない?」
「うーん。言わんとするところは分かる」
夏希は湯気がしんとのぼる煎茶を啜る。ほ、とついた息がわずかな白さを帯びているように見えた。
「だからといって、倒れていてほしかったというわけでもないだろう」
「もちろん、そうだけど」
「ただでさえ困難な状況で、次から次へと暗い話題が出てきたんだ。絆とか、助け合いとか、流行ったけど、要はどこかに希望を見出さないと。負けずに生き抜いたっていう、象徴が欲しかったんだよ、誰もが」
「うん」
それは、わかる。
でも、美談に昇華することで、その足下にある困難から目を逸らしているみたいじゃない?
私はそう言いかけたところで、口を噤んだ。彼の話す、未曾有の巨大な困難を直に経験しているわけでもない自分が言えることではないから、すんでのところで留まった。
両手で抱えるほどのお椀に、こぼれそうなほど豊かに彩られた海鮮物は、強い生命力を感じる味がした。もちろん、捌いたものなのだけれど、豊かな海でのびのびと育ち鍛えられたような、引き締まった弾力性がある。噛むたびに彼等の力が口内で溢れる。体調を案じて少なめにしたけれど、案外もっと食べられたのかもしれない。目の前で、夏希は私の倍以上も盛られたどんぶりを、米ひとつぶ残さずすっきりと完食し、満足げな表情をしている。
なんだか、とても、普通だ。
普通、というのは平凡とも言い換えられ、日常的ともいえる。この地に来たのは初めてではないけれど、ずっと遠のいていた場所の困難さを直視するには勇気を必要とした。しかし、当たり前のように店に入って食事をしていることに、なんの違和感もない。
なんだか、もっと壮絶なものを想像していた。寄る辺がなく、立ち竦むほかないような壮絶な状況。
あらゆるものが流されていった後に、再構築された日常。
ここに至るまでに伴ったであろう痛みを、そうと感じさせないほどに平穏な空気に肩すかしを食らっているようでもある。喜ばしいはずのことへ、不謹慎なことに意外性を感じている。
私が止まっている間に、私が目を背けていた時は絶えず流れて、その間に努力している人たちがいる。
勘定を済ませ、店を出る。美味しかったです、とレジに立った方へ夏希が言葉を添えると、朗らかな笑顔で送ってくださった。他愛もないやりとりが淀みなく耳を通り抜けていくのを実感しながら外に出ると、輪郭を鮮明に自覚する、痛い空気に身を縮こまらせた。中は暖かかったから、余計に温度差がつらい。
寒い寒い、と口にしながら、温まったお腹を膨らませて、私たちは再び車へ乗り込む。
目的地はそう遠くはない。
女川へ行く前に、先程の海鮮丼の店で教えられたという場所へ夏希が行きたいと言うので、助手席を陣取り続ける私が文句を言う隙は無く、少しだけ寄り道をすることになる。
複雑で細い道が入り組んだ住宅街をゆっくりと車は縫っていく。カーラジオがとめどなく流れ続け、聴いたこともない洋楽が間を埋める。
途中の駐車場に車を停めて、冷たい空気をゆっくりと踏み分けるように黙り込んで坂を登っていく。冬の木々に囲まれた道は音が澄んでいる。乾いた枝葉の重なりが、北風に晒されて、秘密の囁きでもしているかのようだった。
頂上には、何人か他の来客もあり、僅かな賑わいすらあった。乾燥した広場のはじに無言の鳥居が建っており、そこを中心として、人が点々と散らばっている。スマホを手に景色を撮っている人も、ぼんやりと高台からの眺めを噛み締めている人もいる。どこからやってきたのかよくわからない、黒いふくよかな野良猫がはじっこであくびをしている。
夏希と私は鳥居の前に立ち、そこからの眺望を目の当たりにする。
鳥居の奥は長い階段となっており、その先の道は左右に分かれてどう繋がっているか、上からは判断できない。通ってきた住宅街にも繋がっているのだろう。その更に奥は鬱蒼とした黒い茂みになっており、冬の無味乾燥とした東北の風に吹かれながらも、落ちない葉を繁らせているものもあり、豊かな木々が集まっている。
その更に奥は、木々の無い場所。
平坦な土地が広がっている。
巨大な橋が河を横切る、その両側はほとんど何も建ってはいない。冬であることも影響しているのだろう、緑も見えない、ただ何もない、灰色の平坦な土地が、森の向こう側に広がっている。その先の、色の無い海まで。
今にも雪のこぼれそうな分厚い雲の下、同じような鈍色をした海の水平線ははっきりとはせず、霧が立ちこめているかのようにぼやけている。あれは太平洋だ。ずっと泳いでいけば、いつかハワイだったり、アメリカだったり、遠い外国にすら届く広大な海である。遠目では明らかな白波も立たず、穏やかなようだった。静かで、じっと耳を澄ませていれば、僅かなさざなみが聞こえてくる予感すらある、静寂の海。
沿岸に近付くほど、本当に何も無かった。もう少し手前になれば、辛うじて残ったのか、それとも新たに建てたのか、マンションのようなアパートのような建物も見えるが、それ以外に目立った建物はほとんど無い。
どこか現実味が薄いと思ってしまう。海辺は遠い。建物が無い、ということは、そこまで波が至ったということだ。海からやってきた巨大な水の塊が、横滑りの雪崩のようにやってきて、ミキサーにかけられた家々が粉々となって濁った水中に崩れていき、そのまま高台へ衝突した。
ここは、当時テレビでも見た覚えがある。押し寄せる津波から逃れようと高台へ避難してきた人が、ここから、壮絶な濁流に町が呑まれていく姿を目の当たりにしていた。濁流は、車などは当然のこと、建物をいともかんたんに押し流し、木々を貫き、町をまるまる喰っていった。濁った水流で満たされ、炎の上がった町を、沿岸を、両のまなこに焼き付けた人々がいる。この場所で。呆然と立ち竦み、あるいは泣き崩れ落ちていた人々がいる。同時に、その波に攫われていった生き物がいる。
突如として日常が、抵抗しようもない暴力によって破壊されていった。
夏希は数枚スマートフォンで写真を撮ったきり、あとはじっと遠景を眺めている。
私は首からカメラをぶらさげて立ち尽くしたまま。記憶に焼き付けようとしているかどうかも分からない。ただ、見ている。じっと見つめている。どこを、と言われても難しく、遠くを見ている、としか言いようがない。冷たい空気に漂う微細なちりも、遠すぎて分からない海の波も、すべてまとめているような不安な遠近感が纏わり付いてくる。
身体を前に傾けたら、そのまま景色に落ちていってしまいそうだった。
夏希に握られた手に力が籠もる。外気から守られた内側にくるまった温もりを逃さないようにした。
遠いようで近い道のりを歩いてきて、私たちは一体なにを口にできるというのだろう。
特別には語らず、たとえば看板を見て、夏には階段沿いに向日葵が咲くらしいよなんていつか巡る季節の話をしたり、外観の特徴的な石ノ森萬画館に夏希が上擦った声をあげたり、どこかの野良猫の堂々たるふるまいに目をまたたかせたり、そんなことをしては、振り返って、遠くの空白を見やった。目を逸らすなと灰色の海から投げかけられている。ここには届かぬはずの波音が、鼓膜を介さずに私の胸へ直接響いている。独りよがりな思い込みであったとしても。
身体がひどく重たい。
さりげなく手すりに腰を委ねて、鞄に入れていたミネラルウォーターを手に取る。純度の高い水が、体内をとどこおりなく流れていき、その動きに意識を向けることで自己を確認した。
水が無ければ生きていけない私たちが、時に水に溺れるという事実。人間はほとんど水で出来ているのに、水中で生きていくことはできない。水は恵みであり、同時に無情にも暴力的にもなる。雨も、河川も、海も。生命が生まれた海を母とするなら、生物はみな海の子供と呼べるだろう。すると、あの日、母親は子供を、子供の創り上げてきたものを、次々に殺していった。
海で育った、あーちゃんのことも。
私の育った長野は内陸であり、海とは縁遠い。近しく生きてきた人ほど、呑み込まれた。
顔が真っ青になっていたらしい私の隣に夏希がいつの間にか座り、背中をゆっくりとさすってくれている。私は言葉を失ってしまったように何も言えなくて、無言の優しさを享受した。つらかったら、いつでも東京に戻ろう。夏希はそう呟いた。東京。私たちを繋いだ場所。誰もを受け入れてくれて、同時に放っておいてもくれる、東京。戻ってじっと蹲っていれば、いずれ正常に戻る。やがて春が来て、忙しなく過ごしているうちに別の悩みに覆われていくだろう。あーちゃんの影が薄まり、私はきっと楽になる。
けれど、消えてなくなるわけではない。
私はどうにかして前に進みたかったし、進まなければならなかった。そのためにここに来たのだから、まだ女川にも着かないうちに根をあげていては、意味が無い。
どこまでも沈んでいくために、沈んで、沈んで、その昏い海底にあるなにかを見つけるために。
首を振り、水を飲む。僅かに歪んだ表情を浮かべた夏希に笑いかけた顔を、私自身が知ることはない。
続きは短編集「どこかの汽水域」にて。他、二篇収載。
1月17日通販開始予定。よろしければお手にとってみてください。
たいへん喜びます!本を読んで文にします。
