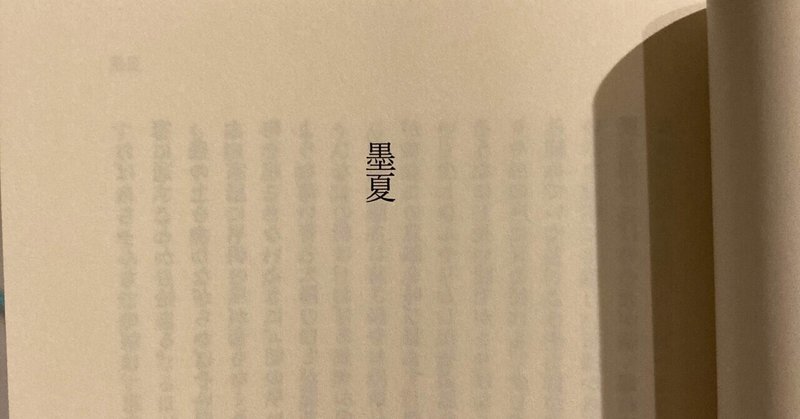
墨夏【試し読み】
あらすじ
毎年お盆におばあちゃんちを訪れるひなこは、お母さんにもお父さんにもおばあちゃんにも言っていない秘密の場所を訪れる。夏の陽光のもと、河川敷では、村に住む少年昴に会える。金星の大接近を待ちわびているひなこは、天体に詳しい昴に教えてもらいながら、星の世界に思いを馳せる。夏の大三角形、カシオペヤ座、北極星ポラリス、そして少年と同じ名を持つ冬の星、昴。星を巡る会話を重ねるごとに、ひなこは昴の真摯な姿に惹かれていくが……。
墨夏
おばあちゃんちでの朝は、家中の襖を順番に開けていって、外を揺蕩うしずかな空気を家に通すことから始まる。
畳の上をすりながらかぼそい指先で行う所作にはいつも余裕があり、眠りについていた古い家屋に早朝の風が音もなく入り込んだら、安心して家が呼吸をしだす。ひとつひとつ、町を起こさないように。朝の早い虫の声が僅かに大きくなり、水に一滴インクをこぼしたような薄い青と太陽の白とが混ざって、外と内の境界線を曖昧にする。
ひなこの朝は、おばあちゃんの物音で始まる。
両脇で眠るお父さんやお母さんの寝息やいびきではなく、かすかに鼓膜をこするあの音がひなこの意識を呼び覚ます。それはまさに風が通り抜けていくようだった。肌を撫でていく少しひんやりとしたそよ風を感じ取るように、ひなこはちいさな瞼を開ける。音が出そうなほど長い睫毛がさりげなく瞬く。続いて、両親の眠る気配を嗅ぎ取り、鳥のさえずりや虫の声に耳を傾ける。少しずつ輪郭があきらかになっていく朝の過程をひとしきり噛み締めていくと、ようやく目が覚めたと自覚する。二人を起こしてしまわないように、ちいさな身体には重たい布団から這い出て、おばあちゃんの開け方よりもずっとゆっくりと襖を開ければ外の光が細く漏れる。部屋を出ると、そのまま縁側に足を踏み入れることになる。
光の透けた縁側をおぼつかない足取りで歩いていると、途中でおばあちゃんに出逢い、挨拶をする。ひなちゃん、早いね。おばあちゃんはゆっくりと礼をしてから、言外に偉いという雰囲気を醸し出させて言う。うん、とひなこは微笑んだ。その後は一足先に居間へと向かい、紫紺の座布団に囲まれたテーブルのはじっこに座る。テーブルの上には、ドロップ缶ほどの大きさの古びたラジオと、まだ手のつけられていない朝刊が置いてある。ひなこはラジオのアンテナをめいっぱい伸ばし、窓側に先端を向け、電源を入れる。既にNHKのちょうどいい周波数に合わせてあるから、すぐに人の声が聞こえ始めた。
政治がうんぬんかんぬん、世界情勢や紛争がうんぬんかんぬん、景気がうんぬんかんぬん、世間を取り巻く報せは飽和しているけれど、ひなこにはどれもよくわからない。まだうんと難しい。けれど、微妙にノイズが混じったような乾いたラジオの音声は耳心地が良く、好きだった。そして、金星が接近するというニュースを待った。ひなこにとって、唯一なんとなくわかるニュースだったし、最近の最大のトピックスだった。宇宙のこまかさは解らないけれど、月のクレーターも土星の輪も知っているし、太陽がものすごく遠くてものすごく熱いこと、そして金星が地球のおとなりさんだということも知っている。おとなりさんなのに気が遠くなるほど遠くて、夜空で見えるときと見えないときがあり、もうすぐ、おとなりさんがものすごく近くまでやってくるということだった。ひなこは無性に日々わくわくしていた。ぼんやりとわくわくしていると、いつのまにか近くで油蝉が鳴き始めていた。
お母さんが起きておばあちゃんと並んで台所に立ったのだろう、やがて包丁がこんこんとまな板を叩く音や、勢いのよい流水の音、ガスコンロで火を点けるときのちちちちという囀りのような音、お湯の沸く音だったり、そうしたさまざまな営みに伴う音たちが、家の静寂を少しずつめくっていく。音は空間を抜けて家のすみずみまで行き渡った。ひなこはそれらの生活音を、ラジオ音声を聴く耳とは別の耳で聴く。家が動き始め、朝が動き始め、人が動き始めた流動的な気配は、少女をにわかに浮き足だった気分にさせ、いてもたってもいられなくなったように立ち上がった。
木製の重厚なテーブルに、次々と朝食が運ばれていく。
にんじんや蒟蒻、じゃが芋やスナップ豌豆等を彩色豊かに敷き詰めた夕べの煮物や、焼いたししゃも、絹豆腐と蕪に若布も入った味噌汁、ひかひかと光沢をはなつ白米などが食卓にいっぺんに並べられる。ひなこは箸を丁寧に並べていく係で、そうしている間に一番遅起きのお父さんも起きてくる。
ひなこが一番好きなのは、朝採ったばかりの真っ赤なミニトマトが入ったサラダだ。プランターで植えられているミニトマトはすぐに用意できるように、台所から直接外に繋がる通用口のすぐ出たところに置いてある。ひなこは料理のお手伝いをするたび、ミニトマトを採りにサンダルを穿いた。真っ赤で、はちきれそうなくらい膨らんで、お日様をたくさん浴びてきらきらしている美味しそうな実を選ぶのだ。
ミニトマトと合わさるのは、冷蔵庫でうんと冷やしたしゃきしゃきのレタス。醤油ベースのドレッシングを適度にかけて頬張ると、レタスは力強く反発し、瑞々しい採れたてのミニトマトは噛み締めると甘い果汁が膨らむ。自分で採ったミニトマトということもあって、美味しさは数倍にもなるのだった。
朝食を終えると自分の皿を流しに出し、ひなこはさっそく出かける準備をする。
お父さん、お母さん、それにおばあちゃんはいつもよくわからない話をして、ひなこは頭の中がまっしろになってしまって、目の前がぐるぐるとして、大人の輪の中に入れず疎外されている雰囲気が居心地悪くて、眠くなってしまう。だからいつもそうなる前に出かけてしまうのだった。おばあちゃんは朝食に合わせてこさえたおにぎりをひなこに持たせ、お父さんは川に近付くなよ、と警告した。いつも口を酸っぱくしてそう言う。
小さなリュックサックにおにぎりの入った弁当と、お母さんが用意してくれた冷たい麦茶がなみなみと入った水筒を放り込んで、玄関口の網戸を開け放ち、ひなこは元気良く駆け出していく。
まだ朝の空気が張り詰めた外は、涼風が吹いている。おばあちゃんの住むこの場所は山に囲まれていて、ひなこの住む都会よりもうんと涼しく、とりわけ朝と夜は冷える。夜の間に急速に冷めた風は、日が出てもしばらくは涼しいままで山間を通り抜けていく。
ピンクのサンダルでひなこは細くゆるい上り坂になった道路を走り、突き当たりを左に曲がっていく。そこは町の商店街と住宅街を兼ねた場所になっていて、とはいってもほとんどが閉まっていて、それは早朝だからという雰囲気でもなく、ほんとうに閉まっている。錆びるに至る町の歴史を匂わせる、萎びた建物が静かに並んでいた。誰もいないようで、風を通すために開けられた玄関の奥では、人の動く気配がある。
ひなこの足音ばかりが町に響く。眠る町をたったひとりきりで冒険しているかのようだった。
ここの上り坂はおばあちゃんの家の前よりもうんと鋭い傾斜になっているけれど、いきどころのない力をたくさん抱えたひなこには大きな敵ではなかった。けれど走り続けるとばててしまうからぽつぽつと歩く。朝は涼しくとも真夏の直射日光はそれなりに鋭く、浴びているだけで汗の粒が額に滲み、やわらかで繊細な髪の毛が曲がりくねって肌に張り付いた。
誰も出入りしない道を、乾いたサンダルの音がこころもとなく通過する。
人気のない侘しい里山で、僅かに清流の音が浮かびあがる。
ひなこはその涼やかな音に引き寄せられるように歩く。つらい坂道をのぼりきると道は右へ向かって殆ど直角に近い大きなカーブを描いている。黄色い看板の前をひなこはちまちまと通り過ぎ、すると、古い家が密集していた景色は一気にひらける。遠くに鬱蒼とした山々、手前では力強く上へ上へと伸びる緑の稲が延々と続く田圃が広がる。蝉の声に蛙のくぐもった声が重なり、虫たちはちりちり、じいじい、ちちちちち、とあちらこちらで好き勝手に囁いている。そうした田圃が敷き詰められるばかりの中を一本の川が横切り、道はその川を跨ぐ橋へと繋がっていた。リュックサックをしょいなおすと、ひなこは迷うことなく橋のふもとの、岸辺へと向かう石階段を降りていった。階段のごつごつとした罅を埋めるようにオオバコの葉がちまちまと生えているところを踏まないよう無意識に気遣いながら、勢いよく駆け下りていき、砂利と雑草で埋め尽くされた河川敷へと辿り着けば、遠かった水流は目前である。
強くなってきた日差しを浴び、草花は自身の持つ色をいちだんと濃く染め上げる。
ひなこは自分の背丈ほどの葦の原を掻き分ける。素肌に当たってくすぐったいような痛いような、密度の高い緑の匂いを存分に吸い込むと、肺に限らず、自分まるごと緑に膨らんでいく。そうしてしばらくくぐりぬけていくと、川の傍までやってきた。足下の砂利のひとつひとつが太陽光を反射してまばゆく光る白銀の貝殻のようだった。今日の水流はゆるやかで透明だった。前日の雨風が強いと、こうはならない。もっと上流にある土石が削れて水嵩も随分増えて、全く異なるいきもののような濁った色となって、今ひなこが通り抜けてきた場所も踏みつけていく。
ひなこはしゃがみこんでからゆっくりとお尻をつけてリュックサックをお腹の方へひっくり返すと、中から水筒を取り出し、氷入りのきんきんに冷えた麦茶を口にした。乾いた喉を存分に潤す恵みが喉を通り抜けて、冷たさを内側に感じる。
ちち、ちちち、と小鳥の群れが頭上を通り過ぎていく瞬間、随分と近くで鳴いたような感覚で聴いていた。
水筒を隣に置いて、もっと水流の方へ近付いてみる。ほとんど濁りのない透明度の高い水で、底を埋める岩の鈍角や、水に流されていく小石の動きが音まで伝わってくるようだった。そうした水流の一番手前の浅瀬に視線を向ければ、ちろちろと指先ほどの大きさの、メダカのようなオタマジャクシのような黒い魚が小さな群れを成して泳いでいる様子を発見して、ひなこは身を乗り出した。ぐぐっと顔を近づけると自分の黒い影の中でその魚たちはひらひらとほんのわずかな尾びれを忙しなく動かしていて、よくよく観察すると風にたなびくシーツのようでもあって、おばあちゃんやおかあさんが外に洗濯物を干すあの透いた清潔感を彷彿させ、それが米粒の大きさの生き物の動きに凝縮されているのが不思議で、ひなこの目は一瞬釘付けになる。気になって数えてみたもののの、十を通り過ぎたあたりで動き回る魚たちに目がしばしばと乾き、わからなくなってしまった。
どうして、とひなこは思う。どうしてこんなにも小さいのに流れに負けないのだろう。今も水流は、轟々という凄まじい勢いまではなくとも、途切れることがなく、穏やかでありながら傾斜に任せて頑張って競うように走り続けている。そして魚たちはもっと頑張っていて、小さな身体のどこにそんな馬力ならぬ魚力があるのか、ひなこには漠然と不思議だった。ひなこは暑い中なんの抵抗もない坂をのぼるだけでも疲れてしまうのに。気になって手を水面下へ投入した。氷で極限まで冷やされた麦茶の温度を想定していたら、意外に少し温かく、しかし魚たちは驚いたのか一目散に分散してしまって、ひなこはあっと声をあげた。
群れは消えた。ばらばらになった。それぞれが孤立し、見えなくなった。
なんだか後ろめたい気持ちになり、別れた魚の中で、できるだけの行方を目で追っていたが、じきに石の隙間や水中から伸びる草の影に消えてしまった。
なんともいえないもやのかかった感情を抱えながら、濡れた手を引く。丸い指先からしたたり落ちる水を簡単に払い、周囲に視線を配る。川を渡る風は涼しくて心地が良かったし、草のざわめきも小さな森の中にいるかのようでひなこの冒険心がくすぐられた。
魚群の発見箇所を離れて左側、川上の方面へ少し歩いてみると、数歩先に濃緑の中に鮮やかな黄色が覗いていて、近寄ってみる、小菊だった。横たわっていた小菊はちょうど盛りだったように花弁をそれぞれ豊かに開いている。見えない場所に置いておくには勿体なく、ひなこの胸の中はむずむずとこそばゆいような思いになり、見えるところに束を直しておけば、いくらか気が紛れていった。
「ひなちゃん」
頭の上から急に声が降り注いで、はっとひなこは振り返る。
すぐ傍まで来ていたのは、ひなこよりも一回り背の高い、いくらか皺の寄ったまっしろなカッターシャツと黒いズボンを身に着けた少年で、夏の色鮮やかな花々というよりも、春の桜のようなやわらかく儚げな笑顔を浮かべていた。
「ひなちゃん、おはよう」
「おはよう」
ひなこもつられて白い歯を見せると、その少年の身体にとびこんだ。濡れたままの手で握りしめるシャツは少し湿り気をおびているようで、でもパリパリと独特の質感がして、おひさまの匂いがして、日干しをしたばかりのおふとんを連想して、ひなこの前で膨らんだ。
少年はひなこよりも頭二つ分ほどは大きく、ひなこの頭が少年のお腹のあたりにたどりつき、パズルのピースがはまるようにちょうどよく収まっている。そうした、互いの成長過程で偶然重なったちょうどよさがひなこを心地よくさせた。
名を昴といった。
ひなこと昴は葦の途切れた川岸に座り、お喋りに興じた。気温がぐんぐん上がってくる気配があったが、絶えず流れる川の傍にいると、いくばくか体感温度は低く、ときおり跳ねてくる水や水流の音楽が更に涼やかにさせた。この場所は納涼の地で、秘密基地だった。
ひなこは、おばあちゃんちに置いてあった図鑑を開いて、昴というのが星にまつわる言葉であることを話した。
おばあちゃんちには、幼いひなこにはとても読めない難しい本から、昔お父さんやお母さんが子供だった頃に読んでいたような気配のある、古びた子供向けの絵本まで、様々な書物が揃っている。本の並ぶ部屋には独特の香りが漂っていた。紙が長年の空気に触れて発酵していった、不思議な香りだ。星の観察についておばあちゃんに相談したら、本の部屋に案内されて、ひなこは初めてその香りを嗅いで、触れて、没入した。第一印象は苦手だったけれど、しばらくいるうちに慣れて、いつのまにか本の空気と自分が一体化しているかのような雰囲気を味わった。おばあちゃんは星の図鑑を取り出した。図鑑は、古いけれどもどこか真新しさも兼ね備えており、きっとあまり人の手に触れることなく本棚に収まっていたのだろう気配があった。おばあちゃんの指は確実にその図鑑を覚えていて、滞りなく背表紙を見つけ出し引き抜いた。写真が大きく載っていて、字も大きくて、丁寧にひとつひとつふりがなが愛情深くふってあって、絵本しか経験したことのないひなこにもなんとか読めそうだった。
ひなこは一冊の重たい図鑑を抱えて、夜の虫が鳴き始める頃、畳に座り込んでページを捲った。
太陽の話、お隣の火星の話、月の話、つまり太陽系の話。巨大な朱い灼熱の太陽の周りを惑星がくるくると円を描いており、青い地球はその中のひとつとしてぽつんと存在していた。
けれど宇宙は太陽系だけのものではなくて、その更に外側にまでずっと延々と続いており、地上から見える星たちについてひなこは見つめた。星座、そして銀河。彗星。あらゆる名をつけられた宇宙が存在していた。昴はその中で慎ましくひっそりと載っていた。おうし座にあるプレアデス星団とよばれる星の群れを示していた。おうし座は理解できたけれど、プレアデスセイダンはちんぷんかんぷんだった。プレアデスセイダンはわからなかったけれど、すばるという響きは既にひなこの中にすんなりと収まっており、ひなこはその時少年昴を思った。星の名を持つ少年が、遙かな宇宙に浮かび、静かに溶けていった。
そうしてひなこは少年を前に、図鑑で見つけた昴の話をした。少年昴はにこにこと相槌を打つ。
「昴は、冬の星なんだ。肉眼でも見える」
「にくがん?」
「夜空をそのまま見上げたら、見つけられるっていうこと」
「今度の金星みたいに?」
「うん、そう」
金星は、いつでも煌々と輝いていて、晴れていれば普段でもよく見えることを少年は知ってか知らずか、口を挟まなかった。
もうじき、金星が地球に接近する。数百年に一度、というほどの大接近、その天体ショーは俄に地上を賑わせていた。偶発的のようで、しかし緻密な計算のうえに導き出された結果である。ひなこは金星の大接近をテーマの中心にして、星の観察を夏の自由研究にしようと考えていた。
「じゃあ、今は昴は見えないんだね」
ひなこは残念そうに言う。
「そうだね。でも、半年後には見えるから、そのときまで覚えていたら空を見上げてみてよ」
「うん」
ひなこは大きく頷き、冬の空について思いを馳せた。
冬の空は曇りがちだ。雲が町に覆い被さり、はっきりとしない天気が続く。曇天から雪が落ち、とりわけこの山の中にある村は雪に埋もれていく。延々と大粒の雪が視界を埋め尽くし、積雪に更に重なっていき、大層な雪の壁となる。除雪車が毎日通り、人力の雪かきは冬の大仕事だ。足である車が動けなくなり、屋根に積もった雪を落とさなければ家が潰されてしまうから、休むことはできない。
雪は大気の汚れをその身で包んで、下へ下へと落としていく。
そのおかげで冬の空気は澄んでおり、時折晴れ渡る夜空は冴え渡って輝く。決して激しい主張ではなく、厳かにたたずまい、しんと光る星たちである。僅かに明滅するひとつひとつの星は、無音ながら、密やかに会話をしているようだった。ひそひそと秘密の言葉を囁いている様子を、地上ではとうてい聞くこともできずただ眺めている。一面を覆う雪はみずから発光しているように、暗闇に青白く広がっている。その雪がまた音を吸い込み、静かに冷気を発する。
その空には、有名なオリオン座を成す七つの星が堂々と輝き、冬の大三角形が描かれている。そして、六つの星が群れを成して浮かんでいる。昴、プレアデス星団のかけらである。
ひなこは想像した。冷え切った澄み渡る空に浮かぶ六連星を、そしてそのままの瞳では見ることができないであろう、青白い霧のような星雲ガスを。寄る辺のない宇宙に浮かぶ、青く美しい星たちについて。図鑑の写真をもとに、想像した。
たったひとり、いや、隣に昴がいる。二人ともコートを着て、外に長くいても寒くならないようにしっかりと着込んで温かくして、お母さんが用意してくれた湯気の立ちのぼる甘いココアを水筒に入れたりして、口からは白い息を吐き、じっと夜空を眺めている。昴は、あれが昴だよ、と指で方角を教えてくれる。優しい声音で、懐の深い声色で、冬の張り詰めた厳かさを邪魔しないように、そっと教えてくれる。
素晴らしく素敵な光景のように思われた。
半年後を覚えていよう、とひなこは決意する。ひなこの星の研究は夏で途切れず、金星の大接近で終わらず、冬まで続いていく。冬の昴をにくがんで観察するまで。
「夏の大三角形は、調べた?」
夏の昴が尋ねる。今ひなこの隣にいる昴は、冬でなく夏に存在する。
ひなこは頷き、リュックにしまっていたノートを取り出した。ムーミン一家が表紙を飾る自由帳には、自由研究ノート、とマジックで書かれている。お父さんに、一つのノートにまとめるといい、とアドバイスされて作ったけれど、まだ白紙ばかりだ。最初のページに金星のことが書いてあって、次のページには昴、そして夏の大三角形と続いていた。
わし座、こと座、そしてはくちょう座、それぞれが抱く三星を結んで描かれる壮大な三角形は、日本では春頃から顔を見せ始め、真夏から九月あたりにかけてよく観察できる。堂々と翼を十字の形に広げたはくちょうは星の散らばった夜空でも圧巻の存在感を示し、ひなこでも容易にそれがはくちょう座だと理解できた。
「アルタイル、ベガ、デネブ、だよね」
「うん、そうそう。よくできました」
昴は頬を綻ばせて頷く。
星に名付けられた言葉は、普段の生活では発することのない特別な響きを内包しており、口にすれば秘密の呪文を唱えているようだ。昴が褒めてくれたことも嬉しかったので、ひなこはもう一度三星を繰り返した。アルタイル、ベガ、デネブ。神秘的な味をした飴玉を転がす。無数に明滅する星たちの中でかつて名付けられた言葉は、宇宙の味がする。
ひなこはふと、自分の名前も星につけたいと考えた。昴も、毎年夜を巡ってくる。青白い綿を発露させてやってくる。それは昴、隣に座る少年の名前。昴のように、ひなこも夜空に存在したら。アルタイル、ベガ、デネブのように特別な響きを持ったなら。そう考えると急に自分の名前も特別なものに変換されていくようで、胸がにわかに沸き立った。今夜、星を観察する時には探そう。ひなこの星を。そう決意した。
昴は河原を埋め尽くしている手頃な小石を拾うと、その場にひとつひとつ並べていく。その手つきをひなこは黙ってじっと見つめているうちに、あ、と声をあげそうになったが、じっと堪えた。彼の指先の動きはとても静かで、なだらかで、延々と眺めていたくなるような穏やかさに満ちており、その一筋の先にあるゴール地点になんの障害もなくひたむきに向かっていく。ひなこは居場所を与えられていく小石の陣形を理解し、昴の指がもたらす即興の描写を見守る。はじめに大きな翼と胴体が現れて、そこから少し距離を置いて、尻尾のついた平行四辺形や、三角形を二つ合わせて翼を広げたような、そういった点々とした地図が描かれる。
最後の一つが置かれて昴が尋ねるように顔を上げる。
「夏の大三角形」
「そう」
二人の意識が星座のように繋がる。
夏の大三角形を成す、三つの星座である。実際は、河原の石のように無数の星が彼等以外に存在する。肉眼では見ることができないほど暗くも遙か遠景のどこかに存在している星や、他に負けじと輝く恒星がちらばっている。
「はくちょう座はやっぱり見つけやすいね。まずはここを探すといい。はくちょう座から、少し離れたところに、カシオペヤ座も見られるかもしれない。カシオペヤは知ってる?」
ひなこは首を横に振る。
昴ははくちょう座の頭から少し距離を置いた方、夏の大三角形とは反対側の方へ石を五つ、軽々と並べた。ぎざぎざに並ぶ、小さな集まり。
「カシオペヤは夏よりも冬の方が見えやすいんだけど、形が特徴的だから条件が良ければ夏でもきちんと見られる。周りが暗いからね、見つけやすいんだ」
「冬の星なのに、夏でも見られるの?」
「そう。北極点に近いからね」
そうして、昴は身体を伸ばし、また小石を並べる。あえて大きな石が置かれ、そこから小さな凧が伸びるように他の石が並べられる。ひなこは真新しいノートを開き、熱心に昴の描く石の星図を書き写し、先程のWの形をした星座の近くにかしおぺあ、とたどたどしい文字を綴った。
「これはこぐま座」
最後に並べた星たちを指して、昴は言う。
「そしてこのお尻のところの輝く星が、北極点。揺らがずに北の方角を示す星だ。だからこの星は季節関係なくほとんど動かない。この星を中心にして、他の星はゆっくりゆっくりと動いていく。昔の人は、北極点を探して、歩く方角が正しいのか考えたりしていたんだよ」
ひなこはふうん、と曖昧に相槌をうち、こぐま座を描く。北極点は大きな丸をつけて、わかりやすくした。
「別名でポラリスともいう」
「ぽらりす」
「うん、ポラリス」
昴はひなこの隣にやってきて、鉛筆を借りる。ひなこよりも一回り大きい手が、ひなこのお気に入りのピンクの鉛筆を無骨に握り、ひなこの星図を邪魔しない程度にさりげなくその名前が記される。ポラリス。きれいな響きだとひなこは思ったし、昴の字体で書かれたポラリスは、更に特別な気配を漂わせているようだった。
ノートに、主要な星座たちが少しずつ現れて、ひなこたちの手元に宇宙が広がっていく。小石を置いていく行為も、ノートに描いていく行為も、空に浮かぶ見えない星たちを写し取っていく作業だった。決して届かない遠いものがてのひらに宿る。下を向いているのに、上空を見上げているような不思議。
「最初から見つけるのは難しいかもしれない。カシオペヤから辿るのが一番解りやすいかも。でも、まずははくちょうだね。そして夏の大三角形だ」
まるで宝の地図を渡されて、その道筋を示されているようだった。
「見つけられるかな」
「見つけられるよ。慣れてしまえばすぐに見つかる。今夜も空を見上げてごらん。ひなちゃんは、いつまでおばあちゃんちにいるんだっけ」
ひなこは少しの間だけ口を噤んだ。
「明日まで」
「そっか」
昴はわずかに微笑んだ。褪せたような色をした声で。
「寂しくなるね」
ひなこには宇宙旅行からの墜落のように思われた。
今まさに、銀河を渡る旅へ向かう途中で、地図をもってさあいこうとはりきっていたところだったのに、出鼻をくじかれたようだった。
続きは短編集「どこかの汽水域」にて。他、二篇収録。
1月17日、通販開始予定。よろしければお手にとってみてください。
たいへん喜びます!本を読んで文にします。
