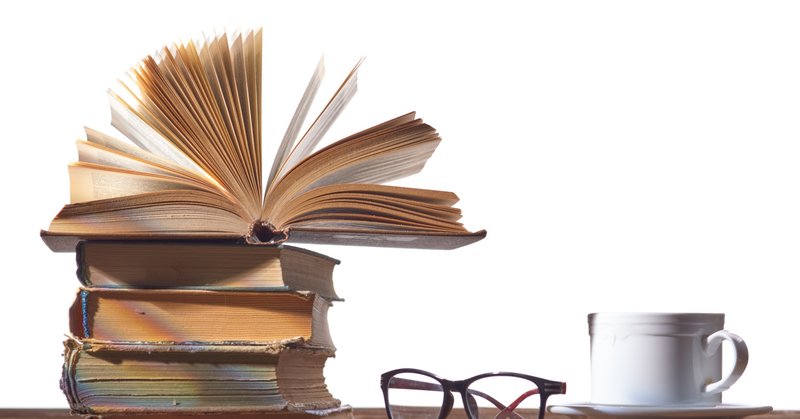
フリーライターはビジネス書を読まない(5)
ビジネス書のつくりかた
ここでちょっと捕捉。
安いノート型ワープロとモデムを購入してパソコン通信を始めたあと、ライターのグループに参加させてもらいながら、プロのライターになる道を模索していた。
そんな折、東京にある編プロの社長から声をかけてもらい、ビジネス書の5項目を書かせてもらうことになった。
じつはパソコン通信を始めてから編プロの社長に声をかけてもらうまで、ざっと2年近くの歳月が流れている。
さほど変化のない時期とはいえ端折りすぎて、ライターのグループに参加してから、わりあい順調にライターへの道が開けたような印象になってしまったかもしれない。
―― ―― ―― ―― ―― ――
さて、
編プロに送った原稿が戻ってきた。
そりゃそうだ。
プロでも修正の指示は付き物だから、素人が書いた原稿が一発OKになるわけがない。
ところが自分でも意外だったのは、修正の指示は5本中の2本だけだった。それも言い回しとか文章の出来ではなく、具体的なデータをもう少し増やせという指示だった。
本当にそれでいいのか心配になったので、電話で問い合わせてみたら「文章はこれでいいです。データはなるべく新しいほうがいいから、新聞の経済欄を参考にしてください」と。
今から思えば、文章は編プロで修正できる。本人に修正させるより、そのほうが少ない労力で済むという判断だったかもしれない。
後日、再び図書館を訪れて、社長に指示されたとおりのデータを盛り込んで修正した原稿を送り返した。
その本が出版されるまで、3カ月ほどかかったと記憶している。
著者でもゴーストライターでもないので、見本版は2冊しかもらえなかった。
宅配便で送られてきた本の表紙には、聞いたことのない人の名が「監修」として載っていた。本には必ず著者があるものと思っていたから、意外な感覚だった。
それはともかく、真っ先に開いたのは、やっぱり自分が書いた項目だ。
文章には思いのほか手が入っておらず、私が書いた文章の片鱗が多く残っていた。
類書からコピーした図表は、デザイナーの手によって、見事に別物に生まれ変わっていた。もちろん出典は明記してある。
たとえ5項目しか書いていなくても、自分で書いた原稿がこうして本の形になっていることが嬉しかった。
と同時に、新しい発見もあった。
書店に並んでいる本には必ずしも著者がいるわけでなく、出版社の下請けで編プロが制作するケースがあることや、そこからさらにライターに依頼して原稿を書かせているという、いわば業界の現実を垣間見たのだった。
その月末、人生初の「原稿料」が振り込まれた。
こうして曲がりなりにも、プロを名乗れることになった。
まさに有頂天だった。
つづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
