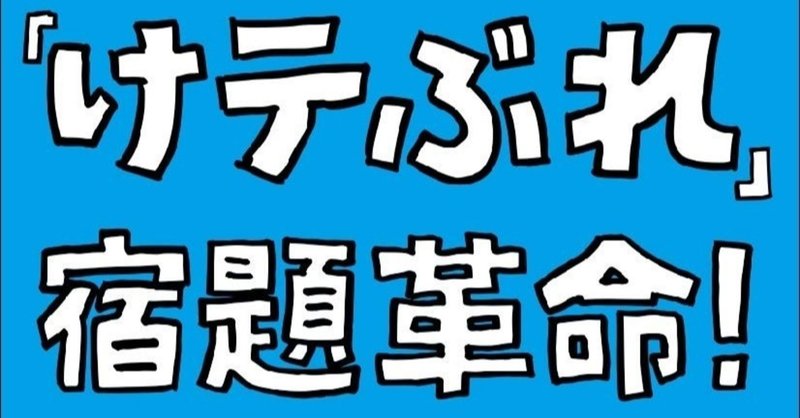
教科担任制でもできるけテぶれ実践!②
こんにちは!けテぶれ実践紹介、パート②です!
前回の内容↓
コンセントを探せ!で終わってましたね。(#何の話)
環境を見つめて、改善策を!
前回のnoteでリストアップした、わたくしの状況はこんな感じ↓
<どうにかなるもの>
・担当教科の授業づくり、仕組みの工夫
・一部の曜日の朝のモジュールタイム(10分)の内容
・火、木の「自主勉day」の内容
<どうにもならないもの>
・月、水、週末に出す学年統一の宿題(なくすことができない)
・受け持ち以外の授業(もちろん授業づくりの相談や情報共有はするが)
・担任裁量での時間割変更
まず何したの??
「教科担任制+学年で統一の宿題がある」ということを加味すると、まずはじめに必ずやらねばならないことは、学年の先生にけテぶれを広めることです。これは、避けては通れません。なぜ、けテぶれなのか。どのように既存の仕組みに組み込みたいのか。何を、どう、一緒に進めてほしいのか。そのあたりを丁寧に伝えましょう。
ここを自分の言葉で語る。周りの先生方からの質問に答えたり、どう自分の学校の仕組みに組み込んでいくか考えたりすることで、より自分の中に理念や大事なポイントが入ってくるでしょう。
ステップ① 学年統一の宿題からテコ入れ!
うちの学校では、国語&算数を内容を統一して出しています。(賛否は一旦スルーでw)せっかく全員に同じ宿題を課しているのであれば、それを利用して、「テ」と「ぶ」の力を伸ばそう!と考えました。4月、けテぶれの流れを子どもたちにもざっと説明した後、「本格的にサイクルを回す前に、普段の宿題のクオリティをあげよう!」と伝えました。
実は、学年がスタートして何度か宿題の実施状況を見ていると・・・
・間違っていても丸をつけている。
・難しそうな問題は答えを写す。
・間違えたらとりあえず赤ペンで直しているだけ。(解説なし)
というような児童が何人もいました。
それだけこれまでの宿題に対する意識が低かったということでしょう。(誰が悪いって話ではなくね。)その意識改革を徹底的にやってやろうじゃないか・・・( ^ω^)って感じですね。
褒める、認める、広げる!
けテぶれサイクルを回し始める前に、本気の丸つけの大切さ、自分のミスを見つめる重要性を伝えたい!と思い、ひたすらに声をかけ続けました。そんなことをしているうちに、少しずつ改善が・・・!
・毎日丸つけミスなくやりきれるようになった子
・自分のミスを書き記し、蓄積していく子
・解説を読んでもわからないときは「わからないから教えてください!」と付箋を貼ってくる子
などなど。自分の学習を自分事にしはじめたなという手ごたえがありました。そんな姿をすかさず褒める!!!めっちゃ認める!!!!!からのシェアしまくる!!!!!!!!(学年の先生にもお願いして両クラスで)
そうすると、どんどん相乗効果で加速していきますよね。
てことで、とりあえず今回はこのくらいで終わり!次回はミスの分類どうしたの~的なことについて書こうかな~。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
