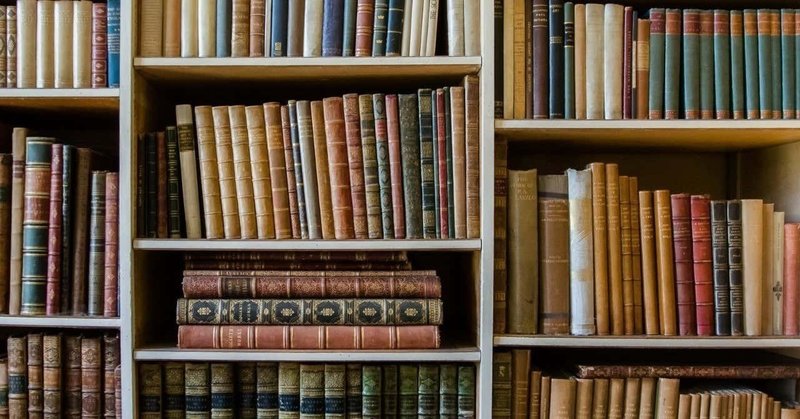
組織について考えるマン
今日は北野唯我さんの著書を2冊紹介します!
一冊目はこちら!「分断を生むエジソン」
あの名作、「天才を殺す凡人」の続編でした。
読了。いやー、天才を殺す凡人に続きすごく良かった。
— つっち~🌪️私立小の先生📮📚️ (@tuchiblanka) February 15, 2020
・ペインとゲイン
・影響力の地図
非常にわかりやすい。
そして、
どの会社にも「新しい物を作る人」と「今あるものを守る人」がいる。どっちが良い悪いではないよなと改めて思った。
分断を生みたがる人よ。自覚しているか?@yuigak pic.twitter.com/DpaGPTlhLH
ペインとゲインって?
この作品では、商品やサービスには「ペイン型」と「ゲイン型」があると述べられていてる。それぞれ簡単に言うと、面倒や苦痛を取り除くものがペイン型。それ自体が楽しく、面白いものがゲイン型。ペイン型の具体例は、Amazon。ゲイン型の具体例は美味しいレストラン。
ペイン型からゲイン型が求められる世の中へ
様々なペイン型のサービスの発展により、人々はゲイン型を求めるようになってくる。よく言われている、「役に立つ」→「意味がある」への転換ですね。もちろん、何か(誰か)の役に立つことにはすごく価値があると思うけど、それ以上に「どんな意味を創出していくか」が求められているんだなということですね。
じゃあ、学校はどうするの?
自分なりにできる一歩目としては、目の前の子どもたちに対し「そんなことやっても意味がないよね」という見方でみるのはやめようってことですかね。「誰にとって何が意味があるのか、どう意味があるのか」は教師の一方的な視点で見極められるものではない。そのあたり子どもたち同士のそれぞれに大切な「意味」が混ざり合っていくような場を作れたらいいな。
分断を生むとは
ツイート内容にあるように、「新しい価値を生み出そうとする人」がいれば、当然そこには「今までの価値を守ろうとする人」がいるわけで、全員がどちらからに偏るってことはない。そこでわざわざ「区別」しようとするせいで、「分断」が生まれる。いろいろな価値観があっていいよね。みんな違って~・・・なんて言うつもりはないけれど、自分の立ち位置をきちんと知って、相対的に周りがどうなっているのかを俯瞰し、溝を掘る作業でなく、橋を架けるアプローチすれば、分断や対立にはならないのかなと考えた。これが「影響力の地図」の話から思ったこと。(本ではわかりやすく図解してあった)
色々な価値観の人々でできあがっている組織。影響力の地図は忘れないでいこう。
もう一冊も紹介!
こちら!「オープネス」
オープネス読了。
— つっち~🌪️私立小の先生📮📚️ (@tuchiblanka) February 24, 2020
北野さんのやっぱり読みやすいな😙
【キーワード】
・組織の規模とオープネスは関係ない
→組織がデカイからって諦めない
・オープネスが高いこと≠正義
→仲良し組織を目指すことが正解ではない
・誰に何をどのようにやってもらうか
→士気と役割のマネジメントだね@yuigak pic.twitter.com/uDEoOExIxw
こっちがツイートにそれなりにアウトプットしてる。(えらい)
そもそもオープネスってなんぞ
この本の中では、「経営開放性」「情報開放性」「自己開示性」と示されてます。経営陣の思いや人柄はわかっているか、アクセスしたい情報にすぐアクセスできるか、自己開示をしても安心な場が保証されているかってことですね。
あなたの職場はどうですか?
上の三つ。ちなみに「風通しが悪い」のに「社員の士気が高い」って会社はほぼ存在していないそうです。(そらそうだ)あと、意外にも給料と社員の士気の相関関係はそこまで高くないらしい!そこで、この「風通しの良さ」(オープネス)に注目し、組織改善の提案をしていこうって流れですね。
ミドル層としてできることは何かな( ^ω^)・・・
と、まぁ読んで自分ができそうなことをメモしておきます。
・気軽に相談してもらえるような環境づくり
・上手くいかなかった実践や児童・保護者対応もシェア
・ニコニコする
・個人の選択を尊重しつつ、意見を述べる
・誰がやっても同じ業務にきちんとラベリングし、気持ちよくやってもらうような声掛けをする(教師の仕事はどうも属人化しがち。)
・改善に対して意欲が高い割合をつかみ、アプローチする人を見定める。(ムーブユアバスとも通じるなと思った)
創造性だけではダメなんだろうな
この本の中の印象的なフレーズ
タレントマネジメント論が本質的に解かなければならないのは「ある程度、人々の創造性を犠牲にしながらも、それでも人々がイキイキと、かつ生産性高く働ける環境をどうつくるのか」という問いである。
やれ、創造性だ!多様性だ!個性だ!とか言いがちな方々の気持ちを一旦冷静にさせる言葉ですね笑 すごくしっくりきました。
終わりに
とりあえずつらつらと書きたいように書きました。組織について学ぶのはホント面白い。また皆さんのおすすめあったら教えてください^^
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
