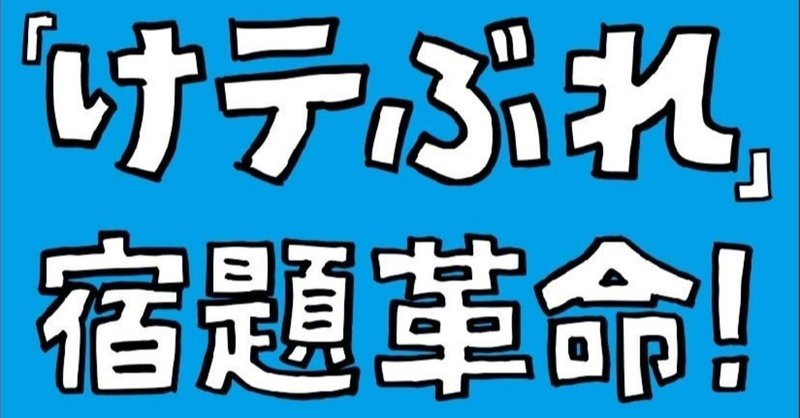
教科担任制でもできるけテぶれ実践!①
おはようございます。気が向いたので、2019年度のけテぶれ実践を振り返ります。来年度実践始めたいと思っている方の助けになればと思います。(/・ω・)/イェア
まぁ、思い立った理由の1つはくずぴ先輩のツイートにエンパワメントされたからで笑
いかん、やりたいことが沸いてきて早く月曜日職場に行きたいってなってる。
— つっち~🌪️私立小の先生📮📚️ (@tuchiblanka) March 28, 2020
久しぶりにくずぴ先輩のTwitter遡って色々見てたらムズムズしてきた。
4月から先行き不透明だけど、やるべきことを、最高のパフォーマンスで、やりたいようにやる。実践者であり、伴走者としてもがんばる。#けテぶれ
この記事のテーマ
わたくし、小学校での実践者です。そして、うちの学校の高学年は教科担任制を実施しています。「教科担任でもできるけテぶれ」をテーマに書いていこうと思います。どちらかというと、中学校のの先生方の参考になればと思います。
自分を取り巻く環境を見つめよ!
まず、実践をスタートする前に把握しておきたいのは、自分が何を担当するのか&実践に際し、自分の裁量で「どうにかなるもの」と「どうにもならないもの」は何か、ですね。
まず、わたくしの2019年度を見てみましょう。
<担当>
・5年1組担任 20人(うちは学年2クラス)
・担当教科 社会科、体育、英語 (1、2組どちらの授業も担当)
道徳(自分のクラスのみ)
<どうにかなるもの>
・担当教科の授業づくり、仕組みの工夫
・一部の曜日の朝のモジュールタイム(10分)の内容
・火、木の「自主勉day」の内容
<どうにもならないもの>
・月、水、週末に出す学年統一の宿題(なくすことができない)
・受け持ち以外の授業(もちろん授業づくりの相談や情報共有はするが)
・担任裁量での時間割変更
思いつく限りこれくらいでしょうか・・・。
差し込み口を探せ!
けテぶれを実践してみたい!!
いつ、どこで、どのように工夫すれば導入できそうか考えてみましょう。
そして、ぴたっとはまるコンセントを見つけてください。
規格や、電圧、穴の形をよく見極めて、どうすればカチッとはまるかを見てみると、意外とやれることは多いと思いますよ。(あれ?コンセントの話になってる)
とりあえず、今回は以上!また次回。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
