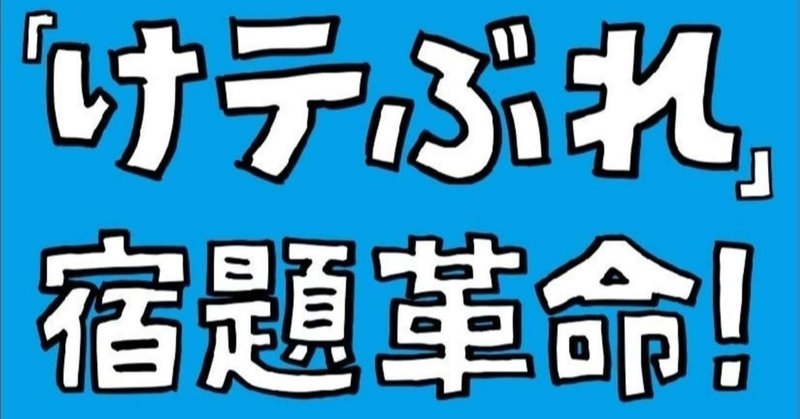
教科担任制でもできるけテぶれ実践!③
新年度スタートお疲れさまです!パート③です!
前回の記事↓
前回のは、テコ入れのステップを紹介した記事!統一の宿題を改善し、「本気の丸つけ&分析の習慣化」をしたよーって話でしたね。今回の記事は、具体的に分析の視点をどう授けたの?ってことを!
ステップ①+α 「分析してね」では分析できない
「本気の丸つけ」の習慣化は比較的簡単なんですよ。次の日のモジュールで同じ問題を扱う、授業で小テストをするなどとアウトプットの場を少し工夫すれば・・・「あれ?宿題でやったはずなのにできないな・・・」→「間違って丸つけしてるやん!」→「ちゃんとやらんと( ^ω^)」みたいな気づきが起こりやすいからです。
※もちろん模範解答と自分の答えを照らし合わせながら丸つけをすることに困難さを感じる子もいるので配慮必須ですよん!
じゃあ、なぜ分析の習慣化は難しいのか?
シンプルに「どんな視点で見つめればいいかわからない」からかなと思います。こちらから視点を提示してあげることで、自分のミスにどんな傾向があるのか、それを見つめ、蓄積し、次の繋げることができます。
てことで、分析の視点ドーン!↓(くろちゃんありがとう)

基本的にこの分類でいけるはずです。
ひたすらに蓄積していく!
子どもたちはどんどん、ワークの空いているスペースやノートの隅に「〇ミス」とメモをしていきます。わたくしは読1→Aミス、読み2&解く2→Bミスなどと名前を変えていました。(英語にするとかっこいいやん?)
ミスした問題の横に「Aミス!」などと書かれていきます。ふと見返すと、「自分は〇ミスが多いんだな・・・」と気づくことができます。
とある男の子の成長を紹介します。その子は理解力は非常に高いのですが、単元テストになるとどうしても満点が取れなかったのです。原因は単位ミスや、単純な計算ミスなど、少し気をつければ間違えなかったような所でのミスでした。教師側から「ちゃんと見直しをしたほうがいいよ。」「スピードより正確さだよ。落ち着いてやればいいのに・・・」とアドバイスをしてもなかなか改善しません。他人からいくら言われようと、自分事になっていなければなかなか改善に向かわないんですね。
ある日、ふと単元テストを見てみると名前の近くにめちゃくちゃ大きな字で「見直しする!!!」と書いてありました。早く解き終わる子ことに縛られず、とても真剣に自分の答案と向き合っていたことを覚えています。(結果はもちろん満点\( 'ω')/)
褒める、認める、広げる!
結局これかーい!というツッコミはスルーしておいて・・・。
そうやって工夫をし始めた子、自分を見つめて一生懸命成長している子の努力をどんどん広めていく。これに尽きます。なぜ2つの記事、連続でここを推すのか?
それは、意識していないと教師がついついスルーしてしまうからです。慣れって本当に怖い。成長を当たり前と認識し始めたら、小さな成長を見逃し、スルーしてしまう。そうでなく、日々、子どもたちの成長にアンテナを張り続け、発信していく覚悟を!
最後に
このミスの分類の大きなメリットを最後に。
わたくしのクラスではミスの分類が浸透してくると、「これってAミスじゃない??」「Bミス多いならこうしたほうがいいよ」などと、分析の視点が共通言語としてクラスで機能してきました。
「けテぶれ」って言葉自体も同じですが、この共通言語化ってかなり大きな武器になると思うんですよ。前提が共通理解されていれば余分なものをすっ飛ばして一気に本丸に迫れるので。
てことで、とりあえず今回はこのあたりで。グッバイ!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
