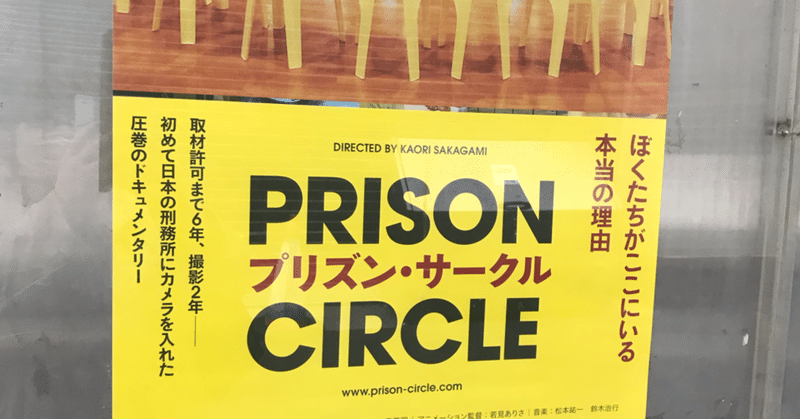
わたしは“彼ら”と同じく人間として生きているのか?「プリズン・サークル」という体験。
わたしをいまもなお、揺り動かさずにはいられない映画「トークバック」。その監督である坂上香監督の新作である「プリズン・サークル」を先週渋谷の映画館で見た。
(「トークバック」については以下のnoteを読んでほしい)
「プリズン・サークル」は、島根の刑務所で行われている受刑者の更生プログラムを丹念に数年にわたってカメラを向けた衝撃的な作品。それを見ていろいろ思うんだけど、1週間たってもまとまらず、結局見た直後のメモを、まとまらないままだが、ここにまた記すことにする。
世間では犯罪者を完全に「あっち」の世界の人間にしてしまってる。自分たちとは違う、異質な怖い人たち。受刑者たちも自己をそう思い納得し生きている。まずこれが現実。だが、プリズン・サークルの更生プログラムでの試みは「そうではない、こっちにおいで、いや、元からわたしたちはひとつの世界で生きているんだよ」と時間をかけて手招きし、それを受刑者に納得させ、共有させ、過去現在未来の自分を肯定する作業なのかなと。
それは、勿論罪を肯定するのではなく、自分が生きてきたこととこれから罪を抱えて生きていくことを肯定する、ということ。
それは時に、自分も誰とも同じ人間で有ることを知り、通じては他者の痛みを知り、尚且つそれでも生きていかねばならないという試練を得る、過酷な作業ともいえる。仮に「死刑になりたいから凶悪事件を起こした」と話すような「甘ちゃん」の受刑者このプログラムを課すとしたら、死ぬよりも厳しい試練だろう。
しかしこの映画の受刑者は、自分の過去現在未来を考えることを、やめない。支援者の力を借りながら、共に考えることをやめない。恥辱と従属のなかからではなく、対話することで自ら人間で有ることを知り、それを諦めない姿勢をいつしか見つけていく姿。それはどこまでも彼らはわたしと同じ、人間であるのだと、知らしめ胸を熱くするものであった。
しかし。その同じ人間でありながら、自分はこの映画で語られている世界では、どこまでも傍観者だとも感じ、それが何より痛かった。見て見ぬふりをしているものを見せられている、感。
そんな自分は、ときに現実から逃げようともする受刑者と、何が違うのか。彼らに向かい合う経験もなく、対話する度胸もなく、まだどこか怖いまま、ただ胸熱になって感動して帰る。それでいいのか。それでいいのか。その思いがいまもわたしの心を痛くさせてる。
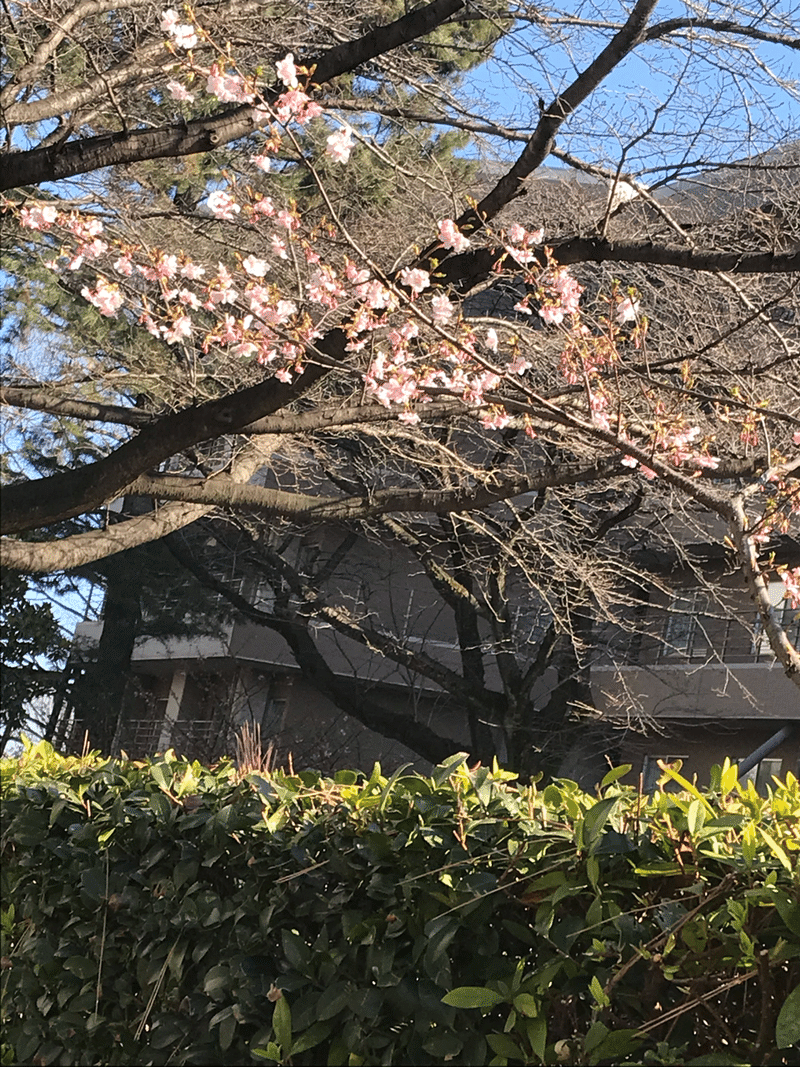
帰り、映画館近くの青山学院大学の試験がちょうど終わり、わたしは渋谷駅まで受験生の波の中歩いた。歩きながら「良いもの見たな」「でもわたしは偉そうに語れる立場か」「この受験生たちが見たらどう思うかな、見てほしいな」「いやなんで他人に見てほしいなんて思うのかな」
そんなことを自問自答していた。
結局、「プリズン・サークル」から突きつけられるのは、自分は彼らと同じく、「人間」として生きているのか、という問いなのかもしれない。
そして感じ取った痛みをこれからの自分の人生のどこに生かせば良いか、という疑問。その答えは今晩パパッと出るものではなく、あてもなく考え続けていかないことだとしか分からない。
囚われてるのは自分も同じではないのかと。全ての人と同じ人間、として生きずに、ただ先入観と諦観のなか、連綿と続いてしまう日常と言う牢獄に囚われ、知らぬ間に差別と偏見に陥りながら生きているのではないか。そうではいけない、と。
そう、映画の受刑者と同じく、わたしも「人間」だから。彼らと同じように、自分と他者と対話の末にたどり着く、あるがままの人間として、生きていかねばならないのだから。
とにもかくにも、いま、このタイミングなら、全国各地で上映されているので、ぜひ見に行ってほしい。どうぞこの機を逃さずに。坂上監督には、また「大きく魂を揺り動かされて」しまったわたしである。
いろいろがんばって日々の濁流の中生きてます。その流れの只中で、ときに手を伸ばし摑まり、一息つける川辺の石にあなたがなってくれたら、これ以上嬉しいことはございません。
