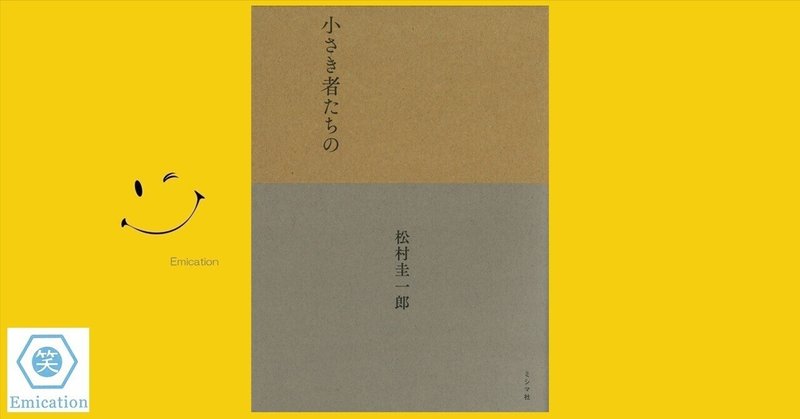
『小さき者たちの』(松村圭一郎・著)
“本のソムリエ”の薦める図書を読もうと、江戸川区の書店「読書のすすめ」の「成幸読書」に参加しました。
<成幸読書へのおもい>
「幸せになりたい」という願いは、古今東西人間であれば、誰もが持ったおもいでしょう。 そのためにこれまでも、たくさんの本や多くの人の思索がおこなわれてきました。
しかし、この願いがちょっとおかしくなってはいないでしょうか。
「成功」と「幸せ」はイコールではありません。「成功」とは功を成すということですが、あくまでも行動した結果論で目指すものではありません。
そんな想いから「成幸」といいいかえて、2002年に「成幸読書頒布会」をはじめました。その後もますます「成功」という言葉に対して、人より抜きん出るとか、上手いこと楽にこなしていく方法論のようにとらえられていくようになりました。
「成幸読書」は「幸せ」というモノへの気づきです。
資本主義社会はテレビやネットを通して見る人たちのさまざまな欲を駆り立てます。その結果、人生観や仕事観など本来の「幸せ」から外れ、余計な悩みや煩悶をつくりだしているのではないでしょうか。
「欲」はけっして悪いものではありません。「欲」が「幸せ」へとつながるのが本来の姿です。それに気づかせてくれるのは、読書を通じてのみだと思っています。私も本当の「幸せ」が理会できているかどうか疑わしいので読書をやめないのです。
皆さんと「成幸読書」をとおしていっしょに本当の「幸せ」と「智慧」を身につけてまいりましょう。
清水克衛
最初に届いたのが『小さき者たちの 』(ミシマ社・刊)です。
帯に
私は日本のことを、自分たちのことを何も知らなかった。(「おわりに」より)
水俣、天草、須恵村…
故郷・熊本の暮らしの記録を初めて解く。
現代の歪みの根源を映し出す、今を生きる人たち必読の生活誌。
とあり、著者の故郷・熊本のことが綴られ、そこから日本のことが述べられているようです。
本書を開き、はじめには
大きくて強くて多い方がいい。そう教えられてきた。人口の少ない田舎町よりも、大都会のほうが便利で進んでいる。就職するなら(略) そうやって、「大きさ」や「多さ」を称える価値観を知らないうちにさらされてきた。
と始まります。この価値観や当たり前を見直す読書となりそうです。
最初の章が「水俣」、そして石牟礼道子さんの小説の一節が最初です。
戦後の高度経済成長期に社会が元気なころ、その一方で“公害”が大きな問題となりました。その一つが「水俣病」で、そのことが述べられていきます。
“水俣病”という名称、メチル水銀化合物に汚染された魚介類を食べたことにより起こった神経系疾患、それが工場排水が発生源であったという程度の知識です。
水俣病をはじめ公害が人々を苦しめ、その回復や補償が行われ、環境改善が進んだと思っています。最近では“公害”という言葉・用語を聞くことがなく、「昔のこと」「済んだこと」と思っている人も多いのではないでしょうか。
本書では、水俣に関する記録から引用された言葉、文章、その背景、次へつないでいくこと、そこから見える「知らない世界」が、ていねいに述べられていきます。
そこにあるのは、“小さき者たちの生活”です。
そして、「生活」や「知」を繋ぐことの難しさがありました。
時代を経て、価値観が変わり、それによって記録された“表象”の判断(新たな価値観)が変わります。
それを、どのように残し、「何」を伝えるのでしょうか。
伝える意味は大きいのですが、その伝える相手(受け手)は「誰」なのでしょうか。
「無くしてはいけない」「風化させてはいけない」、「どうするのか」を考えさせられました。
本書の伝える“こと”を、しっかり受け止められただろうか。
これまでのこと、今のこと、そしてこれからを見つめ直す一冊です。
読書メモより
○ そこにあるのは、ただ手続きとして制度化され、金銭に換算された「責任」だけだった。もっとも大切なはずの「人間の責任」はどこにもなかった。
○ 「もう終わりにする」とチッソに伝えると、職員はほっとした表情で「正直言って、非常に困りました」といった。集団交渉なら企業としてどう対応すればいいか、定まっている。でも緒方は、その企業と患者団体との対決という構図を崩した。(略) 職員たちは、個人として交流せざるをえない舞台に引きずりだされ、困惑したのだ。
○ 原因企業のチッソも、監督指導する立場の行政も、人としての責任を果たそうとしなかった。その背景には「人を人と思わない」考え方の蔓延があった。
○ 元号も令和と変わる。同じように一日がただ過ぎていくだけなのに、そこに大きな時代の断絶を感じる。おそらく何ひとつ解決はしていない。世界の片隅でひっそりと引き継がれる小さき者たちの願いに、あらためて思いを馳せる。
○ 須恵村の女性たちのおおらかな姿に、現代の私たちがかつての日本の暮らしをいかに知らないか、痛感させられる。
○ 日本の隅々までこれだけ多くの大小さまざまな社寺が作られてきた理由がわかる気がする。カミのために人が祈るのではなく、人が祈りを楽しむためにカミが必要とされたのかもしれない。
○ 見えないウイルスに脅かされる日々のなかであらわになったのも、そんな不均衡な世界の姿だ。
○ 自分たちの目の前にはいない世界の片隅に生きる者たちへの想像力が、いま試されている。
目次
はじめに
Ⅰ 水俣1
Ⅱ 水俣2
Ⅲ 水俣3
Ⅳ 天草
Ⅴ 須恵村
おわりに
【関連】
◇松村圭一郎 (@kmatsumura15)(Twitter)
【関連:読書のすすめ】
◇読書のすすめ
◇読書のすすめ(YouTube)
◇読書のすすめ(@dokusume)(Twitter)
◇読書のすすめ(Facebook)
◇読書のすすめ 清水克衛の日々是好日
【関連:成幸読書】
◇成幸読書選定本
◇成幸読書頒布会お申込ページ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
