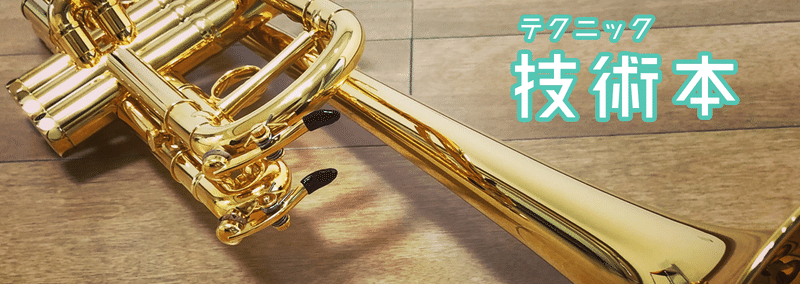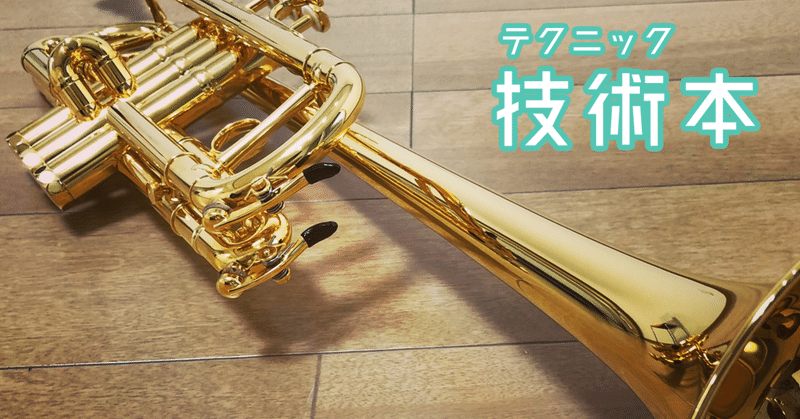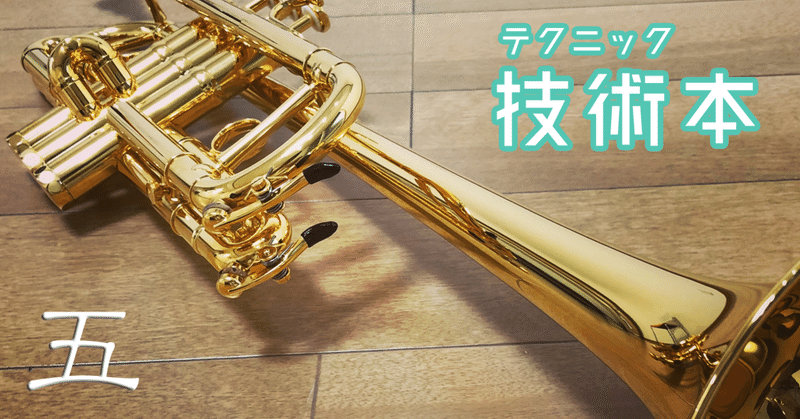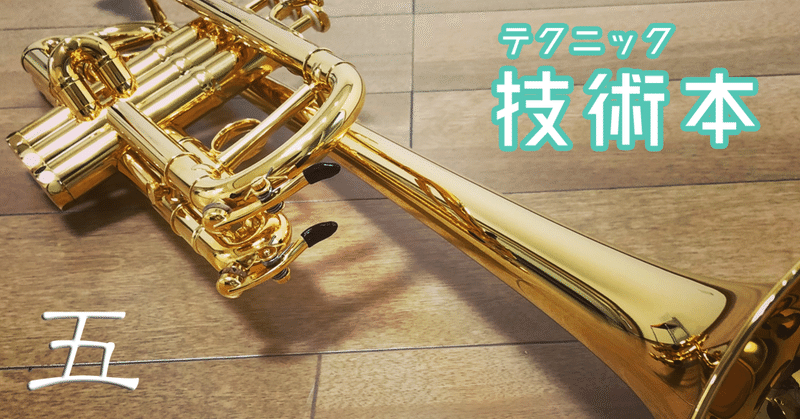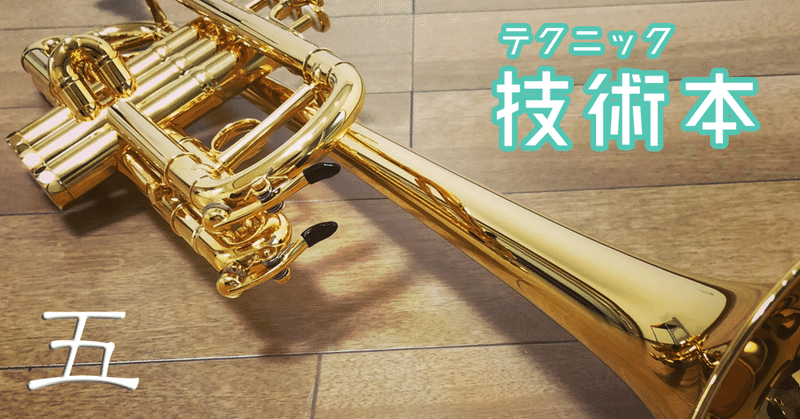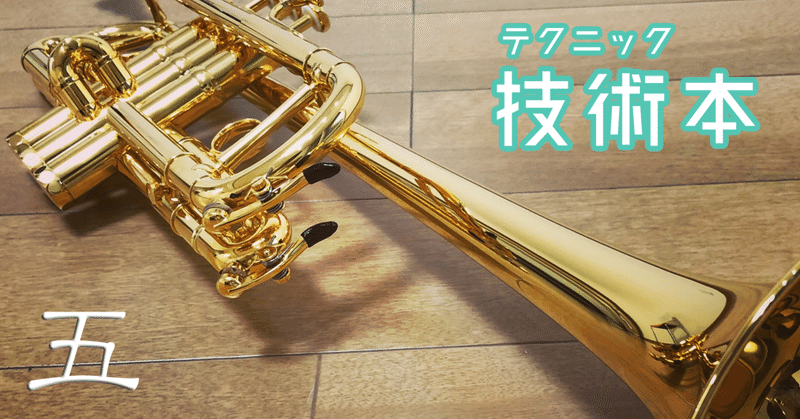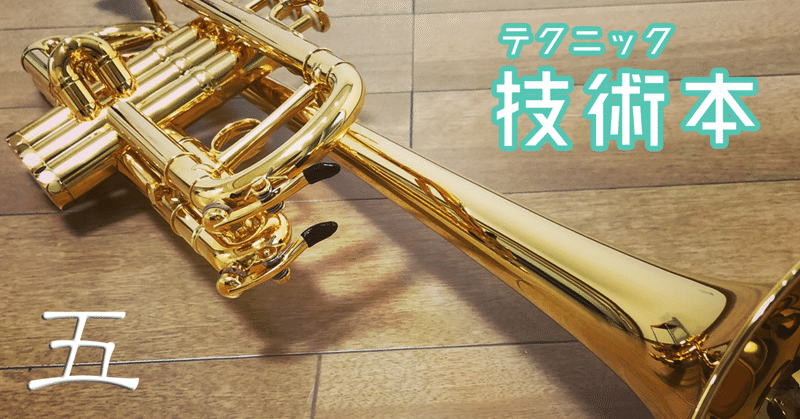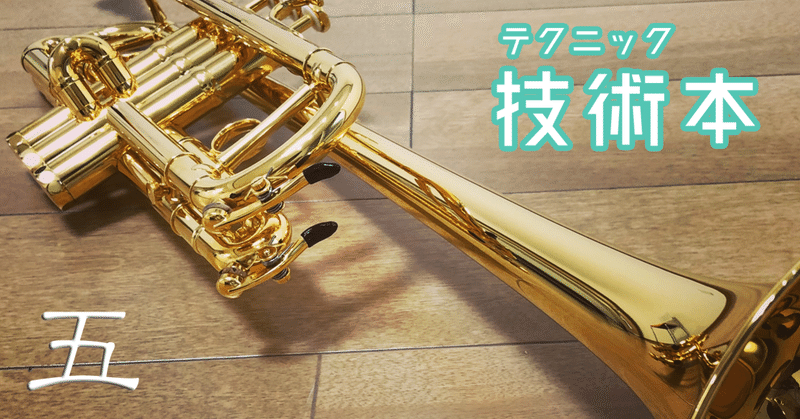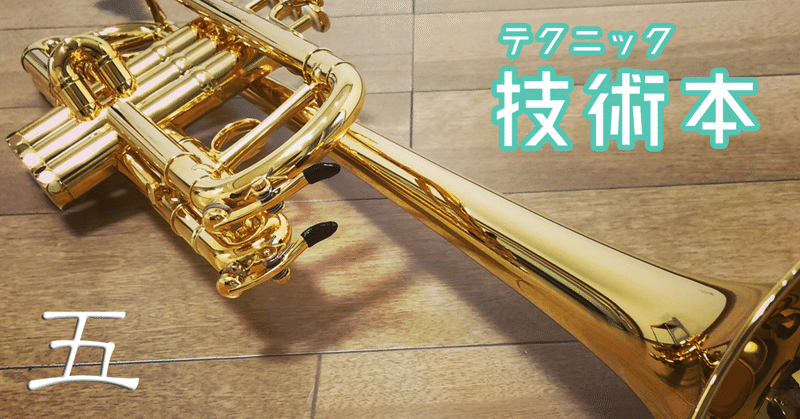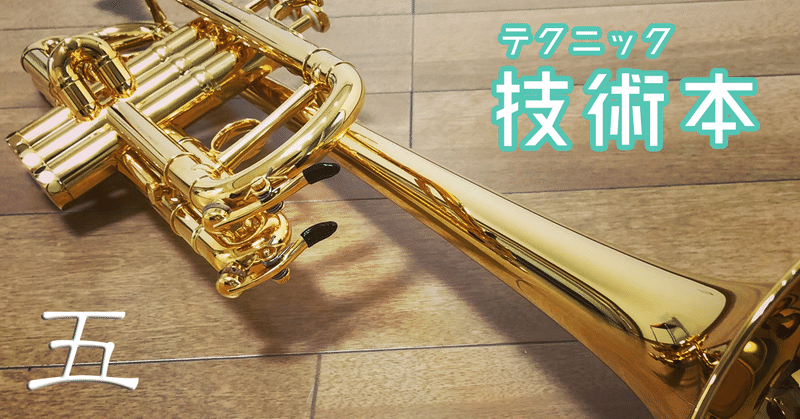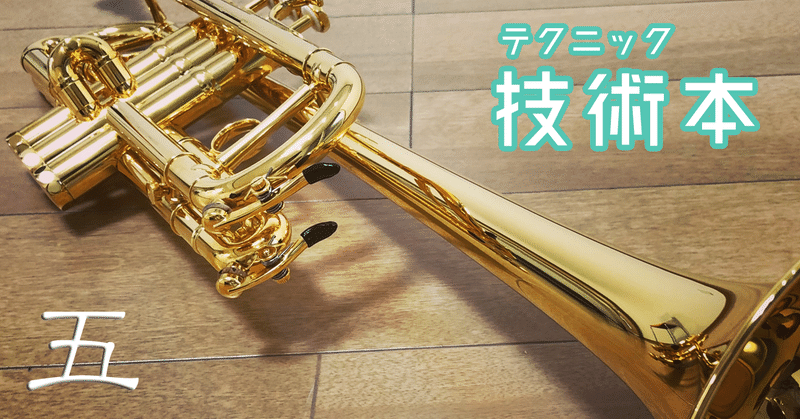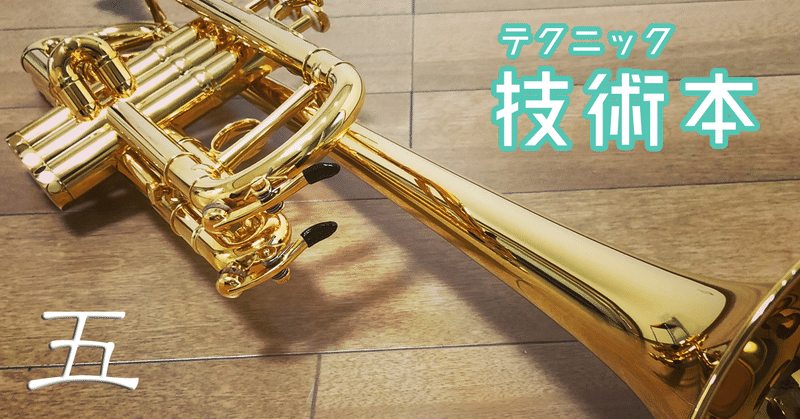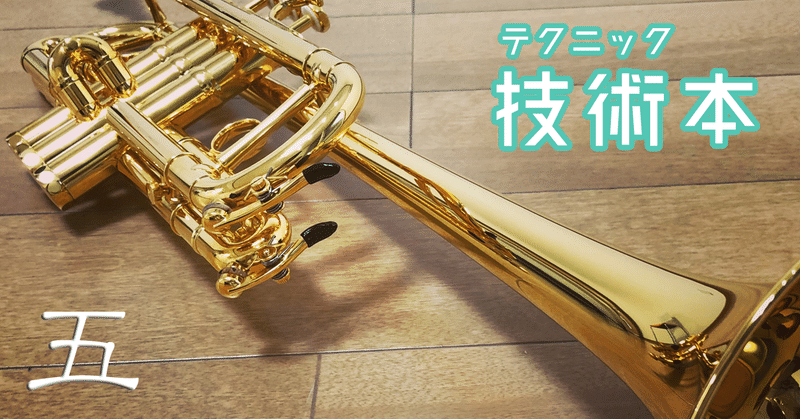記事一覧
5-11.難しいパッセージの練習
いよいよ今回が第5章の最後であり、「技術本」の最後のお話になりました!
最後は「難しいパッセージの練習」について解説します。
原因を見つける
「難しい」「うまく演奏できない」と思っているだけでは当然解決できません。大切なのは「どこが原因なのか」「何が原因なのか」を見つけること。これが解決への第一歩です。
しかし、その前にとても重要なことをお聞きします。その「第一歩」はどこへ向かえば良いので
5-10.速いパッセージの練習(音階、半音階)
最も基礎的な練習の一つである半音階や音階は各教則本にも必ず掲載され、そうでなくとも自主的に練習へ組み込んでいる奏者や部活動も多いと思いますが、テンポが速かったり音価の細かい連符などの場合、みなさんはどのように練習をされていますか?ダーーッとワーーーッと一気に感覚で吹いて練習した気になってはいませんか?
少し気が早いですが、次回掲載予定の記事「難しいパッセージの練習」(なんと最終回!)では、い
5-9.ヴィブラート
ヴィブラートとは
チューナーなどから発せられる電子音が機械的であると感じるのは、音が歪みなく一定の状態で持続するからと言えます。
このようなまったく変化しないものとか、何度も同じ状態が再現される現象には生命を感じられないわけで、それは言い換えるならば良くも悪くも人間は常に不安定で、同じことを繰り返そうとしてもそれが大変に困難なことが「人間味」と言えるのです。
余談ですが、音楽は常にクオリティ
5-8.トリプルタンギング、ダブルタンギング2
前回からトリプルタンギング、ダブルタンギングについて解説しておりまして、「K」の発音は日常の会話で使うものとは違う「ニセのK」を見つけることが必要である、とお話しました。
詳しくは前回の記事をご覧ください。
そして今回は具体的な練習方法について解説しますが、その前にシングルタンギングを含め、すべてのタンギングを考える上で最も基本的で重要なお話をします。
空気があるから発音ができる
実験し
5-7.トリプルタンギング、ダブルタンギング 1
トランペットにおいてタンギングとは「舌による空気の流れのcloseとopen」と定義しています。もしも舌が空気の流れをせき止めるcloseをしなければ、スラーの表現しかできなくなります。そこで音と音の間に区切りを入れて表現するタンギングが必要になり、これによって演奏の表現が広がります。
トリプル、ダブルタンギングの概要
タンギングは同じ方法を何度も繰り返すことが基本で、これを「シングルタンギ
5-6.インターバル(音の跳躍)
「インターバル(音の跳躍)が苦手」とおっしゃる方、結構多いです。確かに、インターバルは金管楽器にとってミスを起こしやすいハイリスクの動きであることは間違いありません。
しかし、それがなぜハイリスクなのか、どのようにすれば解決の方向へ進めるのかを分析すると、具体的な解決方法が見えてきます。
ということで、今回はインターバルについて考えてみましょう。
インターバルの概要
インターバル(inter
5-5.付点のリズム(付点8分音符+16分音符)
レッスンで「では、やってみましょう」とお願いすると、困ったように「あの…テンポはどのくらいでしょうか」と質問されることが少なくありません。
そのような質問をされた時、私は必ず「楽譜に書いてある情報を参考に、その音楽が最も活きると感じるあなたのテンポで演奏してください」とお願いします。
私は音楽教育の場面でよく見かける、メトロノームを鳴らしたり先生が手拍子をしてテンポを提示し、それに合わせて生
5-4.シンコペーション
シンコペーションの概要シンコペーションは英語のsyncopate(音を切分する/言葉を中略する)という意味です。切分する…音楽に使われる日本語って、独特でわかりにくいですよね。しかも切分という言葉は国語辞典を引いても他に出てこないのです。
ともあれ、シンコペーションとは、強拍と弱拍が通常と変わる状態、手法を指します。
アメリカの作曲家、ルロイ・アンダーソン「シンコペイデッド・クロック」とい
5-3.仮想打楽器と仮想指揮者
第5章は基本的にトランペットの具体的なそれぞれのテクニックについて解説するのですが、今回はタイトルからも抽象的な感が現れています。
一体何の話なのか。
プロはすごい!音大受験を目指す高校生の時、師匠の津堅直弘先生のレッスンを受けるため、前室で順番を待っていた時のことです。
当時私もレッスンで教わっていた「アーバン金管教本」の曲がレッスン室の中から聴こえてきたのですが、その演奏のクオリティの
5-2.リップトリル
リップトリルの概要リップスラーは知っているけれど、リップトリルが何かと問われると漠然としたイメージしか持っていない。何か、速いやつでしょ?という方、多いです。
リップトリルとは、名前がそうであるようにひとつの音を基準として、2度や3度などごく狭い音程間をスラー(タンギングではない方法で)移動する奏法を指し、多くの場合はトリルのように反復する方法で練習をします。
有名なところでは、アーバン金
【インデックス】 トランペット技術本
「技術本」全記事掲載完了いたしました!ぜひ順番にご覧いただければ幸いです。
0.はじめに ~技術(テクニック)とは何か~(無料記事)(2019.01.15公開)
第1章 —練習って何?—
1-1.教則本の使い方(2019.01.29公開)
1-2.練習と研究・実験(2019.02.12公開)
1-3.ウォームアップと基礎練習(2019.02.26公開)
第2章 —基礎的な技術を身に
5-1.リップスラー
ついに最終章第5章に入りました!
この章は「技術本(テクニックぼん)」のいわば中枢。トランペット特有の、実際に演奏上必要なテクニックについて解説していきます。
最後までお付き合いいただければ幸いです。
それでは、第5章最初は「リップスラー」について。
リップスラーの概要ある一つの音が鳴ると、その音以外に1オクターブ高い音やなど、高い音がいくつか聞こえることがあります。これらの音のグループを