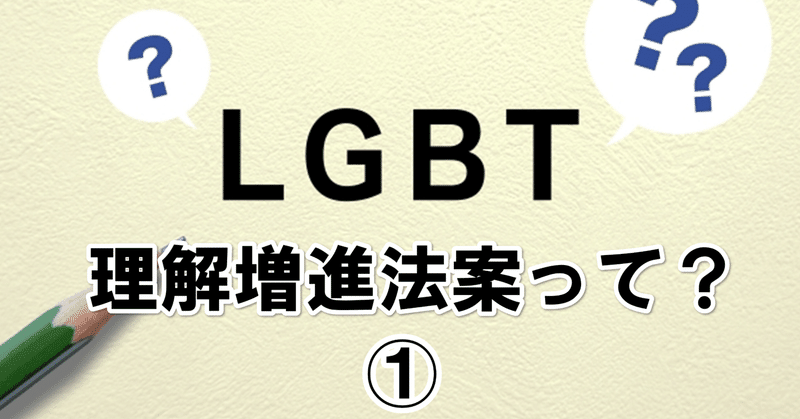
LGBT理解増進法について思うこと①
LGBT理解増進法案についてのニュースが盛り上がっていますね。
与野党で様々な修正がされ、いよいよ成立に向かって動いていきそうです。
自分は日本国内において、同性愛を保護する法律は不要と考えています。
国内において、同性愛に関して、法律を変える必要があるほど、大きな社会問題や人権問題は存在していないと考えているからです。
ただし、T=性同一については法律の保護は必要だし、性の多様性についても偏見やいじめが起きないように学校教育で教えていくことは必要です。
そもそも自分はLGBとTは別物と考えているため、一緒くたに議論されること自体に疑問を持っています。
LGBT理解増進法についてはニュースや動画を追うくらいで法案を全文読んだわけありませんが、その中で思うことを書いていきます。
こちらのニュース(altena 2023年6月9日「LGBT理解増進法案は理解を『阻害』しかねない」、当事者や支援者が危機感示す」)によると、今回、提出された草案は超党派(立憲、)、与党(自公)、維新国民の3つあり、下記の事項でそれぞれの案の違いを比較しています。
①定義
②基本理念
③調査研究
④教育
⑤民間支援
今回は維新国民案を採用し、修正された与党案が可決したようです。
ひとつひとつ見ていきましょう。
①定義
超党派→性自認
与党→性同一性
維新国民→ジェンダーアイデンティティ
ここは一番大きな問題ですね。
超党派の性自認というのはそれに繋がる可能性が一番高いと思います。
本人の言ったもん勝ちになってしまうし、思春期は心の変化も起こるもの。成長に従って実は違っていたと気づくというケースもあります。
また、悪意を持った人が使えば、自分を「女性」と言って女性のパーソナルスペース(トイレ、更衣室、女湯)に侵入できてしまう可能性もあります。
実際に欧米では、外見が男性の人が「女性」と偽り、侵入できたという事件が起こっています。
女性を性的暴力をした男が裁判中に自分を「女性」と言い出し、女子刑務所に収容されたという冗談のような事件も起こっています。
個人的には与党の性同一性に賛同ですが、それではTに「心と体の性が一致していないが、性転換手術はしたくない人」が含まれなくなってしまうので、採用できないのでしょう。
結果的に維新国民案の「ジェンダーアイデンティティ」というふわっとした定義が採用されました。
心の在り方であるLGB、心と体の在り方が両方あるTを一緒にすることに起こってしまうのでしょう。
このジェンダーアイデンティティの解釈をめぐってまた、ひと悶着ありそう…。
②基本理念
超党派→差別は許されない
与党→不当な差別はあってはならない
維新国民→不当な差別はあってはならない
ここも大きく賛否が分かれるところです。
差別はもちろんあってはなりませんが、何を差別とするかの定義が必要になってきます。
受け手が差別と受け取れればなんでも差別になってしまうからです。
自分の経験だと、大学時代、同じサークルであまりに恋愛や性に関する話に積極的に乗らなかったため、「お前、オネエなの?」「俺のケツを掘るのだけは勘弁して」と言われました。
ファッションはメンズのものを着ているし、オネエの言葉も使ったことはないので、ショックでした。
当時はおすぎさんやピー子さん、はるな愛さんがメディアに良く出ていた時代。オネエタレントの特番も組まれる程、まだイロモノとして扱われていました。(そう意味では今のメディアは変わったな)
そういう背景もあってか、半分、悪ふざけのノリだと感じたので、差別とは思わなかった。
ただ、今の時代だと、これは差別となるんだろうなと感じます。
当の本人は思っていなくても、第三者が差別と拡散し、SNSで炎上してしまうことはよくあることです。
行き過ぎた正義感やポリティカルコレクトや、SNSで簡単に世界中に発信できることで、簡単に人を断罪できてしまっています。
欧米諸国はキリスト教を背景とする、同性愛や人種に対する差別が根強く残っています。
それに伴う迫害や暴力事件、さらには殺人にまで発展する事件がたくさん起こっています。
一方、日本では同性愛にはむしろ寛容な歴史でした。平安貴族に始まり、戦国時代の武将たちにも男の妾がいたことは有名ですね。江戸時代には男色専門の遊郭「陰間」もありました。
ただ、その時代は性には奔放であったということも大きな要因だと思います。庶民でも浮気や愛人は当たり前だったようです…。
開国して西洋の文化や考え方が入ってきたこと、憲法の制定、日本の国際化を進めるなどの背景もあって、性に関する考え方が厳しくなっていったのでしょう。
それでもあくまで恋愛観や結婚観の範囲内に留まり、同性愛=悪または排除すべき存在とはならなかったため、暴力や殺人事件に発展しなかったのだと思います。
差別とはなにか、具体的な事例が出そろわない以上、「不当な差別はやめよう」という努力目標のような定義にとどめておくのが無難でしょう。
少し長くなっていまったので、今回はこのあたりで締めます。
残りの項目はまた次回。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
