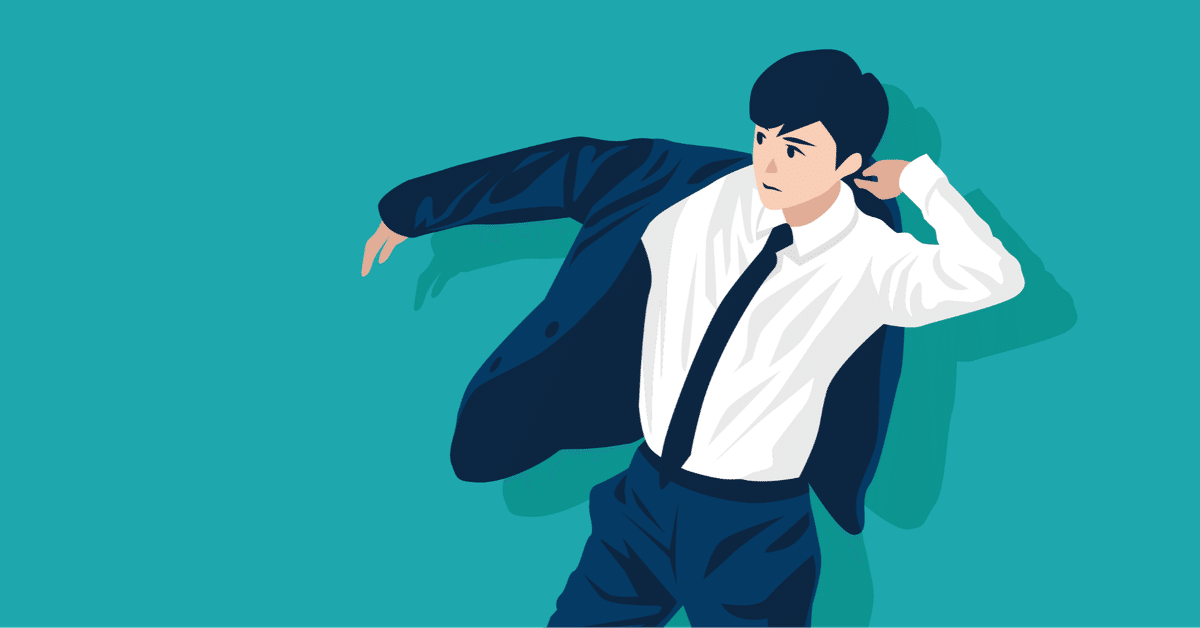
社畜として生きて
日曜日のまだ人気のない道を、優斗は歩いていた。その足取りは重く、憂鬱感がにじみ出ているかのようだ。これで3週間連続出勤となる。そろそろ休ませてくれ、と優斗は心の中で叫び続けている。
やりがいのない仕事。そして誰にでも替わりがきいてしまうという事実が、優斗をさらに憂鬱の谷底に落とし込む。休日も仕事をしていると、なぜ生きているのかと言う気持ちになる。典型的な社畜だ。電車内でこれから余暇を楽しもうという4人の家族連れを見ながら、優斗は自嘲的に笑う。
オフィスにつくと、すでに課長が仏頂面でPC画面を見つめていた。おはようございます、という優斗の声に対し、明らかに不機嫌そうに、おはよう、と答える。優斗がオフィスの自席につくや否や、行政向けに今月提出予定の資料の進捗について確認を受ける。いつまでにできる?えっ今日できないの?使えねぇな。仕事おせぇよ。課長の容赦ない追及に優斗はしどろもどろになる。
ひとまず今日の仕事が終わり、優斗は逃げるようにしてオフィスを後にした。といっても明日もこのオフィスに来て仕事をしなければならない。その事実を優斗は直視することができない。
ごくわずかな時間ではあるが、今日という日をゆっくり過ごそう。急いで優斗は電車に乗り込む。車内には休日を満喫したであろうカップルや大学生、社会人の集団でいっぱいだった。なぜ自分はこんな環境で生きていかなければならないのだろう。涙がこぼれそうになるのを彼はぐっとこらえた。
とりあえず落ち着こうと優斗は思い、電車を降りると駅構内のベンチに腰かけた。すると一気に涙があふれ出てくる。彼が泣いているのを周囲の人は気づいていただろう。多くの人は見て見ぬふりをしている。しかし、その中にいた30代ほどと思われる男性が優斗のもとに近づいて行った。大丈夫ですか。優斗は声を発することができず、ただただうなずくばかりであった。その男性はさっとハンカチを差し出し、彼の肩を優しく触れた。そして自販機で温かい缶コーヒーを購入し、彼に手渡す。何があったか知らないけど、まぁ生きているといろいろあるよね。そう言って彼は立ち去って行った。
優斗はその優しさがうれしかった。今までなんとも冷たい東京という世界で生きてきて、初めて人の温かさに触れた気がした。缶コーヒーをあけ、一口飲むと、いつもより苦い味が気がした。もっと頑張ろうと優斗は強く思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
