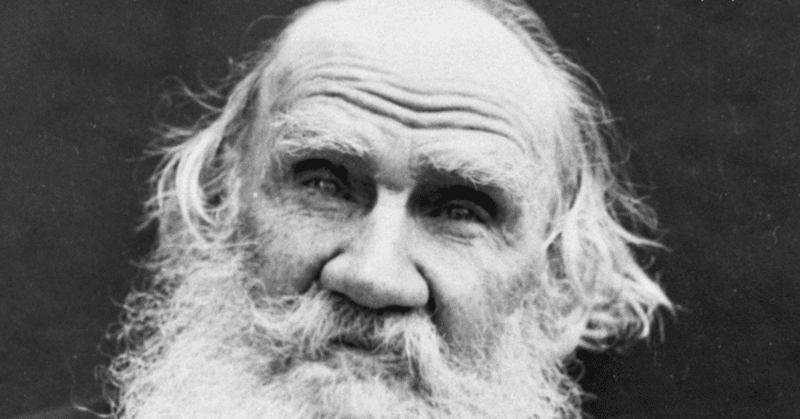
「戦争と平和」 4️⃣ 第三部 第一篇 トルストイ 感想文
「だれでも人間のなかには二面の生がある。その利害が抽象的であればあるほど、自由が多くなる個人的な生と、人間があらかじめ定められた法則を必然的に果たしている、不可抗力的な、群衆的な生である」(岩波文庫 四巻 p.24)
1812年、6月12日、ナポレオンの大軍がロシアに侵入し、いよいよ戦火を交える日も近い。
クレムリンにアレクサンドル皇帝を迎えた時のロシアの人々の熱狂ぶりが、不可抗力的に戦争に呑み込まれていく群集の凄まじい恐ろしい姿として想像させられた。
ナポレオンが、自らの正しさを信じ権力を我が物にしていても、結局は「必然的な法則」につき従っているのだと作者はいう。
「歴史上の事件においては、いわゆる偉大な人物はその事件の名前を示すレッテルにほかならず、レッテルとおなじように、事件そのものとはもっとも関係が小さい」(p.27)
「皇帝は歴史の奴隷にほかならない」p.25 、
歴史において人類の無意識的な群集的な生は、皇帝たちのすべてを自分の目的の為に利用していると、鋭く見つめるトルストイに、歴史に呑み込まれていくだけの人間の卑小さと「群集の生」の冷たい痕跡だけしか残らない歴史の恐ろしさを思った。
一方、自分の内面を真剣に見つめながら、懸命に「個人の生」を生きているピエール・べズーホフとアンドレイ・ボルコンスキーは、自分の内にある嘘と向き合いながら、周りの人間の本質をじっと観察し、真理をみつけようと、自分の内にも世の変革にも、行動の時を待っているような期待を感じるのだ。
「この上もなく慎重に熟慮された計画は実践では何の意味も持たず ー中略ー すべてを決めるのは実際の行動全体がどのように、誰によって動かされているかだ」(p.91)
と、確信していたアンドレイだった。
対戦経験を持つアンドレイが皇帝の周りにいる九つの派閥の討論を聴きながら個々の人間の愚かさを認識するのは容易(たやす)いことであっただろう。
戦争の実体験から見えた「戦争学などというものはまったくないし、あり得ない。いわゆる軍事上の天才などあり得ない」(p.116)という真理がこの討論を前に明らかになり確信するアンドレイだった。
そんな中で、戦争理論家の頑固なプフールに関心を持って観察しているアンドレイは見逃せなかった。やがて没落していくプフールの悲哀、人柄が皆に一目置かれているという人物像には興味があった。
皇帝の周りには、真理を追求するというよりは、自己保身や高名さを追い求めるだけの人間が集まっているように思えた。しかしそんな愚かな結集でも、ある瞬間に何かが結びつき大いなる結果を生み出すという事実もあると作者は書いていたようにに思っているのだが、私はちゃんと読めているのだろうか。
ナポレオンに、ロシアの教会の多さを、「後れている」、とあて擦られ、スペインの教会の多さをハラハラしながら指摘したアレクサンドル皇帝の使者のバラショフ。
フランス軍がスペインに敗北したことへのこれもまたバラショフのナポレオンに対するあて擦りだったのだが、理解されずに終わる。
ナポレオン皇帝ですら自分の思い込みで我を忘れている、このような面白いシーンがとても細かく描かれていて読みどころが多い。
ナポレオンの「後れている」は、あながち間違いではないのだ。
アンドレイが見据えたスペランスキーの先進的な改革への功績の本質への理解、ピエールの「皇帝と国民との協議」という、最も重要でロシアが変われるかどうかに関わる真理は、まだ二人とも決して発言する機会を与えられていない。
「空に立つ彗星をながめ、自分には何か新しいものが開けた」と感じたピエールが、虚しい生活の中でナターシャにまた同じ思いを見出したのだ。
アンドレイの愛と憎しみは、今後どのような展開になるのか。
ピエールとアンドレイのこれからの行方を見届けたい。
そのためには六巻通読しなければ!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
