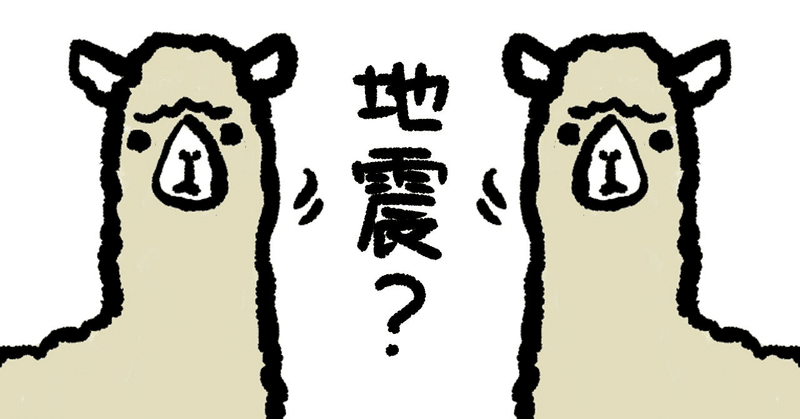
話題のClubhouseは災害時にどう役立つか?
昨夜の地震では東京(震度4)でも長い強い揺れがありました。夜の11時過ぎという時間もだったこともあり、驚いた方々も多かったと思います。
うちの11歳の娘も揺れの後、寝室から飛び出してきて、「こんな大きな地震、生まれて初めて!」「心臓がこんなにバクバクしてる!」「この家、倒れないの?」とかなり動揺していました。NHKのニュース速報で確認すると、「マグニチュードは7(東日本大震災はマグニチュード9)」「津波の心配はない」とのことだったので、娘を一度落ち着かせてベッドに戻らせ、私は自室に戻り、震度6強の揺れが観測された宮城や福島の現状ではどうなっているのだろうということに、思いを巡らせました。
私がロイター通信でニュース記者・プロデューサーとして仕事をしていた時は、「震度6弱以上の揺れの場合はすぐに現場に直行する」というルールを社内で決めていました。今回の揺れはまさにそれにあたり、現役のニュース記者であれば深夜にも関わらず現場に急行するレベルでした。
クラブハウスですぐに立ち上がった、英語での情報交換ルーム
一方、東京で情報収拾をする場合は、近年は災害時にはTwitterをはじめとするSNSをまず第一の情報源としていました。ところが、今回は話題の「クラブハウス」でどのような情報が交換されているのだろうと気になりました。報道関係者であれば、ここで現地の方々の被害の状況など「生の声」を聞けるのではないか? クラブハウスの場でインタビューさえもできてしまうのでは?
それまでに仲間内でクラブハウスの「テスト通話」はやってみたことがありましたが、「実践」でクラブハウスを使ったことはありませんでした。
アプリを開いてみると早速、「Tokyo Needs To Stop Shaking」(「東京の地震、もう勘弁して」)というタイトルのルームが目に入ってきたので、入ってみました。私の知り合いで、日本に住む外国人ドキュメンタリー監督がそのルームの「スピーカー」の一人だったことで、私のタイムラインにも表示されたようです。スピーカーが10人弱、全体で100人弱ほどのコミュニティーが、地震の後15分後くらいにはすでに形成されていました。
ジャーナリストの林信行さんもこのルームに入っておられ、日本語がわからない人たちのための情報共有の場としてのこのクラブハウスのルーム情報を、Twitterで早速シェアされていました。(リスト上段の右から2番目が私です。)
If you are in Tohoku right now and want to share your experience, there is a room on #Clubhouse . pic.twitter.com/ScYMNR4UO0
— Nobi Hayashi 林信行 (@nobi) February 13, 2021
英語ルームの参加者層は?
この英語での情報交換ルームは、東京に長い間在住する外国人が中心になって立ち上げられたようです。
一方で、まだ日本に来たばかりの外国人、日本に住む家族や友人の安否を心配する海外の人たち、日本に以前住んでいたことがあり今は海外に居住する人たち、など様々な外国人(日本語を話さない人たち)が参加していました。
さらに、日本に居住する日本人で英語を話す人たちも参加し、日本各地の現地の情報や自分たちの体験を積極的にシェアされていました。
例えば、震度5の揺れが起こった岩手県にお住まいの日本人(と思われる)女性が、「棚からいろいろなものが落ちてきて家の中はモノが散乱している状態だが、自分や家族は大丈夫」というような貴重な東北地方からのリアルタイムの情報を英語で提供してくれました。
情報だけではなく、心のケアをコミュニティーで共有
私たち日本人は、正直ある程度の揺れには慣れていると思います。震度3から4程度の揺れでは、驚きはしますが、あまり動じません。これは小さい頃からの体験によるものでしょう。
一方で、外国人はそうではありません。まず、地面が揺れということに慣れていない人がほとんどです。小さな揺れにも敏感に反応し、昨日ような規模であればロイター通信なども世界にすぐに記事を配信するので、それを見た海外に住む家族も心配し、日本に住む家族に電話をします。
私は妻が南米人なので家ではスペイン語を話しているのですが、ちなみにスペイン語では "Me movió el piso" (床が動いた)”という比喩表現があり、これは本当に悲惨なことや大事件が起こった時に使う表現です。床が動く、つまり震度が小さくても地震があること自体が、天地がひっくり返ったような大騒ぎであり、実際に「床が動く」ような場所に住んでいること自体に多くの外国人は強いストレスと不安を感じます。
それ故にこの外国人コミュニティーのクラブハウスでの会話も、現状や災害情報を英語で速報してくれるアプリなどに関する情報共有の他は、お互いを心理的なサポートする内容のものが中心でした。
日本に何十年も住んでいる人たちからは3・11の時にどういう気持ちでどういった対応をとったかという体験のシェアがあり、またメディテーション(瞑想)のやり方に詳しい人たちからは、如何にして心の平静を保つかということ、また心を落ち着けることの重要性といった点で意見や情報の共有がありました。
私はしばらく「オーディエンス」として皆さんの話を聞いていたのですが、スピーカーの一人が私がルームに参加していることに気づき、「日本人ジャーナリストのトシが入っているので、意見を聞いてみよう」といって私をspeaker役にinviteしてくれました。
私は主に次のようなことを話しました。
・今回の地震はマグニチュード7であり、3•11とは規模が全く違う
・また津波の心配がないという点でも、3•11とは全く違う
・「震度」という概念は日本人でないとわかりにくいかもしれないが、私の過去の地震の取材も踏まえての個人的な感覚だと、震度4以下は揺れはあっても実害はほとんど発生しない。震度5だと家に中のモノがかなり落ちる。実際に塀や建物が崩れたり、死傷者が発生したりするのは震度6以上の場合である。
・今回のように深夜に地震が起きた場合、翌日の朝になるまで全貌は分からない。今回の地震の規模をみると、恐らく数十人から数百人のケガ人が震度6の地域を中心に出るだろう。死者も出る可能性があるが、そうならないことを祈ろう。
このようなことを話して、少しでも参加者のみなさんの不安を解消できたのか、最初は朝まで延々につづくにではないかと思われたこのルームも地震発生後の1時間半後(深夜0時半頃)までにはお開きとなりました。
クラブハウスについて考えたこと
今回の地震をきっかけにクラブハウスを初体験したわけですが、私が感じたことをまとめると、クラブハウスは、
1) 非常時・災害時に、非常に有効な情報共有の手段となる
2) 気軽に会話をモニターする形で参加出来るため、情報収集が容易にできる
3) ジャーナリズムにおける新しい取材方式となりうる。リアルタイムで取材対象を探し、インタビューをすることも可能である
4) 取材やリサーチに活用する場合、会話や参加者の記録は後から振り返れないので、会話をしている時にしっかりと相手のアイデンティティーや連絡先を確認しておく必要がある。(それをもとに追加取材や確認作業を事後に行う必要がある。)
5) 最後に、これが最も重要なことかもしれないが、参加者にとって自分が求めている情報をリアルタイムで得ることができ、参加者同士での心のつながりを感じられる場となりうる。
6) ルームにはお互いに知らない人たちが入ってくるので、ルームを開催する「オーガナイザー」のMC(司会進行役)としての能力が重要になる。また、参加者(特にスピーカー)全員がお互いにリスペクト(敬意)や配慮、マナー、丁寧さを保つことによってのみ、よいコミュニティーの場とすることができるのではないか
まだ一回だけの体験で色々と書いてしまいましたが、また今後気づいたことがあれば追加でシェアさせていただきたいと思います。
皆さんの Clubhouse 活用方法やその効果はいかがでしょうか?
トシ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
