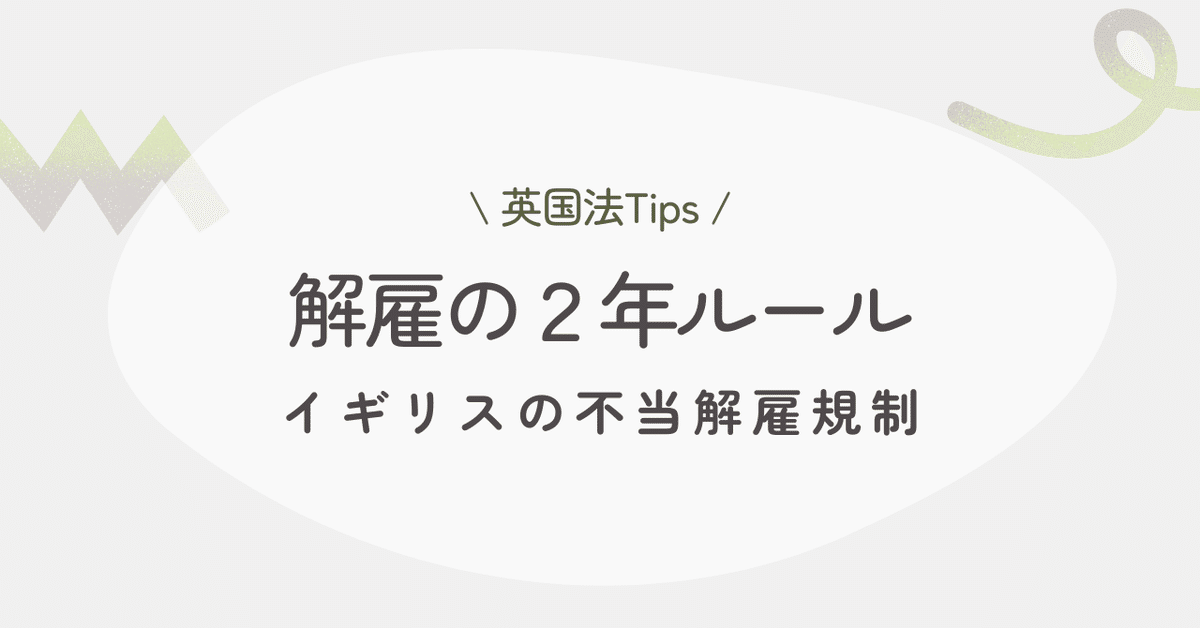
【英国法】解雇の2年ルール ーイギリスの不当解雇規制ー
こんにちは。
お読みいただきありがとうございます。
本日のテーマは労働法、その中でも解雇規制に関するものです。
個人的には、労働法はグローバル化から最も遠い法領域の一つだと思っています。というのも、雇用者と被雇用者が国境をまたいで労働契約を締結することは他の取引契約に比べて稀ですし、労働法制は各国の政治的・社会的事情が色濃く反映されるからです。そのため、国際弁護士を名乗る人は多くても、外国の労働法のアドバイスを提供している人を、ぼくは聞いたことがありません。
その意味で、日本の法務担当者・弁護士にとっても、イギリスの労働法は情報が得にくい分野の一つかと思い、紹介させて頂きます。
なお、法律事務所のニューズレターとは異なり、分かりやすさを重視して、正確性を犠牲にしているところがありますので、ご了承ください。
英国の解雇規制
本題に入る前に、英国の解雇規制の基本的なところをざっくり紹介します。
解雇規制に関する主要な法令は、Employment Rights Act 1996(以下「ERA 1996」)です。
S. 94は、次のように定めています。
94 The right
(1) An employee has the right not to be unfairly dismissed by his employer.
(2) 略
和訳するまでもないかもしれませんが、「被雇用者は、雇用者から不当に解雇されない権利を有する。」と定められています。日本の解雇権濫用法理(労働契約法16条)に近い位置づけの規定ではないかと思います。
つまり、不当な解雇は英国法上認められません。もし、裁判(審判)が起こり、不当解雇が認定されると、被雇用者の復職、再雇用、補償、解雇は不当であったという雇用者の宣言などが行われることになります。
解雇の3類型
英国では、解雇を次の3つの類型に分けて考えます。
解雇の3類型:
① 自動的に公正な理由による解雇
② 自動的に不公正な理由による解雇
③ 潜在的に公正な理由による解雇
このうち、①は、不当解雇になり得ない解雇です。現在、たった2つの事由による解雇の場合にしか認められていません(*1)。逆に、②は、必ず不当解雇となる解雇です。例えば、妊娠・出産を理由とする解雇、労働組合を理由とする解雇などが挙げられます。
③は、潜在的に公正な解雇と呼ばれるカテゴリーのもので、能力や行動を理由とするものが含まれます。この場合、裁判ないし審判において、公正な解雇と認定されれば、不当解雇とはなりません。また、語義にマッチしていないものの、例えば、「一緒に働いていてイライラする」という理由で解雇した場合、潜在的に公正とは言い難いものの、このような理由も③の土俵で判断されます。そのため、潜在的に公正な理由による解雇を行う際には、よく注意しなければなりません。
解雇の2年ルールとは?
ここまで説明した通り、被雇用者は、ERA 1996のs. 94により、不当解雇から保護されています。もっとも、s. 108は次のように定めています(太字はぼく)。
108 Qualifying period of employment.
(1) Section 94 does not apply to the dismissal of an employee unless he has been continuously employed for a period of not less than two years ending with the effective date of termination.
イギリスでは、原則として、雇用期間が2年に満たないうちに解雇された被雇用者には、不当解雇の保護が及びません。日本に置き換えると、正社員で雇用していても2年未満のうちに解雇すれば解雇権濫用法理が適用されないということなので、ちょっとした驚きですよね。
この決まりを(ぼくが勝手に)解雇の2年ルールと呼んでいます。
英国ではこのルールは常識なので、日系現地子会社で人事労務を見ている方にとっては、ここまではよく聞いた話かもしれません。
以下では、解雇の2年ルールにまつわる、ちょっと細かめの論点を見ていきたいと思います。
留意点
雇用期間の開始日と終了日
雇用契約書で開始日を明確にした上で被雇用者がちょうどその日から働き、かつ、終了の際には法令に従った解雇通知に記載の終了日まで実働していた場合には、特に問題は生じません。
しかし、契約上の期間と実際に被雇用者が勤務した期間がずれる場合には、何を基準に開始日と終了日を特定すればよいのかという疑問が生じます。
まず、契約上の期間と勤務期間を比較して、契約上の期間が長い場合は、契約上の期間が開始日/終了日になります(*2)。例えば、契約上の始期が1月10日、勤務開始が1月15日の場合、雇用の開始は1月10日となります。
他方で、勤務期間の方が長い場合には、少し厄介です。契約期間の終了後に勤務することは少し考え難いですが、逆はあり得そうです。例えば、雇用契約上の始期の前に、トレーニングイベントへの参加があったり、ミーティングがあったような場合です。
Koening v Ming Gym事件では、このように契約期間前の勤務が「雇用契約に基づいて履行された」と言えるのならば、その勤務日が開始日となると判断しました。具体的には、その勤務が強制的か否か、有給であったか、雇用主がどの程度そのような慣行を用いているかを考慮して判断するとされています。
つまり、契約上の開始日と勤務の開始日を比較して、勤務期間が長い場合は、それが雇用契約に基づく稼働であれば、勤務期間が開始日となると言えます。私見ですが、終了日についても、同じことが言えると思います。
勤務の中断
英国法上も、産休・育休は被雇用者の権利として認められており、これによって雇用契約が解除されたり停止したりしません。そのため、産休・育休期間中に、被雇用者が実際に勤務していなくとも、雇用期間に算入されます。
被雇用者がストライキを行ったときには、ストライキ中の期間は、雇用期間から差し引かれます。たとえば、12か月のうち2か月の間ストライキにより労務を提供しなかったときには、雇用期間を10か月として扱います。
さらに細かい話ですが、ある興味深い事件があります。ある教師の女性が、9月に採用されて翌7月には事実上解雇されるという形で、9年間にわたり勤務した事例において、彼女は9年間継続的に雇用されたと判断されました(*4)。この他にも、様々な理由で雇用契約を終了してすぐに新たな雇用契約を締結した事案で、雇用の継続性が争われた事例がいくつかあります。このような事情がある場合には、要注意ですね。
自動的に不公正な理由に基づく解雇
2年ルールは、重要な例外を設けています。それは、自動的な不公正な理由に基づく解雇は、原則として2年ルールが適用されないということです。
もっとも、次の理由は、自動的に不公正な理由ですが、2年ルールが適用されます。ややこしいですが、例外の例外ですね。
2年ルールが適用される自動的に不公正な理由
① 事業の譲渡
② 一定期間を経過した有罪判決(spent conviction)
①は、日本の会社法にいう事業譲渡に限らず、合併や会社分割を含みます。英国では通称TUPE(テューピー)と呼ばれる、日本の労働契約承継法に似た法令があります。このTUPEに基づき労働者の移転が生じるような事態に関する一定の解雇については、2年ルールが適用されることになります。
また機会があればTUPEについても書きたいと思います。
追記:書きました!
まとめ
今回お伝えしたかったのは、次の事項です。
イギリスでは、2年以上雇用した被雇用者のみが、不当解雇を主張できる
もっとも、上記に述べたとおり、いくつかの論点もありますので、ご注意ください。
ここまで読んで頂きありがとうございました。
この記事がどなたかのお役に立てば、嬉しいです。
【注釈】
*1 一つ目は、国家安全保障上の理由(s. 10, Employment Rights Act 1996)、もう一つは、不法な争議行為です(s. 237, Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992)。
*2 General of the Salvation Army v. Dewesbury (1984)
*3 Koenig v Mind Gym (2013) EMPLR 031 73
*4 Ford v Warwickshire County Council (1983) ICR 273 75
免責事項:
このnoteは、ぼくの個人的な意見を述べるものであり、ぼくの所属先の意見を代表するものではありません。また、法律上その他のアドバイスを目的としたものでもありません。noteの作成・管理には配慮をしていますが、その内容に関する正確性および完全性については、保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。
X(Twitter)もやっています。
こちらから、フォローお願いします!
こちらのマガジンで、英国法の豆知識をまとめています。
よければご覧ください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
