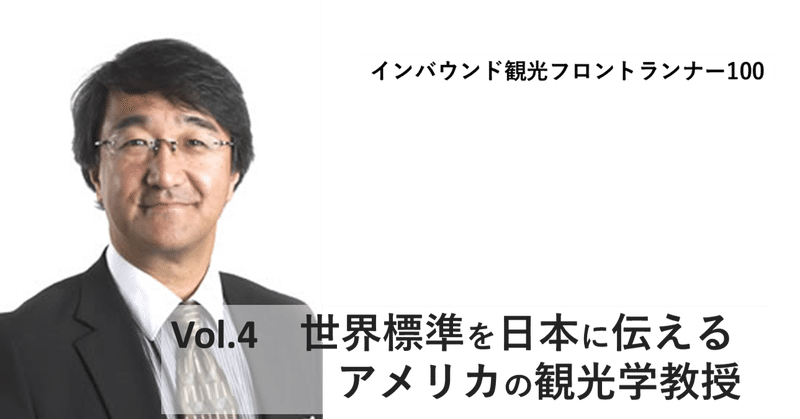
「インバウンド100」 Vol.4 世界標準を日本に伝えるアメリカの観光学教授
DeepJapanでは日本を元気にするために、インバウンドの支援をしています。ところがこの分野は、市場規模や未来のポテンシャルに対してまだまだ情報が整理されていないなという課題に気が付きインバウンド100と題して、100人インタビューを始めることにしました。
第4弾はセントラルフロリダ大学の原先生にアメリカと日本のDMOの違いを伺う時間をもらいました。
日本とアメリカのDMOの違いとは何でしょうか?
日本とアメリカでDMOの運営は大きく違うけど、
「1に人、2に財源、3に独立性」が違います。
それに対して日本のDMOはモデルになってるのが昭和の時代の旅行商品のセールス機能といいますか、平たく言うと旅行代理店の出向者の集まりです
もう少し詳しく話をすると特別税を財源としてDMOの運転資金として使っています。
アメリカで教えているだけあって結論ファーストで、歯に衣着せぬ話し方gがでとても分かりやすいですね!特別税というと私の支援している地域では、DMOの運転資金を宿泊税で考えれないかという議論をしたら、入湯税で消防車買っちゃって観光目的で使われなかったという批判※が、あって宿泊税の議論ができませんでした。
※本来的には入湯税は火災の防止や衛生、観光振興のためにつくっられたので、この批判はやや的外れ
DMOの財源の問題はありますね。京都市の宿泊税も一般財源になっています。そうすると観光客が払った税金が、京都市内の観光以外の何の目的でも使えます。入湯税が観光以外に使われるこのことは、別府でも批判の対象になっています。
財源の比較をさせていただくとフロリダ州オーランド人口140万人に対して7500万人が旅行に来ている。京都市や沖縄県が同じくらいの規模です。それなのにオーランドはオーバーツーリズムになっていない。それでいて300億円の宿泊税収入があります。東京都が1300万人の人口で10万室の部屋数に対して宿泊税収入は20億円ちょっと。
15倍近い税収を出している。人口の比率も考えるともっと大きい観光収入があります。
そんなに差があるんですか。それにしても話が数字ありきなのでとても分かりやすい。アメリカは持続的に金の回る仕組み、経済開発が上手ですね。
東京、京都、大阪はDMOの収益や使い道の点でアメリカのようになっていません。日本で唯一こうした間違いをしていないのは、ニセコの倶知安の定率制の宿泊税。これは観光で外貨を稼ぐというテーマの元、地域住民の生活水準の向上と地域の負担をなくという考え方があります。オーランドの観光のための財源は、オーランド住民の税金は使われていません。
あとオーバーツーリズムがヨーロッパでは起きてますが、これはファンディング(DMOの運転資金)がアメリカに比べて弱いところにも原因があります。
観光で稼ぐことについて、私の師匠のルースジャーマンさんはハワイが、パイナップルやサトウキビ産業から観光にシフトする際にあったエピソードを思い出しました。海外の旅行者に対して学校の先生が子供達に「あの人たちが観光消費してくれるから、あなた達は大学に行けるのよ」と教えてたそうです。
ハワイは日本からするとアメリカ本土に行く延長線上にあるから注目されるけど、観光ではフロリダ州オーランドの方が上。DMOの設立の動機や歴史も違います。ディズニーワールドが1971年に作られ、ホテルもどんどんできたんだけど、その後にオイルショックが起こった。ガソリン価格が4倍になり、そんなことになったら車で来てた人達も航空便も高くなり旅行者がフロリダにこない。そこで地元フロリダ州オーランドのホテル協会が陳情をし始めてできたのがDMO。何をしたかって言うと、レジャー客以外の開拓、新しい旅行セグメントの開拓や、国際会議場という箱物つくり、新しいお客さんを探すといった集団での取り組み。財源は、ホテルで宿泊税を代理徴収。当初の国際会議場建設資金は地方債を発行してもらい地域政府は担保をつけずに将来の宿泊税収を担保として資金調達し、また自分達のDMO運転資金のキャッシュを宿泊税収から確保しています。
DMOの生まれと生い立ちが日本と全然違いますね。アメリカの方と話をしてると、共通して感じるのは彼らの持っている独立・開拓精神の強さが国の強さにつながってることです。それでは一歩踏み込んで本題のDMO戦略やKPIについて教えていただけますか
日本では戦略が色々な意味で使われていてちょっと混乱を生んでいる。
はい。私も同感です。戦略が戦術の意味で使われてたり、スローガンをカッコよくするために使われていたり、日本語の定義をちゃんとするところから始めないといけないと思います。
私たちアメリカで使っている「戦略」はシンプルに三つのことをやるだけです。
「1に現状把握、2に理想を描く、3に現状から理想までの線を引く」
特に日本は現状把握が弱い。認めたくないのか現在地を知らないし、知ろうとしない。例えば沖縄は平均所得が47位で、非正規が多い。それを47県の真ん中くらいを目指そうよ。25年でとか、10年でとか、って時間軸を引く。それが戦略です。
わ、、わかりやすすぎる。。。戦略の言葉の意味に無頓着な方に聞いてもらいたいお話ですね。KPIはどうでしょうか
DMOを運営する際の従属変数※として、満足度や再来訪意向をとってKPI設計することが多いです。
※統計のデータ間にある因果関係について調べる時に、原因となる要因を「独立変数」と呼び、その結果現れるものを「従属変数」と呼びます。つまりここでは、DMOが旅行者から選ばれ続けるための大事な指標KPIは、満足度と再来訪意向を設定している。その「満足度」や「再来訪意向」の原因になる独立変数が何なのか統計的に施策を調べて設計していくのがKPI設計
アメリカと日本で統計調査に関する考え方の違いはありますか
ディスクリティブスタティクス(Descriptive statistics)というのが日本では多い。宿泊したのは何人で、男性が何人、女性が何人、、、とアンケートを取って旅行者の全体像はわかるタイプの統計。
それに対して僕らがやっているのは、どうすれば5000万円売り上げが増えるのか、アクションプランを出すためのモデルを構築するためのインファレンシャルスタティクス(Inferential Statistics)です。どういう経験をした人、何をした人の消費が高いのか、その属性が、なんなのかを分析する仕組みを設計に組み込んでいます。
たしかに日本の統計は受託事業者が仕事の領域に線を引いて、調査会社は調べるだけ、それを使ってよくするのは、行政。行政も予算を出して調べさせるのは、行政の仕事でそれを使うのは、観光事業者の仕事という感じですね。旅行者をどう増やすかを主眼に置き作られている統計は少なく見えますね。
そうなんですよ。私たちは、旅行者の観光支出額がどうやったら増えるのかがゴールなので、アンケートの属性にはこだわっています。年齢・性別・学歴・居住地域・支持政党・年に何回旅行するか、宿泊にかける予算の割合、あとは米国だと人種・宗教・家庭で使う言語、など調べて、これを細かくとっていると重回帰分析※をする時に、従属変数に対して何が効くのかよくわかる。
※重回帰分析はゴールに対して、複数の変数のうちどれが関連(効き目)がある施策を探る統計分析手法です。施策を根拠に基づいて決めるのに対して、日本は責任のある人やみんなの合意で決めているところが違うように感じます。この時に十分なデータや分析結果がないと個々の経験や想いが優先されてしまって、どうしてもバラつきやムラ、利害関係が入ってしまうので、最適解にたどり着きづらいように見えます。アメリカはインターネットが普及しだしたころから数学・統計の重要性に気づきSTEM教育へと発展したそうです。
調査とその結果に基づいた施策の関係は人体に例えると、感覚器から入力された情報を脳で処理して、脳から運動神経で手足がつながるようなものなので、入力精度だけあげても施策に連動させれないと仕方ないのかもしれないですね。野球観戦は上手だけど野球をプレーするのは上手くないみたいな
たとえばオーランドの主要外客は、イギリス、カナダ、ブラジル(日本でいうメインランドチャイナのポジション)です。DMOのページを見てほしいのですがポルトガル語のページがあって、そこに入るとポルトガルかブラジルか選べる。ブラジル人は買い物が好みなので、ブラジルのページを押すと買い物情報がたくさん出てくる。
他にも12、1、2月のカナダの人は寒いのでフロリダに行きたがってるのを僕らは知ってるので、モントリオールの地下鉄広告をジャックする。南国ムードで陽を浴びている写真を出して大量に露出する。こうして2000万円の広告費に見合う成果があるか?1億円かけたマーケティングのROIはどれくらいか?前年よりも2%増えるか?そういったことを分析しています。
多言語サイト制作やマーケティングの仕事を受託している身からすると、うらやましい環境です。来年度予算がつくかどうか?広告施策を打つ会社が毎年コンペで変わりうる、そして民間業者との癒着を防ぐ目的もある人事ローテが頻発して担当者も変わる日本の行政ではなかなかやりづらい施策ですね。早くDMOが自主財源できてマーケターを長期雇用できるようになってほしいですね。
他にも面白いところでいうと、観光産業では食事が重要なんです。DMOがこの重要なセクターに対して何をやっているか?9-10月にマジカルダイニングマンスという取り組みをやっています。何故この期間かは、この間旅行者が少なくレストランが暇な時期です。
オーランドの住民140万人を対象に37ドル(約4,000円)の前菜とデザート付きのセットをだす。こういうのをやると普段10,000円くらいするレストランなので、いつもはお店に来ないタクシーの運転手やチケットのもぎりをしているアルバイトが来てくれる。彼らがレストランの味を知って、旅行客に対して地元のレストランを宣伝してくれる。またレストランも客が入らない時期だからといって、従業員を解雇はできないので消費の底上げができるので、この企画を打っているDMOは感謝される。37ドルのうち1ドルをNPO法人に寄付していて、それがこの前は3500万円の寄付できた。
こういう寄付文化も含めてやり方が上手です。DMOが文字通りに地域マネジメントしていますね。
そう、DMOのMは、マーケティングと言われることもあるんだけど、こちらのDMOは本当にマネジメントしている。
他にもリーマンショックの時のエピソードを話させてください。
この時は本当に大変でレジャーなんかは、けしからんと言う風潮で2割観光客が減っていた。その時、ホテルやレストランを集めて積極的にマーケティングをしたいが、金がない。どうしよう。それなら知恵と現物出資をしようということになりました。
そしたら1000ccのレンタカーなら一週間出すよとか、テーマパークの一日券出すよとか、スタンダードルームを一週間だすよといった協力者がDMO内でいっぱい集まった。そこで始めたのがオーランド69Nights in Orlandoという企画で1組のカップルを無料で69泊オーランドに泊めてあげるキャンペーン。条件は毎日SNSで発信させるというもの。そうしたら応募がたくさん来て、DMOとしては運営のための人件費はかかったが、広告予算はゼロで7000万円くらいと同じ効果のマーケティングになった。これはニューヨークの広告会社に、そのカップルが発信した内容と同じくらいリーチやイイネを集めようと思うとどれくらいの費用が必要か試算をしてもらった結果です。
他にもホテルにお願いして、2泊したら3泊目タダとか、レストランで18才以下は無料とかキャンペーンを打ってもらいました。そうしたら旅行客はちゃんと来てくれて、観光の仕事が生まれて、リーマンショックの苦しい時期でしたが、オーランドの観光産業就業人口は減らなかった。
この自ら仕事を創り出して、成果を生み出していく感覚がヤバですね。苦しい時にどうするか?が、お上に頼るではなくて自分たちでどうしていくか?アメリカのたくましさを感じます。しかし今の日本では二極化が進んでいて低所得帯がボリュームゾーンになって来つつあるから、ボリュームゾーンを追おうとすると、どうしてもチープな企画になりがちだと感じています。
良いところを突きますね。私はファイナンスも専門で、この日本の所得の低い非正規雇用者層が38%もいるってことを問題と捉えています。アメリカの人口に占める黒人の割合が13%なんですが、年収ベースで比較すると彼らと同じくらいかそれ以下の生活水準の人が38%も日本にいるってことは大きい課題。
観光産業は非正規労働者に頼っているところが大きい。彼らの所得が上がるだけで日本経済に対するプラスの効果が大きいと考えています。
米国が過去1年間で経済復興したのは観光産業主導だったのですが、オーランドではパンデミック前から2021年春頃までの時給$10が今や$16~17と60~70%上昇したのです。そうしたら、観光産業の就業者数が増えて、かつて観光産業経営者が言っていた「人手不足」は実は「低賃金職場の魅力不足」だった事がわかりました。つまり具体的な数値を言うならば、日本では、現在年収150万円平均の非正規女性年収を、同255万円に70%上昇させたら、貧困問題にも消費額増にも好影響がある訳です。これは時給750円で一日8時間・週5日勤務で有給2週間の条件を時給1275円ぐらいにしてあげたら国全体に大きな好影響があるという事です。その分の人件費増による営業費用増分は米国の場合は全て小売価格に転嫁して、それでも旅行需要は十分あるので皆が恩恵を被っています。
この辺りの所得、ひいては生産性の問題って悩ましいですよね。
この生産性の問題は教育の問題でもあります。給与が欲しいと言われても、労働者が何もしないで給与あげる事はできないから、労働者の生産性をあげないといけない。生産性を上げるには、労働者の教育レベルをあげないといけない。
日本の社会人教育は20年ぐらい遅れていて、足利学校の古い考え方がベースにあるのか現地に行かないといけないという大学教員の考え方が根底にある。生徒にとって同じような学習効果がえられるなら、どこに住んでいてもまったく問題がない。
非常に共感できる話なのですが、日本ではリカレント教育(recurrent education)をRe(もう一度)-Current(現代を) Education(学ぶ)と訳さずに、生涯学習という、どこかシニアの方がカルチャースクールで学ぶような訳され方をして広まっている一面もあります。今ではリスキリングといって「学び直し」という文脈で紹介されてきています。
こっちではコンテニュイング・エデュケーション(Continuing education)と呼ばれていますね。私の大学では、ディズニーワールドやUSJや、ホテルの人が学んでいる。ちなみに、このコロナ禍でリアルがいいかオンラインがいいかは教員じゃなくて生徒が決めています。結果、オンラインが6割くらい選んだ人がいます。成績がいいと授業料は会社が払ってくれ昇進のスピードが上がるので、みんな意欲的に勉強しています。
面白い仕組みですね。日本だと先生が神格化というか全てを決める側。生徒に選ばせると言う発想は、とても合理的ですね。
ところで州立大学の顧客ってわかりますか?顧客は産業界なんです。学生から学費はもらいますが、私達は産業界が望む仕事人になるよう教育・能力開発して、均一な品質の商品として産業界に送り出している。なので3ヶ月に1回観光業界にヒアリングをしています。私が2005年に初めて大学で働いた時に、旅行代理店経営みたいな講義があったのですが、そんなのこれからの時代にそぐわないからEコマースを教えてくれと言われて授業が変わったのを今でも覚えています。
授業でも地方政府と組んでリーマンショックの時にどうやったら復帰できるかということで、インターネットでMICE団体に連絡して、医薬系の復帰が早いことがわかり、そこ向けにキャンペーンを行いますかとアプローチをしました。
州立大学が存在意義がハッキリしていておもろいですね。オーランドDMOのバイタリティを感じます。借金と稼ぎのバランスはどうなっていますか?
オーランド地方債発行してますが政府補償はありません。DMOの将来のキャッシュフローを担保にして800億円調達しています。
政府保証なしって、補助金に頼らざるおえない日本の観光組織とはえらく違いますね。DMO組織はどう運営しているんですか?
執行役員14人はホテルから出ていて政府系の人はいません。社長含めて内10名が女性です。地元政府からの出向者・出身者はゼロでDMOの独立性は担保しています。ただ政府が業務委託契約として、DMOの仕事を業務委託で発注している建付けなので、その契約を盾に影響力というか議会の解散権のような圧力をかける構造は持っている。
なるほど。興味深いお話ありがとうございました。まだまだお伺いしたいことだらけですが時間が来ましたので、またの機会にお願いいたします。
原忠之 セントラルフロリダ大学ローゼン・
ホスピタリティ経営学部副学部長
日本興業銀行、外務省を経て、米国コーネル大学ホテル経営学部博士号取得。
他にホテル経営、経営、地域科学の3修士号を米英の大学で取得。ローザンヌホテルスクールでも教鞭。早稲田大学国際教養学部及び商学部学術院(MBA)客員准教授、一橋大学大学院商学研究科特任教授(ホスピタリテイMBA)、京都大学経営管理大学院客員教授(観光MBA)歴任、広島大学特任教授、宇都宮共和大学客員教授兼任。観光庁・長官アドバイザリーボード・観光統計調査委員、内閣府地方創生カレッジ委員、文化庁文化政策調査アドバイザー兼務。米国観光ホスピタリティ経営分野で正規教員職、テニュア(研究者終身身分保障)を持つ唯一の日本人。観光・ホスピタリティ経営学部として全米第1位(3,600名)の規模を持つセントラルフロリダ大学ローゼン・ホスピタリティ経営学部のNo.2として米国学部経営(人事、財務、学事、総務、企画戦略)7年担当。世界の観光ホスピタリティ学部経営者としても唯一の日本人。米国フロリダ州オーランド在住。

第4弾の原先生のお話はどうでしたか?アメリカと日本は違う!と切り捨ててしまうことは簡単ですが、私はアメリカの人達の逞しさやリーダーシップ、合理性がスゴイなど素直に学ぶべき点は多くあると感じます。
原先生とお話しするとそのお人柄も相まって、フロリダの綺麗な青空のように晴れやかな気持ちになれます。理論に基づいて、自分もみんなも楽しくなるように行動をする、そんなシンプルなことは世界中誰でもできること。
100人インタビュー企画もシンプルに、自分もみんなも楽しくなる話を聞きながら、イコツコツと発信していくことにします。
<次の記事>
<前の記事>
取材後記
原先生さんのお話は講演やnoteを通じて聞いていましたが、広域DMOの方や行政の方がDMOをどうしていけばいいかわからないということでお時間をいただき合同ヒアリング会を設定させてもらったのが始まりです。
私は先生のお話は100%アグリーですが、「そのまま全てを今、この瞬間に全て日本にコピペすべきである」という考えではありません。たまにそのように受け取ってしまって「机上の空論だ」と否定する方の声を聞き悲しい気持ちになります。別に代替案を自信もって提示して自分の道を選ぶも良いし、ここは取り入れれるけどこれは日本式にした方がいいとか、やりようはいっぱいあると思います。アメリカの考え方は、日本の社会や組織を守ってきた人からすると、自己肯定感が砕かれそうになるパワーがあります。ただ世界の観光地と戦って選ばれ、インバウンドの恩恵を国富にしていくためには、この衝撃を受け止めるのは避けて通れません。きっとメジャーリーグに挑戦する日本の野球選手も言葉だけじゃない壁にぶつかり乗り越えてるんでしょう(木立)
インタビュー・木立徹
DeepJapanのプロデューサー。これまで手掛けたインバウンドの公共事業は140以上。仕様書を読むのが趣味。インバウンドの専門家のコミュニティの運営や在日外国人800人をネットワークしている。
大阪府出身、さいたま市在住
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
