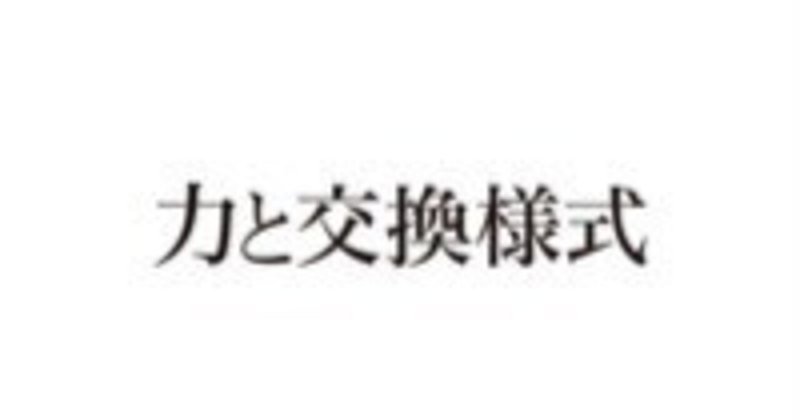
新しい社会の可能性を照射する――柄谷行人『力と交換様式』
🌀柄谷行人『力と交換様式』を読む🌀 その1 書評版
新しい社会の可能性を照射する
――柄谷行人『力と交換様式』

■柄谷行人『力と交換様式』2022年10月5日・岩波書店。
■長篇論考(哲学・社会思想)。
■416頁。
■3,850円。
柄谷自身の創案になる、4つの「交換様式」によって人間の社会構成体を読み解く。A=互酬性、B=服従と保護、C=商品交換、D=Xとなり、それぞれは固有の「霊的な力」を持つとされる。現在の世界、社会はさまざまな問題を抱えているが、その原因の一つにCの商品交換を基盤とする資本制経済が、Bの国家権力、Aのナショナリズムと緊密に結合し合い、その問題の解決を難しくしている。これらの「資本=ネーション=国家」複合体の力に対抗するために、これらを否定する「D」の力が期待されるが、これは人為的なものではなく、われわれ人類の予想を超える形で到来するという。
幾つか問題がある。①あえて交換様式史論を取る意味が分からない。②交換によって力が発生するのではなく、力を相殺するために交換が発生するのではないか。③交換様式Dの内容が曖昧だ。④その力が「霊的な力」だというが、何故、そのような表現が選ばれるのかが分からない。⑤具体的な解決策に結びついていない。
しかしながら、これらをもって、本書の可能性や、この著作を以て、柄谷の今までの業績を否定し去るのはいささか早過ぎるというべきだ。先にDの説明が曖昧だとしたが、本書には、Dであり得たかも知れぬ普遍宗教についての研究が幾つか紹介されている。その中でも、アウグスティヌス『神の国』やトマス・モア『ユートピア』、あるいはエンゲルスの『ドイツ農民戦争』の再評価などが耳目に新しい。ここはきちんと評価すべきであろう。
あるいは柄谷の業績は「交換様式」史論の提唱者として今後知られることになるやも知れぬが、本書も含めて、柄谷は一貫して在来のテキストを如何に解釈するかという、広い意味での文芸批評家であったと考えられる。小林秀雄を始めとする、日本の文芸批評家たちが、この「文芸批評」という枠の中で、いかに多くの、様々なことを成してきたかを考えるとき、その正統的な流れの中に柄谷行人が確かに存在してきたということは否定できまい。
更に言えば、多くの文芸批評家たちが、どういう訳か、文学や思想といった書物やジャーナリズムの世界に狭く留まるだけではなく、現今の社会に対して、アクチュアルな発言や行動を以て、その思想を闡明してきたことだ。柄谷は1991年の湾岸戦争の反戦声明を期に、従来の「相対主義」(?)的な姿勢から、より現実的になり、2000年には社会運動組織「NAM」の結成に至って、その頂点に達した。やはり本書も広くこの社会運動論の中で、吟味されるべき論著であるというべきである。
🐥
1045字(3枚)
20230102 1640
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
