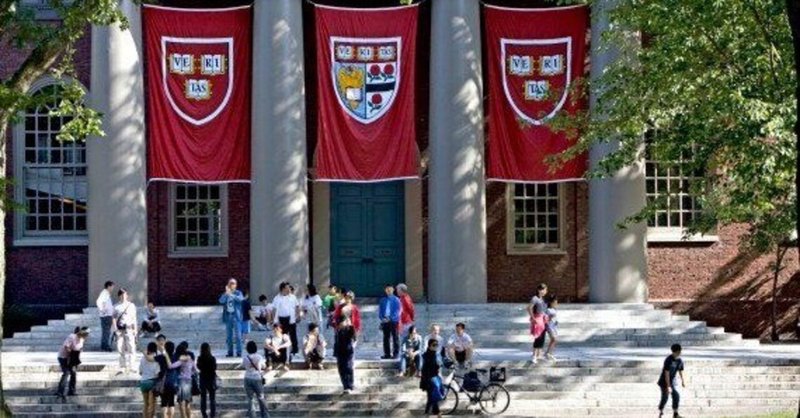
世界に通用する一流の育て方~地方公立校から塾なしでハーバードに現役合格~
上記のタイトルを見てみなさんは何を感じますでしょうか。私は世に溢れるこの手の教育指南本はほぼ信用していないのですが、今回手に取って読んでみました。というのも以前に読んだことがある広津留すみれさんのお母さんが書かれた本だったからです。
一人娘が大分の県立高校から米ハーバード大に異例の現役合格。その背景には母親の“非常識な教育法”があった。妊娠中に育児本を200冊読破。独自の教育法を見出し、0歳から英語と日本語の絵本を読み聞かせ、2歳から英語を学び始め4歳で英検3級。週末はホームパーティで社交性を磨き、幼稚園に通わせるつもりはなかったが、仕方なしに1年だけ通園。偏差値主義や受験システムは無視。もはや東大や京大なんて眼中にない、世界レベルの学力の伸ばし方がわかる。
タイトルにもあるように、筆者の娘のすみれさんは大分の県立上野丘高校からハーバード大学に現役合格しましたが、それでまでに一度も塾に通ったことはないそうです。
ただ、個人的にはこの「塾なし」というのをことさら強調することに違和感を感じます。そもそも「塾」と「ハーバード」に相関関係が全くないからです。そもそもアメリカには基本的に大学入学のための塾というものは存在しません(SATの塾などはありますが、通うのは裕福な韓国人や中国人ばかりです)。
本書の肝となっているのは、「塾に行かなかった」という事実の裏に存在する「家庭教育」の重要性です。
ちなみに母親の真理さんはもともと英語と音楽が得意で、その影響もありすみれさんが2歳の頃から英語の勉強を始めさせます。その結果上記の通り4歳で英検3級に合格します。バイオリンも2歳から始め、その後演奏会で披露したり、コンクールで入賞したりしました。
2歳からバイオリンと聞くと、どんだけ裕福な家庭なんだと訝しく思ってしまいますが、真理さん曰く広津留家は大分の平均的な家庭だったとのことです。バイオリンを習うことができたのは、塾に一切通わなかったため、学費を抑えられたことや小中高すべて公立で、12年間の学費は合計50万円程度だったことが理由だと書かれています。
そんな母真理さんが書かれた本書ですが、印象的な言葉を拾いながら、感想を記していきたいと思います。
常に「親と子供は別人格」と意識しておくこと
これは至極当然の事実なのですが、意識できていない親は驚くほど多いです。実際に子供を自分の分身かのように扱い、「子供のため」と言いながら、実は「自分のため」に行動している親をこれまで数えきれないくらい見てきました。
例えば、自分が若いころに英語ができなかったからと言って、子供に英語の勉強を強いたとしても、それは本当に子供がやりたいことかどうかはわかりません。結局のところ、子供の幸せは本人が自分で定義するべきものであり、親が進学先や職業、友人や結婚相手などを選ぼうとすることは親のエゴでしかありません。
・・・と、自らを戒めたいと思います。
プラス1
教育用語に「プラス1」という言葉があります。これは「現状の能力や学力を1ランクだけ伸ばす努力をする」ことを意味しています。
子供は過度に期待されるとストレスを感じて逆効果になりますが、プラス1だと意欲的になって能力が学力が伸びやすいということです。
ですから、この「プラス1」がどのレベルなのかを知ることが親にとっても教師にとっても非常に重要なファクターとなります。プラス1を正しく設定すれば、子供は自分で力を伸ばしていくことが可能になりますが、難しすぎたり簡単すぎたりするとやる気を失ったり、時間の無駄になったりしてしまします。であれば、子供の興味や学力(何ができて何ができないか)を知ることが非常に重要であり、それは学校や塾にまかせてばかりではなく、家庭でしっかりと把握するべきだということだと思います。
ハーバード生の家庭学習
上述の通り、広津留家は家庭学習を重視し、すみれさんはハーバード大学に合格したのですが、ハーバード生の98%が幼いころからの家庭学習をプラスに感じているということが独自の調査で分かったと書かれています。では、彼らはどんな家庭学習を受けてきたのでしょうか。
ハーバード生が受けた家庭学習
まず家庭学習に関して、非常に多かった意見として以下のものが挙げられます。
今の自分があるのは両親のおかげ
両親は私の最初の先生
親は私の人生のロールモデル(お手本)
幼少期の家庭教育はとても重要
学問の楽しさを教えてくれた
「知」を覆い求める楽しさを教えてくれた
では、彼らは具体的にどんな家庭学習をしたのでしょうか。
読み聞かせをしてくれた。本の読み方を教わった
好奇心を促すリソースを常に与えてくれた
質問にはなんでも答えてくれた
小さいころに勉強の習慣を身につけてくれたから、自立が早かった
宿題・スポーツ・友人関係の3つをうまくこなす時間管理術を教わった
美術館・プラネタリウム・自然キャンプ・旅行などに連れて行ってくれた
自分の意見を持つこと・常に問いかけることの大切さを学んだ
家族で何でもディスカッションした
小学生のころから政治経済・芸術の話をたくさんした
失敗に負けない方法を教えてくれた
日常会話に文化や芸術の話が盛り込まれていた
小さな成功体験をたくさん積み重ねてくれた
学習の大切さ・面白さを教えてくれた
さすがハーバード生の親たちですね。レベルが高い。本書を読むときに教師としての視点というよりは親としての視点で読んでましたが、なかなかまねできないようなこともいくつか含まれていますね。
ちなみに、先日長女(中1)と二人で車の中でラジオを聞いていた時に、「エシカル(ethical=倫理的な)」がテーマになっていたので、「エシカルとは何か」「サステイナブル(sustainable)とは何か」「SDGsって知ってる?」などの話しました。そのラジオで言っていましたが、フランスでは試験的にチラシや広告のポスティング(貼り紙も)を法で禁止にするそうです。確かに毎日ポストに投函されるジャンクメールを見て、資源の無駄遣いだなぁと思っていましたが、それを法で禁じるなんてさすがフランス、さすがヨーロッパ。
子供に勉強の価値を伝える
というわけで、ほとんどのハーバード生が親から大きな影響を受けて育っているわけですが、その中でも以下の4つを親に教えてもらったおかげで、自立して勉強に打ち込めるようになったという意見が多くあったそうです。
Learning Value(学ぶ価値)
Love of Learning(学びを愛すること)
Learning Habit(学ぶ習慣)
Lifelong Love of Education(学びを生涯愛すること)
また、「読み聞かせ」「読書週間」「図書館通い」など、早期から文字学習をしていたことを示唆するキーワードが非常に多く、語彙を増やして会話を豊かにする家庭学習の重要性も感じることができます。
ビジネスと同じ発想で家庭学習をマネジメント
筆者は家庭学習において踏まえておきたい4つのポイントを以下のように挙げています。
・重複していることや費用対効果の低い「ムダ」を削る
・優先順位をつける
・効率的なスケジューリングをする
・ムダを削った分、余暇を増やして有効活用する
要は「選択と集中」ですね。ムダを削ってやるべきことに優先順位をつけ、効率的にスケジューリングする術を家庭で教えるということです。
ちなみにこのあたりは、私も家庭教育である程度実践しています。
例えば、長女が定期試験の1か月前になったら学習計画票を作ってもらいます。自分で現状を分析し、ゴールを設定した後に、逆算してスケジュールを立てる。大人が仕事で毎日やっていることと何ら変わりません。
そして試験が終われば、リフレクション(reflection=振り返り)をさせます。リフレクションには「YWTシート」を使ったりします。YWTとは、
Y:やったこと
W:わかったこと
T:次にやること
の頭文字で、試験だけではなく、何にでも応用できます。
このようにPDCAサイクルを回していくことを教え、習慣として実践させていくようにしています。
これらの教育は学校でやってくれればありがたいのですが、学校任せにするのではなく家庭で負うべき責任だと個人的には思っています。筆者の真理さんが言うように、家庭教育の重要性に関しては論を俟たないところだと思います。しかし、日本では「教育」というと、どうしても学校に丸投げになりがちで、家庭での教育が軽視されがちです。今こそ改めて家庭教育の重要性に光を当て、学校教育と家庭教育の両輪で子供の力を高めていくことで国力を上げていくべきだと思いました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
