
「恐怖克服」運転で性格が急変するのは扁桃体モードのせい
運転で性格が変わる人のメカニズム
いつもは優しくてマイペースな人なのに、運転の時だけ、やたらと言葉が悪くなり、荒っぽくアクセルを踏んだり、危険な運転をする人がいると思います。

これは、脳の働いている部位の変化によるものです。
そのような人は、普段は前頭前野が働いていますが、緊張と恐怖からか扁桃体が優位に働いて扁桃体モードになっているのです。
前頭前野は周知の通り、ワーキングメモリー、反応抑制、行動の切り替え、プランニング、推論などの認知・実行機能を司っています。
扁桃体は、情動反応、記憶、直観、恐怖、ストレス反応など、特に不安や緊張、恐怖に対しての反応を司っています。

運転には様々な注意を払わなければいけないため、本来は前頭前野が働かなくてはならないのです。
扁桃体モードは運転だけじゃない
人間は恐怖や強いストレスを感じると、扁桃体モードになって激しい情動が表れ、冷静な思考や行動、論理的な判断などができなくなります。
会社や学校などで、その人の知らないような知識を尋ねたり、お店のスタッフにマニュアルにない話をしたりするとそれを体験することができます。(やらない方が優しい人でいられますが…)

恐怖の情動は脳が扁桃体モードになり、視床下部も活性化させます。
視床下部は交感神経に緊張を高めるよう指示をするので、心拍数が上がり、息苦しくなり、瞳孔が拡大して恐怖心が増すという危険なループに入っていきます。
いわゆる恐怖による興奮状態です。

「恐怖克服」扁桃体モードを解除するには
これを改善する最善の方法は、「経験をして慣れる」ということです。
車の運転であれば、軽く流すようなドライブの経験を重ね、慣れることで恐怖心が少なくなっていきます。
データでは、ベテランドライバーほど運転中は前頭前野が働いていることが分かっています。
ただし、ベテランドライバーでも扁桃体モードになっている人がいます。
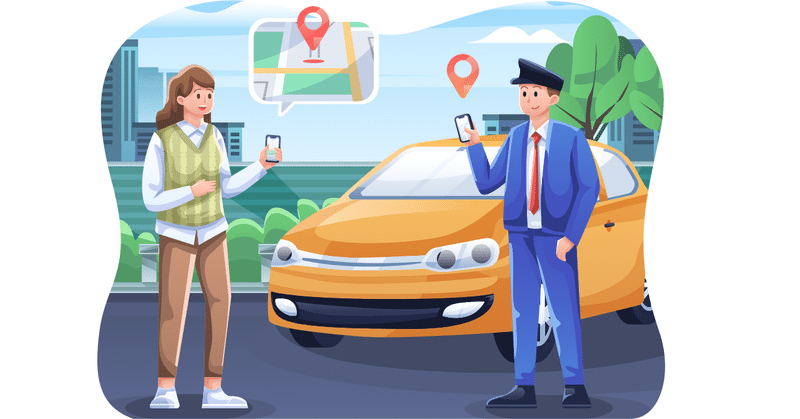
この場合は、無自覚に運転の恐怖が払拭できていないというパターンとなります。
それを改善するには、「自分が車の運転をすると扁桃体モードになる」という問題意識を認識してもらう必要がありますが、運転にはすでに慣れてしまっているため、指摘をすると「オレは運転中に変わらないよ!全然大丈夫!」と言ってくる可能性が高いので、改善するのはなかなか難しいと思います。
サポートは、さらに良い記事を執筆できるように研究費として活用いたします☺️✨️ いつもありがとうございます💖
