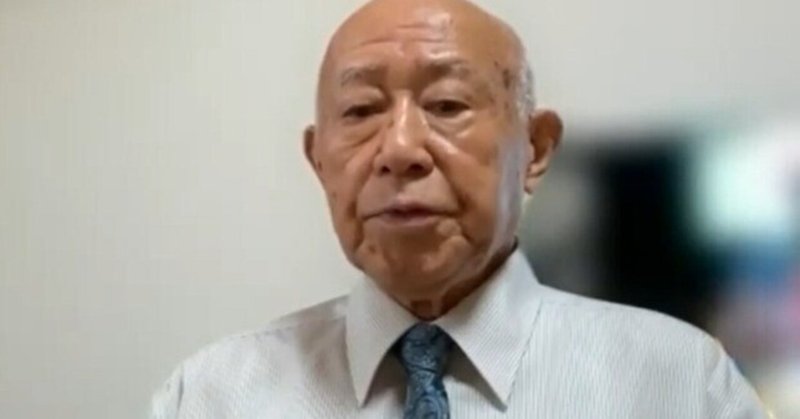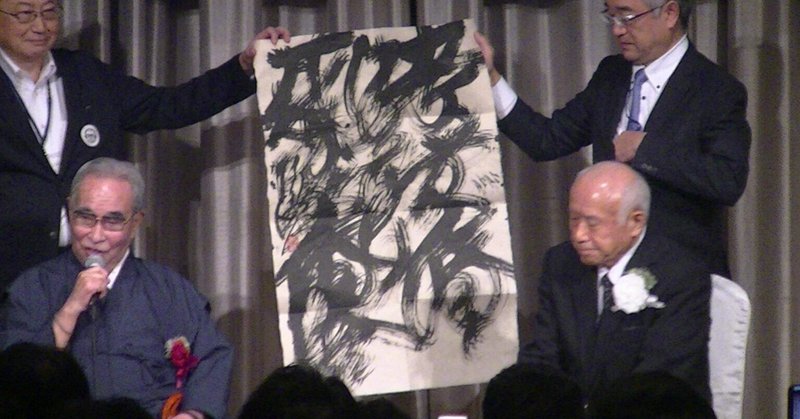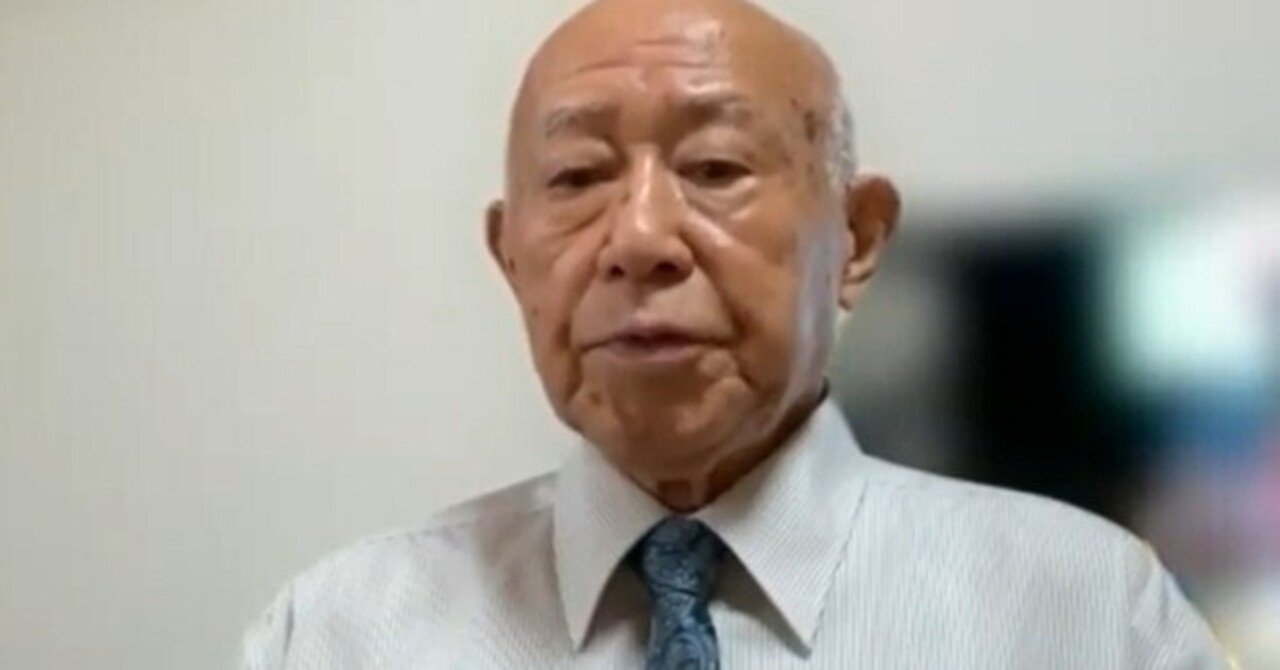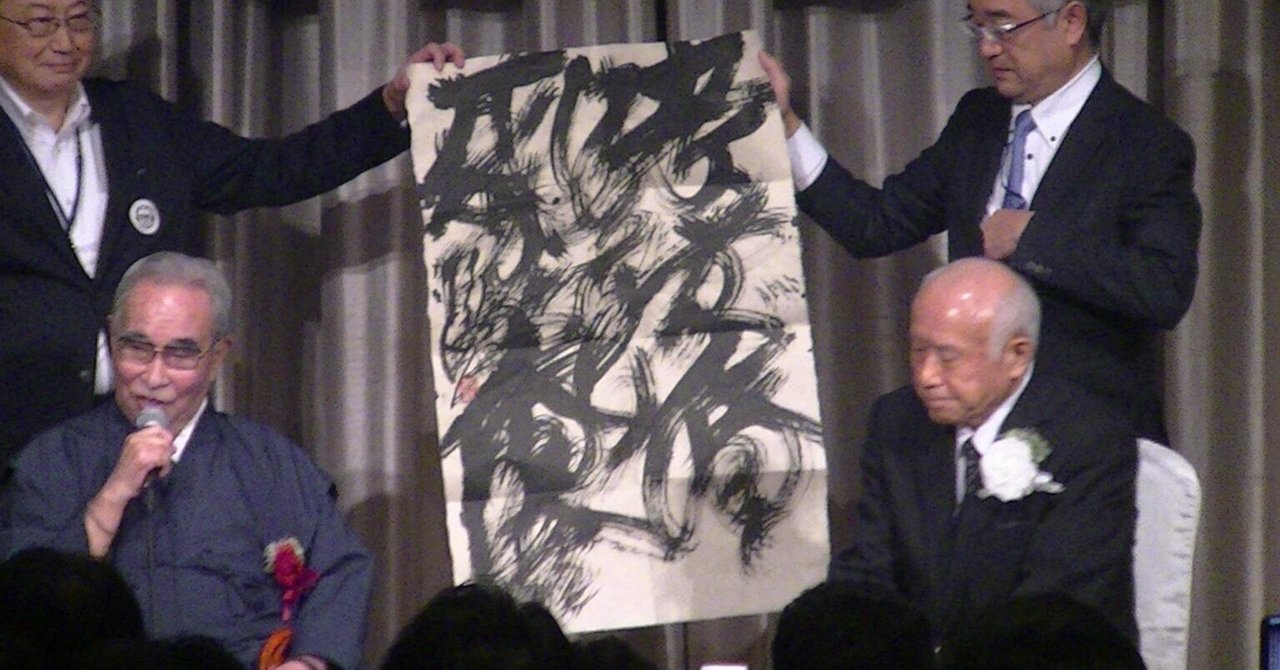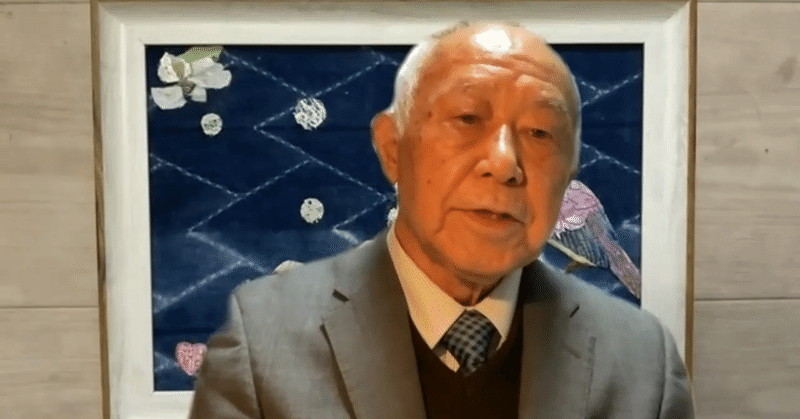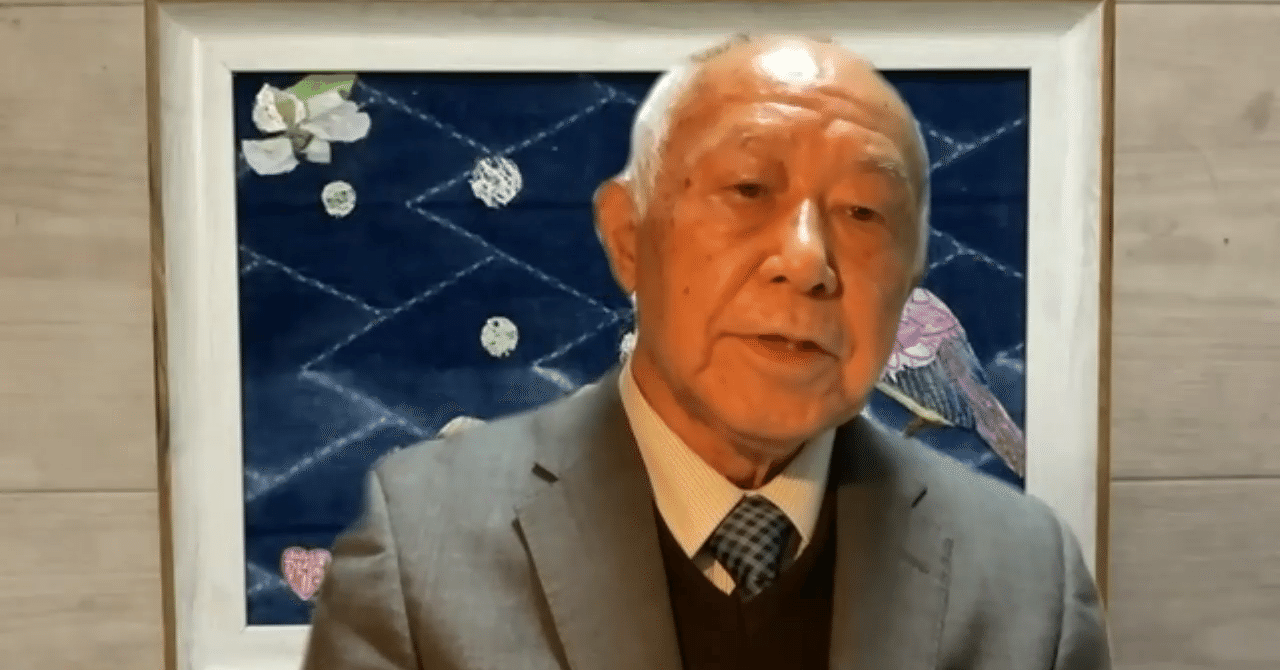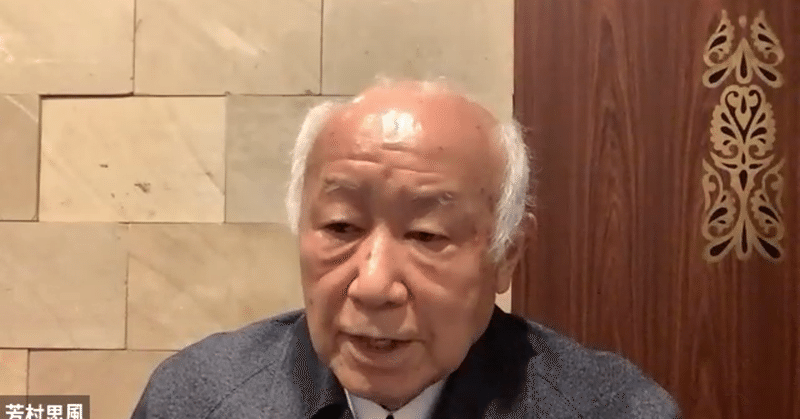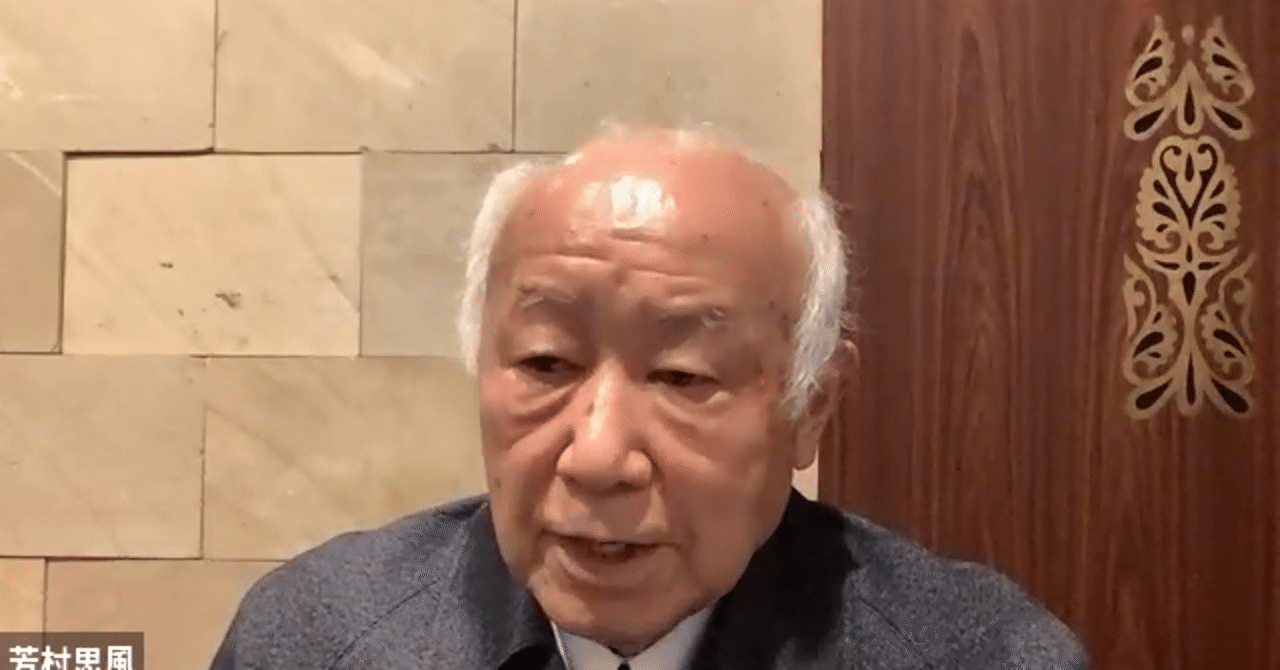最近の記事
 再生
再生2023年6月3日東京思風塾「お金と響き合う」
思風先生から お金をどの様に稼ぐ、蓄えるよりも どう使うか!に重点を置いてお話頂きました。 お金の使い方を考えないと人間と貨幣との間の人間らしい響きあいが難しい。 また、貧富の差を縮めていくやり方を実効的に効力のあるやり方をこれから我々は考えていく必要がある。 その使い方にお金と人間の美しい関係がある。 大事なことは、お金は儲けてください。そのお金を貯めないで流通させてください。本当に貨幣が経済の血流となって、全ての人を潤すというような、そういう真の生きた経済のあり方というのを、自覚的に作っていかなくてはいけない お金の流動のさせ方、お金の分配の見事さに対して感謝し、見事さに賞賛する。そういうことが出来る人を尊敬する 見事に美しく使えるということこそ、人間として尊ぶ、尊敬する時代を創っていかないといけないんじゃないか そうすることによって、自然にお金を持っている裕福な人と、持っていない貧困な人との格差というものがだんだん埋まっていって、お金を持っていても、お金を鮮やかに使うから見事に使うから、お金を持っていることを悪として見られることがなくなる。 鮮やかに儲けて、鮮やかに使う この一対の活動がなかったならば、人間が作った経済活動は、人類を本当には幸せにしない
 再生
再生2023年5月13日東京思風塾「人生のパートナーと響き合う」
愛を自然発生的な段階から、愛を文化たらしめて、愛を人生を生きる力・能力として愛を育てていくという自覚が非常に大事! その自覚を持つことによって、夫婦関係もガラッと違ってきて、お互いに協力し合って、努力して、愛をつくっていくということができるようになり、結論が出ないような夫婦喧嘩でお互いを攻め合い、悩み合うという状況から脱却していくということになっていくのではないか 夫婦の愛の問題については、いろいろな書物で問題にされ、解き明かされてきましたが、 愛の問題というのは学問の研究対象ではなく、文学の対象と言われて 文学では愛のあり方やバリエーションが描かれておりますけれども、 一向に人間は愛に関する生き方において、古代から今日に至るまで成長していない。現代人も愛について悩んでいる。 小説として愛のバリエーションが描かれば描かれるほど、あんな愛、こんな愛…いろんな愛が描かれ、不幸な犯罪や事件となって展開されていくような恋愛小説。事件となってしまうような夫婦関係となってしまうような小説に描かれており、愛のバリエーションがあればあるほど、愛に悩み苦しむ状況から脱却できない 感性論哲学では愛を自然発生で考えるのではなく、全くこれまでとは違う、新たなる次元から愛をとらえる ↓ 人間の愛の原点に帰るということをしないといけない 愛を文化たらしめるという関わり方、捉え方を感性論哲学では推奨している 愛を文化たらしめる=人生を生き抜く力に変えていく 愛はこれまで人生の迷いの対象だった 愛をこれから生き抜く力に変えていく。理性という能力と対比され、匹敵するくらいの愛の能力を成長させていって、この愛に関する力というものを高めていくということをしないと、我々は夫婦の愛、親子の愛、人間関係における愛の苦しみから自分自身を解き放つことができないのではないか 皆さんもぜひ「愛を文化たらしめる」という発想や考え方を一度考えておいてもらいたい もし愛というものが、文化となって、愛というものを能力と考えて、人生を生き抜く力としてとらえるならば、小学校一年生から学年が進むに従って、愛の力が成長していって、学校を卒業するころには、愛の実力というものを獲得して、その愛の実力というものを持って社会に出て行って、さまざまな人間関係を処理していく。そういう力が出来てくるのではないか。 知識や技術によって社会に出て行って、いろんな仕事をしていくように、愛というものについても基本的な知識や技術を学んで、人間関係を処理して、たくましく人生を生きていく そういうことが今人類には求められる段階に入った
 再生
再生2021年4月3日東京思風塾「心が欲しい、心をあげるとは」
原点を考えれば、会社も人間 人間の本質は心 心が欲しいと願っている中で、美しい人間関係を中核にした組織、会社を創ろうとしたら 全社員にいたるまで心を満たしあう意識を持つ事が大切 心が欲しい、心をあげるとは ・認めてもらいたい、わかってもらいたい、褒めてもらいたい、好きになってもらいたい、信じてもらいたい、許してもらいたい、待ってもらいたい そういう7つの欲求が心が欲しいという気持ち それに対して心をあげるとは 認めてあげる努力をする わかってあげる努力をする 好きになってあげる努力をする 信じてあげる努力をする 許してあげる努力をする 待ってあげる努力をする
 再生
再生2021年3月6日東京思風塾「美しい心を持とうと思ったら美しいの対概念である「醜くない」を考える」
美しい心を持とうと思ったら美しさそのものを求めてはならない 美しいあり方とは何か?に直接的に答えようとすると複雑で多岐に渡るので、学問的に考えて答えを出すならば、どういう方法論を使わなければならないのか というところから、話さなくてはならない その方法論としては醜くないあり方とは何なのか? そこから考えていかないと人間として本当の美しい心、人間性を持つ事は出来ない。 美しいの対概念である「醜くない」を考える 醜くない在り方とは何か?人間という立場から考えると、我々は美を求めるが、人間は不完全であるので、完全なる美に到達することはない 人間であるならば、なんらかの醜さというものを、その存在の中に抱えている 自分の心にある醜さを反省することが、美しさであるという自覚に到達する 不完全性というものを、存在論的に受け入れていかなくてはならない人間という命の在り方からする、非常に大事な原点 美しいあり方とは、醜くないあり方 我々は日常、醜い言動をしていることへの自覚をすることにより、対存在としての美しさに気づいていく 本当の自分を隠して相手の気に入るような言動、夫婦間での我慢、遠慮 偽りの自分、。演技された自分をやっていないか 人の不幸を喜んでしまったり ある人を批判したり、責めたり、からかったり、悪口を行ったり、陰口を言ったり、 誹謗中傷したりというのは、自分の心の中にあることを反省し、そういう醜い心を持ってはならないという、その心の在り方というのを、自覚的に求めていく努力をする必要がある それが不完全なる美の追求の仕方 完全な人間はいないので美しい心というのは醜くない心
 再生
再生2021年3月6日東京思風塾「これから我々が求める美しさの核になるのは矛盾を生きる力」
これから我々が求める美しさの核になるのは 矛盾を生きる力 それこそが美しい 考え方が違い、価値観が違う方とどう接していくか 何で考え方が違うのか 体験が違う、経験が違う、知識情報が違う、物事の解釈の仕方が違う、人生における様々な出会いが違う 考え方や違いは後天的に作られるもの ただし人間が成長しようと思ったら 自分に持っていないものを相手から学ぶこと 対立というのは自分が成長する、学び取る為の現象と解釈し 人間が大きくなる 人間性の豊かさ、幅が出来る 違いについての根拠を知る、相手から学ぶその分だけ自分が豊かになる それがこれからの時代の人類に求められる愛のあり方であり 美しい心を創る為の原理方法論
 再生
再生2021年2月6日東京思風塾【人間の美しさの根源は心の美しさ】
【人間の美しさの根源は心の美しさ】 美しい心とは、考え方の違う者が仲良くお互いを理解しあえること 違いについては、宇宙の法則から考えることもでき 対存在 ・闇があって光がある ・男がいて女がいる ・善があり悪がある その様な対存在があってバランスよく成り立っている(=秩序がある)のが宇宙の法則 バランスが取れているというより、秩序が取れているから 違うものが協力しあって生きているから美しい 我々も宇宙の一部分という考え方からすると母なる宇宙がしていることと同じことを、社会という宇宙において実現しなくてはならない 美しい心を持つこと。考え方が違うものが、どうしたら協力しあって生きているか…ということを考えて生きていけること どうしたら対立せずに生きていけるか、人間関係の美しさ=愛 人間一人ひとりの心の中に作らなくてはならない砦=愛=美しい心 秩序を作ろうとする心が美しい心 美しい心が美しい社会を創る
 再生
再生2021年2月6日東京思風塾【美しさは何ゆえに重要か】
今日から21年目の思風塾 今回の東京思風塾から21年目になります。 年間テーマ「美しいと共に生きる」 今月は【美しさは何ゆえに重要か】 思風先生から、時代的な背景を踏まえてお話頂きました。 経済、政治において醜い言動がなされている、報道されている。 現実に対しても「美しく生きる」ことを一人ひとり意識しながら言葉を慎み、行動を慎み、生活を立て直していく。人間関係でも美しさを意識しながら生きるという、新しい人類の生き方を日本発で世界に伝え、素晴らしい未来・世界・社会を作っていくことを考えていかねばならない年。 美しさの価値重要で大切なのか、根拠を話すことから始めたいと思います。 古くから、人間はこの真善美を求めるということが、人間における根源的、最高の価値だといわれる中 価値観としては「真善美」と横並びで言われているように、重要な価値と言われているが、真と善は判断基準が理性にある 「美」は感性 近代になって、経済学が発達するようになってきて、人間的活動というのは、真善美を追求するだけではなく、利という価値も追求するべきという考え方が出てきた 真善美+利 科学と哲学の違いから 科学は事実を探求し、知識を獲得する為に生まれた学問 哲学は 幸福欲を実現する、それを感性論哲学では定義しており 幸福を実現するためにはカントが述べた真善美そして利が存在するが 大切なのは 真善美を追及してしあわせになるか? ↓ それだけでは本当のしあわせは手に入らない 感性論哲学では人生は意志と愛のドラマという人生哲学が存在し 意志と愛を追及する事によって、命の底から湧きあがるしあわせを感じることが出来ると感性論哲学では説いています。 何故意志と愛が必要なのかというと 命には2つの目的があり、自己保存と種族保存 これはあらゆる生命の目的に与えた目的であり、その生命の目的に合致したものでないと本当のしあわせには繋がらない。 自己保存が意志 種族保存が愛 真善美利は手段として活用するもの