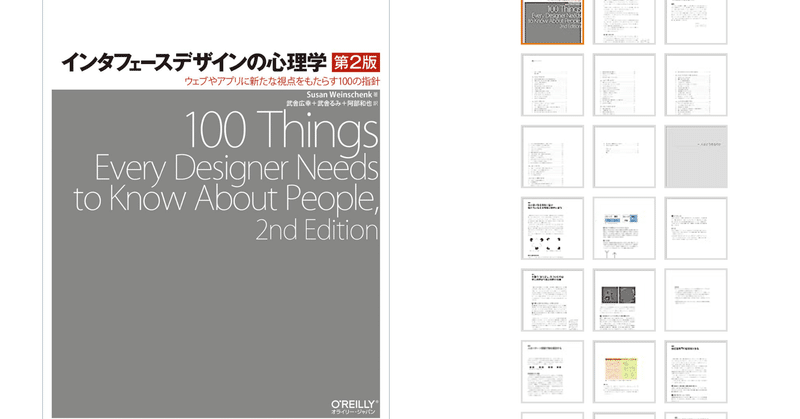
考えさせるよりクリック数を増やす/ 段階的開示/ 「認知」「視覚」「運動」 の順で疲れる/ 注意散漫は当たり前/ 人は中々考えを変えない/ メンタルモデルを知る/ 概念モデルを知る /物語として話すと伝わりやすい/ 画像の例を使うと理解されやすい /人は分類が大好き
考えさせるよりクリック数を増やす
クリック数を増やすか、ユーザーに何かを考えさせるかで迷ったら、クリック数を増やすことを優先する。
クリック数を増えるなと思って、情報をいっぱいにするくらいだったら、
何度もクリックを選択!
段階的開示
ユーザーが欲しい情報がポンポン出てくるように、大半のユーザーが何をいつ必要としているかを調査し、把握する必要がある。
「認知」>「視覚」>「運動」の順番で負担を感じる
・ユーザーが考えたり、思い出したりしなければならない場合の負荷(認知的負荷)は心的資源を最も強く要求する
・ある手法を用いると視覚負担や運動負担は増えるが認知負担を減らせるという場合、その手段を使うべき
(1ページの長い説明より、10回のクリックを選ぶ)
注意散漫は当たり前だから、人はネットサーフィンが好き
・人は限られた時間しか集中することができない
・ハイパーリンクを使って、ぴょんぴょん飛ばせるようにすることを人が好む
・ユーザーが注意散漫になった時でも、「現在位置」がすぐわかるようにする。そして、元の位置に戻りやすくする。
自信がない人の方が主張する
・人が信じている考えようとして、多くの時間を費やしても無駄
・信念を変えるためには、何かをさせてみることが重要
・人の考えに対して、論理的でない支持できないなどの証拠を突きつけるとかえって、逆効果で相手の主張はますます強くなる。
メンタルモデル
・メンタルモデルとは、ある物事が機能している仕組みをその人がどう理解しているのかを表現したもの
・人は過去の経験に基づいてメンタルモデルを持っている
・全ての人がメンタルモデルを持っているわけではない
・ユーザーや顧客を調査することで、対象者のメンタルモデルをより深く理解することができるようになる。(これが調査の理由でもある)
概念モデル
・プロダクトのルールのモデル(実際のインターフェースに接した時に、感じる概念)
・しっかりとした目標を設定してシステムの概念モデルを設計する。技術的な観点からすぐにできるものを作ってそこから「膨らませる」のではない。
・ユーザーが直感的に使えるシステムを設計する秘訣は、システムの概念モデルをユーザーのメンタルモデルと一致させることにある。
・全く新しいシステム(製品)で、そのシステム(製品)に関してはユーザーのメンタルモデルもシステム概念モデルと一致しないと思われる場合は、新たなメンタルモデル構築に役立つトレーニング(動画)などを用意する必要がある。
物語の形で人に説明すると理解さやすい
・物語は、人が情報を処理するのに適した自然な形式
・「因果関係の飛躍」をおこなさせたければ物語を使う
・物語で、伝えるものが無味乾燥なものでも、わかりやすく、興味深く、記憶しやすいものにする。
(財務情報に年次ごとにできた、製品によって助けられた人の話を出したりする)
例を使って説明するべき
・画像(スクリーンショット)や、動画などの例を使うことで、理解されやすくなる。
人間は分類が大好き
・未分類の情報が大量にあると人は分類させたがる
・データをきちんと整理して、分類されたカテゴリをどう呼ぶのかも重要である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
