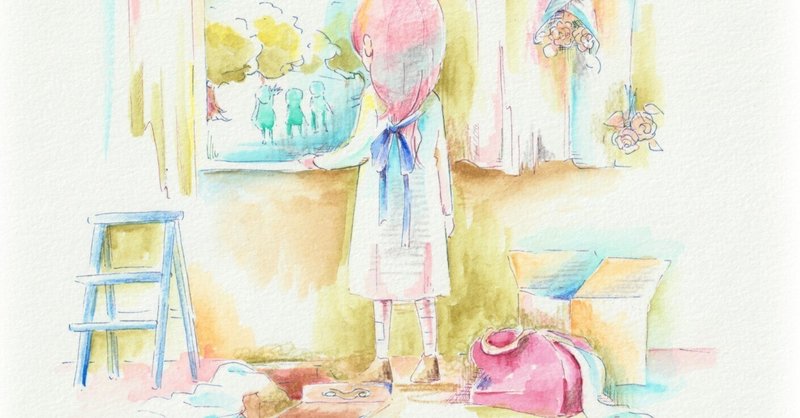
理屈を越える
10月4日。寝ぼけ眼でラジオをつけたら、ミサイルが飛んできた話、Twitterを開いたらひろゆきさんが辺野古基地の座り込みを揶揄した、という話が飛び込んできて、ううむ。混沌とした気持ちで、朝。
個人的には、ひろゆきさんは、ずっとああいう感じの人だと認識してるので「ああ、そうか」という感じなんだけど、彼を「新しい目線」みたいに本気で称賛する人やメディアが多いのを心底怖いと思う。
行動の向こうには必ずそうなった背景があり、そこにいる人の思いがある。それを切り捨てて、上辺の部分の揚げ足取りで“論破”するのが正しいこととは私には思えない。それをよしとする人をまるでジャーナリストのように持ち上げるのはどうなんだろうか。
人や歴史は単純なロジックでは出来ていない。「寸分の矛盾もなく正しいもの」ではない。だからこそ、手間や痛みを伴ってでも、そこを考える必要がある。私だってそんなに詳しいわけではないけれど、沖縄が背負ってきた歴史と今に至るまで続いている問題、そこに実際に生きて、ああして活動をする人の気持ちを鑑みれば、あのように嘲笑することがいかに残酷かというのがよくわかる。笑ってしまえる人は、「沖縄の問題は沖縄(あるいは基地問題を問題視している人だけ)のハナシ」と思っているんじゃないだろうか。他人事なら、何を言っても痛くも痒くもないだろう。
ひろゆきさんやこの件に限らず、差別の話についても似たようなことを思う。「そういう差別で大変な人もいるらしいね」と他人事ポジションで話す人に会うと、内心震えるほど怒ってしまう。
ただ、理解していない(知識がない)ことに対していきなり怒るのもな…と思うので、なぜそれが問題なのかというのを自分が解る範囲で説明する。しかし、話しながら「解説しなければ理解できないほど、この人にとってその話は他人事なのだな」というのがひしひしと感じられると、何とも言えない気持ちになってくる。
社会問題として話すなら、どういった内容であれ、それを“社会問題”として取り上げる時点で誰もが当事者のはずだ。
右とか左とか、賛成とか反対とかそんな二択じゃなくていい。微妙なグラデーションの中でいい。自分はどんなビジョンでものを見ているかを確かめ、それを他者のビジョンと照らし合わせるのが大人として誠実な向き合い方なんじゃないだろうか。
声を上げる人はうるさいだろう。けれど、うるさく声を上げなかったらいないことにされる人や歴史がある。ようやく上げられた声を「ノイジーマイノリティ」なんて言葉で片付ける前に、ノイジーじゃないマイノリティの存在に私たちはもっと敏感であるべきだと思う。
今日の絵

全力でフリーペーパー発行などの活動費にさせていただきます!よろしければ、ぜひサポートをお願いします。
