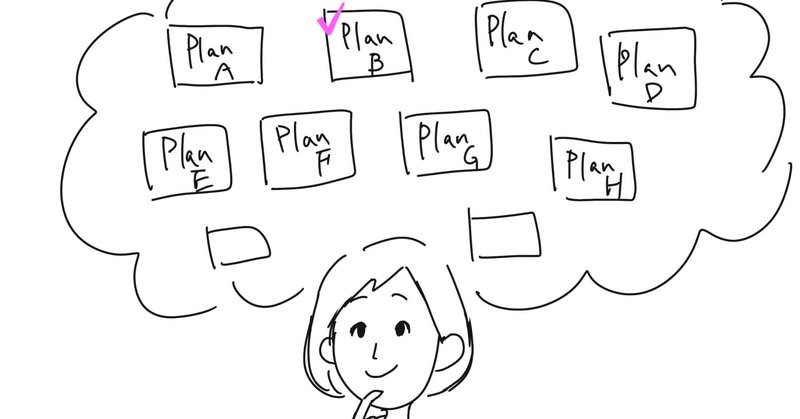
どんな保険設計がベストか
保険設計に正解はなく、どんな保険も役に立ったり、長期に使うことがない場合もあります。ですので、下記は私の考えになります。
外資系生保の設計思想
こちらもプランナーによって設計は違う場合があるので、一概には言えないのですが、傾向として見受けられる内容を書いていきます。
外資系生保は、第一に死亡保障を重視しています。
保険にしかできない機能で、保険の原点、根本的な部分が死亡保障だからです。万が一が起こった際に、どれだけ保険が役に立つかを考えると、残された家族やご自身を守るには、厚い死亡保障を最も重要視しています。
死亡保障にフォーカスした場合、保険設計は積立、カケステのどちらでも良く、万が一が起こった際に、必要保障額が確保できているかという点が重要になります。
例えば、
月1万円で1億円の定期保険(カケステ)
月30万円で1億円の終身保険(積立)
が仮にそれぞれあったとして、どちらに入っていても、死亡時の保険金は同じです。設計思想やコストは大きく違えど、保障額は同じなのです。
積立部分を証券で行うなどありますが、今回は話を単純化します。
ユーザーにたいして、まず必要保障額を算出し、その方のフローやストックなどの状況やご意向から適切な設計(積立やカケステの比率を考える)をしていきます。
アーリーデス(早期死亡)があった場合には、定期保険がベストになり
リブロング(長生き)の場合には、終身保険がベストになります。
誰しも何歳まで生きるかはわかりませんので、設計時に正解はみえません。また、リブブロングに関しては、終身年金の設計がベストになる場合もあります。
窓販の設計の傾向
窓販や一部の日本の保険会社の設計はどんな傾向があるかというと、必要保障額というよりは、第3分野保険(がん保険、医療保険など)に注力している傾向があります。
がん保険や医療保険などは、ユーザー自身のニーズが顕在化している場合が多く、給付金も自身が受け取るケースが多いので、契約率が高い傾向があります。自動車保険などの損保に入るイメージに近いです。入院や手術の際に、高額な費用を自分で払うのが困るから、その問題解決をしたいとった具合です。
厚生労働省は、高額療養費制度を用意しており、年収770万円までの方であれば、多額の医療費がかかった場合でも(自由診療などを除く)
80,100円+(医療費-267,000)×1%
までの自己負担となります。詳しくは、以下サイトにあります。
医療の保障という面においては、国の手厚いサポートがあるにもかかわらず、個人で手厚いがん・医療保険に加入し、肝心の死亡保障が薄い方が多いように感じます。
窓販や日本社でも、しっかりと死亡保障メインで設計されている方もいますのであくまで傾向の話です。
ネットやダイレクト生保の傾向
テレビCMなどで良く観るものですと、がん・医療保険、薄い定期保険でおいくらです!といったものが多いです。
万が一の際に、その保障(保険)で、家族やご自身を守れるのか心配です。
ご家族がいる方が死亡された場合、国から遺族年金などがあります。
また、会社から死亡退職金や弔慰金などがある場合があります。
新しい会社ですと、制度自体がないことが多いです。
また、定年まで同じ会社に勤め上げる方は減っており、転職をする可能性がある場合は、会社からの保障は加味しない方が良い場合もあります。
退職金は、大企業や公務員であれば高額です。
とはいえ、これだけでは全然足りませんので、例えば、35歳の3人家族のご主人が亡くなったとして、本来あと30年働く予定で、生活費が30万円とした場合でも、遺族年金が月に10万円入るとしても、残りの20万円×30年×12ヵ月=7,200万円になります。(死亡退職金や諸々は割愛して単純化しています。)
ご主人が亡くなってしまって、小さなお子さんのいる奥さまが、主人がネットで保険に入ってくれていたと、内容をみてみたら、保険金(保障額)が500万円と知り、全然足りない…というケースが多いのではないかと想定します。某ネット生保のランディングページでは、保障額500万円で***円!という訴求をしています。
一般の方が、能動的に自身の必要保障額を算出して、最適な保険設計をし、自ら加入することがハードルが高すぎるので、プランナーという仕事が存在していると思います。
どんな保険設計が良いのか
かけ金が高すぎでも困るし、医療保険のみでも困るし、少額保険でも足りないし…
保険を自ら勉強して知識や経験を得るのも膨大な時間を要しますし、書店にもそれらに関する良書はほとんどありません。
やはりプロのプランナーに相談して設計をしてもらうのがベストです。
それでもご自身でやってみたい場合は、
日本FP協会などが提供しているキャッシュフロー表を入手して、自身の家族の数値を入力してみる。
必要保障額を算出する。
必要保障額を、終身保険などの積立のみで設計してみる。
定期保険などのカケステのみで設計してみる。
上記の間のバランスをとって、自身のアーリーデスやリブロングの両方を考えて、フローやストック、意向をふまえたプランを設計する。
死亡保障をメインに考えつつ、がん・医療保険などの保障も考慮する。
リブロングの場合の死亡保険金の非課税枠は確保できているかを確認。
各種生命保険料控除を確認。
生命保険、年金保険、医療保険でそれぞれ控除があります。
会社員の方ですと年末に会社に控除証明書を出していると思います。
確定申告時に出されている方もいます。
万が一の際にご家族を守れる保障額になっているか、保障がいつまで続くか、かけ金は途中から値上がりしないか、カケステ部分、積立部分の比率は自身にとって適正か、問題なく支払い続けられるかけ金か、払込終了時(例えば65歳)の総支払額、総解約返戻金、70、75、80…歳時の解約返戻金などをみていくと良いと思います。余力のある方は年払も検討することで、かけ金を数%おさえることができます。
上記の良しあしは、場数を踏んでいるプランナーが感覚をもっていますので、一般の方は、それが良いのかそうでないのかはわかりづらいと思います。これらを全て自身を行うとなると、結構大変です。
また、業界の外、中では情報量が圧倒的に違います。
ですので、一般の方で設計内容が自身に合っているか不安な方は、優秀なプランナー数人に相談をして、それぞれの設計をみてみたり、設計してもらったプランを別のプランナーに伝えて、セカンドオピニオンをとってみるのが良いと思います。
日本においては、これらのプランナーへの依頼は無料ですし、自分でやっても、プランナーに頼んでも、かけ金は変わらないのです。
一流のプランナー(プロ)であれば、あなたへのファクトファインディング(ディープヒアリング)をし、自身では気づけなかった潜在的な課題すら提起してくれるものです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
