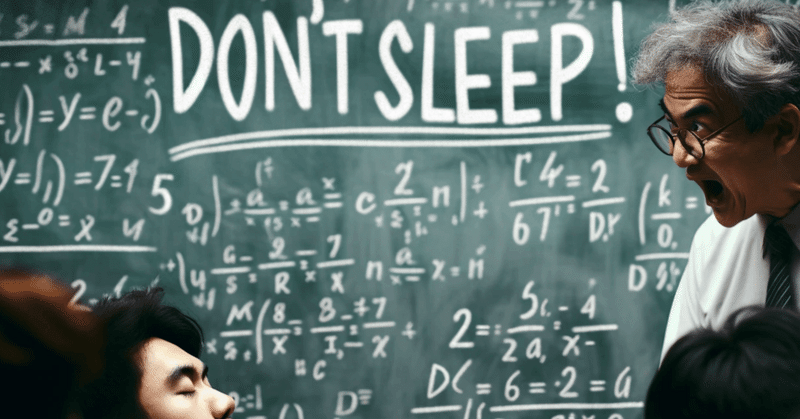
部活動問題(スポーツ業界と学校との緊張関係)②
前回の続きです。
部活動は学校の下部組織ですから、部活動で起きる問題は基本的に学校のせいだと思われるでしょうが、それは違う。スポーツ業界と学校とは100%結託しているのではなくある面では対立しているという話でした。
文科省が抑制しようとしても……
「最近の子どもって部活やりすぎじゃないか、学校に勉強じゃなくて部活しに登校しているようなとこあるけど、それって正規のカリキュラムが軽視されているんじゃないか」という問題があります。
部活動過熱化問題とでもいいましょうか。これも学校のせいではない。
学校サイドの親玉である文部科学省(とその傘下のスポーツ庁)は2018年に『運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン』というのを出して、「平日の活動時間を2時間程度、休養日を週2日以上設けること」といった基準を定めました。私立だろうが公立だろうがこれを目安に活動してねという方針です。
この方針を受けて、所属する自治体(たとえば中学ならば市区町村、高校ならば県)単位でも部活動抑制の具体的なガイドラインが出たところが多いと思います。
だから学校の運営サイドはトップダウンの形で活動時間も大会の日数や時期も学校生活に支障がないように管理しようとしています。土日に部活動やらない方が働き方改革の面でも都合がいいですしね。
ですが、失敗しています。このガイドラインは守られていません。
なぜ守られないのでしょう。
世間のイメージでは、「守っていないのは勝利至上主義に染まった私立の強豪校とかであって、学校が宣伝の名目で部活動やらせ過ぎているからだ」とか「部活動顧問と部員が一体となって情熱を注ぎ過ぎていて、バランス感覚が失われているからだ」みたいに思われているかもしれません。
それも100%の間違いではないんでしょうが、私の見る限りではちょっと違っています。
簡単にいえば、スポーツ業界側がこの方針をハナから守る気がなくてしかもそこそこ強い権力を握っているからだと思うんです。
教員は学校の職員であると同時に部活動顧問として担当のスポーツ業界側とも関係していますから、そのスポーツ業界側の意向が無視できないわけです。ですから雇い主であるはずの学校が「やめろ」といってもなかなかやめられない。
管理側が何を言おうと、実際に部活動をしているのは部活動顧問である教員と部員である生徒です。教員と生徒は学校の管理下であるはずなのに、実態として彼らはスポーツ業界側の管理下にもおかれているため、言うことをきかせられないわけです。
私の知る限りでは、この傾向は私立より公立の教員の方に強くあります。
公立は原則10年以内に異動があります。そのため学校の同僚とは最長でも10年の付き合いになります。ところが部活動を通じての顧問の知り合いとは長ければ30年の付き合いになります。
このため帰属意識が学校よりも部活動に生まれてしまいます。各競技の専門委員会なんて場所にいくとすぐにわかります。顧問同士はすごく仲が良い。それは長い時間をかけて関係を深めていったからです。
教員はある意味で学校と部活動、二つの組織に所属しているみたいなところがあります。学校が打ち出したガイドラインを素直にきけないのは、部活動の側で築き上げた立場がなくなってしまうからです。
部員=生徒の立場でみてもそうです。
スポーツ推薦ってありますよね。卒業後の進学とか就職でさえ、学校の流れではなくスポーツ業界の流れでしようとしていたら、彼らは学校の管理下にいる生徒である以上にスポーツ業界の管理下にいる競技者となります。
学校は「土日部活やるな」といっているがスポーツ業界は「土日も部活やれ」といっている。両者の訴えがずれていたら、部員=生徒はどちらの意向を優先させるでしょうか。
こういった背景があるからガイドラインは守られないのです。
スポーツ業界の手綱は握れない、その結果……
前回ちらりと触れましたが、厄介なことに、スポーツ業界は権力拡大にきわめて貪欲です。
政治家に積極的にロビイングします。政治家もスポーツ業界の票田は欲しいので結託します。こうして公金を用いた大会が開かれます。他にも後援とか大会名称に皇室の名前を借りるとか、様々な手法で自分たちの活動を権威付けし、影響力を高めようとします。
こうした動きにより権力が増大すると、学校側も手綱を握ることができなくなっています。とはいえ、文科省=教育委員会=学校側もこれらの権力を苦々しく思っています。私は両者の間に、政治家も巻き込んだそれなりの緊張関係があるものと推測しています。
「で、何が問題なの? 別に生徒も喜んで部活の大会出ているんだからいいじゃん」という開き直った意見もあるかもしれません。いやいやそう簡単ではない。
たとえば部活動で朝練も放課後練もやっているから授業中寝てばっかりいる生徒がいたとします。これはダメですよね。「課外」を優先させるあまり「課内」がおろそかになっている。
でもスポーツ業界側からみるとこれはダメではない。むしろその競技を一生懸命がんばっている姿とみなされかねない。
スポーツ業界は学校ではないから、プライオリティが違うのです。そうした考えの業界が権力を握ってしまうと、極端にいえば、〇〇部は午後の早い時間から部活動を行いたいので午後の授業を休んで部活しますとか、土日で部活動をたくさんやったので月曜は休ませますといったことだって言い出しかねない。
部活動は通常の教育活動(授業など)に極力、支障が出ないように行う。これって大前提だと思います。もちろん100%支障でないようにするのは不可能というのも承知しています。ですが、スポーツ業界がイニシアチブを握るとこの前提があっさりと崩されていくのです。
サッカーなんかも典型的ですね。昔の学校サッカーはトーナメント戦が主流でした。一発勝負なんで大会はたまにしかありません。(その分、練習試合とかたくさんしていましたが。)勉強と部活の両立もしやすかったわけです。
それが21世紀になってから徐々にリーグ戦に変わっていきました。高円宮杯が今の形式(ほぼ1年近くかけてリーグを戦う形)になったのは2011年だそうです。この形式になってからサッカー部はほぼ毎週土曜日試合という状況が続いています。
多くの学校が困りました。土曜日は授業しているからです。(土曜授業というと私立のイメージかもしれませんが公立でもたまに行っています。)
サッカー部の生徒は土曜日に行われる授業内容が抜けてしまいます。サッカー部の生徒の成績はガンガン下がっていきます。そりゃあ授業が歯抜け状態になったら理解度は下がりますから。このときは教員としてすごく複雑な気持ちになりました。
サッカーの業界団体はこういう懸念をどれくらい勘案したかのでしょうか。私はあんまり気にしなかっただろうと邪推しています。
こうしたケースをみるに、どうやらスポーツ業界は自主的な抑制を苦手としているようです。とにかくスポーツの機会確保とかいった名目、子どもたちはやりたがっているんだから抑えつけてはいけないといった言い分により、バランスを欠く形で大会や試合を増やしたがります。
コロナのときなんか「夜にお店開くな」とかって国が明確に抑制の方針を打ち出しているのに、スポーツ界隈はまあまあ無視してやってましたよね。その感覚のズレを東京五輪で目の当たりにした人も少なくないでしょう。(これは国の抑制方針が政策的に正しいかどうかとは別問題です。あくまでガバナンスの問題。)
バリバリ偏見入っていて申し訳ない。スポーツ業界にだってそうでない人もいるし、バランスを意識した団体もあるのでしょうが、全体としてそういう側面があるのは否定できないはずです。
話が逸れつつあるので戻します。
ここまで繰り返し述べた通り、学校はスポーツ業界の手綱が握れていません。そしてスポーツ業界はバランスを欠いた動きをします。それにより発生したのが部活動の過熱化です。世間がこれを学校のガバナンスの問題と捉えることに強い違和感があります。
進学校はどう躱しているか
この状況で、進学校はどうしているでしょうか。
進学校はなんといっても勉強させねばなりません。勉強優先の生活スタイルを維持するためにスポーツ業界とどうやって距離をおいているのでしょうか。
驚くべからず。一部の進学校では、この手の問題に煩わされるのを嫌うあまり、大会不参加とか団体未登録といった大胆な手段に出ています。
信じられないかもしれませんが、大会にまったくでないサッカー部とかバレー部、そういう部活がふつうにあります。これはこれで何のために練習しているのか意味がわからないですよね。スポーツそのものは楽しいことですが、一部競技では競い合わないと楽しくありません。学業を優先させるあまり、つまらないスポーツ経験になっているとしたら子どもがかわいそうだと思います。
(ちなみに進学校といっても公立と私立で違います。公立は部活動の位置づけに大差ありませんから、進学校であっても普通に大会に参加します。ここでいう進学校とは、首都圏にみられる私立中高一貫校のイメージですね。)
私も最初、試合に出ないのに練習をしている部活があると知ったときは驚きました。いくらなんでも極端だ。競技スポーツは大会があって初めてやる気がでるもんだ。手綱が握れないからってもう少しバランスよくやれないものかと感じました。
いっそのこと、今ある団体とは別に進学校が結託して進学校向けのスポーツ大会運営団体をつくってもいいかもしれません。
部活動は良いもの、なのに……
わりと部活叩きの論調になってしまったんで、最後に言い訳をさせてもらいます。
こんなふうに書いておいてなんですが、私自身は部活動の顧問として熱心に指導してきました。生徒が部活動というものに強い情熱を注いでいることは素晴らしいことだと思うし、なにより生徒が楽しんでいる姿をみるのはうれしいものです。部活動を通じて人間的に成長することも間違いなくあります。
つまり、一生懸命に競技スポーツに取り組むこと自体は教育的にも正しいことだと思っています。
ようは学校側とスポーツ業界側のガバナンスの問題です。それぞれでバランスとれるかということです。
スポーツ業界側がバランスとれない、是正しようとも学校側にその権力がない。学校が手綱を握れないのなら手放さざるをえないでしょう。悲しいことですが、それが私の結論です。
現状、部活動はあくまで学校の活動です。
学校というものが何の目的で存在するのか、その学校の管理下である活動はどういう制約を受けるのか。そこを踏まえて活動できるならいいわけです。でもそれができないのなら、部活動は最終的に学校から切り離すのが正解です。そういう意味でも地域移行すべきかもしれませんね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
