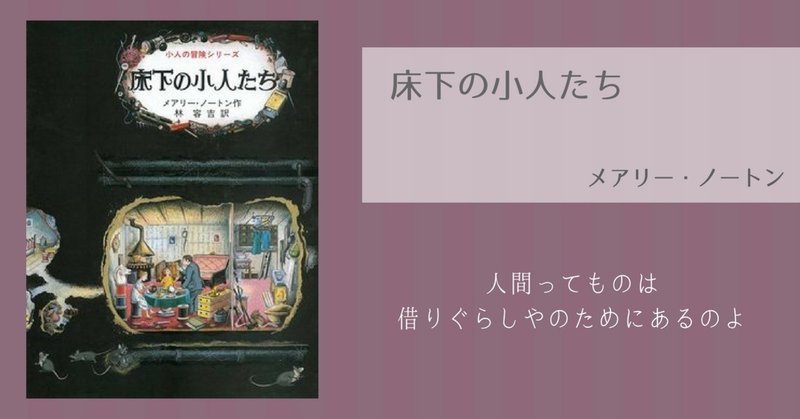
“借りる”の定義ってなんだろう/『床下の小人たち』メアリー・ノートン
金曜ロードショーに合わせてなのか、わたしもジブリ祭りをやっているような気がするこの頃です。
今日読んだのは『床下の小人たち』。
『借りぐらしのアリエッティ』の原作になった作品です。
他のジブリ作品と違って、何度も繰り返し観た!と言えるものではないのですが、音楽とシーンがちょっと斬新だなと印象的だったのと、人間社会で使っているものを小人から見た目線のそこサイズの比率の違いがすごく面白くてきゅんきゅんした記憶があります。
だから読んでいく中でもそういう描写がたくさんあるといいなあと思いながら扉を開きました。
アリエッティたちが住む家のなかにはわたしが期待していたのよりももっとわくわくするような「家具」がたくさんありました。切手が壁にかける絵画になったり、マッチ箱をタンスにしたり、指ぬきを鍋の代わりにしたり…。小人のお家ってこうでなくちゃ!とわくわくします。
ただ、読み進めていくなかでちょっとずつ違和感を感じるようになっていきました。
アリエッティはわらって、「まあ、おかしなこといわないでちょうだい!」といいました。「まさか、あなたの大きさの人が、たくさんいるとでも思ってるんじゃないでしょうね?」
これはなんだろうな、と読み進めていき、アリエッテイが少年と話すシーンで「あ、なるほど」と。
「あのね、」と男の子が聞きました。「≪わたしたちを養う≫って、どういうこと?」
「人間ってものは、借り暮らしのためにあるのよーーパンがバターのためっていうのと、おんなじよ!」
おお…。
“借りる”って言葉って自分のものではないという認識が大前提だと思うんですよね。
“借りる”ときたら、絶対的に“返す”じゃないですか。返すということは元々は自分のものではないからもういいですよ、となるじゃないですか。
人間たちが使うために存在しているものを、無理やり自分たちの主軸に合わせて使っているから“借りる”となる。のに。アリエッテイたちは人間たちの存在意義を小人たちにものを貸すためにあるのだと当たり前のように言うのです。
それって“盗む”こととは違うの?と少年は聞きます。でも、盗むというのは借りてきてアリエッティたちの家にあるものを別の小人が持っていくことをいうから、全然違うのよ、と本気で笑いながら反論されてしまいました。
世界は小人たちを中心に回っているのです。借りられた人間たちのことはお構いなしなのです。
なんて自己中心なんだ、と笑ってしまって。でも、ここで「あれ」と立ち止まってしまいました。
どうあっても、わたしは人間の目線からしか見れないから、わたしたちが作ったものを勝手に使っておいて、貸すために生きてるとまで言われてしまってそれはちょっと違うんじゃないかなって思いました。
うーん…。でも、わたしたちも生活するうえで何かを借りていることがあるのかもしれない。あまり専門的なことはわからないけど、例えば、海や山で採れる資源だったり、生き物だったり。わたしたちは借りているという認識ではなくて、それは「いただいている」というものかもしれないけど。
でも資源や生き物の気持ちになった場合、もしかしたら「勝手にもっていって勝手に使ってる」と思うかもしれないですよね。
でもわたしたちにとってそれは生きるために必要だし、“そういうものだから”と搾取しているのかもしれません。
それだったら小人たちにとってのわたしたちもそうなのかもしれないな、と。
たまたま小人たちとわたしたちの間で意識の共有が出来たから、それっておかしくない?と意義を唱えることが出来たのであって。
むちゃくちゃの違和感を感じて考えてこんでしまったけど、そういうものだと受け継がれているものを大きく変えることや違和感を感じることは難しいですよね、きっと。
ちなみに英語でのタイトルは『The Borrowers』で直訳すると「借りるものたち」。これは完全にわたしたち目線の称しかただなと思います。
人間はわたしたちのためにあると言っていたアリエッテイ一家ですが、人間に見られてしまうと住み続けることは出来ないと、最後は少年の家を旅立ちます。
物語はまだまだ続くし、このあともうまく暮らしていけるのか、わたしが読んだ第1巻では不安なことだらけですが、価値観の違いに気付けたことがとても面白かったので、続きも読んでみようと思いました。
もう少しふんわり楽しめる作品かと思っていたけれど、いろいろと考えさせられる部分があって児童書だなんて言ってほんとに侮れないなと思いました。たぶん小さい頃に読んでいたらここまで思うことはなかったのかも、そう思えるから児童書がだいすきです。
もっともっと新しい世界を知るために本を買いたいなあと思ってます。
