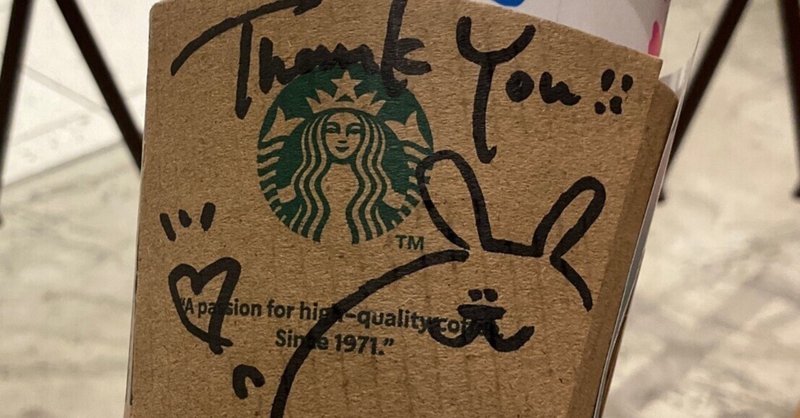
【ShortStore】お年玉どうする?
「アホか、誰が健康食品なんぞに」
私はハッと下宿の部屋で目を覚ました。誰かに言われた記憶がある言葉を夢の中で言われて、とても居心地が悪くなって、とても息苦しくなり、楽になるために起きてしまった。
今は何時かというと、日付で言えば、正月三が日も過ぎ、鏡開きだって終わった頃であるが、いまだに大学は冬休みが続いている頃でもあり、私としては早く大学の冬休みが終わってくれさえすれば大学に通えるので不満も多いものの暇ではない学校生活で時間潰しができるのだが、そんなことは未だ先の残念な1月半ば。
つい先日、成人の日があった。私は市区町村が主催するそのイベントに出て何の意味があるのか全く想像も理解も肯定もできない成人式には「時間の無駄。こんな事でエネルギーを消費するくらいなら下宿で勉強でもした方が幾分かマシだ」と言って参加せず、寒さに負けて下宿先で寝ていたのであるが、午後から学友に力づくで、アホな集まりに加えられるという苦行のために、雪降る街に引っ張り出されてしまったのだった。
あの日は特に寒かった。人が外を歩いていい気温ではなかった。後で聞いた話によると、大寒波がやってきており、南房総でも氷点下になったとか何とかで「こんな地球温暖化で騒がれている21世紀に、そんなことあってたまるか」と言う話だが、この辺りでも前日との気温差が5度もあったそうだ。
何度でも言う。人が外を歩いていい気温ではない。
そんな急に冷え込んだ日に文字通り連れ出されてしまったので、ペラペラの普段着に少し厚めの上着を着ているだけで全体図としてはもうそれはそれは本当にビックリするくらいに頼りのない薄着だったし、けして体が強くない私は見事に体調を崩し、今は下宿の自室でペラペラの布団にくるまって春を待つ熊のように静かにしていた。
「へきし!」
咳をしても独り。そのまま静かにして数日が経ったわけだが、根気よく家から出ない。むしろ布団から出ない、を体現し続けた私に問題は降りかかる。
そろそろ下宿に貯蓄している食料も底をつく頃合いだった。正月前に指が切れると思うくらいに買った食料が無くなりそうだった。冗談抜きで起き上がって買い出しに行かねばならない。そうしないと、私は布団にくるまったまま絶命してしまう。この下宿を訪ねてくる人すら年に何人かと言うレベルである上に、その数人が私を訪ねてくる確率はほぼゼロに等しい。
そうなると冗談ではなく、布団が包帯よろしくミイラと化した頃に見付けられ、この下宿、いや、通っている大学、はたまた住んでいる街の伝説となってしまう。私が事切れた時には虫の知らせとやらが両親に働いて、初めて下宿に来てくれるのだろうか。いや、そもそも来ないだろう。来いと言っても来なかった親だ。大学進学さえも反対して、学費すら一銭も出していない。そんな私を心配するだろうか?
思考が質問で止まってしまった。その質問に私が答えを持ち合わせているのだろうか。その謎を究明すべく、私は思考と言うアマゾンの奥へと向かうことにした。どうせ何もやることはない。寝て起きて寝るだけの生活である。いや、今は食料買い出しのミッションが待ち構えている事を思い出した。とても面倒臭いがそれは昼に行くとしよう。
起き上がり、机に広げられている小物達を全て腕で押して畳の床に落とし、紙とペンを手に取ってマインドマップの様に書き出してみた。
「まずは私」
まずは凡そ中央に丸く円を書いて中に「私の名前」を書き、線で引っ張って横に両親の名を書く。線の上に家族と書く。関係性はこれ以上も以下もない。
小さい頃は可愛がってくれていた様だが、大学進学の話を持ち出すと途端に家族の仲に亀裂が入った事にはビックリした。いや、噂には聞いていたが、亀裂が入る時に鳴ってはない音が聞こえてきたことにビックリして思わず笑いそうになったが両親と私の温度差が酷くて、驚いた顔のままで硬直することにして、両親の話を聞くことに集中したが、この両親の話がとても聞けたものではなかった。
私には3つ下の弟がいるのだが、その弟の進路にお金が掛かったので、私の大学進学へのお金などは工面できないと言い出した。文句があるなら弟に言えと。親の顔に迷いはなかった。
「知ったことか……」
私はすぐに話すことを辞めて両親の支援を諦めた。家族行事は全て断り、勉強とバイトの日々を過ごした。そして、必要書類も入学金や授業料も私が用意して第一志望の大学を合格して、今のこの下宿生活ということだった。
さっきの質問の答えは出てこない。紙をぐしゃぐしゃと丸め、来客用のガラスの灰皿に投げ入れて、マッチを擦って火を起こし、茫茫と広げるはずだった思考の広野をボウボウと燃やしてやった。
ボウボウと燃える紙を凄い顔で見ていると、もう半年は私以外の人間は触っていないドアを叩く音が聞こえる。幻聴だろうか。しかしこんなところ、しかもこの部屋に用事がある奴なんぞ居ない。碌な要件ではない。これは無視するに限る。
「居留守だ! 帰れ!」
私は呻いてまた布団に包まりなおして寝転んだが、聞こえていないのか、「居留守って居るじゃないですか。入りますよぉ」と小さい声が聞こえ、ドアノブをゴリゴリ回し始めた。居留守だと言っているだろう。
入らずに帰れ!
ここ数日は声を殆ど発していないことから、喉が弱っているらしく、思っていた大きさの声の大きさが出なかった。大学が始まるまでにこれは元に戻さないと教授に質問もできないし、食堂のおばちゃんに注文をいうことすらできない。
いや、食堂は食券なのだが、ご飯の追加や他の色々な要望を伝えるには声をあげるしかないのだ。そういえば、どうせなら、要望も食券でどうにかならないのだろうか。
声すらも貧弱の称号を得そうな私の制止を無視して、そいつはドアを開けて中にズカズカと入ってきた。
「こんばんわ。何してまんの」
学友である。彼は普段から眼鏡をかけていてなかなかの視力矯正らしくてレンズ内で意外にクリクリなお目目が小さくなっており、冬の普段のスタイルは襟付きのシャツの上からダウンジャケットを羽織り、マフラーをして耳当てをしていた。ズボンは基本的にジーパン。このクソ寒いのにズボンがジーパンである。
「バランスを考えろ、バランスを」と毎度言うが、学友は毎度「ファッションとは我慢なのです」とファッションを知った口を叩く。
そのくせしてアンバランスな格好や、ガチャガチャした色を好んで着こなしていたが、そこそこの人気があるらしく、講義が終わるやいつもどこかに誰かと消えるのだ。
そんな学友はファッションセンスが正反対の私と遊んだことなど数えるしかない。しかし、イベントがあるとこうやって下宿へ押しかけてきたり、大学内で私を拉致したりして事あるごとに行きたくもないと言っても行きたいと言ってもイベントに巻き込んできた。因みに私はそれで利益を得たことはなく、損もしたことはないので、学友がイベントごとに他の友人を無視して私を巻き込む理由が、本当に何のつもりなのかわからず困惑していた。
「見てわからんか、布団に包まって暖を取っているのだ」
私は布団からも出ずに顔だけを向けてそういったが、彼の姿を見ても今回は何をしにきたのかは想像もできない。お土産もお見舞いも持っていない学友は、そのまま布団の脇に座り込んだ。
「この部屋に半年振りの客人ですよ。さあ、お客さんが来たのでコーヒーでも出してください。寒い中に、暖房もついていないこんな下宿にきたんですから」
「ずーずーしい。出すか、アホ。そこに座ってろ」
そうだ、確かにあったな。コーヒー。
私はかすかな記憶を思い出して、ガサガサと残り少なくなってすっかり萎んでしまってゴミ袋と間違えても仕方がないクシャクシャの買い物袋を探ると、コーヒーの粉が出て来た。スティックタイプで使いやすいタイプである。
「湯、湯を沸かそう。ヤカンはどこだったかな」
「すっかりおじいさんですね」
「うるさいぞ」
火を入れたヤカンで湯を沸くまで、2人は無言を貫いた。そういえば体調を崩して布団にくるまっていることしかできなくなった理由って、こいつのせいだったな。私はコーヒーに毒でも盛ってやろうかと思ったが、あいにく、この下宿に毒などはなかった。
◇
「つまりなんだ、その健康食品会社の頂上流階級におられる令嬢が何故かたまたまウチの大学にいて、お前はその娘を狙っていると」
「はい、そうです」
「パーティーがあるから私同席で参加して、私が引き立て役なんだか恋のキューピットだかになれ、と」
「お察しが良いです。その通りです。貴方みたいなファッションに無頓着で話すこともあまり令嬢寄りではない人がいれば、僕は輝いて見えますから。こんな立派な作戦はありません」
「やかまし!」
つまらん! とも言いつつコーヒーを啜り、買い置きしていた贈答用の少し大きめで甘めに作られているカステラをフォークで一口サイズに切って口に放り込んだ。今日初めての食事だ。ここもとの食事はほぼ1食で賄われていた。といっても外にも出ないし、何をするわけでもないので、ガッツリとご飯を食べるほどに空腹になることはない。しかし不思議なもので寝て起きてグータラしているだけなのだが腹は減る。生きているだけで維持費がかかってしまう。
それはそうと、学友の持ってきた話には全く惹かれるものがなかった。
どうしてこのクソ寒い中で動く気も起きない為にダラダラと過ごしているというのにも関わらず、外に出て他人のパーティーとやらに出席しないといけないのだ。しかも他人の頼みで。
「そんな事をして私にどんなメリットがあるというのだ」
「シャンプーのメリットを買ってあげますよ」
「誰が駄洒落でボケろと言った!」
「あはは、ボケたのわかるって貴方もおじさんですね」
「メリットなんていらんぞ」
「もらえるものは黙ってもらっておいた方がいいですよ」
「何を隠そう私はビダルダスーンを使っている。見ろこのサラサラ具合を」
そう言いつつ、サラサラ具合の表現の為に何日も洗っていないのでドロドロガシガシの髪の毛に指を突っ込んだが当然指通りなど壊滅的なので突っ込んだままの位置から流せず、諦めて指を髪の毛から引き抜いて続けた。
一方、カステラを手掴みで食べて私が淹れたコーヒーで胃に流し込んだ学友。一体、どんな本心でここに来たのかは未だにわからない。
「今更メリットに置き換えられるか」
「まぁ数日お風呂に入っていない貴方のシャンプー事情は興味ありません」
「しかし、前提がおかしいだろうが」
「おかしいとはどういうことでしょうか?」
「誰が好き好んでいくとでも思ってるんだ」
「そういえば言い忘れていましたが、その令嬢、今年の親からのお年玉でスポーツカー買ったらしいですよ」
「早く言え!」
私は勢いよく立ち上がり、布団が絡まってコーヒーの入ったカップを薙ぎ倒した。
「早く準備するぞ!」
「ちょろいな」
◇
私がこのスーツを着るのもいつぶりだろうか。黒の上下でネクタイも黒。そう、葬式以来着ていない。
その葬式は私的には一種の面白話として度々酒の席でも披露している。
ーーあの葬式も冬であった。雪が横から殴りつける午前中に電話一本で呼び出され、あったこともない親戚が亡くなったということで遥々電車やバスを乗って港町まで行ったものだ。 地元ではそこそこの知名度を誇る人だったらしく、親族だけで集まっていると聞いていたのに、着いた頃には地元の人たちも集まって小さな会場に収まりきらない感じだった。私はさっさと焼香をあげて帰ろうとしたが、それは両親が許さなかった。あれは遺産目当てだろうな、と思っていたがそれは見事的中し、通夜で親族が眠たい目を擦っている時に両親は金の話を切り出し、何も交通の便がない深夜2時に家族全員が式場を追い出されたという話。
今となっては両親が死んだ時には葬式で暴露してやろうと思える面白話がある。当時はクソ具合に腹を立てたが、今となっては当然だろうな、と謎の納得がある。
山の上にある豪華なお宅について、私の立ちくらみで動けない時間があったり、着替えに手間取ったり、バスの運転手が腹痛だかなんだかで出発が遅れたおかげで30分ほど近く遅刻してしまったのだが、チャイムを鳴らすと怒られることはなく、老人の声で入るように催促され、入れてからの経路を寒い外で聞かされて、玄関から誰も迎えに来ず、言われたルートをたどって言われたドアの大部屋に突撃したが、そこには何十人という先客がいた。
学友と一緒にきたのだが、これだけの人数がいるとなると令嬢としっぽり話して仲を深めるなんて到底難しい話ではないかと不安になった。
コートを着ずにすっかり冷え切ってしまった私は改めて風邪などを引きたくはなかったのでやめてやめてとうるさい学友を引っ張って、恥を忍んで女学生たちを押し退けて暖炉前を陣取って温まることにした。どうしてコートを着てこなかったのか。スーツを着たまま羽織れるコートなどという高貴なものは持っていない。それだけである。むしろ貧乏学生だがスーツを持っていることについて褒めて欲しいレベルであった。まぁ少し待てば何かが始まるだろうと思い、招待客を見ながら学友と話をして時間を潰すことにした。
学友と時間潰しの雑談を始めて30分も経った、集合時間から1時間経った後、通された大きな部屋に付いているスピーカーに雑音が鳴り、麗しい声が聞こえてきた。これは令嬢の声だ。令嬢はたびたび大学のイベントでスピーチをしていたことや、大学のYouTubeに出ていて、それをもれなく見ていた私には聞き間違えることもなく、すぐにわかった。みずみずしい感じの通った声である。私の下宿先の大家の掠れた壊れかけのラジオから聞こえてくる昔の番組のMCのような声ではない。
『皆さん、こんばんわ』
「「こんばんわ」」
「こん・・・ばんわ・・・」
ぽつりぽつりと集められた男女が挨拶し返す。しかし、この部屋についているスピーカーにはマイクの機能がついているのだろうか。そうでなければ滑稽である。見渡しても特にカメラもマイクらしいものは付いておらず、恐らく令嬢には我々のビビり散らかしたとても小さい声は届いていないだろう。
『本日は私が主催するパーティーにご参加ありがとう』
「こちらこそ・・・」
「どこにいるんですか・・・?」
ぽつりぽつりと集められた男女が返事するが、その返事に対する返答はない。何故ならこの部屋についているスピーカーにはマイクなんて付いていない以下略。
すると突然部屋の明かりが消えた。ざわざわし出したが、すぐに目の前の壁が急に光った。プロジェクターで壁に何か映し出されたらしい。口々に令嬢の名前を呼んでいた。私は無言で映し出されていた令嬢を舐めるように見ていた。令嬢がベッドの上で座っており、こちらに何とも言えない表情をしていた見入っていたという表現が正しい。なんだ、舐めるように見ていたというのは。不適切な表現である。それはそうと、令嬢は色っぽかった。何がなんでどのように色っぽいのかというのはわからないが、なんだか色っぽい。色々なことを妄想してしまい、ぼーっとしてきた。
カメラのレンズをじっと見たり、その右端を見たりしたりしていて、何かを確認しているらしいことはわかった。何を見ているのだろうか。カンペならケータイを見ればいいだろう。
映し出されてから数分は何も喋らず、男女が敷き詰められた部屋はザワザワしっぱなしであった。今から何が始まるんだ、何なんだと。不安が不安を呼ぶ。むしろ私は映像を出力したことでスピーカーかマイクの電源が落ちた説を唱えていた。
「学友よ、マイクがオフってないか、あれ。な? 学友?」
そういえば学友はどこに消えたのだろうか。さっきまでは私の隣で話をしていたし、恐らく、この中には私以外に知り合いは居ないだろう。
もし知り合いがいたらその話が出てきているだろうし、この部屋に通された際にあいさつくらいは行っているだろうから。その私に断りもなくどこかに消えた。オロオロとしてしまった。見知らぬ場所で、唯一の知り合いである学友が神隠しにあったのだ。オロオロするしかない。
突然見えなくなった学友の心配ができる程度に落ちついた頃、ついに令嬢が口を開け、喋り出した。
『突然ですが、私をこの部屋から出したら勝ち。付き合います。私をどこにいるのか探して連れ出してください。そうしたら付き合いましょう。この前、車を買ったので一緒にドライブでもいいじゃないですか?』
令嬢はそういうとベッドに転がり、足の爪にヤスリをかけ始めた。そこで映像は途切れ、部屋は明るくなった。
残された面々は各々の身だしなみを整え始めた。とてもとてもわかりやすく。この令嬢と付き合うとなると、バックは健康食品会社が付いてくるのと同じであり、いわば逆玉! お年玉など、さっき配られた数倍、いや数千倍にもなるだろう。私は頭を抱えた。あまりに急にやってきた人生の転機に、簡単なはずの掛け算が困難になっていたのだ。
しかし消えた学友はそのまま姿が見えないままだった。
◇
全く見つからない。隣と隣の部屋も見たが、令嬢の姿はどこにもいなかった。もしかしたらこの別荘にはいないのかという憶測さえ浮かんで来る。
私には隠されたミッションもあった。それは学友である。ここに来て映像が流れたタイミングで神隠しにあった学友も探し出さないといけなかった。しかし、同じく全く見つかる感じがしなかった。
私はとりあえず学友の電話番号に電話することにした。
すると聞き覚えのある、スマフォの着信音が流れている。耳をすませば、位置がわかるかと思ったが音が反響して場所の特定が難しかった。
もうこうなったら部屋のドアを全て開けていくのがいいと思い、手当たり次第、ドアというドアを開けて行くことにしたが、この家にはどれだけの部屋があるのか。私は住居ににつかわない数のドアに疲れが出てきた。その疲れは顔に出てしまった。
着信は鳴り続けるかと思ったが、向こうから電話は切られてしまった。これではヒントも無くなってしまった。いやいや、そもそも、音が反響してしまってヒントもへったくりもなかったが。
それより早くドアを開けて令嬢を探さなければならない。私は他の面々を思い切り振り払ってドアを開け進めた。そして結局は全ての部屋のドアを開けたが、どこにも学友や令嬢すらいなかった。もうお手上げである。
「どこにも誰もいないぞ! ふざけてる!」
そうして何人かが元の部屋に戻ったり、そもそもこの別荘から消えていった。
私はその中でも諦めることはしなかった。これはもう、そういうことなのだ。別の部屋があって、そこにいるわけで、そのドアを見つければいいというだけの話である。ただし、それが単に見えるところにあるドアではないということだった。
私はミステリー研究会のサークルに入っていたことで得た知識を駆使して、少し考えることにした。
◇
ミステリー研究会を選んだ理由は大した理由ではなかった。ただの浮かれから、袋に入ったおみくじを拾う要領で選んだ感じだった。高校の頃はクラブ活動もせず、非活動的な男たちとくすぶっているばかりだったがしかし、今や私はピカピカの大学一回生である。
非活動的な男たちがいう「幻のキャンパスライフ」への扉が、今ここに無数に開かれているのを目の当たりにし興奮半ばも朦朧としていた。
そんな私に話しかけてくる奴がいた。それが学友となる男だった。
「よかったらミステリー研究会なんてどうですか? 掛け持ちオッケーですよ」
黒髪の乙女達と爽やかに謎めいたミステリー小説などを語り合い、恋の言葉のラリーを打ち合うのだ。
そう考えていた私は手の施し用のないアホだった。
◇
こういう場合に考えられるのは、すでにあった部屋に隠し部屋のヒントやルートがあるというのがセオリーである。
しかし全ての部屋を今から捜索するとなると手間も時間もかかるので、全く現実的ではない話だった。じゃあどうすれば問題がないのだろうか。端的に必要なことを考えよう。
イライラした私は花瓶を投げつけた。すると、花瓶が当たって砕けた。割れて当然だ。それよりも奇妙だったのは壁が少し動いたことが気になった。
まさかと思い、私はその壁を押してみると動き出したのだ。壁は壁ではなく、隠しドアだったのだ!
そのドアを開けると地下へと続く道があり、私はそれを駆け降りていった。すると、地下には1つのドアがあり、私はそのドアを蹴り破った。もう丁寧に開けている気もサラサラ無いほどイライラしていた。我慢のげんかいである。
ドアを蹴破ったその部屋には学友がいた。ティーカップを持っており、いかにもお茶を楽しんでいる風だった。その壁側は扉になっていて扉は開いていた。その先に見えたのは、先ほど映像で見ていた部屋、そう、令嬢がベッドで寝転んでいる部屋だったのだ。
私は驚きと焦りなどが交わって、独特の表情をしていたと思う。しかし、そこまで気にしている場合ではなかった。理解することが先だ、この現状を。尋問するしかない。
「おい学友よ、なぜにここいるんだ」
「あらら見つかっちゃった。実は、僕もゲームの主催者側だったのですよ」
「は?」
「ゲームセットです、おめでとうございます」
「おいおい学友のお前が言うことを信じられるか。私はその令嬢を連れて下山するぞ」
「いや、その」
「ねえ、どういうこと?」
「ちゃんと説明するから。理解してくれない人じゃないから」
「どういうことだ。説明できないならこのまま令嬢を連れて下山するぞ」
学友の顔は歪んでいた。もはや誰の心配をしているのかすらわからないくらいに。その向こう側では有象無象が目を光らせて、我先に、いや次は俺が、と唸るような声で順番を勝ち取るべく争っていた。
「僕は令嬢と付き合ってるんです」
私は理解が追いつかなかった。
「本当なのか? それは、最初からこれに誘き出すために?」
「そうです」
「理解ができんな」
「面白いことをしたいじゃないですか。ただずっとあの下宿に立てこもっていても何もなりませんよ。これは貴方へのお年玉というわけです」
「アホか。令嬢は何も言っていないぞ。お前が勝手に言っている狂言でしかないな。このゲームを成功させて私は令嬢と付き合うぞ」
「そこに僕はいますかね」
「嘘をつくようなアホとは付き合い切れないな」
「僕と、その健康食品と、どっちを取るのですか!」
「なーーにを訳のわからんことを言っとるのだ。お前と連んでいてもお年玉なんてもらえないだろうが! この世は金次第じゃ、アホめ!」
「アホは貴方です! 今なら未だ引き返せます!」
そんな学友の言葉を無視して、私はむさ苦しい男達が敷き詰められている部屋を飛び出して隣の部屋に駆け込み、足を手入れしていた彼女の手を取って会場となっている別荘とやらを後にした。
後日談ではあるが、必死に私を引き止めようとした学友の姿は、あの後、街の中でも大学校内でも見かけることはなかった。ただ、活躍はしているらしく、彼の名前は時々耳にした。
◇
私は息も切れ切れに、必死で令嬢の手を引いて山を降りた。
途中で点在する電車の駅やバスの停留所には、令嬢を連れ戻そうとする奴らの影がちらついており、朝を迎えるまでそこで時間を待つと言うことは許されなかった。
だから仕方ないのだ。公道から外れた土の上を走らないといけないのだ。野薔薇がありそうな道だろうが、石が剥き出しの道だろうが、私は彼女と一緒になる為に、多額のお年玉の為に、これからの薔薇色の生活の為に彼女と一緒に下山して、彼女の家に送り届けないといけないのだ。
使命感で燃えたぎる私。
しかしあとどれくらい走れば街へ着くのだろうか。私は不安になる。体感は既に1時間は経っているが私が住む下宿がある街の明かりは遠いところにある。普段から運動をしていないことや、ましてや山登りなどする訳もなく、そろそろ体力も限界も変えそうな頃合いであるので、さっさと街まで降りて人に紛れて楽がしたかった。それは令嬢も同じだろう。どれだけ令嬢と言われていてもこんな山道をこの速度で駆け下りたこともないだろう。
「痛い」
令嬢はポツリと呟き、ぎゅっと握っていた私の手を振り解いた。
「痛い。もう嫌だ。意味不明。私はこんなことになるなんて聞いてない!」
そう言って俯いた令嬢は私の顔も姿も見ることなく、一目散に公道へ降りて行き、徘徊する取り巻き達に保護された。さっきまで意気込んでいた私は呆気に取られてしまい、完全に気力そのものが消失してしまい、令嬢を連れ戻すこともしようとせず、その様子を見ることしかできなかった。残ったのは令嬢のつけていた手袋の温もりと不可思議な言葉だけだ。
こんなことになるなんて聞いていない? 何か、何かがおかしい。私が気づいた頃には遅かった。
◇
私がクタクタになって下宿に戻った頃、下宿は真っ黒になっていた。いや、まぁ、元々からそんな華やかな下宿ではなかったので、真っ黒なことはよくある話だったので長年住んでいる私は慣れていたが、そんな慣れた私でも「暗い」と思えるくらいに真っ黒だった。
一体何があるんだろうかと考える気力もなく、私は下宿の玄関を進んで、自室に籠った。
私は知るタイミングが無かったのだが、この日の午後に下宿に住んでいる面々は全員引っ越ししたのだった。これはその日中にそこの近くの土地を管理している不動産屋の意向で下宿の取り壊しが決定したからである。
◇
大学が再開して私は待ちきれなかった気持ちを爆発させたように走って登校したのだが、私が仲良くしていた面々は私の顔を見ると何も話さずに遠ざかっていった。この理由も話かけても何も返事をしてくれもしなくなった友人たちしかいなくなったので、私は知る由もなかった。
親からの連絡が来なくなってどれだけ経ったのだろうか。私は周りの人たちとの関わりがなくなり、そうすると、すがるものは親となってしまうが、それも私には無駄な話だった。大学に入学してから正月に実家に帰ると誰もいないし、何が残っているのだろうか、この私には。
気がつけば私と親しくする人間は誰も居なくなった。大学にも、下宿先にも、この街にも、親も。
もうどこに居ても居心地が悪い。早くこんな街から抜け出したかった。
夢であってくれとも思ったかもしれないが、これが夢だとは思えなかったので、実際に思ってもいないだろうし、ましてや口にも出さなかった。口に出しても誰にも聞かれることはない。この下宿先には私しか居ない。もう誰も居ない。
私はその意味の不明な、でも、舐めると喉の調子が良くなるとの口コミがネットで囁かれている、よくわからない成分が含まれた天然成分99.9%の飴を、袋から取り出して舐めたら咽せた。その反動で空気を大きく吸い込んだところ、飴玉も喉に吸い込まれてしまい、私は呼吸ができなくなってしまった。
また咳き込む為に力を入れるが無駄で、全く咳も出なかった。
私はそのまま布団に倒れ込み、視界が悪くなる一方で使い込まれた敷布団を眺めながら悪態をつくように、変わり果ててしまった下宿の部屋の中で、一人寂しくこう言った。
「アホか、誰が健康食品なんぞに」
ーーFin…?
【あとがき】
今回も以前にもお世話になりました、そよかぜさんの短編小説に乗っかって話を書いてみました。以前は旅行の話でしたが、今回は時事ネタでもある、お年玉というネタにしました。
寝れないから時間つぶし半分にパパッと書いたものになりますが、いかがでしたでしょうか。
垂れ流しにして観ていた「四畳半神話大系」の映画の影響をふんだんに受けて、終わって読み返してみたら、設定から何から殆どお借りしちゃいました。
主人公の名前は出さずに「私」で統一してしまったこと、学友は何かしらで絡んできて、実は学友が令嬢と付き合っていたというところなどです。途中に出てくる別荘は、森見さんが出された「新釈走れメロス」の中で出てくる怪談の話で集められた家が舞台だったりします。
小説は「起承転結」を使って書くことが多いのですが、今回は「起承転々」と主人公は転がり落ちて終わってしまいました。
過去にここまで転がり落ちて終わる物語を書いたことがなかったので、読み返した時には違和感に襲われました。
これ、勢いで書いたけど、最後の最後まで書ききってないことにも、違和感の上塗りという感じでした。でも、不完全燃焼ではありません。謎の満足感があります。笑
最後には主人公がどうなったかは読者の皆様の想像にお任せするとします。そこまで結論づけてしまうと面白くないと思いますので。
話は変わりますが、「お年玉」っていいですよね。
何もしてなくても、親族からもらえるお金なので、不労所得そのものなのですが、この有り難みは、小さい頃は当たり前なので知る由もないです。もっと有り難く受け取っておけばよかったと後悔しています。
ぜひお年玉ください。それはもう仰々しく有り難くお礼を何度も言いながら両手で丁寧に受け取ります。笑
Fin.
サポート頂きましたら、記事作成に活用させて頂きます!
