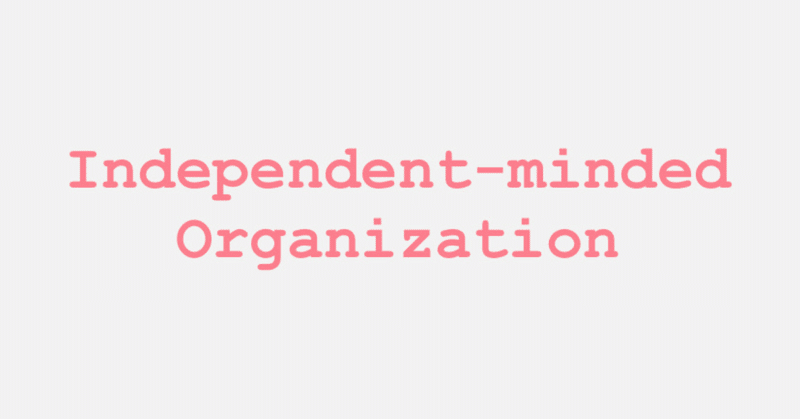
主体性のある組織の作り方
ことしもまたごいっしょに九億四千万キロメートルの宇宙旅行をいたしましょう。これは地球が太陽のまわりを一周する距離です。速度は秒速二十九・七キロメートル。マッハ九十三。安全です。他の乗客たちがごたごたをおこさないよう祈りましょう。
世界中のすべての人が上の文章のような考えを共有することができれば、世界から争いごとは無くなるのかな。
と思う一方で、
ごたごたをおこさないように祈ってるだけじゃダメだよなと思う自分もいる。
ごたごたをおこさないように考え行動しないといけないよな、と。
1年間学生団体で活動してきて、「全員が全員意思決定にかかわる必要はない」と思う一方で、「全員が主体性をもっている組織は強い」と思う。
十分な情報や判断力を持っていない人が組織の意思決定にかかわると、組織としていい判断は下せない。
しかし組織の構成メンバー全員が主体性をもって、心理的安全性を高める言動を心がけたり、組織のあり方や制度に疑問を投げかけたりするといった、細かな努力は必要だと考える。
ではどのようにして主体性をもったメンバーを増やすのか。
その話をする上でまずは、人材についての基本的な考え方について話したい。
人材の基本はMAKEかBUYである。
MAKEとは長期雇用を前提とした内部育成であり、BUYとは外部調達である。
企業に当てはめると、MAKEとは新卒または中途で採用した従業員を長期的に育成していくことであり、BUYとは初めからスキルのある人を中途で採用することである。
さて主体性の話に戻ると、主体性のあるメンバーを増やすためにはMAKEとBUYを効果的に行う必要がある。
BUYに関しては、採用要件に「主体性」という項目を設ければ良い。
主体性の有無を見極めるために、最もわかりやすい判断材料は「複数回のリーダー経験があるか否か」である。よほどのお人好しでない限り、さまざまな環境でリーダーを務めている人は主体性が高い。また、リーダー経験があまりない人でも、あらゆる環境で自ら課題を見つけその解決のために動いてきた人は主体性が高い。
これらの経験をファクトベースで聞いていき、候補者の主体性が気まぐれで発生するものではなくあらゆる環境で発揮されるものなのかを見極める必要がある。
MAKEに関しては、まず自身の行動が自身の利害に直接影響を与える構造を作り、その構造を認識させる必要がある。
どんなに利他的な人でも、その利他的行動によって自身が嬉しい気持ちになりたいという利己的な動機があるとするならば、ほぼすべての人は利己的な動機を持っていると言える。
自身の行動が自身の利害に直結する構造を作るとは具体的には、待遇の決定要因となる評価基準の精度を高めたり、組織環境や業績を高めようとする行動を評価する仕組みを作ったりすることである。
ここで重要なのがあくまでも「〜しようとする行動」であれば評価することが必要だと思う。つまり必ずしもその行動の結果として組織環境や業績を高められていないとしても、その行動を起こした主体性や勇気を評価する風土が重要だと思うのだ。
その上で必要なものとして、自由に動ける環境や雰囲気を整えることである。
いくら主体性をもっている人でも、自由に動けない環境では主体的に行動を起こすことはできない。
「すべてのメンバーが自分で考えそれを行動に起こすこと」を奨励する風土が必要なのだ。
それを実現するためには、組織の中の小組織のリーダーがそのロールモデルとして、メンバーの主体的な行動に対して賞賛をおくる必要がある。
以上がMAKEとBUYに分けた、組織の主体性を上げるための方法だと考える。
ここまで語っていながら僕自身はあまりリーダーをやりたいとは考えていないが、学生団体でリーダーを経験した上での学びを書き留めておきたくて、つらつらと綴った次第です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
