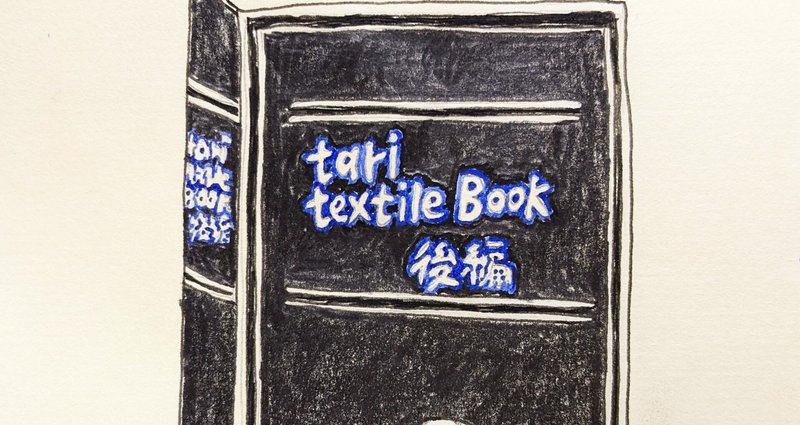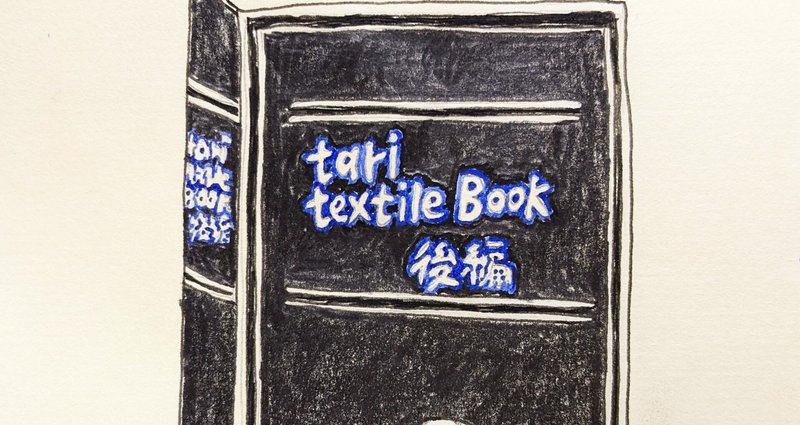tari textile BOOK 後編 #0「専修生」
「専修生」2018年4月~2020年3月
丹波布伝承館長期教室は、先の二年間の「伝習生」が終わると、希望者は「専修生」に進むことができる。専修生は、課題(年間で着尺3反分)を各自のペースで制作し、提出してチェックを受ける。糸紡ぎ作業のみ自宅で行うことが許可され、他の作業は曜日・時間関係なく伝承館の開館している時であればいつでも、道具と部屋の予約を取り、伝承館で行うことができるようになる。伝習生が大学学部生としたら専修生は大学院生といった感じ。伝習生を修了しただけではまだひ