
情熱の放射 澤田宏重と澤田塾(抄)
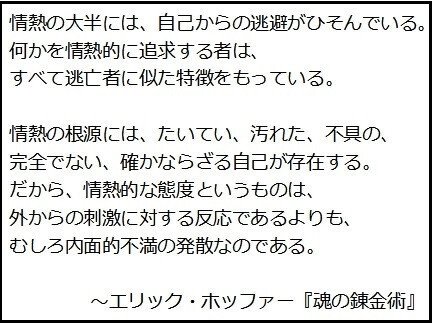
【000】
澤田宏重が主宰した進学塾である澤田塾は、三田の慶応義塾大学の北側にあった。慶大図書館裏の崖下の寺院の敷地内にみずほ会館というモルタルづくり二階建ての建物があり、澤田塾はそこにあった。
みずほ会館には、40人ほどが会合し会議できる部屋が数室あり、澤田塾以外にも会合や会議での利用者もいたが、ほぼ澤田塾の教室となっており、平日は夕方から、土日は昼過ぎから、小学校5年生から高校1年生までの塾生たちが盛んに出入りし、澤田はじめ講師たちの授業する声が響いていた。
特に澤田自身のハリのある声は、他の教室にまで届くことも多くあり、その声によりみずほ会館そのものが澤田の身体のように活気に溢れるのだった。
澤田塾は、正式名称は白光学院と言ったが、澤田塾という名称のほうが有名だった。小学校5年生から高校1年生までを対象にした学習塾で、中学1年生からは入塾試験があり、合格すると試験成績の結果によりクラス分けがされていた。
小学生対象では、主に中学受験を目指す生徒を塾生にしていたが、1クラス40~50人ほどで、港区の三田の周辺、浜松町、新橋あたりの小学校の生徒が通っていた。小学校5年生は、土曜日の週1回の授業で、地理と歴史を、小学校6年生は、土曜日と日曜日の週2回になり、中学受験科目である、算数と国語が加わった。
小学校5年生のクラスは、日本地理から始まった。毎回授業冒頭で、前週の授業の筆記試験が行われた。教わった内容を確実に理解し記憶し身につけてゆかないと毎週おこなわれる試験の成績は悪くなり、だんだんと授業についてゆけなくなりやめることになった。生徒が自分自身で学習能力を意識的に高める努力をせねばならない厳しさはあったが、生徒たちは学校とは違う勉強を経験できたり、新しい友人ができたりで、まだ、のんびりした雰囲気があった。
ところが、小学校6年生になると中学受験を間近に控え、また、遠方から通ってくる生徒も加わり、中学受験に対する緊張感が教室に漂い出すのだった。
【001】
1966年の春、小学校6年生になったばかりの塾生たちへの授業での出来事だった。
冬の寒さと春の温かさが同居してるような天候が続き、教室の窓から仰ぎ見る慶応図書館の屋根の上にはどんよりとした曇り空があった。
澤田が、いつものように力強いリズムで授業を進め、次の展開のためにそれまで黒板一杯にチョークで書かれていた文字を無駄な時間を1秒でも惜しむかのような勢いで消していたその最中、黒板に向いていた澤田の顔が急に教室の方へ向けられ、教室の最前列に座っている女の子たちに、ことばが投げ掛けられた。
「おい、今日はいつものきみたちらしくなく、何かさえない様子だけど、どうした!?」
「!?・・・」
黒板を消す澤田の動きは止まらず、黒板一杯に書かれていた文字がどんどん消されてゆく。
「いつも僕の授業をハキハキと聴いているきみたちが、今日はぼぅっとしているように見えたので、聞いてみたんだ。」早口で手を動かしたまま、さらに、「で、どうした?」とたたみ込んだ。
澤田の授業では前の方の席には、勉強に対する熱意だけでなく、それなりの学力を自他共に認めたものでしか座れない雰囲気ができていた。
澤田が声をかけた、黒板に向かって右側の最前列の席は、特に、いわゆる勉強のできる女子たちで占められていた。
澤田に視線を向けられていた女子のひとりがおずおずとしゃべりだした。
「先生、来年の中学受験に向けてこれから1年間勉強してゆくのだと思うと、もう受験終わるまで遊べないし、楽しいこともないし・・・そんなことを考えていると、もう、元気なくなって、いろんなことが詰まらなくなっちゃってるんです。」
彼女たちの真意を汲むべく、じっと耳を傾けていた澤田は、その発言を聞くと、「なぁ~んだ」と彼女に集中していた緊張感を一気にゆるませ、楽しそうな笑い顔になっていた。
女子の発言したことは、その教室にいた塾生たちはみな思っていることだったので、よくぞ言ってくれたという思いと、それに対して澤田がどんな納得のゆく回答を真面目にしてくれるのかと息を呑んでいたら、澤田が、快活に笑い出したので、塾生たちは、あっけに取られていた。
「なぁ~んだ、そんなことかぁ・・・そうだな、きみたちは、まだ、若いもんな」
小学生相手に、「若い」ということばは奇妙だったが、そこには、小学生相手とはいえ、学ぼうとするものに対しては年齢に関係なく敬意をはらう澤田の心情もあらわれていた。
黒板消しがひと段落すると、澤田は、教室を見回して、あらためて語りかけた。
「ひとつ言えることは、人間っていうのは、どんな苦しい状況でも、楽しみを見つけるということだよ。」
教室の中に、このことばに反応できている塾生はいなかったのだろう。
「よぉ~し、僕の話をひとつしようか。勉強はひと休みだ。」
澤田は、生徒たちに体をむけると一呼吸して続けた。
「僕は、戦争に行ってたんだ。学徒出陣っていうのでね。きみたちも、学徒出陣という言葉ぐらいは、知っているだろう。大学生の時に戦争に行かされたんだ。」
【002】
澤田宏重は、大正12年(1923)愛媛県北宇和郡来村(くのむら)、現宇和島市に二男二女の末っ子として生まれた。父は、来村、九島村で、千軒余りの檀家を持つ来応寺(臨済宗妙心寺派)というその地方では一番大きく裕福な寺の住職だった。小僧さんが3~4人おり、女中さんや寺男が家族とともに夕食を囲んだ。
澤田の記憶によれば、「父は真面目一徹、母は才気強く、気性の激しい女性」(*)だった。
7歳になり、村立の小学校へ入学し、10歳の時に宇和島市立明倫小学校へ転校した。
澤田本人の述懐によれば、小学校5年生にして、「勝ち気で意地っ張りで負けず嫌いで、言い出したことは少々のことでは、我を曲げない」(*)性格だったらしい。学校から帰ると日暮れまで山や川で遊び回り、家に帰ると母親に叱られて勉強するという日々だった。
小学校6年生の時に、中学の受験勉強をはじめ、毎日頭が良くなるような感じを覚え、勉強する楽しさを覚えた。
13歳で、県立宇和島中学(旧制)へ進んだ。当時の旧制中学への進学率は10%前後と言われている。
生来活発だった澤田は、中1の時から弁論部に入部した。中2中3で図書部員となり、政治家や偉人の本を読みまくっていた。中3の時に、柔道で初段を取った。
昼は目いっぱい遊び夜は懸命に勉強するという澤田少年のライフスタイルは、中学生時代には、澤田の好きだったことば「文武両道での切磋琢磨」という形に変化していたようだ。
ところが、中学4年の冬に大きな転機が訪れた。
父が急逝したのだ。
母は、子どもたちを連れて、裕福な寺を出て自活を始めた。この母の人生に対する覇気は子どもたちに大きな影響を与え、子どもたちの人生を長く励ます力強い原動力となった。
澤田は、父の逝去後の中学5年の時に県の弁論大会で優勝している。
昭和16年(1941)18歳で、あこがれていた旧制高校の門を叩き、官立広島高等学校(旧制)へ入学し、学生寮の薫風寮に入り、いきなり寮長になった。
広島高等学校での生活エピソードは、教え子たちによく語られることがあり、その話をするときの澤田の体からこぼれてくる喜びにみちた感情は、教え子たちを和ませるものであった。一生付き合うことになった数々の友人たちとの出会いと汗と喧騒に満ちたつきあい、勉学に励み、柔道に精を出す充実した日々は、澤田の人生のなかで大きな黄金のエポックであったに違いない。
寮長の役割は、「いかに生徒課の要求をはねつけるか、そして旧制高校の古きよきものをどこまで守り通すかにあったような気がする。」(*)と後年自ら語っている。だが、寮長として学校との交渉を重ねるうちに、「学校内の教授間のいろいろな派閥、争い事、暗躍」(*)をも知り、人間の暗部に触れる経験も多くした。そこで養われた人間観は、その後の澤田の人生に深く影響していたようだった。
そして、戦争はいやも応もなく、澤田たちの学生生活に押し寄せてきた。
昭和18年広島で行われた海軍予備学生激励大会で、澤田は、学生の戦争参加を促す開催趣旨とは反対の演説をする。広島文理大学、広島師範学校、広島高等工業、そして、澤田の在籍する広島高校という広島を代表する4校の生徒で一杯の会場には、来賓席には県知事、呉鎮守府長官などが並んでいた。
時勢は学徒出陣に傾くなか、澤田以外の三校の代表は、「今こそ学生はペンを捨てて剣をとり云々」という発言内容を昂揚した声で繰り返していた。
その中で、澤田は、「右手にペンを左手に剣をもって戦うという使命を抱いて」(*)おり、死をも辞せぬ愛国心を抱いている」(*)ことを述べたうえで、「今は、知力を練り、体力を作ることに熱中することが学生の取るべき最上の道だ」(*)と発言し、「我々学生は、軍人以上に国家の将来に責任を持っている」(*)とまで言い切った。
広島高校の生徒たちからのそうだ!そうだ!という応援する声と演説途中から始まった憲兵の弁士注意!の怒号が会場のなかで交錯していた。演説後も、憲兵は控室まできて、「このままではすまさぬ」と言っていたが、その後音沙汰は無かった。
この大会は中国四国地方で放送されたので、宇和島では母親が静かに息子の声に耳を傾けていたという。
昭和19年東京帝国大学法学部政治学科に入学。
同年に学徒出陣。香川県にあった善通寺師団工兵連隊に入隊した。
上等兵のときに、忘れられないひとつの出来事があった。
突然、憲兵隊から呼び出し令状を受け取り、中隊長が広島高校時代のことを心配するなか、憲兵隊へ行った。
憲兵見習士官と伍長、もうひとりの三人に睨み付けられ、広島憲兵隊から送られてきた、極秘と赤い印が押された文書を見せられた。
広島時代の恩師のひとりが、生徒代表澤田宏重に殴打されたとあり、見習士官は、優しい声で、反戦思想家教師をお前は愛国心から殴ったのだなと言った。
澤田の記憶には、ある私的な会食でその恩師と飲んだ帰りに、知り合いの家で澤田がくだを巻きはじめたため、その恩師が止めに入り、連れ出され、ふたりでもみ合いのようになった出来事が浮かんだので、そのままを憲兵隊に話した。
ところが、憲兵隊は、承知しない。どうもその恩師が反戦思想家であるという証言を欲しいようだった。
澤田は、断固拒否し、その恩師をだれかがおとしめようとしているのかと思い、とぼとぼと帰隊した。
「それから二三日後、私は班長に徹底的に殴られた。私が倒れるまで、それでも私は立ち上がった。約一週間内務班で毎日殴られ続けた。憲兵隊に協力しなかった貴様は、非国民であると。私の歯は三本折れ、頬は崩れた。」(*)
その後の中国大陸での戦場でも澤田はこのことをしばしば思い出した。澤田の記憶に間違いがなければ、取り上げられた事件は、酒に酩酊し乱れた澤田をその恩師が咎めたことにすぎず、当事者のふたりと翌日にお詫びにゆくかどうかを相談した友人ぐらいしか知らないはずの私的な出来事だった。
「このことについて、私は当時の軍隊を責めるより、これを捏造した誰かに、怒りよりもむしろ哀れみの念を覚える。」(*)と後年澤田らしい述懐をしている。
下士官身分の教育訓練が終わると、少尉に任官し、善通寺師団工兵連隊震天工兵隊の小隊長として、中国大陸に渡り、各地を転戦した。
上海市郊外にある張家楼鎮に長く駐屯した。張家楼鎮では、上官に敵である中国人に親しむのは危険だといわれながらも自ら進んで村人の中に入りこんだ。老若男女の住民と親しみ、子どもたちと仲よく遊び、住民たちと食事する澤田は、かれらから大変愛され、転戦による別れの際には住人達からたいへん惜しまれたという話が伝えられている。
「死を覚悟しておればこそ、死地で生活していればこそ、ひとを愛する心は国境を超えて光り輝くのだと思う。あの時の張家楼鎮の住民は敵ではなかった。彼らは黙々と畠を耕し、麦を育て、そら豆の花を咲かせる農民であった。彼らは平和を愛し願っていたのだ。・・・教育は愛だ。愛は至るところでいかなる時にも光り輝き、ひとの心を平和にしてくれる。」(*)
【003】
澤田の戦争の話というのは、中国大陸での転戦中の出来事であった。
中国の村から村へと転戦する澤田の部隊は、来る日も来る日も見渡す限り麦畑しか見えない中を歩いていた。
「きみたちに、どう話せばいいんかな。どこまでも目に見える限り、大きな空の下で麦の穂がゆらゆら揺れている。その中を僕たち兵隊は、次の駐屯地目指して歩いてゆくんだ。どこまでも続く麦畑のなかをあるいて長閑だと思うかもしれないが、戦争で行ってるし、戦争で行ってるってことは、いつ敵が現れるかもしれんし、休みはないんだ。そのうち、服もリュックもあちこち破けてきてボロボロだ、繕う時間もない。しかもね、兵隊さんを長くやっていると、だいたい腹を壊している。そう、いわゆる下痢便だぁ。」
女子たちからは、早くも軽い悲鳴が上がっている。
「そのうえ、天気は毎日雨なんてことがよくあった。晴れとった日の記憶はあまりないなぁ。道はどろどろ、服も靴もずぶぬれでよろよろだ。腹を壊してるから力も入らないしヨレヨレと列を作って麦畑のなかを歩いてゆく。雨が降ってると先を急ぐことはあっても途中の休憩はない。そうすると・・・歩きながら、下痢便が垂れてくるんだよ。今聞いている君たちは、汚い!不潔!と思うだろうが、自分が歩いている目の前を歩く兵隊の濡れたズボンから下痢が垂れるのが見えるんだ。自分だってそうだ。」
小学生の塾生たちには、想像もつかない話で、じっと聞くしかない。
「前のやつも自分もおなか壊していてよれよれ歩いている、しかも、今どこに向かっているのか教えてもらえないから、この行軍がいつ終わるのかもわからない。どこかに着いたところで、そこで雨宿りできるのかもわからない。だいたい、こういう天候がどうであろうが体調がどうであろうが、ともかく歩き続ける毎日がいつまで続くかわからない。もう、ただ歩いているだけ、楽しさなんていうのはかけらもない!っていうそういう状態が続くんだ。」
塾生たちから、ため息が聞こえ始めた。
「ところがね、人間って、不思議なんだ。そんなときでも、みんなそれぞれが(いちいちことばにはしないが)どっかに自分の楽しみを見つけてゆくんだよ。だから、あんな状態でも歩いていられるんだと思うけど。ほんとにツマラナイ楽しみなんだ。もう少し歩けば腹の調子がよくなりそうだ、もうちょっと歩けば雨が止みそうだ、今日の目的地は昨日よりも良いところだろうな。前を歩いてる兵隊のリュックの揺れ方がヘンな調子で面白い、とか、あと内地のことをいろいろと思い出す、一緒に遊んだ友だちのこととか思い出しては少しは愉快になっていたりする・・・」
澤田の目が一瞬遠くなった。だが、すぐに気を取り直し、ことばを続けた。
「・・・僕が言いたかったのは、これから1年間は、受験勉強で何でもガマン!ガマン!で、楽しいことなんか一つもないと思ってるかもしれないけど、そんなことはないんだ。必ず、楽しいことや面白いことが出てくるから、大丈夫だ。」
「先生、ホントですかぁ?」
「ほんと、ほんと、それこそ楽しみにしとけばいい。人間っていうのは、不思議なんだよ、苦しい中にもちゃんと楽しいことを見つけるんだ。」
「さぁ、勉強に戻ろう!」
【004】
澤田は、昭和20年晩春、本土決戦に備えるために帰国命令をうけ、帰国。本土で終戦を迎えた。
終戦後、詳しい事情はわからないが、叔父の家に養子で入った。叔父は、愛媛県の県議員を二期務めた政治家であり、戦時中には軍用機を個人で寄付するぐらいの資産家だった。
「東大には行かせてやる、政治家になりたければそれでもよかろうという条件で養子になったのだが、いってみたらこの話はまるっきり嘘。東大へ行ったら商売はできない。政治家になったら財産をつぶすと、私の夢を片っ端からこわしにかかった。
私は瞬く間に自棄になった。毎晩毎夜、芸者をあげて豪遊し、家業はいっさい手伝わなかった。そして大阪、神戸ついには京都の祇園でどんちゃん騒ぎをするところまで発展した。」(*)
祇園では、京大にいた友人たちを呼び出して、連夜どんちゃん騒ぎの宴会を催していた澤田の放蕩は半端ではなかった。
そして、「あっという間に数年がすぎた。もちろん私は東大には行かない。そして恐るべき破局の時が来た。当然のこと、養子離縁裁判である。この裁判が二年間続いた。
この間、旧制東大が新制東大となり、昭和25年に私は授業未納、出校せずという理由で退学処分を受けた。」(*)
澤田は述懐している、「あまりにも長く全く波瀾万丈の明け暮れ」(*)であった「私の二十歳代は悪夢のように過ぎてゆき、線香花火のように、精神も肉体燃え尽きた思い」(*)であった、と。
昭和27年、29歳、やっと養子縁組離縁となった澤田は、県立高校の教師となり、それから2年間、新制高校の先生を務めた。
生死の容赦ないドラマにまみれた戦場からの帰還後、先のない放蕩に明け暮れた20代の澤田は、人びとから疎遠になり、ほかのひとが踏み入ることのできない孤独のなかに立て籠ってしまってはいたが、いよいよ、まだ本人も気づいていない本来の資質が心のひだの奥深くで秘かに育ち、実は、表に出てくる機会をうかがっていたことをつきつけられる時期を迎えることとなった。
この2年間こそ、教育者の澤田宏重が誕生し、教育の現場で試行錯誤しながら成長し、政治家に成りたかった青年が教育者としての資質を自らに見出しつつあった時期でもあったのだ。
ひとりの教育者として、全身全霊で生きていることへの手さぐりを重ねながら、生徒たち、あるいは同僚、学校にあたっていった際の澤田の熱意に溢れた真摯な姿勢は、多くのひとたちの心と人生を揺り動かし、多くのエピソードを残している。
問題を起こす生徒がいると、教師たちの多くは、腫物のように扱ったり、退学などの処分処遇について論議したりするなかで、澤田の取った行動は、問題を起こした生徒本人になぜそういうことをしたのかを直接膝を交えて聴いてみることだった。ある時は、柔道場へ連れ出し肉体をぶつけ合ってお互いの真情を見極める際どいことまでした。また、複数の生徒たちがストライキを起こせばその現場に行って全員に事情を聴いてみた。こうして、生徒たちが何を感じ、何を思い、考え、行動したかを聴きとるうちに、澤田は、生徒たちが学校という場に真に求めていることは、学ぶことだという確信を得たのではないだろうか。学ぶことなら、澤田は、生徒たちとともに歩めるという確信も。
澤田は、生徒たち自身の向学心、向上心が生き生きと動き出す方向に生徒たちを導くことを教師の使命として発見していた。生徒たちが授業後も残って勉強したいといえば、教員の労働規則から外れることでも、生徒と一緒に教室に残り指導を行った。澤田は、生徒たちの向上心を守って育ててゆくことに心血を注ぎ、自分でもその役割に喜びを見出し納得していた。教師-生徒という関係の澤田なりの答えを学校という既成枠にとらわれることなく、見つけていた。
この高校教師時代に、美佐子夫人と出会い、たちまち恋がはじまった。音楽教師だった美佐子夫人にピアノを習いに行ったのがきっかけだったという。
美佐子夫人は、デートのたびに「あなたはこのまま田舎にくすぶっていてはいけない。もう一度勉強をやるべきだわ。」と澤田の未来に賭けているという励ましのメッセージを送り続けた。(*)
澤田は、美佐子夫人の激励を転機に、意を決し、大学受験勉強を再びはじめ、昭和29年、31歳にして新制の東京大学法学部私法学科を受験した。
念願の合格通知が来たときに、澤田との結婚を両親に反対されていた美佐子夫人には、「親が反対するのだったら家出してこい。東京へ行ったら、靴みがきをやってでも東大を卒業するつもりだが、それでもいいか」(*)と自分の強い意志をあらためて伝えた。美佐子夫人は、迷うことなく、澤田の情熱に応え、ふたりで上京し、「それから卒業までの私たちの生活は語るにはあまりにも苦労が多く」(*)という新婚生活が始まった。
東大への再入学後、東大法学部自治会の委員を務め、問題解決にあたっては常にスジを通すという旧制高校以来の姿勢は変わっておらず、正義感の強い熱い論客として学内で有名になるほど活躍していた。一方で、「今度は、真面目に勉強しました。翌年からは特待生として授業料免除、とどこおりなく卒業して、卒業後3年間大学に残」った。(*)
このころに、現役東大生が講師を務めていたことで有名だった進学塾の東大学力増進会が小中学生の部を開設し、澤田は、その責任者に抜擢された。初年度は生徒数が400名ぐらいだったのが、翌年は2000名に膨れ上がっていた。ここから宣伝に重点を置き拡大路線を敷く東大増進会に対して、「塾は宣伝でなく、実績だ。生徒の学力を伸ばすことに精力を注ぐべき」という澤田は真っ向から対立することとなり、袂を分かち、複数の生徒たちへの家庭教師を独立しておこなった。
昭和31年(1958)東京大学法学部私法学科を卒業。卒業後学士入学し、公法学科に学ぶ。
この年、大学卒業後の就職は法律関係の出版で有名な有斐閣に内定していたが、家庭教師をしていた生徒の父兄たちから、「ぜひ澤田先生のご自宅でグループで子どもを教育していただきたい」という強い要望があり、就職は取り消し、沢田塾を正式に開設することとなった。品川区上大崎の10畳の部屋で、塾生は中学1年生のみ14~5名からの出発だった。
その後、沢田塾は、塾生の増加とともに、芝仲門前、白金三光町と移り、「白金の白と三光町の光をとり、また夜空に輝く一等星となれという願いをこめて白光学院と名付けられた。」(*)
やがて、三田に移り、平成元年(1989)に澤田が鬼籍に入るまで、多くの教え子たちを送り出した。
学力向上の実績を次々とつくりあげるだけでなく、多くの教え子や父兄たちから人間的な信頼をもかち得て、東京では知らぬ人のいない私塾として、澤田宏重の際立った個性と情熱が放射される場として、他の進学塾にはない異彩を放ち続けた。
澤田自ら開設した塾への信念は、「塾に看板は不要」「塾は一代限り」(*)のふたつであり、「塾を企業化してはならない。塾は生徒と先生との一対一の心の触れ合いに始まり、それに尽きる。塾は一代限りが本来の姿ではないだろうか。」(*)という思いが澤田の授業には込められていた。
澤田は、「塾は私の天職である。」(*)ことを自他ともに認め、既成の教育者の枠に縛られず、私塾の場を通して人間教育を施すことのできる「先生」であり続けた。
【005】
澤田は、教え子たちを自宅に招き、美佐子夫人とともに歓談することを喜びとしていた。いろんな世代の教え子たちが、澤田家のリビングルームで美佐子夫人のもてなしにくつろぎ、澤田宏重とのユーモアと鋭さにあふれた力強い会話に励まされてきた。塾の休みの日の時もあるし、平日の夜に開かれ深夜に及ぶこともあった。
まだ、1970年代が始まったばかりの頃、鎌倉にあった澤田の自宅を沢田塾を卒業したばかりの高校生たちが20人ばかり訪ねたことがあった。会食後に鎌倉の海岸を澤田夫妻と大きな愛犬とともに海風にあたりながら散歩し、再び澤田家のリビングルームに帰ってきたときに澤田が教え子たちに提案した。
「僕の話ばかり聞いてても飽きただろう。せっかく、僕の家に来たんだから君たちも何か話してゆきなさい。」
リビングルームのスクリーンのような窓から見える海は穏やかに揺れており、静かに晴れた空との間にくっきりとした水平線を描いていた。白いベージュで統一されたリビングルームは、20人ほどがソファやいすに腰掛けても余裕があるほどで、床は、壁際で少し高くなっており、ピアノを教授している美佐子夫人のグランドピアノがあった。
ひとりの女子が皆から囃され、戸惑ってはいたが、ピアノの前に座ると臆することなく、鍵盤に手をおき、激しいイントロを弾いた。ショパンの「幻想即興曲」だった。
囃していた連中もこの印象的なイントロとその後の激流のような展開にのまれ、聞き入ってしまっていた。
演奏が終わるとまだ高校生の教え子たちは、何だか体を覆っていた衣が一枚剝がれたような軽快さを感じ、口が軽くなったのか、一人づつ自分のことをしゃべりだした。
最近身辺で起きたことやそれについて感じたこと、感動した本や映画、あるいはスポーツのことなどを話題にするひともいたが、やはり、多くは、これから向かおうとしている自分の将来、目標とする人生設計、職業、そのために目指す大学のことを話した。
沢田塾卒業生で澤田の自宅を訪問するぐらいの連中なので、世間的に見れば、中流以上の家庭出身のエリート候補生であり、その階級に相応しい明るい未来が語られ、和やかな雰囲気で澤田もひとりひとりにそのひとに向けたアドバイスを挟みながら、教え子たちの話に顔を緩めっぱなしだった。
しかし、そのなかに、ひとりその場の雰囲気にどこか馴染めず、ひねくれていたのがいた。
「僕たちは、これから大学受験をし、大学に進み、おそらく多くは就職し、社会に出てゆくと思うのですが・・・そのために、今以上に勉強し体験し、そして、やがて、人生や生きることの価値を見出してゆくと思うんです。
ところが、世の中には、僕たちがやっている勉強みたいなことはまったくせずに生きている人たちもいます。その中には、例えば、この間テレビで見たんですが、少年のころからずっと漁師をやってきた老人で、人生についての意味や生きることの価値を自然にことばにして語っている人たちがいました。
こういう人たちをみていると、今、僕たちが一生懸命にやろうとしている勉強、間近なことでは、受験勉強がまずありますが・・・
これから僕たちが社会に出てもおそらく続けてゆかねばならない勉強というのは、やりつづける価値はあるのかと思ったりするんですが・・・?」
この少年自身が自分の言いたいことをまとめきれず、何を言いたいかはよくわからなかったが、やむにやまれぬ感情が思わず吐露されてしまった切迫感のようなものがあり、花やいでいた雰囲気に水を差してしまっていた。
じっと少年の話に耳を傾けていた澤田は、少しおいてからしゃべりだした。
「沢田塾は、エリートばかり教えていて、勉強のできない子たちをなぜ教えないんだという人がいる。頭の良い子たちを選別して教えていたわけではなく、僕が塾を始めたとき、僕のやり方で授業をしていたら、ついて来れない子たちもいて、逆にもっと勉強したいという子たちも出てきた。
僕が塾を始めたのは、もっと勉強したいという子たちにもっと学んでほしいからだった。もっと勉強したいけどできないという子とは話し合って、うまくいった時もあったし、うまくいかない時もあった。それは、僕の教え方がそのひとにはうまくゆかなかったことだと思う。僕の力不足だ。
教えるというのは、先生と生徒の一方的なことではなく、先生が一生懸命教えて、生徒がそれに応え、生徒の熱意と行動をみて、先生がさらに高いことを教えてゆくような関係だと僕は思う。生徒の力を引き出せないのは、僕の教師としての力不足だ。
だから、沢田塾はエリートのための塾だといわれると事実そうなってるし、君たちが澤田塾に通うことにいくらかのプライドをもってくれるとしたら、それはそれで嬉しいが、塾には教師としての僕の力不足という面はある。
現に、君たちのような秀才を私ごときが教えるなんていうのは・・・君たちが、塾を卒業したから言うわけではないが・・・本当は教えることなどは何もない。君たちは自分自身の力で勉強していったんだ。僕にできたのは、勉強の厳しさを体験してもらうようにしていただけだ。
ちょっとかっこよく聞こえるかもしれないが、これは、沢田塾を続けてきて、僕が思ってきたことだ。
君たちには、とりあえず目の前には大学受験で希望校に合格したいという目標があるし、その目標ももっと先の社会に貢献する仕事として自分はこんなことをやってみたいという大きな目標にめがけての一歩だろう。さっきから、一人づつしゃべった話からもそういった内容を聞いた。
今の質問にあったように、さらに先の、人生の目標というか、後悔をしない生き方をしたいという目標を今から持っている諸君もいるだろう。
自分の目標をもって、純粋な心で向かって行くことは何よりも大切だと僕は思う。
漁師や農作業に関わるひとたち、あるいは、職人と言われる専門職のひとたちは、ごく若いときからその道に入り、年を取るまで職業への研鑽を続けた彼らのことばには、その道にまい進したからこそ得た深い体験による奥行きのある言葉があり、それは、ひとつの専門職としてのことばのなかに収まりきらず、もっと広く、だれでも経験するかもしれない人生の諦観や有象無象の人間に関する深い洞察が現れていて、ハッとさせられることはある。
ひとつの道にまい進した人間の気高さであり、美しさだろう。
諸君はこれからの人生のなかで、情熱をもって純粋に求めてゆくものが何であろうとひとりの人間としては、自分の中に人間、矛盾した人間というものを発見してゆくんじゃないだろうか。情熱をもって純粋に求めてゆくものがないとしたら、つまらない人生になってしまうんじゃないだろうかとも思う。
僕は、若いころに倉田百三の『出家とその弟子』という戯曲に夢中になったことがある。その当時の僕と同じ世代の青年の多くが熱狂して読んだとも言われているんだが。
そこに描かれていたのは、ひとを超える聖なるものを求めながらも人間の煩悩そのもの、愛欲に夢中になったり、親子がお互いに和解しようという同じ気持ちを持ちながらも感情やら他人に振り回されたりで和解できなかったり、という矛盾だらけの人間の姿だった。ありのままの人間と言ったらいいんだろうか。最終的には、信仰というか祈りということが希望のようになってゆくんだ。
僕が感動したのは、最終的な解決よりも、矛盾だらけの人間というか、人間というのは矛盾だらけで、生きてゆくんだということだったんだ・・・それは、今でもそう思う。
え〜つと、質問に応えようとして、話がいろいろ飛んでしまったが、どうなんだろう、自分がこの道で生きていこうと決めたら、そのまま進めばいいんじゃないだろうか。ただ、安易な道を行ってはいけない。苦しさや痛さを感じながらでも突き進んでこそ、自分の行く道はもっと純粋に鮮明になり、また、そこに自分にははっきりと感じられる矛盾を発見し、ひとに対する見方や接し方が変わってきて、さらに自分の道にまい進する、言い方を換えれば、わがままな生き方を周りの人たちも納得してくれるんじゃないだろうか。
僕は、こう思うんだが、諸君は、どう考えるかな。君の質問の答えになっているかな。」
【006】
澤田塾は、高校1年で卒業となる。あとは自分自身で工夫して勉強せよという澤田の教えである。
塾の卒業生たちのなかには、機会あるごとに澤田のもとに訪れるものも少なからずあり、澤田自身も日々の授業の終了後塾長室に戻り、卒業生の姿を認めると「おぉ、来たか!元気でやってるか!」と話しかけ、授業ではなかなか見せないにこやかな笑顔で迎えた。
ひとりの塾卒業生が、ふと思い立ち、ある日、授業後の澤田を訪ねた。1970年代の前半の頃の話だ。彼の通学する学校で校長と生徒たち、教員が激しく対立するという社会を騒がせるような激しい紛争が起こり、彼もその渦中で高校生にしては多くの人間ドラマを短い期間に大量に経験していた。この紛争が一段落したときに、澤田を思い出し、これといった相談事もなかったが、訪ねる気になったのだった。
少年が塾長室で待つと、授業を終えた澤田が両手いっぱいに教材や生徒たちの答案用紙を抱えて帰ってきた。
少し疲れた様子だったが、「おぉ、君かぁ!来とったかぁ!」とたちまち顔に生気があらわれた。
少年は、小学校5年生から澤田塾に通った、いわば生え抜きだった。と言っても、澤田塾において生え抜きは大した意味もなく、澤田に伝えても、そうだったかと軽い驚きと笑顔が返ってきて終わりだった。塾においては、今現在どうなのか、将来の自分について自分できちんと考え日々鍛えているかが重要だった。
「君の学校の紛争については、塾生の現役からもOBたちからも聴いてきたんで、おおまかなことは知っている。紛争の当事者だった君の学年の塾生OBが何人か訪ねてきて、先生、この紛争についてどう思われますか?って質問攻めだったよ。
君の同級生たちの話からは、君はかなり渦中にいたらしかったし、君の性格からして、紛争中は僕のところに来ないだろうなと思っててね、終わったら、顔ぐらい出すかとね。
今夜、君は、やってきたんだから、僕のカンも冴えてるだろ。
それで、今夜は、何か相談ごとがあるのか?」
「はぁ、特にはありません。進学のことや学校のことも何とかやってますし、今夜は、先生にお会いしてみようかなとふらっと来ました。」
澤田の眼鏡の奥の目が笑っていた。
「そうか。今夜は、僕は急ぎの用事もないし、外出しようと思っていたんだ。君も付き合いなさい。」
澤田は、手際よく塾長室内の机の上を片付けると、少年をタクシーに乗せて、銀座へ向かった。
澤田が少年を連れて行ってくれたのは、バーだった。少年の目には、テレビや映画から出てきたようにみえるキラキラした若い女性たちにあっという間に囲まれてしまった。
「君は、腹が減ってるだろう」と澤田はすぐに寿司を取ってくれ、何やら心のなかはきょろきょろしている少年は、この場所での自分の仕事が見つかったように寿司桶にぱくつき、澤田と女性たちの会話に耳をそばだてるのだった。
「先生は子どもの頃に、お母さまから何て呼ばれてらっしゃたんですか?」
「宏(ひろ)さんと呼ばれたな。お、笑うか、可愛いだろう。末っ子だったんで甘やかされたということもなかったんだが、母にひろさん(愛媛のイントネーション)と呼ばれると大人に扱われているようで嬉しかったな。ちゃんではなく、さんだからな。」
澤田のお酒のペースはどんどん上がり、酔いも回ってきたようで、やはり、旧制高校時代の自分の武勇伝から親しかった友だちの話へとうつっていった。
「とても親しい友人で、大きな映画会社に入って、社長にまでなったのがいてね。入りたての頃は、汗だらけで長い棒やらをもって歩いているところになんか、出くわしてね、何やってるんやと聞くと、ロケや!ロケ!って大きな声で返事が返ってきたもんだった。
その映画会社の女優さんには、ヨシコという名前が何人もいるんだな、漢字が違うけど。
広島の高校2年の終わりごろだったかな、寮で寝ていると、おい澤田!つきあえ!って、彼が呼びに来たんだ。おい夜だぞ!って言っても聞いてくれないで、とうとうふたりで広島の夜の町を歩くことになったんだけど、彼がどこに何をしにゆくのか、黙って凄い顔で歩いているだけで、まったくわからない。ケンカかとも思ったけど、そうでもない。
そのうち、ぐんぐん歩いていたのが、突然止まった。ある二階建ての商家の前だ。そこで、仁王立ちになって、大声で、ヨシコ!ヨシコ!と二階の窓に向かって叫びだしたんだ。
なぁ~んだ、女かとも思ったけど、何で自分まで一緒に連れて来られたのかがわからない。
二階の窓ガラスが静かに開いて、ヨシコさんが登場した。暗くてよく見えなかったが、彼が惚れてんだから美少女だったろうな。
ヨシコ!オレは東大に行くことにした!だから、これから勉強する!もう、ヨシコには会えない!会わないからな!
ヨシコさんは、黙って聴いていて、頷いたようだった。それを確認すると彼は、サワダ!帰ろう!と怒鳴って、いかり肩でのしのしと歩き出した。体が大きかったので、後姿にはひとを寄せ付けない迫力があったな。うぉうぉ泣いてたな。
後で思ったんだが、僕が連れていかれたのは、大学受験のために彼女と別れるという決意をしたものの未練があったものだから、後に引き返せないようにするためだったんだ。
それで、有望な若い女優さんが入ってくると、ヨシコ、ヨシコと名付けたんだ、きっと。」
澤田は、少年の顔をサラッと一瞬見つめ面白いだろうと話しかけた。何かを伝えたかったのかもしれない。
そうこうするうちに、バーは閉店時間となった。澤田とママさんが何やら話して、「次ぎ、行こう!」と、少年は、ママさんも含めた3人で六本木に連れてゆかれた。六本木では、少年ですら名前ぐらいは知っていた有名なゲイバーにいった。深夜の時間に次々と行われるステージショーやそこのおねえさん達との会話は少年が今まで知らなかった種類の面白さだった。そのころ夢中になっていたイタリアの映画監督フェリーニの一場面に入り込んだようだった。
そして、明け方、澤田とママさんと少年は、六本木角のアマンドでスープを啜りながら、あれこれと話していたが、さすがに、長い一夜に疲れ果てていた。鎌倉へ帰る澤田の車で、ママさんと少年は途中で落としてもらった。
少年は、あまりの不可思議な体験に、2~3日は、ぼぅっとしていた。友人たちに話そうとは思うのだが、どう話せば少年の体験をわかってもらえるのかがまったくわからなかった。
後年、少年が社会人になり、接待や遊びで酒席を設けたり、宴席に身を寄せるときに、澤田の好奇心に満ちたきれいな遊び方は、ひとつの規範となった。折につけ、澤田の酒席での振る舞いを細かく思い出すこととなった。少年は、少年を遥かに過ぎ老年を迎えても澤田を心のなかに訪ね、対話をすることがあった。
【007】
澤田宏重は、多くの教え子たちにとっては、生涯忘れることのできない、尊敬すべき教師であり、また、先生や教師といったことばが実によく似合っていた。
強い信念に裏付けられていることを感じさせる張りのある声は、中背の痩身に共鳴し、眼鏡の奥から放たれている鋭い眼光とともに、相手に向けられ、その体全体からは品のある情熱が遠赤外線的輻射をなすように放たれているのであった。
澤田自身のことばには、直接はなかなか出てこないが、澤田が塾生たちに伝えようとしたことのひとつに、現在を大切にする、ということがあるように思える。
「塾は一代」という澤田の発言はいろんな意味にとれるが、澤田が生きている現在こそが塾であり、澤田自身が亡くなったあとにその衣鉢を継ぐことは不可能なことであり、また、そんなことをさせることはみっともないことであることを澤田自身がいちばん深く気づいていた。
僕の人生を継ぐより、君の人生を始めたまえ! である。
澤田宏重を称え顕彰する会よりも自分たちの人生を喜びあう宴を開いてくれるほうがどれだけ嬉しいことか! である。
「澤田先生には、学校の教科だけでなく、人生や生き方についてあんなことこんなことほんとにいろんなことを教わり、感謝してます。」
と、澤田に伝えたら、どんなことばが返ってくるだろうか。
澤田宏重をわが先生として所有する誇りには優しい眼差しを向けるが、その誇りに媚びることがあれば厳しい目となるだろう。
含羞を含んだ笑みを浮かべながら、こんなことを言いだすのでは、と思ったりする。
「諸君に感謝されるのは、嬉しいかぎりで、ほんとに光栄だが・・・塾のOBたちと会って、僕が話したいのは、今の君の人生はどうなっているかについて、だな。今何を目指してそのために日々何をやって鍛えているかを聞き、話しあいたい!。人生のゴールが見えていたとしても、だ!」
参考図書
・澤田宏重 『私塾の心 この爽やかな真実』日経事業出版 昭和54年発行
・澤田宏重 『早稲田 慶應を一回で合格する法』KKロングセラーズ 昭和58年発行
・澤田宏重を偲ぶ会編集『白光の余韻』 澤田美佐子発行 1995年発行
文中の「~」(*)は、上記の本より引用しました。
肖像画は、澤田宏重を偲ぶ会編集『白光の余韻』より引用しました。
追記
澤田宏重の謦咳に触れたことのある、教え子は数多く、それぞれが澤田宏重への記憶を刻んでおり、自分の人間形成期に出会った鮮烈な人格であったことを何とか言葉にして率直に語る元塾生も少なくはない。
「オレにとって、澤田先生は、人生で初めて出会った『俗』という強烈な存在だった。澤田先生の人格、存在を通して『俗』ということを知った。」
これは、一般塾生よりは、澤田宏重と深くかかわり、澤田宏重の懐に飛び込んでいたと、傍からは見られていた教え子のひとりが半世紀前の澤田とのかかわりを聞かれたときに、長年の堰が切れたかのように激しい勢いで口から飛び出してきた言葉だ。
彼は、「澤田宏重はいわゆる俗物である。」ということを言いたかったわけではない。
『俗』ということは、人間が生きてゆく限り、その生活の周辺に必ずついて回るもので、それを切れば人間世界から絆を絶たれ孤絶するだろうし、それを受け入れすぎれば、小心翼々の浅はかな自己利益に生きることになるだろうという厄介な代物だ。
代物である以上、そこに手をのばしてもぐっとつかめる実態はなく、そのときどきのその場の利益らしき物事やエントロピーが宿る媒体なのだ。
彼は、澤田宏重との出会いと交流の中で、世の中には、『俗』といわれるそういう厄介な代物があり、それに憑依されるといわゆる『俗物』になることを少年時に雷に打たれたように感じたとでも言っているのか。
そして、彼は不敵に安堵した笑顔を見せながら、「だから、澤田先生をやたらに持ち上げる輩には、毒にも薬にもならない俗物もいるんじゃないかっていうことだよ。」とでも言いたげだった。
(2023.10.27)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
