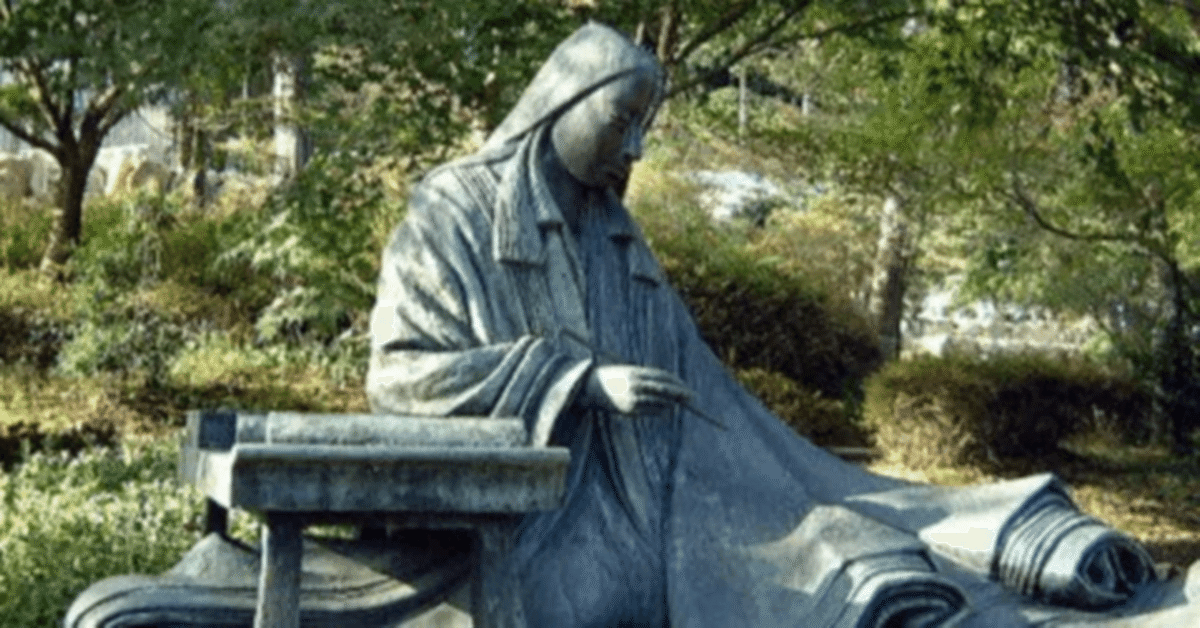
「光る君へ」第21回 「旅立ち」 想いに区切りをつけて、旅立つまひろと道長
はじめに
当たり前ですが、時間は巻き戻るものではありません。自分自身の思惑、真意に反した出来事であったとしても起きたことは変えられない。哀しいけれど、それが世のルール、起きた出来事に向き合う以外の方法を持っていません(時間旅行などタイムパラッドクスの作品なら別ですが)。
それは、「光る君へ」の人々も同じです。前回、政変へと転じていくさまが描かれた長徳の変は、政の主体である一条帝や道長の意図した政変ではありません。前回note記事で触れたように、道長の公明正大な徳治政治、有能な人材の登用という正攻法の遣り方が、人々の予想外の思惑を生み、事件を政変へと変えていったのです。謂わば、前途多難といえど、新しさと希望に満ちて始まったはずの道長政権の影を早々から見せるものでした。
帝も道長も、為政者として、自分の気持ちとは関係なく、起きた事態に正しく処理をしなければなりません。しかし、その結果が関係者を救うとは限らず、また自身の心を深く傷つけるものになることもあり得ます。当然、大事になった事件とその結末は、周りから要らぬ憶測と評価を生みます。それが、第20回で描かれた長徳の変の顛末です。
しかし、それでもその結果を引き受けて、自らの先を選択しなければなりません。それは、道長や帝だけではなく、悲観して落飾した定子も彼女についていくと決めた少納言も、そして道長の政の結果、父について越前へ行く選択をしたまひろもです。そのためには、人には、これまでのことを受け止めた上で気持ちに一区切りつける必要があります。人はどうしても過去や後悔に引きずられざるを得ませんから。
そこで、今回は長徳の変の顛末を引き受け、人々がどう気持ちに整理をつけ、次の道へと進んでいこうとするのかを考えてみましょう。
1.女性たちの「長徳の変」始末
(1)定子の落飾の余波
アバンタイトルは、前回のラストから始まります。伊周を捕縛するため、二条邸へと踏み込んだ実資率いる検非違使たちを前にふらりと現れた定子は、突如、彼らの刀を奪い「よるな~ッ!」と脅すと、間髪入れずバッサリと髪を下ろしてしまいます。この所業に一番、衝撃を受けたのは、当の本人ではなく、母の貴子です。彼女が、隆家が潔く出頭するのを涙ながらに見届け、伊周を捕らえに来た実資らが二条邸に土足で踏み込むことの屈辱に耐えていたのは、亡き道隆への思いと自ら作ってきた中関白家の誇りがあるからでしょう。とはいえ、耐えるのも限界といったところだったはず。そこへ、中関白家の栄華を支える柱石であった中宮定子が、目の前で突然、出家してしまったのです。貴子は、手塩にかけた娘が人生を儚んで捨てる瞬間と中関白家が瓦解する瞬間の二つを眼前で見届けることになったのです。
「ああっ…うああああああああッ!!!」…人生のすべてを失っていく貴子の絶叫が響き渡ります。息も絶え絶えの母の前に、何故か安堵したかのような表情の定子は、静かに「「出家いたします」と告げます。俗世の縁を断つ…中宮という地位を捨て、親兄弟の縁を切るという定子の言葉は、兄弟の愚行の大本にある中関白家の栄華への執着、それ自体を終わらせるということです。もう終わりにしましょう、定子は母に静かに終焉を告げているのです。
まひろと共に物陰で樹木になりすまし、この一連の流れを見ていたききょうが「どうして…中宮さま…」と無意識のうちに飛び出そうとして、まひろに止められていますが、定子が何故、この凶行に及んだのか、明確なことは語られていません。ただ、その後の二条邸の火事のとき、ききょうに語った「生きていても虚しいだけだ」と言う言葉からすると、彼女は自分のこれまでの人生、そしてこれからの人生が無意味に見えたことだけは間違いないようです。
定子は、幼い頃より、我が「家」と帝をつなぎ繁栄させるため、入内することだけを目的に育てられた人です。それ以外の生き方を知りません。入内後、幸い帝を愛するようになり、また帝も自身を寵愛するようになりました。そして、その寵愛をもとに彼女なりに、父や兄たちのために心を砕いてきました。一方で、皇子を産まないことを父と兄に責められ、傷ついてもきました。それが、定子のこれまでの人生です。
今、中関白家は、伊周・隆家兄弟の不始末で滅びようとしています。兄たちの愚行については、おそらく彼女自身も同情するところはないでしょう。それでも肉親の情はありますし、また自身の不甲斐なさが、彼らを凶行に及ばせ、そして帝につらい決断をさせた、その責任も感じているでしょう。勿論、彼女には何の罪もないのですが、我が家と帝をつなぐために生きてきた彼女の無力感は消えません。
また、帝を愛してしまい、それだけを寄る辺としてきた定子にとっては、宿下がりそのものが寵愛を失ったことであり、不安なことであったはずです。その宿下がりが、伊周たちが罪人として失脚することとセットであると斉信から伝えられたとき(第20回)、最早、帝からの寵愛は得られぬと思い込んだ面もあったように思われます。
宮中で生きることしか知らない彼女にとって、帝の愛なき、この先の人生は想像すらできないことと映ったでしょう。生きる意味を失ってしまったのですね。この絶望感に帝への申し訳なさ、罪悪感もこの絶望感に加わります。罪深い上に無意味な人生…生きていても仕方がないという絶望と罪悪感が、彼女に刀を取らせ、髪を下ろさせるのも不思議ではありません。
髪を下ろしたことで定子は、これまで内外から受けていたさまざまな重圧、自分の努力の無意味さ、帝への愛など自分を縛ってきたものから解放されたと感じたのか、一時的にスッキリした表情を見せ、母に我が家の終焉を告げています。自分が出家したとすれば、出世の見込みがなくなる愚かな兄、伊周も栄華に執着して、これ以上の醜態を晒すこともなくなるだろうとの思いもわずかにあるでしょうね。そして、これが皇子を産めなかった謝罪でもあるかもしれません。どちらにせよ、その空虚な笑顔には痛々しいものがあります。
場を包む異様な空気は、予想外の落飾を止められなかった実資の表情に表れています。彼もまた、急転直下の事態に言葉を失い、呆然となるより他ありません。そして、定子の決意は、さまざまな人の心に深く瑕として刺さります。
まずは一条帝です。「中宮が自ら髪を下ろしたのか…」と定子の真意を測りかね、衝撃を受けた彼は、思わず「誰も止めなかったのか!」と声を荒げてしまいます。その場の異様な空気に呑まれ、伊周を捕まえることもかなわず戻ってきた実資は、帝の心痛を察し言葉もありません。ただ「一切の責めはこの私が負うべきもの、この身が至らぬゆえのことでございます。お詫びの申し上げようもございません」とだけ述べ、自分の責任問題であり、他の誰でもないとだけ答えます。
政務とは結果です。結果を出せなかった以上、見苦しい言い訳をしないという実資の潔さはさすがですね。また、失敗した場合、部下の責任も自分が引き受けるというのも、上に立つ者の言動として信頼に足るものです。当人は比べられたくもないでしょうが、何事も他人へ責任転嫁する伊周とは大違いです。
また、実資は誠意から、こうした言動をしているのですが、激高している相手には弁明は逆効果です。その点でも、実資は的確な対応をしていると言えるでしょう。
実資の誠実な態度に、やや冷静さを取り戻した若き帝は「お前を責めておるのではない」と心遣いを見せると「朕のせいであろう…」と虚ろな表情で答えます。その表情は、御簾越しですから道長たちには見えないのですが、声の響きだけでその悲しさは伝わるのでしょう、道長の表情は沈鬱です。
物思いに耽るように「中宮は朕に腹を立て、髪を下ろしたのであろう…」と定子の胸中の苦しみを慮ります。勿論、この推量は外れています。ひたすらに帝に尽くし、慈しむ定子は、帝への申し訳なさはあれど、腹を立ててはいません。定子は、ただただ、この現状が空しく、そして将来に悲観的になってしまったのです。
にもかかわらず、定子が腹を立てたと帝が思うのは、伊周を太宰府に配流するという裁可に対して、自身に迷いがあったからでしょう。禁じられた呪詛をしたという証拠(冤罪の可能性が高いですが反証がない)、花山院を矢で射た不敬…どちらも帝の政に対する暴挙といってよいものです。身内であるからこそ、厳しい沙汰をくださなければ、周りに示しがつきません。今後の政権運営にも差し障りが生じるでしょう。
それでも、定子への愛から罪一等を減じての温情措置をしたのが、今回の裁可でした。客観的に見れば、バランスの取れたものですが、定子を愛する彼からすれば、それだけでは足りなかっただろうか…と迷うところがあったのでしょう。
因みに、この裁可に異を唱えることもなく、それどころか、帝から温情措置を引き出すように図ったのは、道長です。前回、道長は、秘かに土御門殿を訪れた伊周の懇願を受け入れ、なんとか帝の心を動かそうと思案します。そのために定子を秘かに内裏に招き入れ、帝の情に訴える策を講じたのです。帝も、道長が定子を内裏に引き入れたことを知っています。だから、右大臣の意向が温情であるということ。それに後押しされて、帝は定子への情を考慮した裁可をしたのです。つまり、伊周兄弟への裁可は帝と道長の談合。道長にも大いに責任があるのですね。
だからこそ、帝に結果的に苦しむ決断をさせたことを申し訳なく思うのです。彼らに良かれと思って図ったことが、すべて裏目に出てしまったことにも忸怩たる思いがあるでしょう。帝の苦悩がわかるこそ、そしてこの場が公であるからこそ、道長は敢えて、その私情には口を挟まず、あくまで右大臣として「伊周はまだそう遠くには行っていないと思われます。都の内外に追手を遣わし、必ず捕らえます」と述べ、後は帝の御心を惑わすことなく、私たちの責任でなんとかしますと精一杯の配慮を上申します。
右大臣の言葉に帝は「朝廷の権威を踏みにじった伊周の行いは許さぬ」と怒りを滲ませます。伊周さえ、太宰府配流すら温情であると理解し、素直に受け入れさえしていれば、この最悪の事態は避けられたからです。
その上で、元は何の咎もないとはいえ、許可なく落飾した定子についても、事が明らかになった以上は「事の重大さも弁えず、いきなり髪を下ろし、朕の政に異を唱えた中宮も同罪である」と言い放ち、温情をかけるに及ばずと明言します。こちらは怒りではなく、苦渋が滲みます。朝廷という社稷の権威を守るのが、帝の役割です。その主上にある以上、一条帝は寵姫にして中宮である定子に対しても、等しく厳しくあらねばならないのです。
良くも悪くも、詮子が彼に厳しく施した帝王学は、こういうときにきちんと機能し、正しい判断をさせているのが皮肉です。事件の黒幕は、その母であるかもしれないのですから。
帝の命が下ると、その場にいた右大臣道長、検非違使別当実資、蔵人頭行成は、互いの顔を見合わせ、頷き合うと行成と実資は早々に去り、道長のみがこの場に残ります。三人の目配せは、この後の段取り(実資は探索、行成は公卿への連絡)の確認が主であると思われますが、この御前での帝の怒りと苦悩は御簾越しでも道長らに伝わるものでした。今の厳命にしても、帝という立場上、激情を抑えてのものであったことも察せられます。ですから、彼の気持ちを慮り、後は道長に任せて、行成と実資は早々に去った面もあると思われます。
果たして、行成、実資が去ると、一条帝はたった一人、その場に残った、彼にとっての唯一の叔父の前で、がっくりと座り込むと「愚かであった…中宮はもう朕には会わぬ覚悟なのか…」と定子に見捨てられ、見放されたことに対する正直な思いを吐露します。勅命は権威のあるものです。それゆえに、それを出した帝であっても軽々しく覆すことはできません。勿論、一条帝は熟慮を重ねて、流刑の裁可をくだしています。それでも、それは万能の結果を生むとは限りません。そして、公表してしまったものは、取り返しがつかないものなのです。
「うわああ…うああああああああッ!」…若き帝の慟哭と嗚咽が道長の胸に刺さります。彼らは、朝廷の権威と身内への情のバランスを取る裁可をくだしました。その匙加減は間違っていたとは言えないでしょう。良かれと思ってしたことが、何故こうも裏目に出るのか、帝にとっては不思議なことだったでしょう。
敢えて一条帝の問題点を指摘するとすれば、帝ともあろう人が「伊周や、定子もきっと私の苦悩や温情をわかってくれる」と下々の善意を信じてしまったことでしょう。禁欲的で善人であるほど、人の欲望や猜疑心、悪意というものに縁がありません。だから、人のそうした負の感情が想像できないのです。まあ、仲も悪くなく嫌ってはいなかった伊周の虚栄心と傲慢に裏にある子どもっぽさ、これに気づくのは至難の業だったかもしれません。
そして、なんといっても彼はまだ15、6歳の少年です。この年齢で、愛する人をも処罰するような高度な政治判断を要求されていること自体が悲劇的とも言えますね。
逆に、帝を補佐する道長は、最悪の事態の可能性も考慮すべきだったかもしれません。彼は、人様の善意を信じすぎて、直秀を死なせてしまうという致命的な失敗をして、泣くほど後悔しましたからね。身内だけに甘さが出たことが裏目に出たのかもしれません。
帝の嘆きを受け止めつつ、道長は、ここまで来た以上は確実に事を片付け、これ以上、関係者の心の傷を広げないよう処理しようと誓います。特に、年若き帝の心の傷はいかばかりか。となれば、この件によって起こる問題や悲劇、悪評、そのすべてを自分が引き受けるしかありません。ふうっと息をつく道長の顔が、引き締まったものになるのは、政の頂点として、その責を負う覚悟をしたからでしょう。
勿論、検非違使別当として実働部隊を率いる現場監督ともいうべき、実資の心労も相当のものです。夜、彼の腰を揉む婉子が甘ったるい声で「コチコチにこざいます」と言われるほど身体を酷使し、連日連夜、休むことなく探索していることが窺えます。彼にしてみれば、正攻法の捜査であったにもかかわらず、中宮の落飾を目の当たりにし、帝の心中を思えば、「もう罪人の行方探しなどお止めくださいませ。博識な貴方のおやりになることではございません」と辞任を促す婉子の言葉に「まったくだ」と納得しつつも、伊周を捕らえ、配流に処すまでは辞められないと覚悟を決めます。
「このごろつまりませぬ」と夜構ってもらえないことを、むずかるような言動で困らせる若妻のなすがままになりながらも「今少し待て、今少しじゃ」と虚空を見る彼の目には、この事態の意味するところを考えるようなところがありますね。
ところで、この件とは本来、無関係でありながら、ききょうによって巻き込まれ、定子の落飾を目の当たりにしてしまったまひろにも、この件は少なからず衝撃を与えました。ききょうから聞いた話しか知らないまひろからすれば、定子の落飾は愚かな兄弟の犠牲となった定子の顛末としか映らなかったはずですが、あの高貴で鷹揚な中宮を知るだけにその姿は哀れで痛々しいものであったのは確かです。
またもまひろが現場にいたことに驚く宣孝が、「中宮さまのお顔は存じ上げぬが、あれだけ帝のお心を惹き付けられるんじゃ。すこぶるよいおなごなのであろう」「女を捨てるにはもったいないの…ああ実にもったいない」などと容姿について興味本位に語ることにムッとするのも、女たらしの宣孝への呆れや持ち前の正義感、潔癖だけではなく、ただただ同じ女性として、慕うお人と二度と会えなくなる出家を選択した定子の思いについて、思いを馳せるからです。
ムキになって怒るまひろに対して、宣孝は、わざわざ身を正すと「わかった。大きにご無礼つかまつった」と大袈裟に謝ります。その滑稽なまでのご機嫌取りに、まんざらでもないまひろは、思わず表情を緩めます。まあ、宣孝の下品な軽口は、潔癖なまひろをからかう面がたぶんにあったので、そもそも定子に関する物言いは真剣なものではありません。まひろに合わせて、撤回するのはわけもないのですが。
まひろが機嫌を直したことを確認すると、宣孝は「見方を変えるといたそう」と言うと「この騒動で得をしたのは誰であろうか?」と問いかけます。政に感心の高いまひろに合わせた話題の振り方、こうした臨機応変さと柔軟さと頭の回転の速さが、宣孝という人をよく言えば魅力的に、悪く言えば小娘すらたぶらかす女たらしにしていますね。
話を戻しましょう。宣孝は、今回の件で政治的に得をした人間について「右大臣さまであろう。花山院との小競り合いを殊更大事にしたのは右大臣だ。右大臣が女院と手を結び、伊周を追い落とした。前の前の関白の嫡男、中宮の兄でもある伊周を追い落としてしまえば、右大臣の敵はいなくなる」と滔々と語ります。今まで単に不祥事の処罰としてしか見ていなかった事件に、政治的な遠近法を与えられたまひろは、はっとしてしまいます。
宣孝は、興味津々のまひろの表情を確認すると「女院も子を宿さぬのに、帝の心をとらえて離さない中宮が気に食わない。これは右大臣と女院による謀やもしれん」と続けます。この宣孝の台詞が興味深いのは、詮子がかなりの重病との噂が、都中にまことしやかに知れ渡っているということです。本当は仮病にもかかわらず、流れているということは、詮子側でそうした噂を流したことが察せられます。
一方で、土御門殿での呪詛の噂は立っていないようです。つまり、前回note記事で確認したように、やはり女院の土御門殿での企ては、倫子がきっちり内々で片を付け、外に漏らさぬようにしたのだということが、宣孝の話からわかるのですね。さすがは、倫子です。無論、まひろはそんなことまで知る由もありません。
事件の核心に迫るような推論に、まひろはゴクリと息を飲みます。勿論、これは世間に流れる噂の数々を総合して、宣孝が考えたものに過ぎず、現実はそう単純ではないことを視聴者は知っています。しかし、その理にかなった内容は、おそらく都の貴族たちの中でも思いつくであろうことだということです。そして、現在も長徳の変の通説として言われる説でもあります。つまり、道長は、こうした自身に対する悪評も、それがたとえ根も葉もないものであったとしても、自身の政の反動として受け止めなければならないのですね。先の道長の覚悟の表情が、より重いものとなってきますね。
そして、道長&女院黒幕説を聞いたまひろもまた、その説得力に、優しい、大らかなあの人が政のために人を陥れるのだろうかと疑念を抱きます。そして、自分の権勢のために、一人の女性を出家に追い込んで平気でいられるのだろうかと。道長を知る彼女は、遠くにあった長徳の変が急速に自分事として迫ってきます。自分との約束の果てに、道長が権謀術策だけの非情な政治家となったのであれば、それは自分の問題だからです。まひろの心は千々に乱れたでしょう。
ただ、この話、当の宣孝は、あくまで政治好きなまひろを喜ばせるための与太話として振っています(苦笑)ですから、「どうだ?こういう真面目な話ならよかろう」と真面目な話もできる自分をアピールして、ドヤ顔をするのですね。
(2)伊周に引導を渡す貴子と定子
定子落飾と帝の心痛に、それぞれ責任を感じる道長と実資は、探索を続けますが伊周の行方は要として知れません。あまりに見つからないことから、灯台下暗し、「二条邸にこっそり戻っておるやも」と気づいた道長は、実資の要望どおり帝の許可を取ると、実資に二条邸の再探索を命じます。
実資たち検非違使たちが土足で二条邸を探して回るのを、御簾のうちにいる定子は超然と、貴子は渋い顔をして耐えています。ききょうは不安げです。この様子に、「探さずともここにおる」と現れた伊周は、不精髭に裹頭(かとう)装束(武蔵坊弁慶が付けている頭巾ですね)といういで立ちです。逃げ回っていたせいか、やややつれた雰囲気はあるものの、物言いが偉そうであるのはかわりません。
「出家したゆえ任地には赴けん。その旨、帝にそうお伝えせよ」と、傲然と言い放ち、あくまでここを動かない宣言をします。その言葉に御簾の中の貴子は、この期に及んでの言い訳に情けない顔をしますが言葉にはしません。定子の表情には何も浮かんでいません。
さて、いつもの傲岸不遜の伊周を一瞥した実資は、まったく動じることもなく「伊周どの、被りものを取られよ」と返します。実資は、追いつめられたときの傲岸は、虚勢であると看破したのですね。そもそも恫喝しか術がなく、腹芸のできない伊周は、すぐに狼狽えます。その様子にあからさまな侮蔑の色を目に浮かべた実資は「取られよ…取られよ!」と一喝します。
すると伊周、「うるさーい!」と翻ると、見栄も外聞もなく逃げ出します。難なく捕らえられた伊周は見苦しく「止めろ!離せ!」とジタバタとするばかり。あまりの往生際の悪さに呆れ果てる実資の心中、察するに余りあります。帝の心痛、中宮の無念に心を痛めながら、悲壮な覚悟で実資は、この任に当たっているのですから。
相変わらず、自分のことしか考えていない伊周は、蔑む実資の目も意に介さず、この期に及んでも「これから剃髪するゆえ。任地には赴けん。帝にそうお伝えせよ」と上から目線で命じようとします。最早、彼は内大臣でもなく、ただただ、中関白家という家柄にのみすがり、とにかく都に留まろうと時間稼ぎをし始めます。
そこへ、それまで静かに黙っていた定子が御簾の奥から「見苦しゅうございますよ、兄上!」と一喝します。定子の言葉に目を閉じ、「致し方なし」との表情をする貴子も覚悟を決めたようですね。常に兄を立て、決して不必要な反論をしなかった定子の強い物言いに驚くのは、ききょうのほうでした。そして、穏やかでありながらも、反駁を許さない強い調子で「この上は帝の命に速やかにお従いくださいませ」と突き放します。
実は、定子は、前回も同じ台詞で伊周を説得しようとして跳ねのけられているのですが、前回のそれは妹としての兄への懇願でした。しかし、今回の実資たちを前にして言い放つこの言葉は、同じ文言でも中宮の公的な命としての発言なのです。定子は中宮として、臣下である伊周に引導を渡したのです。
それは、他ならぬ中関白家の栄華を支えた中宮の言葉によって、その実家、中関白家が権勢の命脈を断たれたことを意味します。出家により、既に生きながら死んでいるも同然という心境の定子が、気持ちを振るって、ここまで決定的な終焉を告げなければならなかった心中を思うと、ますます居たたまれませんね。貴子も、娘にここまでさせてしまったことを恥じているでしょう。
中宮の命に勢いを得た実資は「直ちに大宰府に向けてご出立を。お連れいたせ!」と命じますが、それでも「嫌だ嫌だ嫌だー」と転げまわる伊周は、駄々をこね続けます。幼児のワガママに等しいその態度に誰もが呆れかえる中、伊周は「私はここを離れるわけにはいかぬ…亡き父上に誓ったのだ、私が我が家を守ると!」と泣きながら主張します。
この言葉が虚しいのは、我が「家」を守るために伊周が何もしてはいないからです。その是非はともかく、専横によって中関白家の権勢を盤石にしようとした父のような工作も、中関白家の権勢をソフトに裏から支えようとした貴子のサロン計画も、後宮を掌握し、中関白家を帝に近い関係性にした定子の心遣いも、中関白家を支えた諸事は伊周によるものではありません。伊周は、これらを当然のものとして享受し、傲慢に振る舞ったに過ぎません。人望を得る、政で成果を出すといった地道な行いにも、真剣ではありませんでした。
都を離れたがらない彼の我が「家」への愛着とは、結局、自分を守るゆりかごとしての中関白家への幼稚なものでしかありません。この情けなさ、それでいながら駄々をこねるような「家」への愛着…嫡男のあまりの心の幼さを目の当たりにした貴子は、自らの施した教育の誤りを悟ったのでしょう。後に彼女は輿のなかで、伊周に「私がそなたに多くを背負わせてしまったのよね」と述べ、彼女は文武を施すあまりに、彼の心の成長を見なかったことを悔いています。この場も、涙を流しながら「私が行かせる」と進み出たのは、甘やかした母としての責任を取ろうとしたのでしょうね。
御簾から出て、ひっくり返る伊周に「伊周、もうよい」と優しげに語ると、彼のもとに座ると「母も共に参るゆえ、大宰府に出立いたそう」と笑顔で促します。元々、お母さん子の匂いを見せていた伊周は、ようやく落ち着き、素直に従います。
貴子の振る舞い、どこまでも、甘やかしていると言われれば、それまでですが、事ここに及んで、伊周の心の最後の砦である母が、しっかりなさいと突き放したところで、今は逆効果です。宥めすかして、命に従わせるしかないのです。せめて、ついていくことで今度こそ立ち直らせたいという親心もあるのやもしれません。
ともあれ、こうして中関白家で最後まで道長たちに抵抗していた伊周は、中関白家を支えてきた女性二人に引導を渡される形で捕らえられ、配流に処されます。この顛末は、中関白家の栄華が、いかに女性たちによって支えられてきたかを象徴している点で興味深いですね。「光る君へ」の政では、女性たちの比重が極めて高いからこそ、こうした展開になるのだと思われます。
さて、母と共に太宰府へ行くということは、かえって帝の怒りを増幅します。実資が既に「伊周は母を伴って、配流先へ出立いたしました」と言うのを、「許さぬ。ただちに引き離せ」と、それを追いかけてまで引きはがせと命じます。一条帝からすれば、「都に止まるために愚かなことを」して、朝廷を愚弄し、中宮を出家させた挙句、母親に甘え切って配流先まで行く伊周の態度には、どこにも反省の色はなく、罪の意識もないことが窺えます。許せるものではないのです。
命に従おうとせず最後まで抵抗した罪人に厳しくせよという命は理に適っていますが、そこには多分に怒りが強く混ざっています。これまで信頼し、一度は関白に任じようとすら思っただけに、可愛さ余って憎さ百倍というのもあるでしょう。
しかし、道長も実資も、この帝の怒りの命に粛々と従います。人一倍苦しんだ一条帝の御心を収めるのも、政の一部だからです。ただ、本来、ここは検非違使別当である実資が行けば済むことですが、責任を感じる道長は、これに同行します。どんなにつらい結末が待とうとも、それが自分の政、自分の無力の結果です。目を逸らすことなく見届けなければならない。冒頭シーンの御前で見せた道長の覚悟は、この場面でも窺えます。
そして、嫌がる貴子、伊周、母子を輿から引きずり出すと、強制的に別れさせます。このとき、母を庇う伊周はともかく、貴子の「どうかどうかお許しを。定子も出家して、私にはこの子しかおりませぬ。どうか…どうか」という、なりふり構わない懇願が哀しいですね。冒頭の定子の落飾の際に見せた絶叫が、どれほどの心痛と衝撃であったかを窺わせます。
二人は、馬を降りてきた道長に、なおも「右大臣どの…頼む、見逃してくれ」「お助けください、右大臣さま」と涙ながらに訴えますが、道長は彼らを静かに見下ろすだけで、一言も発することはありません。検非違使らが貴子を引き戻し、伊周を馬に乗せて改めて下向させようとすることにも口を出さず、ただただ目の前の無残な母子の別れ(それは今生の別れなのですが)を沈鬱な表情で見届けるのみです。
興味深いには粛々と命をこなす実資も、貴子の哀れな様子には思うところがあるのか、何とも言えない戸惑い、困惑の表情を浮かべています。罪人である伊周の配流は職務のうちのことですから、そこに特別な感情はありませんが、すべての子から引き剥がされた貴子には何の咎もありません。その彼女がここまでの苦痛と哀しみを背負うことになるのは、人として居たたまれなくなるのは当然でしょう。結局、伊周に引導を渡した罪なき定子と貴子が、この事件でもっとも心を痛めることになるというのは、理不尽とも言えます。
道長にとって伊周は、その性格ゆえに難物ではあっても嫌っていたわけではありません。貴子にいたっては、若い頃は自分を可愛がってくれた賢い義姉でした。疎遠になっていたとはいえ、敬意を抱いていたでしょう。そもそも、政治的に対立した兄、道隆も元々は仲良くしていたのです。伊周がどれだけ道長を不倶戴天と見なそうとも、道長自身には、中関白家を敵視する、恨む気持ちはありませんでしたし、まして排斥など考えてもいなかったのです。
しかし、両者のおかれた立場は、結局、政争を生み、彼らを排斥するという結果をもたらしました。それは、盤石の道長政権の誕生を意味します。自分の気持ちを無視して進んでいく、政権争いの力学の恐ろしさを目の当たりにしたのも、今回の道長が知った沈鬱な現実でしょう。
帝は、自身の心中を察し、身を粉にしてくれた道長と実資に「此度の騒ぎにおける働きまことに見事であった」と労います。その仕事が心中穏やかざるものであったことは、帝にもよくわかっています。自分にかわって、苦難を引き受けてくれたことへの謝意もあるのです。だから、実資を中納言とし、望みどおり別当を解任し、そして右大臣道長は左大臣へと昇進します。長らく続く、道長の内覧左大臣時代が、いよいよ到来します。これこそが、先に述べた盤石の道長政権の誕生です。
しかし、実資は道長のその表情が明るいものではないことを察し、「浮かないお顔ですな」と心配します。道長は「お上の恩寵を賜ったのだ。そのような顔はしておらん」と、無理に笑顔をつくって返します。実資だけは、このたびの政変が道長政権の盤石を意味しながら、それは道長の意図することではないことに気づいたのでしょう。左大臣になり、かえって中関白家の諸氏への憐憫を強めたことでしょう。
道長の返答に、そうした複雑な胸中を思い遣った実資は「左様でございますか、気のせいでございました、気のせい、気のせい」と気を利かせて去っていきます。実資の気遣いをありがたく思いながらも、道長の遣り切れない、寂しい顔は印象的ですね。彼は、自分の進む道が思っていた以上に孤独で大変であることを改めて実感したのです。
(3)詮子を牽制する倫子
さて、4月の長徳の変からしばらく経ち、道長が左大臣に昇進する少し前の夏、二条邸が火事に見舞われます。前の前の関白である道隆が亡くなり、それから1年も経たぬうちにその子どもたちが内裏から去り、一気に凋落した中関白家の二条邸は、それだけで飽き足らず、最後には火事にも見舞われます。踏んだり蹴ったりとはこのことですね。
土御門殿では、夜半に起きてきた詮子が、その火事を物憂げに眺めています。その姿を遠巻きに認めた倫子は、怪訝そうな顔をしながら詮子に近づくと、その相手をします。詮子はしみじみと「道隆の兄上は己の命が短いことを悟っておられたのかしら?定子を中宮にするのを急ぎ、伊周らの昇進を急がれた。今日のこの哀しい有り様は、兄上の焦りから始まっているような気がする」と中関白家の凋落は、道隆自らがそうしてしまったのかもしれないと、しみじみと言い出します。
詮子の指摘は、ある意味では慧眼です。道隆は最初から独善的でしたが、それが専横としてはっきりと公卿らの目に映り、人望を失うきっかけとなったのは、定子の中宮擁立でした。このときから陣定を無視するようになりましたからね。人事も縁故採用ばかり。そして、自らの体調不良が鮮明になって後は、強引な伊周の昇進を推し進めようとしていました。この点については、以前のnote記事でも道隆の根底にあるのは、怯えと焦りと指摘しましたが、劇中でも詮子によって言及されることになりましたね。
もっとも、道隆政権が長くないことは、晴明が予見していました(第14回)ものの、道隆がその短命に自覚的であったかどうかはわかりません。ただ、彼の強引さは二つの面があるでしょう。一つは、後継者として純粋培養された彼は、父兼家の強引な手法という外形だけを真似ることしか知らず、根回しをするなど政治工作ができる人間ではなかったということです。そして、もう一つ、彼は不測の事態に弱いタイプでした。どちらかと言えば風流人であり政治家ではありませんでした。そんな彼が、偉大な父のように政権を維持するためには、強引さと盤石さに頼る以外になかったのでしょう。
結局、為政者としては、兼家の劣化コピーにしかなれなかった道隆は、雑な政権運営と縁故優先の人事で政そのものを弱体化させてしまったのです。焦りと怯えは、道隆の資質と大きくかかわりますが、一方でそうでなくても時間の問題だったかもしれません。
さて、倫子は、詮子の指摘には応えず、「一度に伊周さま、隆家さま、中宮さまを失った貴子さまは、お気の毒でございますね」と、道隆の嫡妻に思いを馳せます。これは、この前の場面が、貴子が伊周と引き離された場面を受けてのことですが、なかなか意味深だと思います。道長が、その様子を語ったのかもしれませが、好きな殿御のために「家」を支えんと努力した女性の人生だからこそ、今、道長を支えようよとする倫子はそこに注目するのですね。
「光る君へ」の中関白家の描写で当初から特徴的だったのは、高階貴子の賢妻ぶり、名参謀ぶりでした。元来、兼家が期待するほどには政治家に向いてはいない道隆を、将来、政の頂点とすべく、嫁いだときから要所、要所で働いたのが貴子です。「光る君へ」は、高階貴子を中関白家の中心人物としてクローズアップしてくれたところが興味深いのです。
中関白家の栄華は、おそらく道隆が病に倒れなければ、しばらく続いていたはずです。また、道隆が倒れて弱体化したにもかかわらず、詮子がその存在を潰さなければならないと危惧したのが中関白家の権勢です。道隆はその専横によって、嫡男伊周はその横柄な態度で、人心を失っていたにもかかわらず、そこまでになったのは貴子の献身によるところが大きいと言えるでしょう。
例えば、定子を後宮を掌握できるほどの才覚に厳しく育て上げたも貴子ですし、道隆の専横への不満を和らげ、若い貴族を味方につけるため登華殿を最先端の文化サロンとしたのも貴子のアイデアでした。今回、最後に伊周に引導を渡したのが、貴子でしたが、それは当然だったと言えます。貴子こそが、中関白家を雅の一族として作ったからです。
高階家は家格も高いわけではなく、裕福ではありません。そんな彼女の家に、彼女に惚れたというだけで婿入りしてくれたのが、最高の名家の嫡男だった道隆です。彼女が自分に惚れてくれた、好いた殿御に恥をかかせないため、全力を尽くしたことは想像に難くありません。あんな家に婿入りしたから、道隆は出世できなかったのだと言われることは避けなければなりません。彼女にあるのは、漢籍すらできる学才だけです。だからこそ、知恵を絞って中関白家を盛り立てたのです。
結果から言えば、夫を立てるあまり、その専横に疑問を持たない、嫡男を甘やかし、家を滅ぼすきっかけを作るような子にしてしまったなど失敗や問題はあったのでしょう。しかし、生涯をかけて、努力してきた結果、夫を病で失い、それから1年も経たぬうちに子どもたち全員を失うことになるのは、あまりと言えばあまりです。
道長と実資も彼女には同情的でしたが、やはり倫子がこうして彼女の心中を慮ることには意味があるでしょう。彼女の哀れさに目を向けつつ、自分は違う遣り方で道長を支えていこうと考えるからです。貴子の生き方は、倫子のなかで発展的に受け継がれる面があるのでしょう。それは、息子たちの処分後、心労からこの年のうちに亡くなっています貴子への手向けともなりますね。
さて、倫子の言葉に「先のことは…わからぬのう」と真顔で応じる詮子には、道隆の二の轍を踏まないよう、それでいながら自身の思う盤石の政治体制を築こうとする野心が見え隠れします。そして、その構想に道長が含まれていることは間違いありません。
そして、呪詛が彼女の自作自演と看破した倫子が、詮子の言葉の含みに気づかないはずがありません。そこで、倫子はいずれ一計を案じねばと、このとき思ったようです。
長徳の変から半年近くの頃、土御門殿の詮子の居室では、道長と倫子を前に詮子が、定子に代わるお后候補の選定について、道長を詰問しています。未だ定子に心惹かれる帝の心中はさておいても、遅かれ早かれ、その血筋を残すことは皇族の常の問題ですから、それ自体は仕方のないところです。しかし、隠し切れない喜々とした様子には、定子の出家を内心喜ぶような気持ちがあるのは明らかでしょう。
道長は、右大臣藤原顕光の娘、元子の名をあげます。「よいではないか!それにしなさい」と飛びつくのは、顕光の嫡妻である盛子内親王が村上帝の娘だからです。彼女は「義子も定子も、それよりずーっと尊い生まれ。帝のお子を生むにはうってつけだわ」と喜色満面です。皇族ですから、高貴な身に連なるほうがよいわけです。因みに義子というのは、大納言藤原公季の娘で、長徳の変から3か月後に入内した女御です。
その喜色満面に突如、うふふふふと倫子が忍び笑いをし始めます。あまりに朗らかな笑いに訝しむ詮子に「女院さまがあまりにお元気になられましたので」と寿ぐがごとく言います。ああ、そんなことかと見た詮子は「もう呪詛されてはおらぬゆえ」と破顔します。すると、倫子、「あの呪詛は不思議なことにございましたね」と道長や詮子の顔を窺うように、半年前のことを蒸し返します。「ん?」となる二人に、倫子は事もなげに「女院さまと殿のお父上は仮病がお得意であったとか」と、また艶やかに笑い出します。
この言葉にぎょっとして、顔が完全に凍りついたのが詮子です。倫子は暗に、「あの病は、兼家がしたことを真似た仮病」「呪詛は詮子の自作自演」と仄めかしているのですから、詮子は、何故、呪詛騒ぎが土御門殿で内々に収められたのか、その理由が倫子に見抜かれていたからだということを、今更突きつけられたのですね。あの策は、倫子をなめてかかったものでしたから、今の一言は、意趣返しです。
呪詛を内々で収めた件は道長も納得ずくのことでしたが、さすがの道長も「今、それを言うのか」と驚きのまま、固まっています。ただ、道長の驚きは、詮子に怯まない倫子の度胸と腹芸に対してのものもあると思います。彼女は狙って、詮子を牽制したのですから。あの呪詛は、危うい陰謀にその意思のない道長自身を巻き込む危険なものでした。殊更、騒ぎ立てることは道長が、伊周失脚の黒幕と言いふらすようなものです。そうでなくても、その噂は立つというのに火に油を注がれては迷惑です。
そして、土御門殿を、道長が安心して政に専念できるようにするための憩いと安らぎの場とすることが、母から受け継いだ倫子の大臣の妻としての役割です。放っておけば、これから先も詮子は隙を見ては、この屋敷で道長を陰謀に巻き込みかねません。ですから、この屋敷で勝手なことはするなよ、お見通しなんだよ、と釘を刺すことは、道長を守るためにも必須なのです。
当然、時期も見計らっていたはずです。彼女が自身の企てた陰謀のことを忘れかけている、つまり警戒心が解けている時期を選んでいます。また、人というのは絶頂期こそ、一番油断しているときです。息子の后を思いどおりにできると喜々としている今こそ、無防備というものです。そして、きちんと夫の前で宣言しておくことで、妙な暗闘にせず、このことを屋敷内の公認としておけます。笑顔の裏で、そこまで完璧な計算がなされた上での攻撃なのですね。
思わぬ一撃を食らった詮子は、わざとらしい笑いを浮かべながら「産み月が近く、気が立っているようだ。労っておやり」と気遣う言葉でタジタジになっているのがよいですね。何を言うのかしら、というふりをしつつも、今後は気をつけようと心から誓っているはずです。
女たちの腹芸の緊張感に耐えかねた道長が、詮子の言葉に「はっ!」と力強く最敬礼する返事をしているのが、また最高です。当然、本当の最敬礼の相手は倫子です(笑)二人を驚かせて、してやったりの倫子は「うふふふふふふふ」と笑いが止まりません。
いやはや、道長の嫡妻は、やはり倫子しかいませんね。この胆力、機転、腹芸、政治家の妻たるすべてを兼ね備えた完璧超人です。空気の読めないまひろがまかり間違って嫡妻になってもこうはいきません。頭でっかちでコンプレックスの彼女だと、貴子型の支え方しかできないでしょうし。それにしても、道長はゆめゆめ忘れないことです。男の権勢なぞは、女性たちの支えがあってこそであり、奢ることがあってはならないということを。それを忘れたとき、彼は兼家や道隆と同じ道を歩むことになるでしょう。実際、彼の栄華は、倫子という嫡妻と彰子という娘あってのものですし。
(4)女性たちの絆が後押しした「枕草子」
ところで、定子の落飾に最も衝撃を受けたのは三人です。まずは母である貴子です。そして、次に夫である一条帝です。そして三人目が、定子を人生の生き甲斐と定めたききょう、清少納言です。心ここにあらずの状態でただ庭を眺めている尼髪の定子のもとへ「少納言が参りました」との知らせが来ますが、にべもなく「帰せ」との返事。それを予測していたのでしょう。ききょうは、「帰りませぬ」とズカズカと定子の御前に進み出ると、「あのとき、里に下がったのは間違いでございました」と沈鬱な表情で後悔の思いを告げます。そして、改めて居住まいを正すと「どうか再び私を側にお置きくださいませ」と懇願します。
当然のように、定子はまったくの無表情のまま「ならぬ、私は既に生きながら死んだ身である」とのみ。これは、ききょうを巻き込みたくない気遣いよりも、すべてが虚しくなり、自分の憂いさえも持て余す今の彼女には他人を構う余裕がない、煩わしい、放っておいてほしいという捨て鉢な思いのほうが強く出ていると思われます。本来の定子は、鷹揚で心遣いのある人ですが、追いつめられ、ボロボロになったときは、どうにもできないものです。
しかし、こうした定子の言葉が返ってくることは、ここに来るまでにわかっていたのでしょう。ききょうはまったく怯まず「何がどうあろうとも、私は中宮さまのお側におらねばと思い、覚悟を決めてまいりました」と強い決意をその目にみなぎらせます。ききょうは、傷心という言葉では足りないほどにボロボロになった推しの姿を見て、寧ろ、今こそ、ここにいなければならないと闘志が湧いてきたのではないでしょうか。「命あるかぎり、私は中宮さまのお傍を離れません。ご命とあれば、私も髪を下ろします!」となおも追いすがります。
引かない清少納言に、いらっとした定子は「ならん、下がれ」と語気を強めますが、それが心身共に病み切った身体によくなかったのでしょう。ききょうの腕へと倒れ込んでしまいます。
おそらく倒れた定子の面倒をみるうちになし崩し的に、ききょうはまた清少納言として定子の傍にいることになったのでしょう。どんなに「下がれ」と言っても帰らないききょうに、元々、無気力な定子は抵抗するのも面倒くさくなったのでしょうね。ですから、彼女が傍に控えるようになったからといって、定子の表情が晴れることはありません。
伊周に引導を渡した際に、つわりが起き、実は懐妊していることにききょうは気づきますが、それでも定子は無関心です。かの二条邸の火事の折も、燃え盛る炎の中、駆けつけたききょうに「お前だけ逃げよ、私はここで死ぬ」と、迫る炎にすら恐れる気配がありません。寧ろ、そのときを待っていたような口ぶりです。
「生きていても虚しいだけだ。私はもうよい…もうよいのだ」と寂しく微笑む彼女の心にあるのは…おそらく一条帝なのかもしれません。彼との穏やかで楽しい日々だけが、彼女の支えだったのでしょう。しかし、一条帝からは見放され、彼女自身も自棄になって落飾してしまい、もう二度と会うことはできません。生きていくための支えがないのです。
まったく生きる気力のない定子に「お腹の御子のため、中宮さまはお生きにならねばなりませぬ。生きねばなりませぬ」と繰り返すききょうの必死さが空回りしているのが哀しいですね。自身の生き甲斐のために、我が子を置いて出てきたききょうが、「御子のために生きよ」というのは、どんな手段をもってしても、彼女に生きる気持ちを抱いてほしいからでしょう。まして、愛する帝との間の子であれば、「推しの子」。尚更ないがしろにしてはいけません。
しかし、ここまでの出来事があっても、憔悴しきった定子の心は何一つ癒されることもなく、ただただ時間だけが無為に過ぎていきます。思いあぐねたききょうは、突拍子もない思いつきでいつもききょうを驚かせるまひろに相談にいきます(まあ、友達が少ないききょうが愚痴でも話せるのはまひろしかいないんですが)。事情を包み隠さず話すと、困り果てたように「中宮さまをお元気にするにはどうしたらいいかしら。まひろさまによいお考えはない?」とすがるように聞いてしまいます。聞いたものの、そう簡単に答えが出るはずがないことはききょうもわかっています。戸惑うまひろに、自分から「そうよね…」と自嘲して、話を終わらせようとします。
すると、まひろはふと思いついたように「ききょうさま、以前、中宮さまから高価な紙を賜ったとお話してくださったでしょ?」と言い出します。思いがけないことを聞かれたききょうは、「ええ、伊周さまが帝と中宮さまに献上された紙を」と言いながら、そのときの「帝は司馬遷の「史記」を書き写されたところ、中宮さまが「私は何を書いたらいいのかしら」とお尋ねになった」ことに「枕詞を書かれたらいかがでしょう、と申し上げました」というエピソードを楽しげに話し始めました。ちょっと自慢も混じりつつ、うっとりと思い出を語るききょうの口ぶりは、まさに「枕草子」のそれですね。ファーストサマーウイカさんの声質と語調がまた心地よいのですね。
オチまで聞いたところで、まひろはすかさず「「史記」が敷物だから、枕ですか?」とそのこころを聞き返します。さすがの機転に「よくお分かりだこと。そうしましたら、中宮さまが大層、面白がられて、その紙を私にくださったのです」と笑うききょう。こういう打てば響く会話ができるから、ききょうはまひろが大切な友なのですね。
するとまひろは「でしたら、その紙に中宮さまのために何かお書きになってみたら良いのでは?」と提案をします。「え?」と驚くききょうに「帝は司馬遷の「史記」だから、ききょうさまは春夏秋冬の四季とか」といたずらっぽく笑います。機転の利いた言葉に「まひろさま…言葉遊びがお上手なのね」と感心すると、二人は通じ合ったように忍び笑いをします。この会話で、それも面白いかもとききょうに思わせたのですね。
この「枕草子」成立にまひろが一枚噛んでいたという、「光る君へ」オリジナルの解釈。「枕草子」をこよなく愛する方のなかには拒否反応を示す方もいらっしゃるような気がします。清少納言の純然たる創作意欲であるべきだと思う人たちにとって、余計な邪念が入ることは汚されるような気がするのかもしれません。
ただ、このシーンはそう単純ではないように思われます。たしかにまひろとのたわいない会話が、ききょうの書こうという気持ちに影響を与えたという描かれ方ですが、そもそも、誰かのために「何かお書きになってみたら良いのでは?」という発想自体、本作では、まひろのオリジナルではありません。
「書くこと」に関するまひろの軌跡を確認してみましょう。まひろが誰かのためにものを書いたのは、若い頃の代筆業が最初ですが、彼女はここで技術だけ優れた和歌を書き、失敗します。相手を知り、思う真心が伴わなければ人の心は動かせないことを、まひろは市井の女性の心から学びます。次に書いたのは、直秀たち散楽師の散楽のシナリオです。生活が苦しいがゆえに人々は笑いを求める…直秀からはそれを学び、人々の笑う様子に彼女自身もまた心動かされました。人から学ぶばかりが、 まひろの「書くこと」なのです。
道長とのやり取りでは言葉だけでは伝わり切らない思いを知りました。そして、哀しい恋を経た後、石山寺で道綱の母、寧子と出会ったことは、彼女の心にこれまでの「書くこと」を総括するように深く刻まれます。寧子は、まひろに「私は日記を書くことで、己の哀しみを救いました」と伝えます。抱えきれない悩みに苦しむまひろにとって、それは天啓のように刻まれます。
そして、親友さわからは、まひろの心づくしの文を書写することで、まひろの心に近づこうとし、自分を救ったと教えられました。自分の書いたものが、自分の意図を越えて人を救うこともある。このこともまた彼女にとっては衝撃的でした。何故なら、一人の女性の思いが、「書くこと」を通じて連なっていくからです。
日々の生活、社会、身分、さまざまなことで哀しい思いをする女性たちを見てきたまひろは、そんな女性たちが書くことで癒され、書いたもので癒され、言葉をとおして思いがつながっていくという事実に、大きな可能性を感じたのですね。このように見ていくと、誰かのために「何かお書きになってみたら良いのでは?」という提案は、それによって実際に救われ、言葉を通じてつながっていく女性たちの思いが、まひろに言わせている言葉だということが見えてきます。
今、そこにいるのは悩めるききょうです。そして、その先にいるのは憔悴しきった定子です。ききょうが定子を元気にしたい、その切なる願いを、女性たちの思いがほんの少しだけ背中を後押しした。それがまひろとききょうのやり取りなのではないでしょうか。
あくまでききょうの定子への熱い思いと書く意志が大切です。まひろの言葉は補助に過ぎません。だから、白紙に向かうききょうが、清少納言として筆を執る決意をするまでをたっぷり見せた上で「春はあけぼの~」の美しい文字が、紙に踊るのですね。
定子のためだけに書き上げたそれは、ただ眠る定子の御簾へそっと差し入れられます。定子は、少納言の気配に気づきますが、何も言わず、見向きもすることなく、また眠ります。しかし、少納言が定子を思い、定子たちと過ごした思い出を追憶していく「春はあけぼの」の言葉は、桜を舞い込ませます。彼女の真心の籠った言葉が、春を呼ぶ…その想像力が文学の力でしょう。
定子は変わりませんが、いつか彼女が起きたときのため、少納言は次々と書いていきます。彼女が自分の連ねる言葉の力を実感するのが、「夏は夜。月のころはさらなり。やみもなほ、蛍の多く飛びちがひたる」のくだりを書くところです。少納言はふと気づきます、部屋にも外にも蛍がところ狭しと現れ、彼女の周りを幻想的に彩ります。こうなると、彼女自身も書くことで救われていくのだろうと思われます。
そして、蛍は書を差し入れられた定子のもとにも…そして、ふと定子は起き上がります。
月日は経ち、紅葉深くなる秋のある日、食事の用意をもって歩く清少納言は、主が自身の書いたものを静かに穏やかに読む姿を目撃します。このシーンで大切なことは、定子の独白で「春はあけぼの」が読まれることですね。書くことで救われ、書いたものを読むことで救われる…このつながりこそが、まひろの…いや「光る君へ」での「書くこと」の意味なのですから。
そして、そんな定子の姿を目撃した、清少納言が嗚咽を抑えて、震える姿をシルエットでロング捉えるカメラワークが絶妙ですね。そして、何事もないようにいつもどおりに中宮定子のもとに来た清少納言は、起きた(蘇りかけた)定子に深々と礼をします。この瞬間、主と女房、身分を越えた女同士、親友、書き手と読者、定子と清少納言の間にあるさまざまな関係性のすべてが凝縮されていきます。再び、二人は心からつながりあったのですね。
そんな二人のシルエットをロングで捉えた映像に「たった一人の哀しき中宮のために、「枕草子」は書き始められた」とのナレーションが入るのが美しいですね。中宮定子の哀しみを救い、主を思う清少納言の苦しみを救い、二人を固くつなげた「枕草子」は、やがて時代も場所も超えて、多くの女性たちの思いを救い、つなげていくことになります。まさに文学の力が体現された、「枕草子」の誕生だったのではないでしょうか。
2.新しい道へ進むためのまひろの選択
(1)出立前日の為時家の幸福
越前へ出立前の為時は、まひろの目にもわかるほどに顔色が冴えません。その原因は、道長に呼び出され、言い渡された重大な命令のためです。道長は呼び出した為時が、気を遣ってまひろの話をすることにも顔色を変えず、世間話もそこそこに呼び出した理由について切り出します。まひろの話に反応しないだけでも、この件がただ事ではないことがわかります。
道長の話の要諦は「越前の松原客館に留め置いてある、商いを望む宋人70余名に博多以外では交易には応じないことを言い含め、彼らを穏便に帰国させる」ことです。越前の敦賀(「どうする家康」で出てきた金ヶ崎城のあった地域)は、平安中期までは渤海との交易で栄えたところで、宋人との交易も可能な場所です。
にもかかわらず、朝廷がそれを拒絶するのは、異国人たちを警戒するからです。道長曰く、「越前と都は近い。都に乗り込む足掛かりとなることも考えられる。彼らは商人だなどと言っておるが、証拠はない。70人がまとまってやってくるというのも、妙ではないか。彼らは商人とは偽り、真は官人、それどころか戦人であるやもしれん」と。
つまり、宋人は貿易にかこつけて、越前を日本侵略の橋頭保にするのではないか、あるいは海賊行為を行うのではないかと、その可能性を危惧しているのです。第18回、宋人が多く訪れた件で陣定(じんのさだめ)全体に動揺が走ったのは、このことだったようですね。
894年に遣唐使を廃止して以降、半鎖国状態になった日本は国交には積極的ではなく、貿易は私貿易として行われていました。それは宋(南宋)の時代になっても変わらず、宋とは正式な国交を開くには至っていません。こうした状況ですから、宋に関する公的な情報があまり多くないと言えるでしょう。宋の対外政策はよくわからないというのが、朝廷の本音と思われます。また、8~11世紀は異国人らの海賊に日本は悩まされてきました。その中心は主に九州沿岸部ですが、それが広がらないとも限らないわけです。このような日本のおかれた状況を考えると、大人数での宋からの渡来に警戒するのも、あながち邪推とは言えないのかもしれません。
とはいえ、国防が絡んだ宋人たちとの交渉となれば、為時にとっては荷が勝ちすぎるのも事実。10年任官から離れており、決して世情に明るいわけでもない。また漢籍に優れ、唐の言葉も話せるとはいえ、独学によるもので、任官から離れていた彼が異国の人々と直接交流はほとんどなかったでしょう。若き頃に宋船に潜り込んだときくらいでしょうか。真面目な為時だけに「知恵の限りを尽くし、一心にその任にあたります」との返答に偽りはありませんが、自分に国家の一大事を担えるのか、との不安と緊張がよぎるでしょう。
それにしても、道長もいきなり、大きな重責を担わせたものです。ですが、このことは、国替えが単に昔の女への情にほだされただけの甘ったるい縁故人事でなかったことを証明していますね。、道長自身も責任を問われることを覚悟し、国難に立ち向かえる有能な人材を送り込む。そういう任官なのです。それゆえに道長は、わざわざ為時を呼び出し、「彼らに開かれた港は博多の津のみと了見させ、穏便に宋に返すこと。これが越前守のもっとも大きな仕事と心得よ」と直接、自身の真意を言い含めたのでしょう。
重大事ゆえに娘にも相談できず、出立前の別れの宴席にそんな話を持ち出すことはできない為時なのです。そうとは知らぬ宣孝は、「行ってしまえば国司は楽な仕事よ、土地の者どもと仲よくやれば、懐も膨らむ一方だ。行けば直る」と、心配顔のまひろに呑気な言葉で返します。私腹を肥やせるぞとのあからさまな宣孝の言葉に、まひろは「また、そのような軽薄な…」と呆れますが、一方で宣孝の「土地の者と仲良くする」は、現地の人々の要望に耳を傾けるということですし、「行けば直る」は、案ずるよりも生むが易しということです。そう考えると、宣孝の物言いは、実は本質を突いているとも言えるでしょう。
宣孝は、為時やまひろのように学問に通じているタイプではありませんが、「光る君へ」の登場人物のなかで最もこの平安社会を謳歌している人物です。それができる裏には、物事の本質を見抜き、割り切る達観した眼差しがあるのでしょう。ですから、彼の言葉や洞察には、それなりに説得力があるのです。前の道長×女院黒幕説にそれなりの理屈があり、道長を知るまひろすら「なるほど」と思わせたのは、そのためです。
ただ、宣孝はこうした才覚は、人生を楽しむためにあるもの。道長×女院黒幕説を話したのも、自分もまんざら捨てたものではないことをまひろに見せたいというだけですし、今回の一面正しい洞察もそれを感じさせることのない軽口にしてしまったのも、ムキになって反論してくるまひろを期待してのことです。まひろとの会話を楽しみたいだけです。
「まひろに叱られた」などと言いながらも、悪びれもせず「父がまだ出立する前から、懐を肥やせ、肥やせと人聞きの悪い。父はそのようなことが誰よりも苦手でございます。そのことは宣孝さまが一番よくご存知ですのに…」と言い返すまひろの苦情を楽しげに聞いています。それを堪能し、芝居がかったように「これはとんだご無礼をつかまつった」と謝るまでがセットです。この言葉で、まひろが言いすぎを照れ笑いをするのを見られますからね。
和んだところで「いつからまひろに叱られる身になったのかの」と笑い返す宣孝の目には真剣なものが混ざっています。この言葉は、「まひろはいつから私を叱ることができるような大人のいい女になったのだろう」の意味ですが、機微に疎いまひろは気づくはずもありません。彼女の自意識の中では、未だ親戚の面白いおじさん枠の中にいるのでしょう。
ただ、恋愛沙汰に目ざとい乳母のいとは「叱られるとき、宣孝さまはいつも嬉しそうに見えますが…」と不思議そうに声をかけます。さすがにいとも、宣孝がまひろを女性として見ているとまでは思っていないようですが、まひろと道長の仲について「女の私ならわかります」「狂いはございません」と豪語したいとだけに、それを察知しただけでも大したものです(笑)
鈍感なまひろは、宣孝の言葉を額面通り、軽口と受け取ると「私も父と越前に行きますので、あちらで宋人に会うのが楽しみでございますぅ」とにっこり笑うと、前回、「船に乗って宋にでも渡りそうな危うさがある」と言われた意趣返しに「宋人のよき殿御を見つけ、宋の国に渡ってしまうやもしれません」と冗談とも本気ともつかないようなことを言い出します。彼女も宣孝の軽口が移ったようになっているところに、前回note記事で触れたように二人の会話に阿吽の呼吸のようなものが通い合っていますね。さらに年月も積み重なっています。
まひろの軽口に、宣孝は「それもいっそ良いかもしれんな」と応じるも「もうお前に叱られんかと思うと…寂しいがのう…」とつい本音が漏れます。つい、熱い視線をまひろに送ってしまう宣孝は、内心慌てているのかもしれません。そして、しばらくは彼女に逢うことができなくなる寂しさを実感してしまったのでしょう。
国司の任期は四年。都に近いとはいうのはあくまで他の国と比べてのことで、越前もまた容易に行ける場所ではありません。伊周の太宰府行ほどの距離ではないにせよ、この頃の地方への旅は、命がけです。ですから、その別れとは、今の単身赴任よりも遥かに重い意味合いを持っています。肥前に旅立つさわが泣いたことが思い出されますね(第18回)。
もっとも、まひろは、いつもと違う寂しげな彼の物言いに「?」という顔をするものの、それまでです。まあ、年の離れた親戚のおじさんのような古くからの知り合いに恋心を抱かれるなど想像もしていないのは仕方のないところ。本作は平安期のため、女性が若すぎる夫婦(例えば実資×婉子は15歳差)も、近親の夫婦(道兼×繁子は甥と叔母)も出てきますが、現代ならキモいの一言で済まされてしまいますから。
ただ、宣孝が本音を気づかれないまま終わったのは、まひろの鈍感だけではなく、そこへ惟規が「本日、文章生になった」との報告をもって現れたからです。彼も越前守となった父が後顧の憂いなく旅立てるように、全力を尽くしたのだと思われます。惟規の家族思い、そして彼の昇進を心から喜ぶ為時一家。為時には赴任地と密命に対する不安はありますが、一方で誰も彼もが自分の越前行を後押ししてくれています。まひろも、惟規も、いとも、乙丸も、宣孝も…そして密命を託した道長も。心おきなく旅立ち、彼らに応えるしかないのです。
こうした中で、「殿様、越前にお供できません」と思い詰めたようにいとが、為時に別れを告げます。彼女は、惟規が文章生になったことを受け、この家に戻る惟規の世話、そして「悪い女に誑かされる」ことを防ぐために、残ることに決めます。彼女が、為時を思っていることは、以前からよく書かれていましたし、嫡妻ちやはが亡くなり、一家を支えるようになってからは、さらに募っていたでしょう。それでも彼女は、「家」を守る自分の役割に生き甲斐を見出すのです。
とはいえ、愛しい殿御との別れ、「四年後のお帰りお待ち申し上げております」との言葉には万感の想いが込められています。先にも述べたように、この頃の旅は命がけ、今生の別れとなりかねないのです。ですから、「無事」のお帰りを祈ることが一番の愛情表現なのです。この言葉に、為時もまた「お前も達者でおれ」と、彼女の健康を願います。
一見、家族も同然の彼女に向けた言葉なのですが、この台詞、後述するまひろと道長の会話と静かに響き合っています。そう考えると、為時といとの間に男女の関係があったのかも、ということが匂わされていることに気がつかされます。はたして真相はわかりませんが。
(2)10年前のあの日の選択を再度選ぶまひろ
さて、越前行のすべてが整ったその夜、まひろは思い詰めたように紙にむかいます。まひろのが都を旅立つ上での心残りはただ一つ。この10年抱えた自分の想いの結果が何であったのかです。それは、自分自身の選択そのものも指しますが、同時にそれは想い人の命運を決める選択でもありました。それが、あの夜に道長との「民を救う」という約束です。名門に生まれた道長は偉くなることで、下級貴族のまひろは自分に見合った生き方として、それをなそうとしたのです。
その約束は、ときには自分の支えとなり、ときには挫折として、彼女の10年間の根幹とになっていました。道長に思いは馳せるものの、まさか道長が覚えているとまでは信じていませんでした。しかし、偶然、悲田院で出会ったことで、道長が未だに自分を想い、自分との約束を果たそうと努力していることを悟ります。それは、彼女のこの10年が無駄でなかったと思わせるものでもあったたでしょう。
そんな道長が政の頂点に立ち、その公正な計らいで為時は官職を得ました。しかし、政敵を陥れた長徳の変の黒幕の一人が道長であるという宣孝の推測は、そんな道長の努力、あるいは彼の性格とは真逆のものです。信じられない気持ちがある一方、この政変で得をしたのが道長と女院であるという理屈も筋が通っています。
ですから、これが真実か否か。そして、万が一、道長の美徳が変質してしまったとしたら、「民を救う」ために努力していたはずの彼がどうして変わってしまったのか、その理由を知らなければなりません。もしも道長が変質したのであれば、それは自分との約束を叶えようと自身を追い詰めたからかもしれないからです。まひろは、自分と道長との約束が、志が、この10年でどういう結果をもたらしたのか、そのことに向き合わなければなりません。
道長の変わらぬ人間性と志に改めて思いを託し新しい道へと進むのか、あるいは道長の変質は自分のせいとの慚愧の念と彼との完全な決別を胸に生きていくのか、どのような結果が待とうと都に半端な思いを残しては旅立てないのですね。意を決したまひろは、筆を取り、道長を呼び出す文をしたためます。
まあ、描かれませんでしたけど、乙丸と百舌彦が、二人を心配しながらもしぶしぶ取り次いだのでしょうね。従者ズも大変です(笑)そして、あれほど倫子に関係がバレることを恐れていたにもかかわらずの大胆な誘いをしたことも驚きですね。それだけ、どうしても確認しなければならなかった、今聞かなければ必ず後悔するという確信もあったのでしょう。
場所は勿論、六条の廃屋です。果たして道長は、妻帯していようとも、10年が経とうとも、左大臣にまで昇りつめようとも、一番愛した女の呼び出しには一も二もなくやってきます。「光る君へ」の藤原道長とは、そういう人です。正直、やってきたという事実だけでも、まひろの疑問の答えになっているのですが、それでは足りません。
何故なら、二人は、何度か出会っているもののきちんとした対話はおろか、挨拶すらまともにしてはいないからです。例えば、疫病の看病(第16回)の際は、道長が一方的にまひろに話し続けただけです。唯一、話す機会があったのは、第18回での廃屋での思わぬ再会でしたが、このとき彼らはそれぞれに「自分の過去」と向き合うためにやってきました。今、現在の相手に会うためではない。まひろは彼の脇をすり抜けて去っていきました。
だから、今夜こそが、10年経ち、後戻りできない現在のお互いと向き合う、本当の意味での再会なのです。しかも、最初で最後になるかもしれない再会です。ですから、10年という時間が、二人に直接のやり取りを要求するのです。
現れた道長の顔は、政務を執る左大臣の顔をしています。そんな道長が、まひろに言える言葉は「父を越前守にしてくださり、ありがとうございました」という御礼です。感謝自体は本心ですが、物言いは他人行儀にならざるを得ません。
まひろの感謝に、道長は「お前が書いた文、帝がお誉めであった」と返します。「まひろ、お前の学才が、父を越前守にしたのだ、俺ではない」と謙遜を言うあたりが、実に道長らしいですね。
これは奥ゆかしいというだけではないでしょう。この数年、まひろは、道長の予想外のところで先回りするようにさまざまな形で現れました。おそらく、そのたびに道長は、自分がまだまひろに敵わない、追いつけていないと思ったのではないでしょうか。そして、今の彼は、長徳の変の結末に気を落としています。自然と返す言葉に、自嘲が混じってしまうと察せられます。
勿論、まひろはそんな道長の思いを察する余裕はありません。それよりも「私が書いたとお分かりになったのですか?!」と、このことです。前回note記事で触れたように、やはりまひろは自分の筆跡に道長が気づくというあざとい計算はなかったようです(笑)
まひろの驚きに、道長はやや軟化した表情になると「お前の字は…わかる」と答えます。「わかる」で、うんと頷く瞬間だけ、いつもの道長の顔になるのは、まひろへの思いが出たからでしょう。一方のまひろは、信じられないと息を飲んでいるのですが、「おいおい、10年前の文を後生大事に持っている男の真心をなめんなよ」とツッコミを入れたくなりますね(笑)ただ、自己肯定感がめちゃくちゃ低いまひろなので、道長のこうしたところに気づけないのは仕方がないところです。
まひろへの変わらぬ想いの断片は見せた道長ですが、まひろが自分を呼び出した意図はわかりませんから、「明日出立だな」と当たり障りのない話題を振りながら、まひろと並ぶ形で廃屋の庭を眺めます。ここからの二人の会話、切り返しショットが何度か使われますが、道長を捉えるカメラのアングルはやや見上げる形で、まひろを捉えるほうはわずかに見下ろすアングルです。これは、二人の視点位置に添うアングルにすることで、見る側に二人の心情に共感させようとしているのだろうと思われます。
わずかに間があった後、まひろは意を決して「最後にお聞きしたいことがあり、文を差し上げました」と切り出します。「なんだ?」とまひろを見もせずに応える道長の構える様子はないものの、感情はなく硬いものです。これから聞かれることに予感があったのかもしれません。
「中宮さまを追い詰めたのは道長さまですか?」との問いは、まひろからだけは聞きたくなかったものでしょう。暗く硬い表情でまひろを見る道長ですが、口火を切った以上まひろは、「小さな騒ぎを殊更、大事にし、伊周さまを追い落としたのも貴方の謀なのですか?」と、宣孝の語った理屈をぶつけてみます。
その問いに「そうだ」と即答し、自分を見つめるまひろに向き直ると「だからなんだ ?」と開き直ったように応じる道長の思いは、哀しいですね。下級貴族の娘であるまひろ、つまり政の末端にすらいない彼女から、長徳の変は道長の起こした謀だと聞いたことは、世間に広まっている自分の評判はそのようなものであると突きつけられたも同然だからです。
一方で、長徳の変を治めはしたものの、その結果、若き帝にもっとしたくない決断をさせ、敬意を抱いた義姉から息子たちと娘を奪い、差配を振るった自分や実資も心を痛めただけです。詮子や斉信のようにほくそ笑む者たちもいるでしょうが、心ならずも多くの無実の者の心を深く傷つけたことだけが、道長の眼前にあった事件の真実です。
そして、それは、自らの政によって起きたことです。その現実も変えられません。先にも述べた通り、道長はこの一件の顛末で、「民を救う」と意気込んだ政の反動が起こるということ、政の負の部分に直面しました。しかし、政は結果です。どんなに自身が深く傷つこうとも、その結果を引き受けて、次の政に進まなければならないのが、為政者の逃げられない役割なのです。
ですから、道長は、この政変で起きた数多の悲劇をすべて自分の政の結果であると、その責任を負う覚悟をしていたのです。ですから、彼は、まひろの問いに「そうだ」と即答するしかなかったのですね。
半ば開き直ったかのような道長の言葉の裏にあるのは、自分の政で起きた悲劇も悪評を甘んじて受けようとする諦めに似た覚悟です。ですから、彼はまひろに向き合って応じたのです。
まひろもまた道長の言葉そのものではなく、自分と向き合うその目、その表情をじっと見つめます。見極めようというような疑いを含むものではなく、ただ静かに。やがて、久しぶりに近くで見つめた愛しいその顔に、変わらぬ優しさ、真摯さ、そしてそれゆえの哀しさを認めたまひろは「なんだ、変わんないじゃない」とばかりに口元に薄く笑みを浮かべます。吉高由里子さんの匙加減が絶妙で決して下品なものにならないのがよいですね。
彼の本質が変わっていないことに安堵したまひろは、表情をわずかに緩め、目を外すと自嘲気味に「つまらぬことを申しました。世間の噂に惑わされ、一時でも貴方を疑ったことを恥じます」と素直に謝ります。そこには安心と、「よりにもよってあの軽薄な男の言葉を信じてしまった」という申し訳なさと、わずかばかり宣孝をなじる気持ちがあったのではないでしょうか。
そして「お顔を見てわかりました。貴方はそういう人ではないと」とはにかむような笑みを浮かべながら、上目遣いに道長を見やります。道長は、まひろが自分の心根を汲んでくれることにほっとしつつも「貴方はそういう人ではない」という言葉には、その政の結果が伴っていない以上、返す言葉に自嘲の色は隠せません。道長にしても、まひろにしても理想が高いだけに、それに反比例するように自己評価は低くなるので、すぐに自嘲しますね(苦笑)似た者同士ゆえにソウルメイトになれるのかもしれませんが。
道長は「似たようなものだ。俺の無力のせいで、誰も彼もすべて不幸になった」と、この政変の顛末について沈鬱な表情を浮かべると、加えて「お前とかわした約束は、未だ何一つ果たせておらん」と口惜しげに、無念と慚愧を語ります。
そんな道長をただだだ見つめるまひろ。「見つめ続けます」…あの日の約束のように。彼が心からの思いを吐露するのを静かに受け入れる彼女ですが、その表情がわずかに動くのは、一つは道長の無力感と苦しみを感じるからでしょう。そして、今一つ、こんなにも彼を悩ませているのが自分のせいであるからです。申し訳ない気持ち、憐れみの両方が彼女の表情からは窺えるように思われます。
話しているうちに、だんだん昔の、本来の様子に戻ってしまった道長は、いよいよ涙目に泣き出しそうな顔になると「これからどこへ向かっていけば良いのか…それも見えぬ」と、将来が不安で不安でたまらないと声を震わせます。
道長は基本的に人前で泣きません。父が亡くなったときは泣きかけていますが、あのときは周りに人はいませんでした。道兼の死に放心したときすら、倫子や詮子に涙を見せてはいません。彼が人目もはばからず号泣したのは、直秀をまひろと二人で埋葬したあのときだけです。声をあげて己を責める道長を、たまらずまひろが泣きながら彼を抱き抱えたシーンが印象に残っている方も多いのではないでしょうか。
道長にとって、自分の感情を露わにして泣くことができる唯一の相手が、まひろなのです。どんな賢妻でもまひろに敵わないのは、この一点です。道長が安心して心を預けられるのはまひろだけです。そこに理屈はありません。強いていうならば、幼い頃に出会い、身分に関係なく付き合えたからでしょう。
泣きかけた道長に、まひろは息を飲みますが、それでも目を反らすことはありません。そんな彼を情けなく思うのではなく、愛おしく高ぶらせるのがまひろです。彼女が道長への想いを自覚したのも、号泣する彼を抱き抱えたあのときですから。
そして、道長は今の自分の無力と至らなさを痛感するのでしょう。「おそらく、俺はあのとき、お前と遠くの国へ逃げて行っても…お前を守りきれなかったであろう」と告げ、お前が正しかったと10年越しに詫びます。やっとまひろの言いたかったことを理解したというところでしょうか。
しかし、道長の心の痛みを静かに受け止めたまひろは、道長の10年が、まひろの無力と挫折の10年と同じであったと知ります。共に歩むまいが、共に歩もうが苦しまねばならない10年だったと言えるでしょう。ですから、「かの地で、貴方と共に滅びるのも良かったのやもしれません」と答えるのは、道長への心遣いだけではなく、強い本心があります。この世は生きるだけでも、辛く哀しい。だとすれば、共に滅ぶことの何が不幸せなのでしょうか。まひろの10年越しの本音なのですね。
妾になってもよいとまでまひろが思い詰めていたことを知らない道長は、まひろの心遣いだけを受け取り、昔の埒もないことを言ったというように話を切ります。
そして「越前の冬は寒いという、身体を厭え」と伝え、まひろも「はい、道長さまもお健やかに」と。気持ちこそ込もっていますが、なんとなく他人行儀なのは、二人は向き合うことをやめ、庭へ目を移しているからです。正確には意識しすぎているだけなのですが。
まひろは盗み見れように道長の横顔を見ています。その横顔には、年を経て、やや精悍になりはしたものの、変わらぬ真摯さ、優しさ、自分としま約束のための努力と苦悩…さまざまなものが畳まれています。そして、そのすべてが、まひろには好ましく愛おしいものです。そして、この10年、月を眺めながら焦がれ尽くしてきたその顔が今そこにあるのです。秘め続けた想いと今、目の前にいる現在の道長への愛おしさ…二つが重なり、想いが溢れたとき、まひろはごく自然に道長の肩に頬をあて寄り添います。
こうされては、道長の想いも堰を切り、まひろを抱き締めるしかありません。
長い前振りの会話の後、ようやく気持ちに正直になり抱き締め合う二人。まひろは太い息を漏らしながら「この10年、貴方を諦めたこと、後悔しながら生きて参りました」と、ずっとずっと秘めてきた思いをごく自然に口にします。
その瞬間、呆けたように口が半開きになる道長の表情がよいですね。道長もまた、ずっと後悔していたはずだからです。あの夜、まひろが去っていくのを引き留められず、思いを断ち切ろうと倫子を抱き、後戻りできなくしてしまった道長。それでよかったのか、との思いを持っていたと察せられます(倫子には超失礼ですが)。ただ、それは、自分だけが勝手に思っている後悔なのだと自嘲していたことでしょう。
しかし、そうではなかった。道長と同じ想いを、まひろもずっと抱いていた。「お前はこの10年、俺のことを思うことはなかったか」…それこそが、道長の聞きたかった本音です。後悔とは本来、哀しいものです。ただ、今夜のそれは、二人の想いの通じ合いを意味するため、喜びでもあります。去来する後悔と嬉しさとがない交ぜになった道長は呆然とするしかありません。
まひろは「妾でもよいから、貴方の側にいたいと願っていたのに、何故あのとき、己の気持ちに従わなかったのか…」と道長の胸のなかさらなる思いをつづると、目を一度つぶった後、「いつもいつもそのことを悔やんでおりました」と、この10年抱え込み続けた思いの丈を告白します。
「左大臣の娘と結婚する」と告げたあの夜、道長は、カッコをつけて「幸せとは思わぬ。されど、地位を得て、まひろの望む世を作るべく、精一杯務めようと胸に誓っておる」と宣言しました。しかし、道長の心のなかで念じていたことは、「妾でもよいといってくれ」でした。本音は、頑張るから、辛い思いをする自分の傍にいてくれだったのですね。10年越しに聞きたかった言葉を聞かされたのです。やっと知りたかったまひろの心に触れることができた今、泣きたいような、ほっとしたような気持ちで、またまた呆然としてしまう道長です。
「つまり、つまり…」と繰り返しながら、肝心の言葉が出てこないまひろの後を紡ぐように、道長は、彼女をしっかり抱きながら、「いつの日も、いつの日もそなたのことを…」と万感の想いを口にし、想いを一つにします。二人はようやく、あの夜、本当は同じ想いであったこと、そしてお互いを想うがゆえに言葉にできず、別れるしかなかったということに思い当たるのです。
しかし、まひろが、10年越しに道長に本当の想いを伝えたのは、昔に戻りたいわけでもなく、やり直したいわけでもありません。二人には、それぞれに過ごした10年があり、その現実は、変えられません。そして、その現実は苦しみ、悩み抜いた結果得たもの、あるいは失ったもので、今の自分にとって無視できないものです。そう、あの日に戻れるはずがないのです。
ただ、あの日抱いた道長への想い、それを振り切ってまでした選択と誓い合った「民を救う」という約束…それがお互いを苦しめ、変質させただけであったのなら。それが怖かったのです。しかし、今、道長を間近で見て、「この10年、貴方を諦めたこと、後悔しながら生き」てきたことが無駄ではなかったこと、正しかったことを確信できたのですね。
だからこそ、自分のこの10年の苦しみをここに置いていくことができる。それがまひろの真意です。まひろは、こうして道長と再会したことで、あの日、自分の気持ちに逆らってまでした選択を再度、する決心を固めることができたのです。
ですから、「今度こそ、越前の地で生まれ変わりたいと願っておりまする」と心からの晴れやかな笑顔で言うことができるのです。10年前、涙をこらえながら絞り出した「私は私らしく自分の生まれてきた意味を探して参ります」は、恋に破れ、生まれてきた意味を見失ってしまった慟哭を強がりで固めた言葉でしかありませんでしたが、今度は違います。
それを聞く道長は、まひろほど簡単ではないでしょう。今なお後ろ髪引かれる思いのままの部分があるように思われます。まあ、大概、男性のほうが女々しいもんですね(笑)しかし、まひろの思いを知り、通じ合えた幸福感があるのも事実。穏やかに「そうか、身体を厭え」と言います。今度の「身体を厭え」は、形式的なそれではなく、遠方に旅立つ想い人に再び逢うこと願う万感の想いです。旅立つ君に向ける最愛を示す言葉は、愛しているではなく、無事に帰ってきてくれですよね。
快く送り出してくれる道長に、彼の変わらぬ自分への愛情が感じられ、まひろの心も高ぶります。越前へ行く機会を作り、送り出してくれる道長への心からの感謝、そして、やはり彼のことが今も愛おしいのだと再確認した思い、その二つが溢れてきたまひろは、もう自分を止められませんでした。彼女、自ら彼を引き寄せると口を重ねるという大胆な行動に出ます。普段、人見知りで気遣いしいのまひろですが、本来の彼女はこの大胆さのほうです。ですから、納得の行動です。
この後、二人がどうしたのかは、ぼかされていますが、視聴者の想像に任されたということでよいでしょう。二人は愛を確かめ、その充実をもって、再び互いの「進むべき道」を行くことにしたということです。まあ、気がかりがあるとすれば、土御門殿で朝帰りした道長が、まあた油断した顔を倫子に見られないかということがありますが、まあ、相手のまひろは既に都にいないから良いのか(笑)
おわりに
道長政権が始まり、古きものが淘汰される中で、新しき政への希望と不安が出そろったのが、長徳の変でした。そうしたなかで、これまでの自分に各々が区切りをつけ、岐路に立たされています。特に政の頂点に立ち、敵のいなくなった道長は、今まで以上に自分を律し、自分の政が起こした結果の清濁と向き合うことになりそうです。まひろとの約束を果たす「民を救う」政は、その初心が貫けるか否かも含めて、ようやくスタートラインに立ったというところです。
前途は多難ですが、一つだけ希望があるとすれば、彼の周りには人がいることです。人望だけが彼の頼みの綱となるでしょう。当然、倫子たち女性たちに支えられていることは忘れないでほしいところです。伊周は、明日の我が身なのですから。
時代が一区切りを迎えた一方、実は、道長とまひろの関係もあの夜の別れから丁度、10年という一区切りとなりました。10年経っての再会と別れ、それはあの夜のような哀しみに満ちたものだけではありませんでした。勿論、二人が夫婦と結ばれることはありませんし、戻ることもできません。そして、あのとき抱いた後悔も消えるどころか深まることもあるでしょう。
しかし、後悔の上に立つあの日の選択、そして、自分の生きてきた苦しい10年を肯定する総括する再会だったのも事実です。思いに一区切りつけ、新たな10年を歩み、再び道長と再会するとき、どんなことになっているのでしょうか、楽しみですね。
まずは新天地、越前…終盤、そして予告編だけでも波乱含みですが、果たして…!
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
