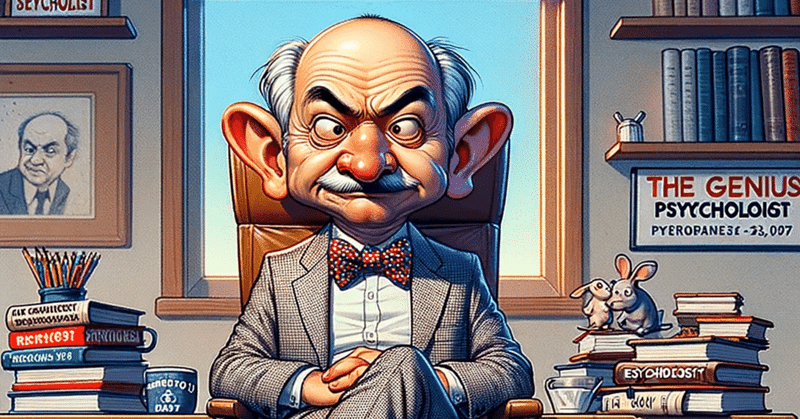
「学者先生」が嫌われる理由
反知性の時代?
自分が書く記事のなかにもあまりにマニアックすぎて、「まあ、これは一般受けしねえだろうな」と思うものがあります。そういうものは、やっぱりたいがいスキがつきません。ところが、ときどきそうした予想を裏切ってスカれるものがあって、びっくりさせられることがあります。
嬉しい驚きなんですが、いくら考えても、どうしてこんなものがウケたのかよくわからない。でも、少し前に気づいたんですが、どうやらそういう記事にもある共通点が一つあるようで、しかもそれがマーケッティング術に収まらない問題を指し示してる。それは、一般に「学者先生」という語でくくられるような方々、とくに大学に関係する人々に対する批判を含んでるという点であります。
そのような批判を聞きたがるのはどういう人たちなのか、はっきりしないんでありますが、どうやら一種類の人たちだけではなくて、かなり広範な層の人たちから反感を買っているようなのであります。ですから、嫌われる理由もまた一つや二つではないと思われます。恐らく現実の「学者先生」方というよりは、一般の人たちに抱かれている「学者先生」のイメージに対するものでしょうし、それはまたマス・メディアに露出の多い先生方が与える印象に引っ張られているのかもしれません。
これは今に始まったことではないし、社会的に尊敬される人びとはまた妬みの対象にもなりますから、ある程度の反感を買うのは致し方ないのかもしれません。大部分の学者先生がたは地味に目立たずがんばってる人たちですから、迷惑してる被害者であると思ってもよいかもしれません。それでも、大学や学問にたいする風当たりが強くなってる時節ですから、自分たちのイメージが悪化してるという自覚をもった方がよろしいのでは。そう思わされるところがあります。
と言いますのも、そんな批判を書いてる自分もまた、大学で培養された学者・知識人くずれみたいな人間でありますから、スカれたからといって喜んでばかりもいられない。実際に、自分がそのような批判を書くのも、何らかの負い目があって、自己批判とか罪滅ぼしの一面もありそうですから、余計にそうであります。
自分が書くような文章も、やっぱりどこか世間から憎まれるようなところがある。それは一つ、どんなにそうならないように気をつけても、どこか学者くさい文章だからだと思うんです。そして、書かれた内容にかかわらず、そういう文章の様式自体が、多くの人、とくにネットに多く集まる新しい世代をイライラさせる何かを含んでいる。そんなふうに感じるんですね。そして、「そんなものは、わがままな客による一種のカスハラだ」とは言い切れない部分があるように思える。
先回りされること
XだかYだかZだかよく知らないのでありますが、ちょうど自分の娘息子たちの世代を観察していて気づかされるのは、そのロマン主義的な心性であります。ロマン主義というのはかっちりと定義するのがむずかしい代物なんですが、一つの特徴としては「完成」とか「完全」というものを嫌って、「無限」をそれに対置する傾向があります。なにか自分自身を超えるものに憧れて、つねに自分を超え出ようとするんですね。
これは昭和生まれの自分にもありましたし、その前の新左翼の世代にも見られる傾向ですから、必ずしも新しいものではない。しかし、これがかなり普及して、文芸とか政治などにも携わらない人々にも拡がっている。今日の大衆文化の一部になっているようなところがあります。
この考えのご先祖は、19世紀の初頭にごく少数の文化エリートのあいだで生まれて共有されたものでして、なんでも平均化、平準化してしまう啓蒙思想に対する反動であります。そこで「個性」とか「多様性」いうものが大事になってくるんですね。同じような個人が契約を交わして社会を構成してる(自由主義の見解)のではない。かといって、様々な身分の人間が寄り集まって、相互に補完しながら一つの有機的な全体を構成している(保守主義の見解)のでもない。ロマン主義にとって重要なのは、個性をもった個人であります。一人ひとりが人間のとりうるあらゆる可能性の実現でありまして、それ自体一つで完結している宇宙なんですね。ですから、全体のために個性を犠牲にすることは、一つの宇宙の可能性を否定することになる。
そういう宇宙観がありますから、ロマン主義者は他人に言われた通りに生きるのではなくて、自分で自分の道を選んで進みたがる。自分で問いを発し、自分でその答えを探求していかないとならない。結果として他人と同じものに行きつくかもしれませんが(たとえば、ロマン主義者にはプロテスタンティズムからカトリックに改宗する人が多かった)、大事なのは選ばれた結果ではない。自分で悩み苦しみながら自分自身を超え出ていく、その過程なんですね。
そういう人たちにとって何よりイヤなのは、自分のやることを先取りされることです。「まあ、好きにやってみるがいい。結局はオレたちと同じところに行きつくに決まってる」などと決めつけられることです。そんなことを言われたら、もう悩み苦しむことが無駄な徒労にしか思えなくなる。
学者先生方に対する反感には、ひとつには、聞かれもしないうちにぜんぶ答えを教えようとするようなところがあるからと思われるんですね。「それはもう学問的には否定された道だからやめときなさい。こっちの道を選びなさい」というかたちで指導したがる。そうやって個々人が自ら探求すべきものを先回りして教えてしまうんですから、たとえ答えが正しかったとしても、というより正しく見えれば見えるほど迷惑です。それが教育者としての仕事の一部なんですから仕方がない面もあるんですが、これがあんまりうるさいと、自由を奪うように感じられる。
人生における意味とか目的といった重大事に関しては、自らの心の奥底から湧き起ってくる心情にしたがって、個々人がそれぞれ探求するべきであって、他人が押しつけてはならない。最後は大同小異の結果になるにしろ、まずは自分自身に忠実でなければならない。これがどうも現代における暗黙の理解の枠組みなんですね。自分で見つける前に他人に教えてもらっちゃうと、自分ではなくて他人の答えの模倣になってしまう。だから人生のネタバレみたいなものとして、かえって忌まれるんですね。自分の人生は自分で書いていく小説みたいなもので、他人に結末を指定されしまったら、もう書けなくなる。
教える方は親切で教えるのかもしれませんが、それが唯一可能な答えだという但し書きと一緒に与えられると、もう自由な巡礼の旅を続ける気力が削がれてしまう。開かれているはずの未来が閉ざされてしまう。たといそこに行きつくとしても、自分で迷いながら行きつかないとならない、余計なこと言うな。後から生まれてくる者には、そういう感覚があると思うんですね。平成の若者にもあるかもしれませんが、昭和生まれの自分にもまたありました。
先回りしようとすること
ですから、「世界はこうだ」とか「人生とはこういうもんだ」という断定的なことをいう人には、あんまり聞く耳をもたない。「こうしたいならこうすればいい」という仮言法のハウツー助言までは歓迎ですが、「人生の究極の価値はこれだ」みたいなカテゴリカルな言い方は嫌う。
みんながみんな孤独な巡礼者みたいになるんですが、だからといって、孤独を好むだけではない。やっぱり仲間を求める。同じ孤独な巡礼者たちが集まって、「自分はこういう経験をした」と語り合うのを好む。権威によって上からこうだって決めつけられるのは嫌ですが、自由で平等な個人が、ウエメセではなく対等な立場で交わるんです。ネット文化では、部分的にではあれ、こうした平等の理想が実現されていますね。ときには醜い見栄の張り合いみたいにもなるんですが、互いに励ましあうことにもなってる。そう言われると、動員型のコミュニケーションを除くと、ネット受けするのは、平等な巡礼者たちが互いの経験を共有するような内容のものが多い。
そういう場所で、やたらに経験豊かで物知りな人というのは迷惑であります。反論の余地がある「物知り顔」の人であれば、まだ許せる。だけども本当にいろいろと知ってそうな「学者先生」は厄介であります。そんな人たちの話を聞いてしまったら、もう旅を続けるのがバカらしくなってしまいかねない。だから、本当にエライ学者先生であっても、やっぱり一人の「物知り顔」扱いして、「なんだい、お前らの知らないこともたくさんあるんだぞ」と思ってる方がよろしいということになります(そして、それは確かに間違っていません)。
「学者先生」や彼らが書くような文章に対する反感の源泉も、ひとつはそこではないかと思われます。見栄からにしろ、親切心からにしろ、「お前らの知らんことを教えてやって、無駄を省いてやろう」という態度が見え透く。この形式の語りが、自由な探求を欲する者の警戒を呼び起す。これは学者先生にかぎらず、伝統的なウヨク、サヨクの指導者たちにも言えると思います。まだ「動員」の時代のメンタリティで、問われる前に答えを押しつけて、十把ひとからげに人々を一定方向に動かそうとするんですね。「○○党を支持してるような奴はダメだ」みたいなかたちで。
そうではなくて、自分もまた一人の孤独な巡礼として、「自分はこういう道を辿ってきて、今はここにいる」っていう形式の語りが求められているんではないか、より具体的には、「自分はこういう問いを得て、こういうふうに考えて、こういう答えを出した。だけども、またここからどこに行くかはわからない」というような形式ですね。暗に「あなたの参考になればいいけど、参考になるかどうかは私じゃなくてあなた自身が決めるべきだ」ということが含意されています。
永遠の「工事中」
そんなことばかり言っていたら、客観的な真理や真実がことごとく否定されて、学問や学者なんてものが成り立たなくなっちゃうじゃないか。学者がそうでない人と区別されるのは、単なる感想や意見ではなく客観的な知を有してるからであり、その区別をとっぱらったら、学者の意見も凡人の意見も同等になってしまう。ぜんぶがぜんぶ「それってあなたの感想でしょ」ですまされるようになってしまう。そう思われますし、それはそれで一面正当な懸念であります。
実際のところ、学者先生方は物知りな人々であります。他人が理解できない言語を苦労して習得して、他人が読まないような本をたくさん読んで、他人が知らないようなことをたくさん知っておられます。その理路整然とした語りを聞いてると、「なるほど、そういうもんか」と感心するばかりで、疑問を抱いて質問する余地さえ見出しがたい。だから、学問というのはもうほとんど完成していて、あとは学ぶだけである。少なくとも自分のような俗事に忙しい凡人にとっては、もう学者先生がすでに知ってることを学ぶだけでも、人生が足りなさそうである。そんな学者先生方さえ知らないことなんて、フツーの人には縁のない細かい話にちがいない。
一般の人たちはそう感じているでしょうし、自分もまた学生のころはそんな風に感じていました。ところが、実際に教えたり研究したりする現場に入ってみて、びっくりしました。設計図もなければ、現場監督もいない工事現場みたいなところなんです。まったくの無秩序でもないですが、みんなが勝手にあっちを掘ったりこっちに建てたりしてる。そうして、恐ろしい量の産業廃棄物が出る。
だから時々整理整頓して無駄を減らす必要にも迫られるんですが、決められた設計図に従って現場監督がきっちり管理するようなことにはならないし、なったら学問の生命力が失われることになる。すべての分野じゃないかもしれませんが、自分が知るかぎりはそういう暗黙の了解があります。
だから人が何かを建ててるその横で、その土台を掘り崩していくような奴がいて、せっかく建てたものが取り壊されてゴミになったりする。でも、ガラクタだと思われたものが新しい建造物の基礎になったりもするから、「最初からゴミは出さなけりゃいい」ということにはならないんです。
そういう永遠の「工事中」みたいなのが学問の現場でして、過去から受け継いだ遺産も多すぎるほどあるんですが、同時に、その遺産を乗り越えていこうというロマン主義的な情熱も欠けていないんですね。で、やっぱり、他の世間みたいに、限られた資源を奪い合う政治闘争やつまらない口喧嘩みたいのも起こりますが、そうやって個人事業主みたいな人々が、自律性を保ちながらも相互に交わることによって、学問の進歩が促進されています。
ここから先は
コーヒー一杯ごちそうしてくれれば、生きていく糧になりそうな話をしてくれる。そういう人間にわたしはなりたい。とくにコーヒー飲みたくなったときには。
