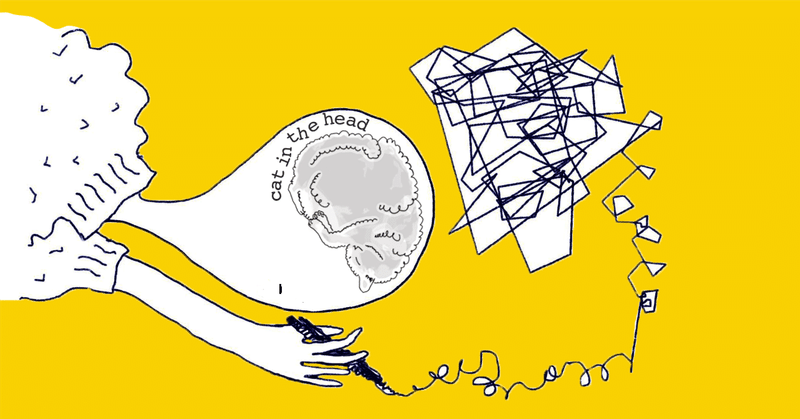
私らしくならないために書くことによって私らしくなってしまうということ
書き方と書く意味
早いもので、note を書き始めてからもう4年以上が経ったみたい。その前にはミクシィというところで日記を書いてたし、またその前には、誰も読む人がいないのに、一人でいろいろと書いてた。仕事や勉強以外で。
人が何かを書く理由は数かぎりなくある。だから書かれるものの種類もたくさんある。みんなが書くわけでもないし、他人から求められないかぎりは書かない人のほうがきっと多数派だ。書くのは面倒な作業だから、必要に迫られなければ書かないほうが自然だ。
けど、自分が頼まれもしないものをなぜ書き始めたか考えると、どうも「自分をわかってもらうため」ということになりそうだ。つまり、自分を知らない人に対して、あるいは知っている人に対してでも、まだ知られない自分を開示する必要を感じた。開示されるものは、記憶や考え、感情や気分、冗談や物語などの創作物など種々あるけど、自分の内面で起こったものである。そうしないと、「本当の自分」がわかってもらえない。そんな風に思ったらしい。
ということで、今回の話は、自分がなぜ書き始めたのかという個人的な回想。なるべく正直に話すつもりだが、例によって自分カタリなんてあまりあてにならんものだから、半分は「語り」、もう半分は「騙り」くらいに聞き置いてもらっていい。だが、ここは書くのが好きな人たちが集まっている場所だから、他人の経験と自分の経験を比べてみると、いろいろと面白いことがわかってくるんじゃないかと思う。
「note の書き方」というお題とはちょっとズレるかもしれないけど、方法論にはかならずその根拠となる世界観がある。書く方法は「書く」ことの意味とは切っても切り離せない。「どうすれば(うまく)書けるか」という問いには答えられないが、他人がなぜ書くのかを知れば、自分の書き方を考える際の一つの参照点にはなるかもしれない(反発し、拒絶するにしてもだ)。
「私を開示するために書く」と言ったが、奇妙なのは、自分はたぶんあまり「私らしさ」ということを気にしないほうの人間。わざわざ「私らしく」なろうと意識したことがない。たぶん世代もあるかと思うけど、無理して私らしくなろうとしなくても、もう十分私らしいと過信してるようなところがある。「自分と誰か別のものと間違えるような頓馬は、まあいねえだろ」くらいに思って安心してる。
だからといって、別に自分の個性に自信があるわけじゃない。むしろ引け目を感じて、自分を変えよう、変えようとしてきた。それにはいろんな意味があるんだけど、一つには、あまり変わり者だと思われないように、世間並みの常識は身につけておこうと心がけてた。そのために新聞も毎日読んでたし、すべてのことじゃないけど世間の話題にもほぼ追いついてた(と思う)。大概のことについては他人の意見を聞くまでは、自分の意見も持たないようにしてた。つまり、あまり「私らしく」ならないようにしてたとも言える。
だけども、その結果、やっぱり「変な人」になったんだから、もう仕方がないやと諦めてるようなところがある。実は、自分では変どころかけっこうまともだと思ってるんだけど、他人にそう思われるために努力する気力も財力も足りないから、「そうしなくて済むなら変な人でもいいや」と開き直ってる。つまり、どっちでもいい。言ってみれば、「私らしさ」は運命のもたらしたもの、好むと好まざるとにかかわらず受け容れるしかない呪いみたいなもの。そんな感じ。
だけど、この境地に達したのは世間から剣突を喰らって追い払われたあとのことで、昔はそうじゃなかった。それまでは、少なくとも「変な人」だって思われないようにいろいろ気を使ってた。たぶん人並以上に。そして、自分が物を書き始めたのも、実はそれと関係がある。
なぜ書き始めたか
自分は今でこそ毎日何か書いてるけど、物書きとしては、たぶんかなり遅咲きのほう。子どもの頃に小説もどきのものをいくつか書いたことがあるけど、本格的に書き始めたのは三十代も後半。二十代から三十代にかけては、勉強や仕事で要求されること以外は何も書かなかった。
学生のころは、自分では書かなくても、印象に残ったロック音楽の歌詞なんかを書き写して、よくエモい気分に浸っていたから、きっと書こうと思えば書けた。手紙なんかもめったに書かなかったけど、たまに書いたりすると、だいたい自己憐憫の気分に支配された感傷的なものになった。例の「誰もオレのことをわかってくれねえ、バカばっかりの世の中でオレは独りぼっち」ってやつ。
それが、学生から社会人になった途端に、ぴたりと書かなくなった。なぜかというに、別に書くことがなかった。学生から社会人になって、大人の仕事や楽しみを体験するのに忙しかった。その体験を記録するようなものは書けたかもしれんが、わざわざ生きることを中断して、自分のなかにあるものを整理する必要をまったく感じなかった。よくも悪くも生きることに忙しかった。なにかうまくいかないことがあっても、物なんか書いてる暇にほかにやることがいくらでもあった。
自分が物を書く転換点となったのは、いわゆるミッドライフ・クライシス、「中年の危機」という奴である。実入りのいい定職を得て、結婚して、子どもも生まれて、庭つきの家(今なら都心のマンションか)はまだ買ってないけど、それを現金で買えるくらいの貯金が銀行の口座に眠ってる。言ってみれば、中産階級の夢がかなった。ところが、この夢がかなった瞬間に、心の中になんだか不穏なものが醸成されてくる。「本当にこれがオレの生きたい人生なのか」という厄介な問いが、無視できなくなってくる。
実は、この問いは二十代の頃からまとわりついてた。自分は元来コミュ障な人間で、学生時代は寂しい奴だったんだが、社会人生活の出だしによい仲間や先輩に恵まれたおかげで、青年期の人間嫌いはあっけなく霧散してしまった。どうやら未知のものに対する恐れを隠すためのジェスチャーに過ぎなかったらしい。だから、たくさんの先輩や友人たちに囲まれて、楽しく過ごすようになって、なんだ人間ってそんな悪いもんじゃないなって、恥知らずなほど簡単に転向しちゃった。だけど、心の奥底ではなんとなく孤独を感じてもいた。本当に自分がしたいのはこんな話じゃないはずなのに、そういう話をする相手は周囲にいない。まだ、そういう風に思うところがどこかにあった。
青臭いと言われても仕方がないんだけど、たぶん、ひとつは育った環境という奴で、自分は教養主義的な雰囲気の中で育てられてしまったから、日本の共通文化たる大衆文化的なものに、ちょっと貴族主義的な反発や嫌悪を感じるところがあった。もう一つは、その頃は自覚してなかったんだけど、自分は知らないうちに父からプロテスタント的倫理を受け継いでいたから、楽しく暮らすだけで満足してる自分を責める「良心の声」がうるさかった。
正確な引用じゃないけど、プロテスタント倫理には「現世の事物を使用しなさい、しかし享受してはならない」というアウグスティヌスの言葉のようなところがあって、現世の生活で献身を要求しながらも、それがもたらす報酬からは距離を置くように要求するところがある。だから、充実した社会人生活を営みながらも、人生の大事はどこか別のところにあるんじゃないかという不安がぬぐえなかった。だけど、そんなことを周囲の誰かに相談するのは憚られたから、胸のうちにしまっておいた。そうしておいても、楽しいうちは大した支障がなかった。
それに、もう一つは、この孤独感は恋愛によって癒されるだろうという期待があった。本当に自分のことを理解してくれる人がどこかにいて、その人に出会いさえすれば、もう何も欠けるものはない。そして、今の自分にはそういう理想の人に出会えるチャンスがいくらでもありそうである。そう思えた。
だけど、中年の危機に際して無視しえないほど大きくなったのは、この内なる声だった。プロフェッショナルな成功でも恋愛でも家族でも癒せない孤独があって、それを癒すためには、いくら居心地がよくてもここから出ていかないといけない。そういう声(実は上司のパワハラのおかげでもう居心地が悪くなっていたから、大した決断力は要らなかったんだけどな)。自分はたぶん昔であったら出家するようなタイプの人間なんだが、今は時代がちがうから大学院に戻った。
大学院での修業は厳しかったけど、自分には楽しかった。やっぱりこれがオレの天職だなと思った。だけども、米国の大学院でも、自分と同じように楽しんでる仲間を見つけることは難しかった。大学の先生方でさえ物足りなかった。学問好きな奴はいるにはいるけど、学者生活のライフハックとか楽屋落ちのゴシップみたいのに通じているだけで、あんまり学問そのものには意義を感じてなさそうな、そういう連中だったから、むしろ自分からはいっそう遠い存在だった。だから、自分の友人は変に院生ズレしてない人ばかりだった。それはそれで貴重な友情だったんだけど、肝心な部分では相変わらず孤独なままだった。
自分が文章を書き始めたのはそのときで、最初は日記みたいなかたちで独りで書いてた。その後、ミクシィという日本の SNS があるのを知って、そこで書いたものを公表し始めたけど、まずは自分自身のために書いてたし、今でもそういうところがあると思う。なんで書くことが孤独感を取り除かないまでも和らげることになるのか、よくわかんないままにとにかく書き続けてた。
書いて孤独を癒す
いま考えてみるに、今まで自分が口にするのを憚っていた内なる声を言語化するということ自体が、一種のカタルシスをもたらしたんじゃないかと思う。自信なさそうに小声でもごもごとしか言えなかったものを、独りきりになってペン(というかワープロを打つ指)の勢いで文章に落とすことができたとする。これができたということ自体がもう、自分の内的経験は他人にも理解可能なものであり共有されうる、という一つの証拠である。いな、互いに伝えられてないだけで、既に同じような経験をした人もいるかもしれない。そういう希望がもてる。
この体験をさらに深く掘ってみると、そもそも「わかってもらいたい自分」というものが、自分にもよくわかってなかった。だから他人にもうまく伝えられなかった。だから、まず自分でそれを知らないとならない。知るためには文章に落として、もやもやした気分みたいなものを明確な輪郭をもつ対象にしないとならなかったんじゃないかと思う。
つまり、「いつもごにょごにょ言ってるけど、いったいお前は何が言いたいんだ」と自分自身に何度も問うて、それに答えていくのが、自分にとっての「書く」という行為だったんじゃないかと思う。だから、まずは自分自身が納得できる答えを出さないとならない。それができたら、他人にもわかりやすい、あるいは魅力ある文章に書き直す必要があるが、読んでくれる人がいると思っているかぎり、そこはかえって楽しい片づけ作業にすぎない。だから、読まれないとわかれば、もう力は入れなくなる。でも、自分のためには書き続ける。こっちが「書く」ことの本丸だ。
まあ、そうやって書くことによって孤独をますます深くしちゃうんだから、人生なんて皮肉なもんだと思う。というのは、書くためには、いろいろ読んで調べて反省しないとならない。自身との対話を重ねないと書けない。でも、そうやって読者に先駆けて一連の反省を一人でやってしまって、ますます他人からの距離を広げてしまう。わかってもらうために書くということには、そういう反作用が伴う。他人に読んでもらうための書き換え作業に必要なのは、この反省過程を逆にたどって、まだそのような反省を経ない者の立場に立つことなんだが、もう反省しちゃった者にはこれがうまくできるとはかぎらない。
おそらく、書き始める前の三十代までの自分であったら、まだ「フツーの人」に成りすますことがむずかしくなかった。たぶん他人もそう思っていたし、自分にもそうなりたいという気持ちがあった(「絶対そうならないぞ」と粋がってるところもあったけど、寂しくなると「ああ、オレって孤独だなあ」という自己憐憫に圧倒された)。自分が本当に「私らしく」なったのは、おそらく「書く」ことによってである。しかし、それはわけのわからんことばかり言う「変な人」になることでもあって、他人に自分のことを普通だと証明しようと躍起になってるうちに、その逆の結果になった。
「私」の原因じゃなく結果としての「私」
まあ、だからといって、「私」が理解不能な惑星ソラリスのようなものになったとも思ってない。自分の感覚だと、まず他人とはちがう「私」があって、それで他人とちがうことを考え書く人間になったというよりも、その逆の方がもっともらしい。つまり、他人と同じようだった自分が、書いて反省を重ねたことによって、他人とは容易に重ならない部分を多く含む「私」になっていった。
ここから先は
コーヒー一杯ごちそうしてくれれば、生きていく糧になりそうな話をしてくれる。そういう人間にわたしはなりたい。とくにコーヒー飲みたくなったときには。
