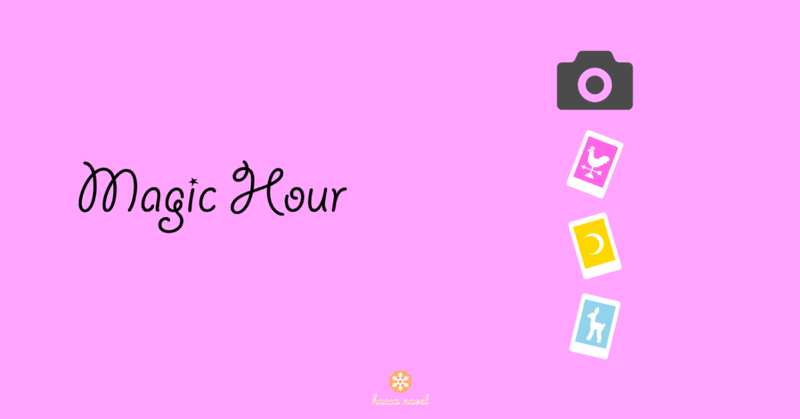
【中編小説】 マジックアワー vol.5
月曜の朝、空はバカみたいに晴れていた。昨日の夕方から続く梅雨の晴れ間というやつで、それはなんだか余計にわたしを憂鬱にさせる。
「おはよう、ヒーコ」
「おはよう、文月」
それでも日常は続いてゆく。
「おはよう、ヒーコ」
「あ、おはよう、エミリー」
エミリーがおはようなんて声をかけてくるのは珍しい。わたしは悠馬さんとの会話を思い出して身構える。
「ヒーコ、あんたが茨木さんの写真を撮ったんだって」
満面の笑みでエミリーが言う。
「うん。まあね」
「じゃあ、今度はわたしを撮ってよ」
わたしは、曖昧に笑みを浮かべる。
「何? 撮ってくれないの?」
「あー、うーん」
「なんで? あんなに素敵に撮れるのに」
「うーん、どうしても」
「わたしを撮るのが嫌だってこと?」
エミリーの表情がどんどん険しくなる。
「いや、そうじゃなくて。なんて言えばいいかな。もうわたし、写真撮らない」
「は? 何それ。どういうこと」
エミリーは完全にお怒りモードだ。わたし、もう学校来られなくなっちゃうかも。
「どうということもないけど、撮らない」
「意味がわかんない。茨木さんのことは撮影できてもわたしがダメなのはなんでよ」
「あー、もう。わたし、写真やめたの」
「なんで」
「だって、いやだから」
「いや、って何よ。なんなのそれ」
「あー、もう、わたし、人を撮りたくないんだって!」
たまらず大きな声を出す。教室中の視線がわたしたちに集まる。
エミリーが瞳を大きく開く。そして、低い声で脅すようにわたしに言う。
「ちょっと、あんた、スマホ出しなさいよ」
わたしはエミリーに気圧されて、渋々スマホを取り出す。
「ロック解除して」
ロックを解除するやいなや、エミリーがわたしのスマホを取り上げる。さっと操作して、わたしの腕を取る。
「さあ、わたしを撮りなさい」
「なっ」
エミリーはわたしの腕を握り、わたしの手のひらを取り、無理やりスマホの画面を触らせようとする。
「ちょっと、やめて、エミリー、何?」
カシャン、とシャッターの切れる音がする。
「ふん! あんた、神様にでもなったつもり? 冗談じゃない! 茨木さんはあんたが撮影したから亡くなったっていうの? 思い上がるのもいい加減にして。そんなわけ、あるわけないじゃん! 冗談じゃない。茨木さんは、本当に本当に、素敵で、美しくて優しくて、だからあんたが殺せるはずない! バカじゃないの! わたしだってあんたに撮影されたくらいで死んだりしない。冗談じゃない! わたし、絶対に死なないから!」
エミリーがわたしの手を離す。スマホが床に落ちる。わたしはひっくり返ったそれをしばらくじっと見つめていた。
教室中がざわついている。
「お、なんか変な雰囲気だな」
担任の萩原先生が教室に入ってくる。
わたしは慌ててスマホを拾った。画面にヒビは入っていなかった。その代わり、鬼のような形相のエミリーが画面いっぱいに映し出されていた。
その日の帰り道、いつものように文月と一緒に歩く。朝の快晴とはうってかわって空はどんよりと曇っている。雨はまだ、降っていない。
「ヒーコが写真撮らないっていうの、わたしは分かるよ」
教室にいた文月は、もちろんエミリーとのやりとりの一部始終を知っている。
「ありがと、文月」
文月が足元の小石を蹴る。
「わたし、ヒーコとは別の意味で、マダムが亡くなったこと、ショックだったんだよ」
わたしに視線を向けることなく文月は続ける。
「なんでマダムが病気だって気づいてあげられなかったのかなって。わたし、ずいぶん前にね、街でマダムが杖をついて歩いているのを見たことがあるんだよ。でも、お屋敷で会ったマダムは別人のようで、だからあの時までちっとも気づいてなかった」
文月は下を向いたまま、また小石を蹴った。
「あの時、マダムが棺桶の中に入っている時、あ、この人見たことあるって思ったの。真っ白な顔で、それは、つまりちょっと病的な感じに白かったの、杖をついていたマダムはね。その表情にそっくりだったの。だからたぶん見間違いではないと思うんだ。わたし、けっこう気さくにマダムに接していたんだけれど、それってとても失礼じゃなかったかな、もしかして体に負担をかけていたのじゃないかなってすごく後悔してるんだ。もちろん、わたし、医療の知識なんて全然ないから、マダムにしてあげられることなんて何にもないんだけれどさ。何にもない自分にすごく腹が立って。それで、ヒーコが写真撮るの怖くなるのも分かるんだよ。全然、因果関係なんてないんだけれどさ、でも、何かしらきっかけになったのじゃないかって不安になるんだよ」
文月が曇り空を見上げる。
「でもね、ヒーコに怒られるの承知で、わたしは言うよ。ヒーコ、写真、やめないで」
「なんで、文月まで」
「わたし、ヒーコの写真はマダムの何かを救ったような気がするの。これはただの勘だけれど。じゃなきゃ、その届けてもらったっていう謝礼も払おうとはしないだろうからね。お金持ちってそういうとこ、逆にしっかりしてるから。それで、ヒーコは写真を撮り続けるべきだし、わたしは、マダムに対して恥ずかしくない生き方をしなくちゃならないと思ったの」
文月がわたしの方を向く。
「わたしね、杖をついたマダムを置き去りにしたことがあるの」
しばらく、にらむようにわたしを見たあとで視線をそらして続ける。
「街から自宅に帰るのにバスに乗ろうと急いでいた時だった。バス停の少し手前でマダムのことを追い越したんだ。すぐにバスはやってきて、わたしは乗り込んだ。マダムもバス停まで来たんだけれど、その目の前でドアが閉められたの。ひどいでしょ。でも、わたし、席に着いてしまったの。分かる? あの時、運転手に、乗る人がいます! って言えばよかったんだよ。すごい意地悪みたいにマダムの目の前でドアを閉めたんだよ。それは去年の夏のことで、すごく暑かったでしょ。バス停に屋根はなくて、杖をついているからマダム、日傘もさしていなくて。それでね、」
文月が大きな石を蹴る。
「わたし、マダムの寿命をそこでちぢめさせてしまったのじゃないかって思ったんだよ。それは、ヒーコが写真をもう撮らないって言って初めて気がついた。あの杖の人がマダムだって気づいていたけれど、ヒーコがそう言うまで、わたしがマダムを傷つけたことには思い至らなかった」
文月が沈黙する。
「……。なら、なおさらわたしは写真を撮ることなんてできないよ」
「ヒーコ、わたしね、看護系の専門学校か短大に、もしくは大学に進路を変えた。いままでは被服科のある短大にしようと考えていたんだけれど、それにはこれといった意味はなくて、漠然と洋服のこと知りたいな、と思っていたから。でも方向転換をした。それはマダムが教えてくれたことだと思っている。
意地悪な世の中にあらがいたいの。もちろん丁寧なバス運転手になるっていうやり方もあると思うんだけれど、わたし、たぶん車の運転は得意じゃない。それよりも、もっとそばで体や心が弱っている人に寄り添えるようになりたい。介護のもう少し手前で、あの時のマダムのような辛い思いをしている人の役に立ちたい。きっと、わたし、そういう人の中にずっと、あの時杖をついたマダムの姿を見つけると思う。そして、それを無視したらマダムが悲しむから回復のお手伝いをしたい。マダムのために働くの。
だから、ヒーコは写真を続けるべき」
「……、なんでそこに繋がるんだよ」
わたしは、腹を立てていた。そんなわたしを無視して文月は続ける。
「わたしもエミリーに賛成。マダム、絶対に喜んでいたもの。お金を払うってそういうことだと思うんだよ。だって義理で10万円も払うわけないじゃん。マダムは写真を見ることはできなかったけれど、ヒーコの被写体になった時間がすごく嬉しかったんだと思うよ。杖をついたマダムと肖像写真のマダム、本当に別人だもの。
あー、わたしもエミリーみたいにかっこよく言えたらいいんだけど。ヒーコ、いつかわたしのことも撮ってよ。わたしも死んだりしない、約束する。それに、」
文月が耳元で囁く。
「ウェデイングドレス姿って夢じゃない? それを親友が撮影するのって感動的じゃない?」
文月がわたしの髪の毛をくしゃくしゃとなでる。そしてわたしの手のひらを握る。
「この小さな手のひらがわたしの幸せを包むように写すんだよ」
「……でも、文月、フッてばっかじゃん」
「まだまだわたしの王子様はあらわれないー!」
手を振りほどき、駆け出す文月。
「イマドキの女子は王子様なんて待ってちゃダメだよ」
わたしは文月を追いかける。
「それは、どっちでもいいじゃない。とにかくドレスを着てみたいんだよ」
わたしは走りながら、途方に暮れていた。
わたしがカメラを構える。
被写体のエミリーが死ぬ。
文月が死ぬ。
とてもとても耐えられない。
(絶対に死なないから!)
耳の奥にエミリーの声がこだまする。なんてそれは力強い言葉だ。そうだ、確かにわたしに死を操る力なんてないんだ。もちろんカメラにもその力はない。そんな力があるのなら、元々の持ち主であるお兄ちゃんはどれほどの人間を殺すことになっただろう。
馬鹿げた呪いだ。でも、でも。
立ち止まり、手のひらを見る。握りしめていたそれは、ほんのりと赤くなっている。それでも血で染められたようには見えなかった。今はただ、薄く頼りなく広がっている。
その日の夜、フィルグラに通知が来ていた。しばらくフィルグラに投稿もしていなければ、開いてさえもいなかった。そんなわたしのアプリにフォロワーからメッセージが届いている。フォロワー同士はダイレクトメッセージを送ることができる。
「誰だろ?」
開くことは少しためらわれたけれど、思い切ってメッセージを読むことにした。
「あ、deerくんだ」
それは、わたしの好きな写真を撮る人からだった。たぶん、同じ街に住む、北欧インテリアに囲まれたモダンな男の子。
メッセージを開いてそれを読み、おののいて後ろを振り向いた。
>こんばんは、ヒーコ。僕も君が写真をやめると言ったら辛くなるよ。君の写真をいつでも楽しみにしている。
「は? は?」
deerくんて、もしかして、もしかしてクラスメイト?
さあっと血の気が引く。わたし、フィルグラもヒーコって名前でやっているから、身バレが確定したというわけじゃない。でも、でも間違いなく、今日のエミリーとのやりとりを見ていた人だ。いったい誰だ? deer、鹿のことだよね。鹿っていう名前の人、クラスにはいなかったと思うけど。
次から次へとたたみかけられる出来事に動揺している。そんなわたしにさらに追い打ちがかけられる。
***
「ヒーコ! はいこれ」
昼休みに、写真部の先輩、斉藤さんがプリントを持ってやって来た。
「夏休みの合宿は、このプリントに書いてあるけど強制参加だからね。だから都合のつく日程をいくつかピックアップして教えてちょうだい。レポート出さないと廃部になっちゃうって。じゃあよろしくね」
そのプリントにはこんな内容が書かれていた。
写真部合宿のお知らせ
本年度の夏休みの写真部の合宿は1泊2日で開催されます。
1日目:写真の歴史の座学(萩原先生)
2日目:当日課題が発表されます
写真部の合宿は、今年は人数が少ないのと予算がないのとで、学校に宿泊しての開催となりました。部員は強制参加です。3人しかいないので、ひとりでも欠席者がいると活動報告ができず、廃部になります。必ず参加してください。
また、今回は来年の『写真インターハイ全国大会』に出場するための合宿となります。ですので、写真の基礎の復習と臨機応変の撮影スタイルの確立を目指します。
なんでみんなこんなにわたしのことを苦しめるのだろう。わたしはもう写真を撮らないって決めているのに。みんなみんなみんな嫌い! 別にわたしひとり写真を撮らなくなったっていいじゃない。誰かが死ぬわけじゃあるまいし。むしろ、誰も死ななくて済む。
そう心の中でつぶやいたわたしの脳裏にキレながら叫ぶエミリーの姿が浮かぶ。
窓際のエミリーをそっと覗く。長い足を投げ出して本当に楽しそうに笑っている。エミリーは茨木さんが亡くなって悲しくないの。なんでそんな風に笑っていられるの。
***
わたしはしばらくの間、抜け殻のように過ごした。そうしたら期末テストの結果が(赤点はなかったものの)散々だったので、さすがにこれはやばい、と思うようになった。気合いを入れて勉強をしなければならない。将来の夢が見定まらなくなってしまった今、とにかく何か勉強しないといけないと焦る気持ちになった。
あー、やっぱり、わたしフォトグラファーになろうとしてたのかな。
大きくかぶりを振って、わたしは気持ちを切り替える。さっさと宿題をしてしまおう。
あー、わたし、どうしたいのかな。わたし、どうなっちゃうのかな。
煮え切らない気持ちで過ごしているうちにあっという間に夏休みに入った。写真部の合宿は、夏休みの後半に組み込まれたから、わたしは家にこもって宿題をする日々。誰とも、文月とさえ会わなかった。メッセージのやりとりはしているけれど、遊ぶ約束は交わさなかった。
なんて夢のない高校2年生の夏休みだ。
目的なく、ただ宿題だけをこなしているうちに、気がつけば写真部の合宿の日になってしまった。なんの準備もしていなかったけれど、斉藤先輩の
「来なかったらわたしの内申に響くんだからわかってるわよね」
という脅しに屈してしまった。もちろん、そんなこと無視してもよかった。無視してもよかったのに、わたしはカメラを取り出す。
久しぶりに取り出したわたしのミラーレスカメラはひんやりとしている。
合宿参加者は3年の斉藤先輩。1年の蜂飼くん。今年、わたしと蜂飼くんが入部したので写真部は存続することが出来た。ちなみにわたしは1年の時は美術部に在籍していた。その当時、写真部の3年生が仲良く撮影会をしていたり、演劇部や軽音部の写真撮影に駆り出されるのを見て、とても気になっていたのは確かだった。美術部もそれなりに楽しかったんだけれど、お兄ちゃんからもらったカメラが大きさの割にずっしりしていて、その重さが嬉しくて絵筆をカメラに持ち替えた。
このカメラ、そういえば無理をしてもらったのだったな、と思い出す。お兄ちゃんが新しいカメラを買う時、本当は下取りに出すつもりだったみたい。お兄ちゃんが気まぐれに
「ヒーコ、使ってみる?」
と聞き、わたしが使ってみたい、なんて言ったものだから、お兄ちゃん、ちょっとびっくりしたみたい。それで、お兄ちゃんは、そうかそうか、と嬉しそうにレンズと合わせてカメラ一式をプレゼントしてくれた。
お兄ちゃんは何も言わないけれど、心の底では、わたしに写真を続けて欲しい、って思っているんだろうな。
<< マジックアワー vol.4 | マジックアワー vol.6 >>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

