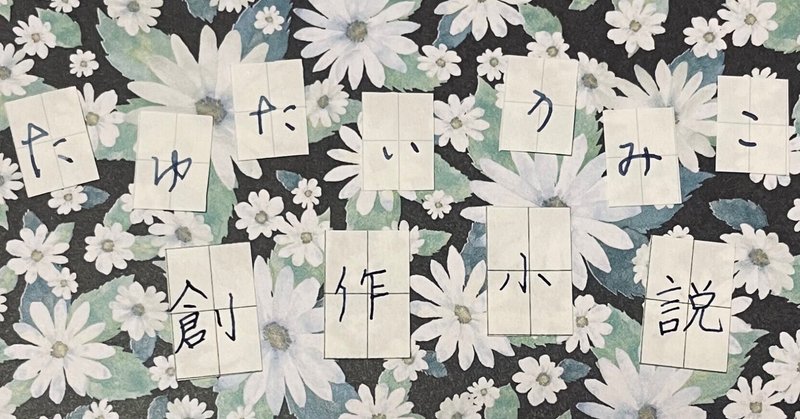
「魔法の指輪」
知らない場所のはずなのに、どこか懐かしい気がして立ち止まる。馴染みのない店の名前に、馴染みのない商品達。そこにぽつんとひとつだけ、微かな記憶と重なる一冊の本。日に焼け、薄汚れて見えるそれは周囲を飾る色とりどりのガラス細工の中で浮いている。まるで、そこだけが過去。
不思議に思うも、手に取るのは憚られ、あたかも商品に興味があるように振る舞う。数秒そうしていれば、店の奥から店員が笑顔で話しかけてきた。
「いらっしゃいませ。どうぞお手にとってご覧くださいね。」
「あの、これは……?」
両腕を組んで、本を見下ろすように立つ。店員は、あぁ!と嬉しそうな声を上げた。
「もしかしてこの本の持ち主さんですか?」
「え?あ、いえ……」
そんなことを聞かれるとは思わなかったので面食らってまごついていると、店員は「すみません、はやとちりしちゃいました」と明るく言って、気不味くならないようにという気遣いからかそれについて聞かせてくれた。
「実はここ、昔は喫茶店だったんです。私の父が趣味で始めたようなものなんですけどね。その時のお客さんの忘れ物らしくって。」
「へぇ」
「読まれたことあるんですか?」
「あぁ、まぁ……」
「よかったら、」
店員は本を手に取り、差し出してくる。言われるがまま受け取ると、ずしんと重いその厚みが記憶を刺激する。あぁ、そうだ。あの時の私は今よりもっと手が小さくて、今よりもっと……。
と、記憶と違うものがきらりと光ってそこに目をやる。栞紐の先に、……指輪?
「普通はお客様の忘れ物だからって長々と保管したりはしないんですけど、それがあるからなんだか処分できなくって。」
赤い栞紐に、銀色の指輪が結びつけてある。中央で光るのは……アクアマリンだ。
心臓がどくどくと強く脈打ち始める。知っている。私は、この本を知っている。
震える指を抑えながら表紙を開く。そこには記憶の中のそれと寸分違わない蔵書印。それを指でなぞりながら、私は全てを思い出した。
「あの……この本の持ち主を、知っているかもしれません。」
「え!?」
「一度確認して、ご連絡差し上げてもよろしいでしょうか。」
「えぇ、はい!それはもちろん……!」
私は本を店員に返し、連絡先を聞いてから足早に店を出た。カツカツと鳴るヒールが心臓の音に重なる。あぁ、体が熱い。耳が痛い。視界がぼやける。汗を拭うフリをして涙を誤魔化す。泣くな、泣くなと思えば思うほど涙が止まらない。
思い出の中に閉じ込めたあの人の声が、笑顔が、溢れるように頭の中を駆け巡る。白くて柔らかな手のひらがページを捲る微かな音までも。
人目を避けながら歩き続け、シャッター街に足を踏み入れる。ぽつんと置かれた自動販売機に100円を入れて冷たいお茶を買った。痺れた指でキャップを開けて、ごくごくと喉に通す。よろよろと肩を寄せたシャッターがカシャンと音を立てる。鞄からスマートフォンを取り出し、連絡先から母の名前を選択して短い言葉を送った。数秒後、着信音が鳴る。
『もしもし?』
「お母さん、お姉ちゃんって、山口でみつかったん?」
『……なんで、』
「お姉ちゃんの本が、山口の店にあった。忘れ物やって、店の人が保管してくれとって、栞にお姉ちゃんの指輪がついとったよ」
母の喉が薄く鳴る音がする。それが先の質問の肯定になっていた。
私には一回りも歳の離れた姉がいた。姉は生まれつき身体が弱く、活発だった私を連れて公園に来ては、ベンチに座って本を読んでいた。公園で走り回って疲れた私が姉の隣に座ると、姉は本を読む手を止めて水筒からジュースを注いで飲ませてくれた。「元気なあんた見とると、楽しい。」姉が笑うので、私は姉の前で逆立ちをしたり、側転をしたりした。すごいね、と言いながら私の手についた土を優しく払って、「あんたは主人公みたいやなぁ」と言った。
『主人公って、勇者?』
『そう、勇者。あんたにぴったりやわ。』
『お姉ちゃんは?』
『うーん、私は……そうやなぁ、魔法使いかな。』
『!!!!待ってて!!さっきかっこえぇ杖みつけた!!』
そう言って私が差し出した木の枝を、姉は嬉しそうに「これはえぇ杖やねぇ」と言って受け取った。その手の小指には綺麗な指輪が光っていた。
『それ魔法の指輪や!こないだみたやつ!』
『あんたはすぐ影響されるんやから』
『ちゃうの?そんなに綺麗やのに?』
『違わへんよ。これはお姉ちゃんの大切な魔法の指輪。』
『何できるん?』
『癒しの魔法。怪我したり病気したりした人を治せるんよ。』
『ホンマ!じゃああっこから飛び降りてもえぇ?』
ジャングルジムを指すと、それ絶対やったらあかんやつやん!と姉が笑う。
とても、楽しかった。
姉がいなくなったのは、それから少し経った冬のことだった。父と母はお姉ちゃんは病気を治すために入院しているのだと言った。お見舞いに行きたいというと、遠い病院だから、と断られた。それを何回も繰り返して、何ヶ月も経った頃、お姉ちゃんはもう帰って来れなくなったと言われた。どうして?と聞くと、病気がお姉ちゃんを遠いところへ連れて行ってしまったのだと言われた。死んでしまったのだ、とわかった。私は魔法の指輪が姉ことを治してくれなかったことがとても悲しかった。
「酷なこと、聞くけど」
声が、震える。
「お姉ちゃん、病気で死んだんとちゃうんやろ」
母の悲しみが溢れた声が聞こえた。私の目からはまた涙が溢れてきた。
『病気よ。病気のせい、あの子は、病気のせいで死んだんよ!』
「……そう……………ごめん、変なこと言って。」
電話を切ると、足の力がふっと抜けて、私は蹲った。知っていた。……本当は、姉が何故死んだのか、私は知っていた。
『その指輪でお姉ちゃんの病気も治せへんの?』
『せやねぇ、お姉ちゃんのは魔王にかけられた特大の呪いやからなぁ〜。』
『魔王倒したら治る?』
『治らんなぁ〜。』
『えぇ〜、弱い!魔法の指輪やのに!』
『弱くないよ〜。あんな、癒しの魔法には色んなのがあってね。悲しかったり苦しかったりする気持ちを頑張れ〜って勇気付けてくれるのもあるの。』
『ふうん?』
『あんたにもそのうち分かるよ。心の怪我を治す力がどんな魔法よりも強いんやって。』
『勇者より?』
『せやね、勇者より!』
どうして、私は姉の最期を知らないのか。どうして、父も母もあまり姉のことを話さないのか。それなのにどうして、姉の部屋はずっとそのまま遺してあるのか。
色んな疑問を口に出すことはできなかった。幼い私は寂しさを埋めるために度々姉の部屋に忍び込んだが、歳を重ねるにつれそれもしなくなった。
だけど、大きな木の箱の前で泣き崩れる母と親不孝者と怒鳴った父のことを私は忘れられないまま、姉がいなくなった時と同じ年齢になった。
山口に行ってくる、と言った時、一瞬母の動きが止まったことに気付いていた。父は誤魔化すように新聞で顔を隠した。
「何しに行くの?」
「観光」
「そう。」
「なんかね、ずっと行ってみたかったんだよね。何でかはわかんないけど。」
小さな嘘をついた。
本当の理由は、姉がいつか行きたいと言っていたからだ。姉がいつも読んでいる本の作者が、山口県出身なのだと言っていた。この本は宝物だと、よく読み聞かせてくれた。セピア色の、少し寂しい詩。
姉は、身体がよくなったら山口に行くのだと言っていた。お母さんとお父さんは長旅を許してくれないだろうから、行く時はあんたにこっそり教えるねと言っていた。しかし終ぞその時はこないまま、姉はいなくなってしまった。だから、私が姉の代わりに山口を訪れようと思ったのだ。
「うそつき……」
私に教えてくれるんじゃなかったの?と思いながら、誰にも言わず、黙ってこの土地を訪れた姉を責める気にはなれなかった。
どんな気持ちでこの土地を訪れ、あの店で食事をし、宝物を置いていったのか。
何故、魔法の指輪を外したのか。
……やめよう。姉の心を勝手に暴くようで、気が進まない。
私は立ち上がり、宿へと向かった。お店の電話番号を聞いていたので、電話をかけ、詳しい内情は伏せて本を引き取りたいと申し出た。
「何も証明するものがないので難しいとは思いますが……」
『もう10年以上前の忘れ物ですし、私も何となくもし持ち主が現れたら〜なんて思って置いていただけですから。それにさっき父に聞いたら、本を忘れて行った人とお話くださった方の風貌も似てますし、父も渡して構わないということなので』
「ありがとうございます。それであの……重ねて申し訳ないのですが、早朝にここを立つ予定でして……」
『大丈夫ですよ!6時には店におりますから、お待ちしております。』
お礼を言って、電話を切る。本当は姉の最期の姿を覚えている人に話を聞きたかったが、それは望みすぎだろう。……というか、奇跡のような話なのだ、これは。12年も昔の忘れ物を、お店が変わっても保管していてくれて、そしてそれを歩行者の目の付くところに飾っていてくれた。そしてそれを、私が見つけた。そして、それがあの本だと気付いた。
「ほんまに、魔法使いやったんかな。」
魔法使いは、最期に指輪に魔法をかけたのだろうか。十数年後、大人になった勇者が指輪を手にするようにと。
翌日、本を受け取りに店に向かう。
早朝の冷えた空気と薄暗い道、まだ暖簾が上がってない店のドアをコンコンと叩く。
「おはようございます!」
「昨日はどうも……」
「いいえ〜。昨日ね、父とこの本について話したんです。持ち主が見つかったって!父もとても喜んでました。それでね、」
と言って、彼女は手に持っていた箱を開けた。
「これ、その人が使ってたカップです。」
「え?」
「父の喫茶店ではお客さんにカップとソーサーを選んでもらってたらしくって。これも父の趣味みたいなもんなんですけどね。よかったら、本と一緒にどうぞ。」
「そんな、申し訳ないです」
「いいのいいの!父からの気持ちですって!父の作ったケーキをとても褒めてくださったお礼。家族に趣味って言われて案外落ち込んでたらしいんですよ」
明るい笑顔と言葉に、心も和らぐ。
善い場所で、善き人と。
姉の最期がどんなものでも、彼女がここで佳き時間を過ごしたことは間違い無いだろう。だからここに本と指輪を置いていったのかもしれない。
ここが、姉の最期の場所だとでも言うかのように。
「必ずまた来ます。」
「えぇ、お待ちしてます。」
カップソーサーの入った箱と本を受け取って、お礼を言い、別れた足で駅へ向かう。
ベンチに座って栞紐から指輪を外して、あの日の姉と同じ場所にそれを通すと、きらっと水色の光が目に飛び込んでくる。
「勇者は魔法の指輪を手に入れた!」
……なんて、と小さく笑う。
銀色の指輪が朝日を反射して眩しかった。
[終]
本作品は診断メーカー
「こんなお話いかがですか」様より書き出しと終わりをお借りし、生まれた物語です。
この場を借りてお礼申し上げます。
ありがとうございます。
