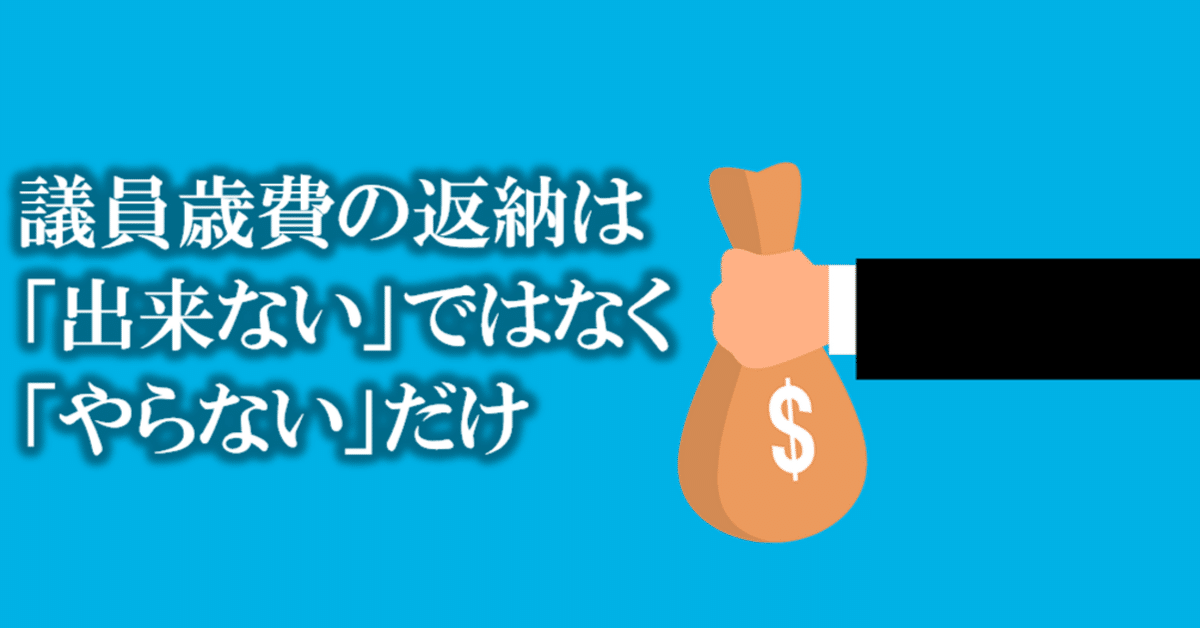
議員歳費の返納は「出来ない」ではなく「やらない」だけ
※お知らせ※
減税新聞では有料記事設定をさせて頂いていますが、筆者のやる気の源であるプリン代になる投げ銭的な意味合いですので、記事は全文最後まで無料でお読みいただけます。
こんにちわこんばんわ。
全ての増税に反対し、全ての減税に賛成する自由人、七篠ひとり(@w4rZ1NTzltBKRwQ)です。
今日はこちらのポストから。
立憲民主党は、自衛隊員や裁判官、一般公務員の賃上げ法案には賛成しました。
— 泉健太🌎立憲民主党代表 (@izmkenta) November 15, 2023
しかし総理の報酬が46万円UPする法案と、国会議員の報酬が18万7600円増となることには反対です。
現行法では議員報酬の国庫返納が違法のため、今回の増額分は各議員から党に集め、国内外の社会公益活動に寄付いたします。 https://t.co/hTWSh2hfXP
こちらは14日に衆院本会議で可決された
首相や閣僚を含む特別職の国家公務員給与引き上げ法案
についての立憲民主党の泉代表のポストです。
ちなみに立憲民主党の名誉のために言っておきますと、この法案に賛成したのは
自民・公明・国民民主党
で、立憲は反対しています。
さて、この法案については沢山の人が怒りの声を上げていることでしょうから、ここ減税新聞ではちょっと違う
議員歳費の返納は「出来ない」ではなく「やらない」だけ
という視点でこの件を斬って皆さんの血圧をさらに上げたいと思います笑
まず冒頭の立憲・泉代表のポストの
現行法では議員報酬の国庫返納が違法のため、今回の増額分は各議員から党に集め、国内外の社会公益活動に寄付いたします。
の部分についてですが、この「国庫返納が違法な理由」って何だと思いますか?
実は「議員報酬の国庫返納は公選法で禁止されている寄付にあたるから」です。
歳費の国庫への返納が寄付にあたるって皆さん意味がわかりますか?
ただでさえ意味不明なのに、返納が寄付になるということならこの泉代表のポストは
「報酬返納は寄付にあたり違法なために寄付します」
と益々意味不明なことを言っていることになります。
でも法律上はこれが正しく、泉代表に文句を言うなとまでは言いませんが、個人攻撃をしても仕方がない話であることは付け加えさせてください。
ではなぜこんなことになるのか、議員報酬の返納が寄付行為になるのかという点について詳しく解説しましょう。
まず、議員の歳費については、憲法49条によって
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
と定められています。
そして国会法や国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律によって、その金額等が決められています。
議員は、一般職の国家公務員の最高の給与額(地域手当等の手当を除く。)より少なくない歳費を受ける。
各議院の議長は二百十七万円を、副議長は百五十八万四千円を、議員は百二十九万四千円を、それぞれ歳費月額として受ける。
国会法の「より少なくない歳費」といういやらしい書き方はさて置き、このように憲法および法律による「法的根拠」をもって議員は歳費の受け取りを保障されています。
次に「歳費の返納がなぜ寄付になるのか」について考えてみましょう。
「寄付」の定義は、公選法ではこう書かれています。
この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。
超大雑把に言うと
寄付の定義は財産上の利益を相手に提供すること
という意味ですね。
つまり
会費などや、物やサービスを購入した際の代金の支払い以外の財産の提供は寄付
という風になっていて、これは選挙の公正を守るため「寄付の定義」が広く決められていることを意味します。
なので歳費については、その返納が寄付にあたるというよりは「歳費の返納が寄付ではない条件には該当しない」という意味合いになり、それにより「寄付にあたる」という解釈がされるということです。
それを都合よく「歳費返納は寄付行為だから出来ないわー残念だわー貰うしかないわー(棒)」としているのが現状ということでしょう。
しかしこれは逆に言えば、公選法の寄付の定義に「議員歳費の返納は除外」と追記する法改正をすれば問題は解決するということになります。
実際に令和元年に参議院で月額77000円の歳費返納を行う法改正が行われた時は、公選法ではないものの
当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法第百九十九条の二の規定は、適用しない
との一文が明記されています。
「参議院議員が、令和四年七月三十一日までの間において、支給を受けた歳費の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法第百九十九条の二の規定は、適用しない。
前項の規定により歳費の一部に相当する額を国庫に返納するに当たつては、同項の措置が参議院に係る経費の節減に資するためのものであることに留意し、月額七万七千円を目安とするものとする。」
同じように「返納は寄付にあたらない」と明記すれば歳費の返納は可能ですから、冒頭の泉代表のポストにある
現行法では議員報酬の国庫返納が違法のため
は正しいけど、正確ではなく
法改正をしないことで議員報酬の国庫返納を違法にしている
ということでしかありません。
ちなみに前述した参議院での月額77000円の歳費返納は、あくまでも「返納する場合は」であって、「返納すること」とは一言も書かれていません。
また金額も「目安」であって月額77000円とは決まっていません。
要は
返納してもしなくてもいいけど、する場合は「寄付」にはあたらない。金額も77000円くらいを上限に各自で決めてね
という逃げ道一杯のなんとも曖昧なものです。
しかもしっかり「令和4年7月末まで」という期限付きです。
「暫定税率」は50年も続けるのに、こういった法律はしっかり区切りるのですから本当にふざけるなと思いますよね。
ということで議員の歳費の返納は「やらないだけ」であって、寄付の定義を変える法改正一つで可能です。
寄付について更に言うとこれまでの説明通り、歳費の返納は現行法では寄付に当たるため出来ないと解釈されています。
それなのに泉代表が「増額分は国内外の社会公益活動に寄付します」と言っているのは、議員から政党への寄付は禁止されていないことと、政党からの寄付は合法であることからです。
だから
今回の増額分は各議員から党に集め、国内外の社会公益活動に寄付いたします
という表現をしているわけです。
公益活動への寄付と言えば、世の中には「贖罪寄付」というものがあります。
「贖罪寄付」とは、脱税や薬物犯罪などの示談できる被害者がいない犯罪を犯した被疑者の人が、法テラスや犯罪被害者支援団体などの公益活動を行う団体に寄付を行い情状酌量を求める制度のことなのですが、この「贖罪寄付」では裁判所に寄付の証拠としてそれを受けた団体からの領収書を提出します。
もちろんそれと同じように、立憲民主党もそうした領収書を証拠として毎月有権者に公開すべきなのは言うまでもないでしょう。
有権者に「報酬増額分は寄付をする」と約束したのですから当然のことですし、その領収書をこの法案に賛成した自公国の3党の国会議員に「ふざけるな」と突き付ける材料にすべきです。
他にも歳費削減法のこともあるのですが、長くなるのでまた次の機会にしようと思います。
長々書きましたがとりあえず
「公選法上の寄付の定義に『歳費返納は含まず』を入れるだけで歳費返納は可能」
ということだけ覚えておいてください。
では、今日の記事はここまで。
更新の励みになりますので、ナイス減税!と思った人はスキ、コメント、サポートお願いします(・ω・。)
「おむつの消費税ゼロ」運動をやっています。
詳しくはこちらから
それでは、ナイス減税!
ここから先は
¥ 300
温かいサポートありがとうございます! 頂いたサポート代は、書籍の購入などに使用し減税活動に還元させていただきます。
