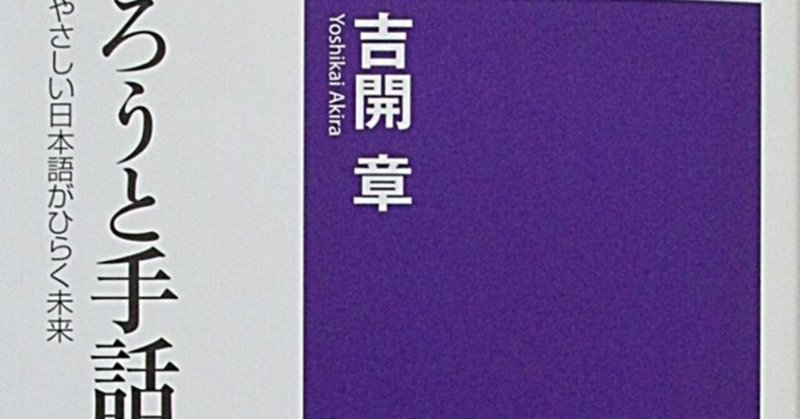
『ろうと手話』(吉開章・筑摩選書)
てっきり、手話通訳者かそれに準ずるような人が書いたものかと思っていた。しかし肩書きなどからすると「やさしい日本語」の推進をメインにしている人のようだ。つまり、外国語を母語とする人が日本語の環境で生活する必要になったときに、必要なことは、できるだけ分かりやすい日本語で生活情報が得られるような仕組みである。福岡の柳川でその事業を行っているという。西日本新聞に時折「やさしい日本語」によるニュースの運動が展開していたのは、この人に関わっていたのだ。
すると、ろう者もまた、「外国語を母語とする人が日本語の環境で生活する必要」があるという点で、共通する条件の下にある。ろう者のすべてが手話を使うわけではないが、さしあたり日本手話が言語として使われている場合があるとして、この構造の中で、彼らのために何ができるのか、それを考える本となっている。
結論的に言うと、少し欲張りすぎたのかもしれない、とも思う。というのは、本書が誰に向けて訴えているのか、という点で、もうひとつよく分からないように思えたからだ。
前半は、恐らく聴者に対してだろうと思う。この「聴者」という呼称が適切であるかどうかにも注意すべきであり、そうした問題にも実に詳しく触れてある点で優れた本であるのだが、ここではそこはざっくりと表現させて戴きたい。いったいろうとはどういうことか、聴覚障害とはどういうことなのか、定義のようなことも含め、かなりきっちりと解説を入れる。科学的な、また法的なものも、実に詳細に説明が施される。これは何か厳密な議論が必要なときには役に立つことだろう。
それから、ろう教育の歴史が細かくレポートされる。高橋潔氏と指文字のことや、西川吉之助氏の運命のことなど、興味深い経緯が多々あるのだが、本書ではそうした点はあまり関心がないようであった。日本のろう教育が全般的にどういうふうであったかを明らかにし、手話禁止と口話法などがどのようであったか、そして近年人工内耳の発達に伴いその問題がどのような変化を受けてきたのかについて、報告してくれている。これらは、もちろんろう者の中にも知らない人もいるかもしれないが、概ね、聴者に対して、ろう者の置かれた歴史的環境を周知のものとさせるためのものであるように見える。
私もよく知らなかったのだが、一時、わざわざ助詞を指文字で含む方法が唱えられたという。今の日本語対応手話でもやらないことだし、私は本当に知らなかった。この辺りから明確になってくるのだが、著者の関心はろうの子どもに対する教育ということにあるらしい。確かに、よく見ると「障害者教育」という言葉がちらちら見える。だが、本書がここまでしてきたことは、ろう者の社会的な問題であって、必ずしも教育問題を論じますよ、というふうではなかった。その意味でも、欲張ったために、あれにもこれにも触れながら、肝腎の主眼が読者にはっきりと示されていなかった、ということが分かる。つまり、読者はこの本が何のための訴えであるのか、分かりにくかったのである。聴者が読むとき、これはろう者の定義に始まり、その後は社会問題のように受け取りながら読み進んでしまうということになったのではないかと思う。
中央を過ぎた頃合いで、「ろう教育」ということが掲げられる。かと思いきや、話題は「手話言語法」という法律についてぐるぐる回り、「バイリンガルろう教育」と「ろうあ連盟」との意見の対立が大きな問題として展開する。政治問題も絡めながら、ろう者の人権といったことに関心が集められてゆくと、「ろう教育」はどうなったのか、行方不明になってしまった。この「バイリンガル」というのは、母語としての日本手話をもたせた上で、聴者の日本語をも使えるようにしていくということなのらしいが、あまりこれについて詳しい説明や定義を与えなかったわりには、いつの間にか対立の片側としてそびえ立つようになってきており、どうやら著者はこれに加担したいのではないかと推察されるようになってくるが、しかしいつの間にか舞台に登場して、主役級の役割を担ってきたように、急に感じたのは事実である。
ここでまた突然のように、「やさしい日本語」という概念がこの問題に急に重なってくる。著者の専門のところなので、ご自身の中では当たり前のことなのだろうが、読者として、それがどこからどういう必然性でここにつながってくるのか、分かりにくい。
とにかく歴史的背景や、政治的判断など、様々な資料を駆使して説明してくるので、きっと根拠はたくさんあるのだろうとは分かるのだが、一体何を言いたいためにそれを持ち出しているのか、あるいはいま話していることの主軸は何であるのか、それがなんだか分かりづらい。それというのも、説明にしても何にしても、欲張りすぎているからなのだと私は感じる。あれもこれも説明したい、資料を提供したい、その熱意は分かるが、何の問題を説明するためにその資料や背景を持ち出しているのか、それが読者に伝わらないのではないかと思うのだ。そこへ、「やさしい日本語」というある意味で別問題が折に触れ重なってくると、戸惑うばかりだ。そこにまた手話通訳の報酬問題も持ち出されてくると、まるでおもちゃ箱をひっくり返したような騒ぎになってきてしまう。
とまた、突然今度は、当事者に意見を強く言うことはできない、などとまとめてくる。一体これまで何を議論していたのか、何を提言していたのか、卓袱台をひっくり返されたような気持ちになる。そして私たちはバイリンガルろう教育に加担すべきであると言い、やさしい日本語の社会にしよう、となると、何を言おうとしているのか本当に分からなくなる。そして「おわりに」において、「手話」という表現ではなく「手語」というのがよいのではないかと、何かしら本音めいた意見を突然提唱する。今度は強く主張しているようで、先ほどの言明は何だったのかと混乱する。そしてまた最後には、手話の種類はろう者に考えてもらおう、そしてバイリンガルろう教育がいいと思う、でもそれに統一しろとかそれが優れていると言っているのではありませんよ、という結論を示す。何か強く言いたいことがあるが、強く言いすぎてはいけないとでも言うように、ふらふらと言葉が揺れていて、いったいなんやねん、と思いたくなる。こうしてついに、優しい日本語と聴覚障害者はつながったのである、と締めくくっているが、どうつながったのだろうか。筆者の思いの中でつながったということなのかもしれないが、読者の中ではつながらない。
実際に手話という言語がどういう文化であるのか、著者の口からそれに触れることはなかったと思う。少なくとも表記の上では、ろう文化に対するリスペクトが感じられなかった。政治的歴史的なことはよく調べてあるが、手話のもつ豊かな言語性についてご存じなようには感じられなかった。実際に手話でろう者とお話ししたことがあるようには伝わってこなかった。たとえていえば、野球はすばらしいスポーツだと歴史や組織のことは饒舌に喋るが、自分は一度もボールを投げたり打ったりしたことのない人が、野球はこうあるべきだ、と提言しているようなふうに見えるのだった。
残念ながら、本書の構成と段取り、述べ方、どれをとっても、私には「やさしい」ものではなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
