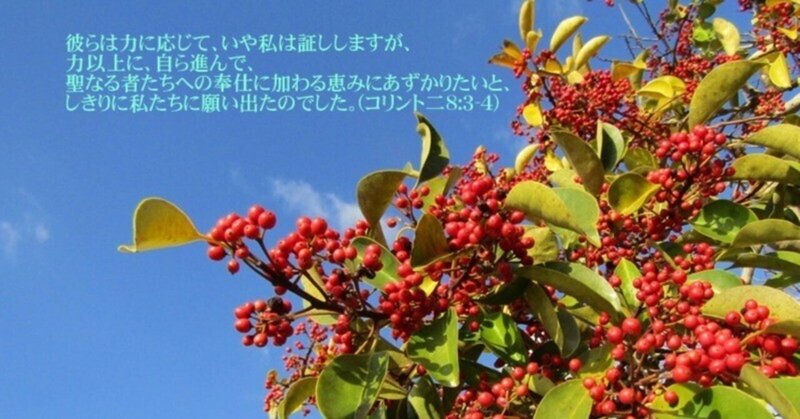
能登半島地震から1か月
家族が集まった正月。そのとき、ごちそうを前にして、東京の長男家族と、Zoomで会っていた。画面の向こうから、「揺れた」という声が聞こえた。
テレビが、騒ぎ始めた。北陸で大きな地震が発生したとのことだった。震度や地震の規模の発表からして、それは尋常ではなかった。経験上、これは大変なことになった、と思われた。阪神淡路大震災や東日本大震災の第一報を知っているからだ。
NHKからは、緊張というよりも切迫したアナウンスが繰り返されていた。これまでの地震の教訓からだろう。なりふりかまわず叫ぶようなそのメッセージは、後に話題になった。たぶん、それでよかったと思う。余裕の分析やコメントよりも、まずは逃げることなのだ。
1か月を数える。痛む胸を抱えつつ関心を寄せていたい。できることは僅かだが、声ひとつでも、助けとなることがあればいいと願う。ここでいま、そのことについてこれ以上立ち入ることは控える。
気づいたのは、時の遅さである。「復興」という言葉は語弊があるが、何らかの形で動いていくこと、立て直すこと、それがあまりにも遅いと感じるのである。
もちろん、関係者の努力には敬服するしかない。表に出てこなくても、地道に懸命に事に当たっている方々には、最大級の敬意を払う者である。だが、その労苦の割には、救援が進んでいないように見える。
半島という地理が、まずネックになった。道が塞がれ、人が踏み込めないし、出られない。液状化が広範囲に発生し、ライフラインのダメージが大きい。いろいろな理由があろうかと思う。なんとかならないか、と見ている私たちも、悔しい思いがしたくらいである。当地の方々の苦難は、どれほどであっただろう。ボランティアさえ、呼べない情況だったのだ。
検証したとは言えないが、阪神淡路大震災・東日本大震災・熊本地震と比較して、1か月後の姿が、少し違うような気がする。これらの地震の後には、発生後1か月間の新聞が集約されたものが出版されている。私はどれも買い求めている。特に神戸新聞は、京都新聞の協力によって発行を続けた、すばらしい実績がある。こうした本の売り上げの一部は復興に役立てられる、ということもあったが、即時の報道記録は、貴重な資料である。改めて、そこで何が起こっていたかを認識する縁となる。当時の有様の記録は重要である。
すると、その1か月経ったときの様子が、いまの能登半島より、少しばかり立ち上がる力が紙面から伝わってくるように私は感じた。議論も、再建へと向いている。しかし、仮設住居については、能登のほうが速やかに動いているようにも見える。避難生活者の実情は、あのときも今度も同じようなものであろう。中学生たちの移動も、やはり見られた。今回も、そうした措置が取られている。過去の教訓は活かされて然るべきなのだ。
決定的な差は、ボランティアである。災害の度に敬服するのが、ボランティアの方々である。若い力も多い。現地でなんとかしたい、できることが自分にある、思いは様々であろうが、ひとのために尽力する方々がいることを、頼もしく、また誇らしく思う。しかし、今回はその受け容れが難しい状態で、ここまできている。ボランティアをしたいという登録者は万の桁の数いるのに、受け容れの要請が非常に少ないという。現場の情況によるものだと思われる。
繰り返すが、これは私の偏った見方に基づく情報である。検証したわけではないから、無責任な発言であることをお断りする。情報として、鵜呑みにしないで戴きたい。誤解や無知からきている思い込みなのだろう、というくらいに見てくだされば有り難い。もしどなたかが、実際はどうなのか、と調べて働きかけていくようなことになったら、少しうれしい。
阪神淡路大震災も、1月だった。寒かった。東北も3月だから、まだまだ寒かった。しかし、北陸の正月となると、また別格である。ビニルハウスの中で暮らすなど、信じられないほどである。
ただ、かつての震災から、私たちは何らかの経験を得ている。阪神淡路大震災のときには、中井久夫先生が、大きなはたらきをなした。安克昌先生の命懸けのはたらきは、本で紹介され、ドラマにもなった。そのときの教訓が活かされるといいと思う。子どもたちが地震ごっこをすることも、心にとり必要なことなのだ。そんなことが、人々に認識されるといい。自分の感情で何かをしようというのではなく、必要なことを理解できるようになりたい。
重い1か月だったが、まだ続く。生活の復興が必要だ。そしてやがて、心のことも、重視されなければならなくなる。いや、いまもうすでに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
