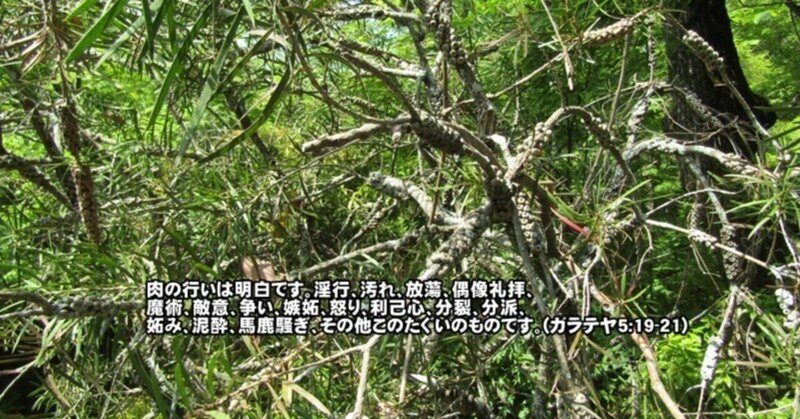
暗い言葉
「ひもじい」という言葉がある。「ひだるし」の「ひ」の一つの「文字」で表す「もじことば」である。「しゃもじ」(杓子から)はいまも知られるが、「お目もじ」(お目にかかる)すら、もう死語の部類だろうか。
この「ひもじい」の意味は、「おなかがすく」とは違う。ありきたりの辞典での説明としてはそれでよいのかもしれないが、学校から帰ってきて「ひもじい」と口にする子どもはいない。
それというのも、子どもたちの多くは、「ひもじい」という体験をしていない故に、その言葉を知らないのであるらしい。
尤も、「こども食堂」のきっかけになったように、栄養や食事量の足りていない子どもたちが決して少なくはない、という事実に目を瞑っていてはならないだろう。その子たちは、まさに「ひもじい」思いをしている、と私たち大人は考えるのだが、果たして当人たちは「ひもじい」という言葉を使うのだろうか。
何度か言及したが、「ののしる」という言葉も、子どもたちには通じない。古文の授業で、「ののしる」はかつては「大騒ぎをする」というような意味であったが、その意味でこの言葉を現代では使うことがない。つまり現代語と意味が違う語として、紛らわしい語の代表なのである。――が、中学生にとっては、現代語の「ののしる」を知らないものだから、この比較自体がナンセンスとなる。ただの新しい単語として学習することになるのである。
なかなか賢い小学3年生の子どもたちに、「いまの文章で意味の分からない言葉があったら質問しなさい」と求めると、二つ、挙がってきた。「うなだれる」と「みじめな」であった。私も慣れてきたので、予想していたから、今回は驚かなかったが、生活の基本語であっても、「いい育ち」をしている子どもたちには、これらの語は縁が無いのだろう、という予想を確信させることとなった。
このように、国語の授業では、大人側からすると、子どもたちも普通知っているという言葉について、全く理解されていない、ということが多々あることを警戒しなければならない。もちろん、小学校の現場にいる先生方は、そういう前提で常に子どもたちに接しているのは当然であるが、教会学校担当者などは、気をつけておくべきことのひとつであろう。
子どもたちは、「いじめ」という語には敏感である。だが「ののしる」は分からない。京都の「いけず」は文化かもしれないが、「ねたむ」という表現は通じない。それは「うらやましい」とはまた違うはずだ。古い言葉が廃れていく、ということをただ懐かしむ気持ちにはなれないが、言葉そのものが消えるというのは、その概念、その考え方や心情が表現する必要がなくなっているかもしれないことを意味するとすると、何か問題があるように思われてならない。
確かに、差別語が無思慮に用いられるのはどうかと思う。差別語とされるものには、そうした人々に対する共感を生むものもないわけではなかったが、排除したりバカにしたりする悪い作用のほうが大きいであろうことは間違いない。但し、私はその言葉そのものは知っておくほうがよいのではないか、と考えている。言葉を知るからこそ、その概念を意識に上らせることができる。もやもやとした感情でのみ懐いているとき、障害者を無用なものだ、と斬り捨てるような考えが、ある種の人々の中でクリアな言葉に作り上げられていったような気がしてならないのである。
その考え方から、子どもたちが使わなくなった言葉について、私は懸念している。子どもたちは、ほんとうに「ののしる」ことがなくなっているのだろうか。「うなだれる」ことがないのだろうか。「みじめな」思いをすることが、なくなっているのだろうか。「ねたむ」ことはないのだろうか。
聖書には、こうした言葉がたくさん登場する。聖書はその「聖」に騙されるかもしれないが、「聖」なのは神であって、そこに書かれてある人間の姿は、醜い罪ばかりである。誤解を恐れず言えば、聖書とは「罪のリスト」にほかならない。しかし、先の子どもたちのように、人間の心の否定的な要素を表す言葉自体を知らないでいるとなると、聖書の「罪のリスト」が何を意味しているかも伝わらないことになりかねない。それは、「罪」とは何かということに、気づくことが非常に難しくなる、ということになるのではないか。
人間は、暗い感情に襲われることから免れはしないだろう。それに襲われたとき、せめて言葉にすることで、何かそれに対処する可能性が生まれる、ということはあり得るものだ。言葉にすると、何かしらそれを他のものから分かち(「分かる」という言葉の原点)、対象化する契機となるかもしれないからである。だが、言葉にできずもやもやとしたままでいると、それができず、心全体がそれに支配されてしまう可能性を増やしてしまうと考えられる。
キリスト教的に「罪」として意識できたら、次の「救い」というものへ向かうことができるかもしれないのだが、そうでなくても、自分の中の否定的な感情について、言葉を用いて意識することは、大切なことではないかと思う。実は全般的に、子どもたちの中に、語彙の貧困を感じている。読書不足が関係するかもしれないし、電子機器の日常化が招いているのかもしれないし、あるいはまた他者とのコミュニケーションが影響するのかもしれないが、この言語化するという観点は、子どもたちのみならず、もっと真摯に取り組まなければならない問題ではないか、と私は捉えている。
同じマンションでも、全く挨拶をしない・返さない人が増えてきた。そこにも、この問題とのつながりを感じる毎日である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
